GX-ETS(GX排出量取引制度)は、2026年度から本格的に始動する日本初の全国的な排出量取引制度です。政府主導で制度設計が進むなか、企業には排出量データの第三者検証(Verification)が義務付けられる見通しであり、信頼性確保の要として注目されています。本記事では、GX-ETSの制度概要から第2フェーズの最新設計、排出枠の割当・補正制度、そして第三者検証の位置づけまで、最新情報を記載した記事を体系的に整理しました。制度対応を進める企業担当者やサステナビリティ推進部門の方に必見の内容です。興味ある内容を是非ともご覧ください。


1.制度の概要関連
【排出量取引】ETSとは?仕組みと世界の動向について解説
排出量取引(ETS)は、温室効果ガス排出に上限(キャップ)を設け、その範囲内で削減義務を企業に課す市場メカニズムです。企業間で排出枠の余剰や不足を売買することで、効率的な削減とコスト最適化を可能にします。経済的インセンティブの活用により、環境保護と経済成長の両立を目指す制度として注目されています。世界ではEU(2005年に開始された大規模なETS)や中国(世界最大規模のETS)など、多様な制度が導入されています。それぞれの特徴や動向が議論されています。ETSの仕組みと世界の動向について下記記事では解説しています。

【排出量取引】GXリーグとは?排出量取引を支える日本独自の枠組み
GXリーグは、2050年カーボンニュートラル達成を目指す日本において設計された自主参加型の排出量取引制度です。2023年に試行が開始され、企業が自主的に温室効果ガス削減目標を設定・報告し、排出枠の取引(超過削減枠の売買など)を通じて透明性と効率性を高め、脱炭素社会への移行を促進します。他国の強制的なETSとは異なる日本独自の枠組みであり、官民連携で市場創造に向けたルール形成にも取り組んでいます。例えば、排出データの透明性向上や第三者検証プロセスの整備などに注力しています。GXリーグの概要と役割について下記記事では解説しています。

【排出量取引】試行期間を解説ーGXリーグ第1フェーズについて
GXリーグ第1フェーズ(2023~2025年度)は、本格運用前の試行期間として位置づけられています。この期間に企業と政府は、排出量取引制度を実際に運用しつつ、排出量算定・報告方法や取引ルール等を検証し、課題を洗い出して改善につなげます。参加企業は自社の基準年を定め、2030年および2025年の温室効果ガス削減目標を自主設定し、その達成に取り組みます。2025年度末までの試行結果を踏まえ、第2フェーズ(義務化)でより実効性の高い制度設計が進められる予定です。GXリーグ第1フェーズの試行期間の概要について下記記事では解説しています。

【排出量取引】義務化とその展望―GXリーグ第2フェーズとは?
GXリーグの排出量取引制度(GX-ETS)は、2026年度から義務的な「第2フェーズ」に移行します。第1フェーズ(2023~2025年度)の試行結果を踏まえ、実効性を高めた制度設計が予定されています。第2フェーズでは、政府による排出枠の無償割当(過去の排出実績に基づく配分)や、排出量算定基準の適用、第三者検証の義務化、排出枠の市場取引制度、価格安定化措置などが導入されます。2024年度から排出枠申請が始まり、2026年度からの本格施行に向けたスケジュールも策定されています。GXリーグ第2フェーズにおける義務化の内容と展望について下記記事では解説しています。

【排出量取引】第2フェーズ設計の更新―令和7年7月経済産業省 委員会を受けて
2025年7月に開催された経済産業省の委員会(GXグループ)でGX-ETS第2フェーズの詳細設計に関する方針が示され、制度内容がアップデートされました。本記事では、2024年12月の論点整理(案)と今回の2025年7月方針を照らし合わせ、排出量取引制度の対象範囲(法人単体から企業グループへ拡大)、義務の形態(排出枠の年度末保有義務への転換)、未履行ペナルティ係数(1.1倍への確定)など7つのテーマについて最新の設計内容を解説しています。令和7年7月の委員会を踏まえたGX-ETS第2フェーズ設計の更新内容について下記記事では解説しています。

2.割当制度関連
【排出量取引】ベンチマーク・グランドファザリングの概要と課題
GX-ETSの排出枠無償配分では、ベンチマーク方式(BM方式)とグランドファザリング方式(GF方式)の併用が検討されています。本記事では、両方式の仕組みとそれぞれの利点・課題、および企業への影響や公平性の観点を整理しています。ベンチマーク方式は業種ごとの排出原単位に基づき効率的な企業を優遇する一方、グランドファザリング方式は各社の過去排出実績に依拠するため、早期削減者が不利になる課題があります。EU-ETSやカリフォルニア州の事例も交え、両者の比較を通じて最適な割当設計への指針を示しています。ベンチマーク方式とグランドファザリング方式の概要と課題について下記記事では解説しています。

【排出量取引】ベンチマークとグランドファザリングから見る割当設計
GX-ETS第2フェーズ(2026年度~)では、排出枠の無償配分にベンチマーク方式(BM)とグランドファザリング方式(GF)が採用され、業種の特性に応じて併用されます。エネルギー多消費型などベンチマーク値を設定できる業種ではBM方式、それ以外ではGF方式を適用します。さらに、早期削減企業へのインセンティブや海外への産業移転(リーケージ)リスクへの対策など、公平性を担保する調整措置も講じられる予定です。本記事では、2025年10月開催の排出量取引制度小委員会での議論を基に、BM方式とGF方式それぞれの仕組みと割当設計上の要点を解説します。ベンチマーク方式とグランドファザリング方式による割当設計について下記記事では解説しています。

【排出量取引】ベンチマーク・グランドファザリング方式による排出枠割当量の計算方法
GX-ETSでは、企業への排出枠割当てにベンチマーク方式とグランドファザリング方式の2つの主要な手法が採用されています。ベンチマーク方式は効率的な企業の排出原単位を基準に配分量を算定し、グランドファザリング方式は各社の過去排出実績に削減率を適用して割当量を決定する手法です。本記事では、それぞれの基本概念から具体的な割当量の計算プロセス、さらには制度の将来展望に至るまで、割当量計算の全体像を詳細に解説します。企業が自身の排出枠をどのように算定するかを理解する上で役立つ内容です。ベンチマーク方式およびグランドファザリング方式による排出枠割当量の計算方法について下記記事では解説しています。

3.割当制度(業界別)関連
【排出量取引】製造業・発電WGによる排出量取引制度の最適化
2026年度本格運用のGX-ETSに向けて、製造業ベンチマークWGと発電ベンチマークWGが設置されました。GX推進法改正を受け、多様な製造業・発電業の業種特性を踏まえた公平な排出枠割当制度の構築が進められています。従来の一律目標では業種間の違いを反映できず、業種別ベンチマーク指標の策定によって各企業の効率性を公正に評価し、技術革新を促す狙いがあります。製造業と発電業は国内排出量の約4割を占め、2030年度46%削減目標の達成にはこれら多排出産業での効率的な排出削減推進が急務です。本記事では、両WG設置の背景から多排出産業の削減戦略まで、日本の脱炭素化に向けた制度設計の最適化について詳しく解説します。製造業・発電部門における排出量取引制度の最適化について下記記事では解説しています。

【排出量取引】発電部門の排出枠移行とグランドファザリング調整策
GX-ETSの発電部門では、排出枠配分のベンチマーク(BM)を燃料別から全体平均へ段階的に移行する計画です。当初3年間は石炭・LNGなど燃料種別のBM値を適用し、その後火力全体の平均BMとの併用を経て、最終的に全電源平均BMへの統合を目指します。これにより急激な負担増を抑えつつ、公平性と効率向上の両立を図ります。一方、グランドファザリング(GF)方式では、エネルギー起源CO₂に年1.7%、プロセス起源CO₂に年0.3%の削減率を適用する案が示されています。また、事業活動量の大幅変動時には効率改善を加味した割当調整ルールを設け、過度な不利益を防ぐ措置も検討されています。発電部門の排出枠配分の移行とGF方式の調整策について下記記事では解説しています。

【排出量取引】主要業種排出ベンチマーク解説-石油・鉄鋼・化学・紙パルプ・セメント・石灰製造
石油精製、鉄鋼、化学、紙パルプ、セメント、石灰製造といった主要産業の温室効果ガス排出に関するベンチマーク指標について解説しています。各業種のScope1(燃料燃焼・プロセス)およびScope2(電力等)排出構造や、政府が検討する基準排出原単位(ベンチマーク値)、最近の排出実績の傾向を示し、さらには水素還元製鉄やCCUS、省エネ・燃料転換などの削減技術の導入状況と課題にも触れています。これらを踏まえ、各業界の実務担当者が取るべき対応ステップについても解説しています。主要業種(石油・鉄鋼・化学・紙パルプ・セメント・石灰)における排出ベンチマークのポイントについて下記記事では解説しています。

4.勘案事項関連
【排出量取引】GX-ETS 排出枠補正制度の設計
GX-ETSの無償割当では、企業ごとの排出構造の違いに配慮した補正制度が検討されています。製品の品種構成(例:紙と板紙の生産比率)、副生燃料の利用状況、自家発電と外部電力購入比率などの要因によって、同じ業種でも排出原単位や排出量に差が生じるためです。経済産業省の資料でも、品種構成や直接排出比率の違いに応じた補正の必要性が指摘されており、具体的な制度設計の方向性が示されています。本記事では、紙パルプ業界における製品種別補正の例などを挙げながら、補正係数を用いた排出枠補正制度の考え方を解説しています。排出枠配分の公平性を確保するGX-ETSの補正制度設計について下記記事では解説しています。

【排出量取引】GX-ETS 早期削減と価格安定化策
GX-ETSでは、早期削減を促す仕組みと排出枠価格の安定化策が導入される予定です。企業が制度開始前から積極的に排出削減に取り組むインセンティブとして、割当量の算定時に過去の削減努力が考慮される措置や、クレジットの活用促進策が検討されています。また、市場の排出枠価格が過度に変動しないよう、価格の上限・下限を設定した安定化措置が導入されます。具体的には、価格が一定水準を超えた場合に不足分を上限価格で国に納付する制度や、価格低迷時にGX推進機構が排出枠を買い取るリバースオークション等で需給を調整する仕組みが検討されています。GX-ETSにおける早期削減インセンティブと価格安定化策について下記記事では解説しています。

5.第三者検証
【第三者保証】第三者保証(Assurance)について解説
第三者保証(Assurance)とは、企業が公表する情報の正確性・信頼性を独立した外部機関が評価し確認するプロセスを指します。温室効果ガス(GHG)排出量やサステナビリティ報告などの非財務情報に対する透明性を確保し、ステークホルダーの信頼を得るために重要な手段です。第三者保証を受けることで、企業は開示情報の信頼性を高め、利害関係者との関係強化や法規制遵守のアピール、さらには企業価値向上の基盤を築くことができます。現代ではESG投資の拡大や報告基準の強化に伴い、この第三者保証の意義がますます高まっています。第三者保証(Assurance)の基本と重要性について下記記事では解説しています。
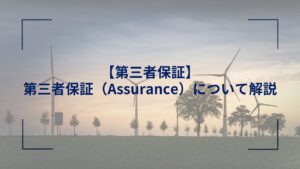
【排出量取引】排出量取引制度と第三者保証の重要性
排出量取引制度(ETS)において、報告される温室効果ガス排出量の信頼性は制度の根幹を支えます。第三者保証は、参加企業の排出量データを独立した視点で検証することで、取引の公平性と透明性を確保し、不正や誤報を防止する役割を果たします。正確に検証された排出データに基づく排出量取引は、削減努力の成果を適切に評価し、市場メカニズムの実効性を高めます。また、第三者保証を導入することで、企業は規制遵守を示すとともにステークホルダーからの信頼を獲得でき、制度全体の信頼性向上にも寄与します。排出量取引制度における第三者保証の重要性について下記記事では解説しています。

【第三者保証】合理的保証における法定開示を見据えた内部統制
企業のサステナビリティ情報開示において、より高い信頼性を確保するために「合理的保証」の取得を視野に入れた内部統制の整備が求められています。法定開示に向けて、財務情報の監査に匹敵するレベルで非財務情報(GHG排出量等)の正確性を担保する必要があるためです。本記事では、合理的保証(高い保証水準)の要件を満たすために企業が構築すべき内部統制のポイントを解説しています。具体的には、データ収集・管理プロセスの整備、責任者の明確化、記録の追跡可能性確保など、法定開示対応に必要な体制づくりを取り上げます。合理的保証を見据えたサステナビリティ情報の内部統制強化について下記記事では解説しています。

【第三者保証】サステナビリティ情報開示・保証制度の最新動向 2025年11月
2025年11月時点でのサステナビリティ情報開示・第三者保証制度の最新動向を解説します。金融庁の「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」での議論を踏まえ、国際基準(ISSBやEU CSRD等)と整合した開示基準の導入状況や、非財務情報への第三者保証義務化に向けた検討状況を紹介しています。日本では2024年度から大企業にサステナビリティ情報の開示が求められ、将来的にその保証(Assurance)の義務化も視野に入っています。本記事では、国内外の制度動向と企業の対応状況を整理し、今後の方向性を解説します。2025年11月時点のサステナビリティ情報開示・保証制度の最新動向について下記記事では解説しています。

【第三者保証】ISO14064温室効果ガス算定と報告の国際規格
ISO14064は、組織の温室効果ガス(GHG)排出量の算定・報告および検証に関する国際規格です。この規格に基づきGHG排出量を算定・開示することで、企業はデータの信頼性と比較可能性を高めることができます。ISO14064-1は組織単位でのGHG算定・報告の手順を定め、ISO14064-3は第三者検証のガイドラインを提供します。国際標準に沿ったGHG報告は、排出量取引市場やステークホルダーへの説明において重要な役割を果たします。本記事では、ISO14064規格の概要とその活用メリットを解説し、企業がGHG排出管理を国際基準に適合させる意義を説明しています。ISO14064による温室効果ガス算定・報告の国際規格について下記記事では解説しています。

6.その他
【排出量取引】GX推進機構の役割と最新動向徹底解説2025年版ガイド
GX推進機構(脱炭素成長型経済構造移行推進機構)は、GX推進法に基づき2024年7月に発足した公的機関で、今後10年間で150兆円超に及ぶGX投資を加速させることを使命としています。主な役割は、①金融支援(債務保証・出資等による企業の脱炭素投資支援)、②成長志向型カーボンプライシングの実施(化石燃料への賦課金と排出量取引制度の運営)、③官民連携のハブ機能の提供、の三本柱で展開されます。また本記事では、日本の都市型キャップ&トレードである「東京都排出量取引制度」の概要と2026年度改定の動向も整理し、企業の資金調達戦略や内部カーボンプライシング、MRV強化、排出枠ポートフォリオ戦略について総合的に解説しています。GX推進機構の役割と最新動向について下記記事では徹底解説しています。

【SHIFT】SHIFT事業支援による工場・事業場脱炭素化の先進事例紹介
政府の「SHIFT事業」は、工場や事業場の脱炭素化を支援するための補助金・支援制度であり、省エネルギー設備の導入や再生可能エネルギー活用を促進しています。本記事では、SHIFT事業の概要とともに、同制度を活用して脱炭素化に成功した先進事例を紹介しています。具体的には、製造業の工場における最新設備への更新や、事業場での再エネ電力導入などにより大幅なCO₂削減を達成した企業事例を取り上げ、支援の効果と得られた成果を解説します。SHIFT事業による工場・事業場の脱炭素化先進事例について下記記事では紹介しています。

【JCM】JCMの仕組み・メリットとGX-ETSとの関係について
JCM(Joint Crediting Mechanism)とは、日本が途上国との協力で温室効果ガス削減プロジェクトを実施し、その削減分を両国で分け合う二国間クレジット制度です。日本企業にとっては、海外での削減プロジェクトを通じてコスト効率よくクレジットを獲得できるメリットがあり、技術移転による国際貢献にも繋がります。本記事では、JCMの仕組みと利点を解説するとともに、日本国内のGX-ETS(排出量取引制度)との関係性を紹介しています。GX-ETSにおいてJCMクレジットは国内削減分の補完として活用可能であり、企業の排出削減戦略に組み込むことで柔軟性が向上します。JCMの仕組みやメリット、およびGX-ETSとの関係について下記記事では解説しています。

【東京都排出量取引制度】制度概要と企業事例、国際比較まで解説
東京都排出量取引制度(東京都キャップ&トレード)は、東京の大規模事業所を対象に温室効果ガス排出削減を義務付ける国内初の排出量取引制度です(2010年度開始)。本記事では、その制度概要として対象施設や削減義務量の設定方法、クレジット取引の仕組みを解説し、実際に削減目標を上回る成果をあげた企業事例を紹介しています。また、東京制度を海外の排出量取引スキーム(EU ETS等)と比較し、その特徴や効果を分析しています。東京都排出量取引制度の概要、企業の取組事例、国際的な制度比較について下記記事では解説しています。












