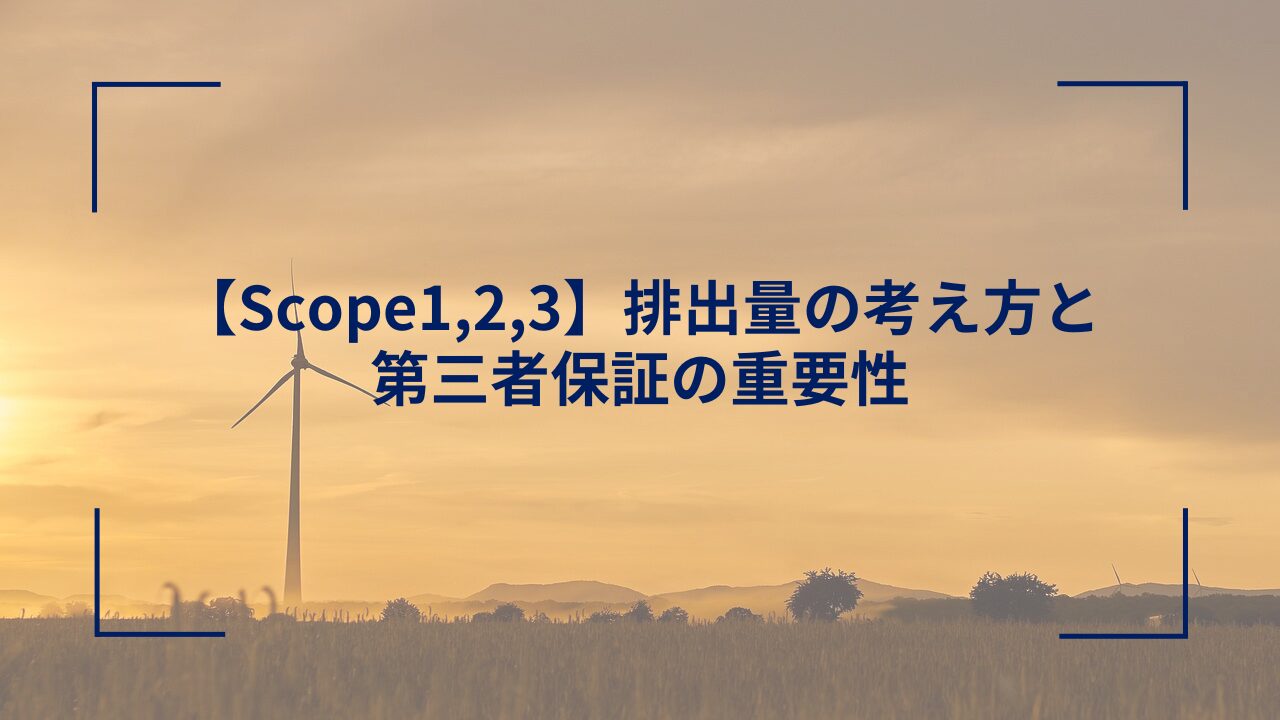企業の温室効果ガス排出量は、「Scope1(直接排出)」「Scope2(間接排出)」「Scope3(バリューチェーン排出)」に分類されます。Scope3はサプライチェーン全体の排出量を含み、多くの企業にとって最大の排出源です。適切な算定と管理は、脱炭素経営やESG投資への対応に不可欠です。また、GHG排出量の信頼性を確保するためには、第三者保証が重要であり、企業の透明性向上に寄与します。本記事では、Scope1,2,3の詳細と第三者保証の重要性について解説します。


1. Scope1,2,3とは?その定義と重要性
企業の温室効果ガス排出量(GHG排出量)は、排出源に応じて「Scope1」「Scope2」「Scope3」に分類されます。これはGHGプロトコルという国際基準で定義された区分です。Scope1は企業が自らの活動で直接排出する温室効果ガス(自社施設での燃料燃焼や社有車からの排出など)を指し、Scope2は他社から供給された電気や熱・蒸気などの使用に伴う間接排出を指します。そしてScope3はScope1・2以外のすべての間接排出、つまり自社のバリューチェーン上で他社から発生する排出を指します。
例えば原材料の調達や製品の使用・廃棄に伴うCO2はScope3に分類され、企業のサプライチェーン排出量(カーボンフットプリント)とも呼ばれます。これらScope1から3までを網羅的に算定・管理することは、企業の脱炭素経営において極めて重要です。なぜなら、自社のカーボンニュートラル(温室効果ガス実質ゼロ)を実現するには、自社からの直接排出だけでなく、供給網や製品ライフサイクル全体での排出まで含めた全体像を把握・削減する必要があるためです。
実際、製造業などではScope3が自社の総GHG排出量の大半を占めるケースも多く、Scope1,2だけでは企業全体の気候変動インパクトを正確に評価できません。また、近年は投資家によるESG投資の観点やCDPなどの開示要求、さらにはSBT(Science Based Targets)のような科学的目標設定においても、Scope3を含めたサプライチェーン全体での排出量管理・削減が求められています。したがって、Scope1,2,3の定義を正しく理解し、自社のGHG排出量を網羅的に算定・報告することが企業の環境戦略の出発点となります。
2. Scope1,2の排出量算出方法と管理手法
下記にScope1、Scope2の算出方法を示します。
Scope1(直接排出)の算出方法
基本的に自社が所有または管理する設備や車両等で消費した燃料量や生成された排出量を集計する形で行います。例えば、ボイラーや発電機で使用した燃料の使用量、社有車の走行燃料量、工業プロセスで発生するCO2量、空調機器から漏洩する冷媒ガス量など、各排出源の活動量(燃料使用量など)に対応する排出係数(燃料1単位当たりのCO2換算排出量)を掛け合わせてCO2排出量を算定します。
具体例として、ガソリン車のScope1排出量は「消費したガソリン量 × ガソリンのCO2排出係数」により算出されます。Scope1排出は自社の敷地内・設備内で発生するため比較的データが収集しやすく、企業が直接コントロール可能であることから最も管理・削減しやすい排出源と言えます。多くの企業ではエネルギー使用量のモニタリングや高効率設備への更新、燃料転換(例:重油から都市ガスへ、フォークリフトを電動化など)によってScope1排出量削減に取り組んでいます。また必要に応じて植林や炭素クレジットによるオフセットで残余排出量のカーボンニュートラル化を図る例もあります。
Scope2(間接排出)算定
購入電力や蒸気・熱供給による間接CO2排出を計算します。基本式はScope1と同様に「消費した電力量や熱量 × 当該エネルギーの排出原単位」です。例えば、使用電力量(kWh)に電力のCO2排出係数(g-CO2/kWh)を掛けて算出します。電力の排出係数は国や地域の平均値(いわゆるロケーションベース)だけでなく、契約している電力メニューや非化石証書の利用状況に応じた実績値(マーケットベース)でも算定することが推奨されています。
GHGプロトコルのScope2ガイダンスでは、このロケーションベースとマーケットベースの二通りの報告が求められており、再生可能エネルギー電力を調達した場合などはマーケットベースで排出削減効果が反映されます。企業の管理手法としては、省エネ施策による使用電力量削減や、再生可能エネルギーへの切り替え(自家消費太陽光の導入やグリーン電力証書の購入、PPA契約など)によってScope2排出量を削減する取り組みが一般的です。
RE100
RE100などのイニシアチブ参加企業は電力を100%再エネ化することでScope2排出を実質ゼロにする目標を掲げています。なお、日本国内では温対法(温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度)により一定規模以上の事業者は毎年自社の温室効果ガス排出量を政府へ報告することが義務付けられています。この制度で報告されるのは事業者単体のScope1,2排出量に概ね相当し、環境省のガイドラインでもScope1,2算定方法はこの制度に準じて行うことが示されています。つまり、自社施設で使用した燃料や購入電力の量を基に排出係数を掛けて算定するアプローチが標準となっています。
Scope1,2は自社のエネルギー管理の延長で算出できるため、環境報告書やサステナビリティ報告では多くの企業が高い精度で報告しており、国内外で信頼性の高いデータ整備が進んでいます。

3. Scope3のカテゴリー別詳細と算定方法
自社以外から発生する間接排出であるScope3は、その範囲が広大なため15のカテゴリーに細分化されています。GHGプロトコルの企業価値連鎖(バリューチェーン)会計・報告基準では、企業活動に関連するあらゆる上流・下流の排出源を網羅する形でカテゴリ1から15が定義されています。カテゴリ1~8が「上流」の排出、つまり原材料の調達や物流、従業員の活動などサプライチェーン上流側で生じる排出です。
一方、カテゴリ9~15が「下流」の排出、つまり自社が販売した製品の流通・使用・廃棄、投資先などバリューチェーン下流側で生じる排出を指します。例えば、自動車メーカーを例にすると、部品の生産や原材料の採掘・輸送は上流(Scope3のカテゴリ1や4など)に該当し、完成車のユーザーによる運転時の排ガスや、廃車時の処理は下流(カテゴリ11や12)に該当します。
Scope3算定方法
Scope3排出量の算定方法はカテゴリによって異なりますが、基本的な考え方は「活動量 × 排出原単位 = 排出量」という式に集約できます。活動量とは各カテゴリにおける排出源の量(例えば購入した原材料の重量、輸送距離、出張の移動距離、投資額など)であり、排出原単位はその活動量1あたりに排出されるGHG量(CO2換算)の値です。
多くの場合、企業は社内データやサプライヤーから提供された情報を活動量として用い、政府や研究機関が公開する排出原単位データベース(例えば環境省の排出原単位DBやGHGプロトコルの排出ファクタツール)から適切な排出係数を適用して排出量を算定します。しかし実際には、すべてのカテゴリで詳細な一次データを集めるのは困難な場合も多く、その場合は推計による算定も認められています。例えばカテゴリ1(購入した製品・サービス)の排出量は、購入量や重量ベースで算定する方法のほか、購入金額(支出額)を活動量として用いる方法もあります。後者では「〇円の購買につき△kg-CO2」という金額当たりの排出原単位を掛けて算定します。このようにデータ入手容易性に応じて物量ベース・金額ベース等のアプローチを使い分けることもScope3算定では一般的です。
Scope3は範囲が広いため、まず自社の排出量全体像を把握する目的なのか、特定のイニシアチブ(例えばSBT認定やCDP高得点取得)のためなのかによって、算定範囲や精度の優先度を決めることが実務上重要です。全カテゴリを概算でも網羅的に把握することで、自社のカーボンフットプリントでどこに重点的な排出源があるかを把握できます。一方、排出量が大きいカテゴリや、自社で削減施策を講じやすいカテゴリに絞って精緻に算定し、重点管理する戦略も考えられます。いずれにせよ、Scope3排出量の算定は一度限りではなく、サプライチェーン全体での協力を通じてデータ精度を向上させていくプロセスです。将来的により正確な排出量把握や削減のために、重要サプライヤーとの情報共有や、カテゴリごとのデータ管理体制構築を進めることが、脱炭素経営の深化に繋がります。
4. Scope3のカテゴリー1~8の排出量計算
それではScope3の各カテゴリについて、上流(カテゴリ1~8)の具体的な内容と算定方法のポイントを概観します。
カテゴリ1:購入した製品・サービス
自社が調達する原材料、部品、包装資材、オフィス消耗品などあらゆる購入品で排出されたGHGが対象です。多くの製造業ではこのカテゴリ1がScope3排出量の中で最大の割合を占めます。算定方法としては、調達した物品の重量や数量にその製造過程の排出係数を掛ける方法が基本です。例えば鉄鋼○トン購入なら「鉄鋼1トンあたりの製造時CO2排出量 × ○トン」で算定します。自社で詳細なLCAデータがない場合、環境省の排出原単位データ(経済産業省IOデータ等)を用いて購入金額ベースで推計することも可能です。いずれにせよカテゴリ1は取引先(サプライヤー)の排出に依存するため、主要サプライヤーへのCO2排出削減要請や情報開示要求(サプライヤーエンゲージメント)も重要になってきます。
カテゴリ2:資本財
建物や生産設備、機械、車両など耐用年数が複数年に及ぶ資本的支出による財の排出が対象です。要は自社の設備投資によって調達した機械装置や建設物資などの製造に伴う排出です。算定は基本的にカテゴリ1と同様で、取得した資本財ごとの重量や金額に応じて排出量を推計します。例えば新工場建設に使ったコンクリート〇トン分のCO2排出量や、新規導入した製造装置の製造時排出量などを合計します。資本財は一度きりの購入ですが大型投資の場合排出量も大きくなり得るため、こちらも主要な機械メーカー等から製品のカーボンフットプリント情報を入手できれば精度高く算定できます。
カテゴリ3:エネルギー(燃料・電力)の上流工程
自社が使用する燃料や電力の精製・輸送段階で排出されたGHGが対象です(※ただし燃料燃焼時の直接排出はScope1、発電時の排出はScope2で既に計上)。例えば、自社が使ったガソリンや都市ガスそのものを採掘・精製する過程での排出、購入電力を発電するために採掘された石炭や天然ガスの上流排出、および電力の送配電損失分に対応する発電排出などが該当します。算定方法は、自社の燃料使用量・電力使用量に対して、それぞれの原料採掘から精製・輸送までの排出原単位を掛けて算出します。例えばガソリン1ℓ当たりの上流排出(製油や輸送に伴うCO2)×使用量、電力1kWh当たりの上流排出(発電燃料の採掘等)×使用電力量、といった具合です。エネルギー起源の上流排出は、多くの企業で算定可能なScope3の基本項目であり、GHGプロトコルでも必須ではないものの算定が推奨されています。また再生可能エネルギーの利用拡大により、このカテゴリ3の排出も削減されていきます。
カテゴリ4:輸送・配送(上流)
購入した原材料や部品の調達物流、自社間の輸送(拠点間輸送)、製品出荷時に自社が支払う配送などサプライチェーン上流側の輸送に伴う排出です。自社保有の車両による輸送はScope1に含まれるため、カテゴリ4は他社に委託した輸送が中心となります。例えばサプライヤーから部品をトラックで納入する際の排出や、工場から倉庫までの輸送を外部業者に委託した場合の排出が該当します。算定には輸送距離や貨物重量のデータを用い、トンキロメートル(ton-km)当たりの排出係数を掛ける方法が一般的です。自社で輸送燃料の使用量データ(例えば委託輸送業者の燃料請求書など)を入手できれば燃料ベースで計算することもあります。なお環境省のガイドラインでは、このカテゴリ4と下流のカテゴリ9における輸送は任意算定項目と位置付けられていますが、物流由来の排出は製造業や流通業で無視できないため、できる範囲で把握することが推奨されます。
カテゴリ5:事業から出る廃棄物
自社の事業活動(生産工程やオフィス等)で発生した廃棄物を処理する際に排出されるGHGが対象です。具体的には、自社で発生した産業廃棄物や一般廃棄物が焼却・埋立処分される際のCO2やCH4排出などが該当します(有価物としてリサイクルに回されたものは除きます)。算定方法は、廃棄物の種類ごとの発生量(重量)に対し、それぞれの処理方法別排出係数を掛けて算出します。例えば可燃ごみ〇kgに対し焼却処理の排出原単位を適用、プラスチック廃棄物△kgに対し埋立処分の排出原単位を適用、といった形で計算し合計します。自社の廃棄物排出量は産廃処理業者のマニフェストやオフィスの廃棄物回収記録から把握できます。環境負荷削減の観点からは、廃棄物発生抑制やリサイクル率向上によってこのカテゴリ5の排出も削減可能です。
カテゴリ6:出張
従業員の公務出張に伴う排出です。主に航空機・鉄道・自動車(レンタカーやタクシー)などでの移動による燃料起源CO2排出が該当します。算定には、出張の移動距離または利用実績データを用います。例えば航空券の区間マイル数や乗車券の経路距離から総移動距離を算出し、交通手段ごとの排出係数(航空機ならクラス別CO2/kg-距離など)を掛けてCO2排出量を計算します。簡便な方法では、航空機利用回数×平均排出量/回や、出張旅費から概算する手法もありますが、可能であれば社内の経費精算システム等から移動距離ベースで集計する方が精度が上がります。出張由来の排出はテレワーク推進やオンライン会議の活用によって削減が期待できる分野です。
カテゴリ7:雇用者の通勤
従業員の通勤に伴うGHG排出です。社員が自家用車やバイクで通勤する場合の燃料起源CO2、公共交通機関利用時のエネルギー由来CO2などが該当します。算定は、社員の通勤手段ごとの人数や距離を把握し、各手段の排出係数を掛けて行います。例えば、社員○人が電車で片道△km通勤する場合の年間排出量、◇人が自動車通勤(燃費×距離から算出)する場合の排出量、といった形です。社員通勤のデータは従業員アンケートや通勤手当支給情報等から推計できます。こちらもテレワーク導入や社宅・寮の活用、公共交通利用奨励などによって削減可能な排出源です。
カテゴリ8:リース資産(上流)
自社がリース・レンタルで借りて利用している資産(設備や建物など)からの排出です。本来、排出原則ではオペレーショナルコントロールに基づき、自社が実質的に管理しているリース資産で生じる直接・間接排出はScope1,2に計上することが推奨されています。そのため日本の算定制度上はカテゴリ8に該当する排出源はほとんど無い(大半はScope1,2で報告済み)ケースが多いです。しかし、会計上の都合等で自社スコープに含めていないリース利用がある場合、その運用時排出をここで計上します。算定方法は、リース資産で消費したエネルギー量に対しScope1,2と同様の係数を用いて算出します。例えば借用中のオフィスフロアの電力使用量×電力係数によるCO2、リース車両の燃料使用量×燃料係数によるCO2、といった形です。該当する場合は貸主(リース会社)からエネルギー使用情報を入手するか、床面積などから推計します。
以上がカテゴリ1~8(上流側)の概要と算定アプローチです。自社の事業形態によって重要度は異なりますが、カテゴリ1(原材料・購入品)とカテゴリ3(燃料・電力の上流)は多くの業種で共通して押さえておきたい排出源です。カテゴリ1はサプライチェーン全体のカーボンフットプリント把握に直結し、カテゴリ3はScope1,2で見落としがちな上流排出を補完する役割があります。これら上流カテゴリの詳細な算定手順や具体的事例については、子記事にてさらに踏み込んで解説します。

5. Scope3のカテゴリー9~15の排出量計算
次に、Scope3の下流(ダウンストリーム)にあたるカテゴリ9~15について、その内容と排出量算出の考え方を説明します。下流カテゴリは、自社が販売した製品やサービスが市場に出た後に生じるGHG排出を対象としており、特に製品を提供する企業にとって重要な項目です。
カテゴリ9:輸送・配送(下流)
自社製品の出荷後、最終顧客に届けられるまでの物流・流通過程での排出が該当します。具体的には、自社が出荷した後に発生する輸送(卸業者から小売店への配送、小売店から消費者への宅配など)や流通倉庫での保管に伴うエネルギー起源排出が含まれます。また場合によっては消費者が店舗に製品を買いに来る際の移動による排出も、このカテゴリに含めて算定することがあります(必須ではありませんが、例として捉えられることがあります)。算定方法はカテゴリ4と似ており、輸送距離・重量データや流通段階のエネルギー使用量から推計します。自社が輸送コストを負担しない範囲まで含めるかは任意ですが、可能な範囲で製品の配送フロー全体を把握することが望ましいでしょう。
カテゴリ10: 販売した製品の加工
自社が販売した中間製品や部品が、他社によって加工・組み立てられる際の排出を指します。いわば、自社製品(中間財)を顧客企業が使用して最終製品を製造する際の排出です。例えば、自社が製造したゴム素材をタイヤメーカーに販売した場合、タイヤメーカーがそのゴムを加工してタイヤを製造する際のエネルギー起源排出がカテゴリ10となります。算定は、販売した中間製品の数量や用途に基づいて、一般的な加工プロセスの排出係数を掛ける方法があります。顧客企業から実際の排出データを得られるのが理想ですが難しい場合、業界平均のエネルギー使用量データ等を用いて見積もります。このカテゴリは主に素材メーカーや部品メーカーなどBtoB企業で関連性が高く、自社製品が使われるダウンストリーム工程の効率改善によって間接的に排出削減に貢献できる分野です。
カテゴリ11:販売した製品の使用
自社が販売した最終製品が使用される段階で排出されるGHGです。これは、自社の製品がお客様によって使用される際のエネルギー消費や燃料消費に伴う排出を指します。例えば、自動車メーカーにとってのカテゴリ11は、販売した車がユーザーによって運転される際の燃料燃焼CO2です。家電メーカーであれば製品(エアコンや冷蔵庫等)の使用時の電力消費に伴うCO2、石油会社であれば販売したガソリンや天然ガスが顧客によって燃焼される際のCO2が該当します。算定方法は、製品ごとの使用フェーズにおける平均的なエネルギー消費量に、そのエネルギーの排出係数を掛け、当該製品の販売数量と使用年数を考慮して算出します。自動車の場合、1台あたり年間走行距離や燃費から年間排出量を算定し、平均使用年数分を累積する、といった形になります。製品の使用段階は、多くの企業でScope3排出量の大きな割合を占め得るカテゴリです(特に自動車・化石燃料・電気製品など)。そのため、製品の省エネ性能向上や電動化など、顧客による使用時の排出を低減するイノベーションが企業の脱炭素戦略上重要となります。
カテゴリ12: 販売した製品の廃棄
自社の製品やその梱包材が使用後に廃棄・処理される際の排出が対象です。消費者や事業者によって使用済み製品が捨てられるとき、焼却処分によるCO2や、埋立処分によるメタンガス発生などが起こります。例えば、電子機器のプラスチック筐体が焼却される際のCO2、食品メーカーの製品容器が埋立地で分解される際のCH4などです。算定には、自社製品の材質組成や耐用年数、廃棄時の処理方法の分布(何%が焼却/埋立/リサイクルされるか)などの仮定を置き、それに各処理方法の排出係数を適用します。例えば年間販売した製品総重量×焼却率×焼却排出係数、といった形です。実際の廃棄段階データを取得するのは難しいため、多くは統計データや仮定に基づく推計となります。このカテゴリ12は、製品設計段階でのリサイクル容易性やバイオ素材への切替などにより将来的な排出削減につなげる余地がある点でも注目されています。
カテゴリ13: リース資産(下流)
自社が貸し出している資産(他者にリース・レンタル提供している設備や製品)の使用に伴う排出です。例えば、リース会社が顧客に貸与した車両からの排出や、自社が保有する建物をテナントに貸している場合のエネルギー起源排出が該当します。算定方法は、貸し出した資産で消費されるエネルギーを把握し、その量に対して排出係数を掛けます。レンタカー会社であれば貸出車両の走行燃料総量×燃料排出係数、ビルオーナー企業であればテナントの電力使用量×電力係数、といった具合です。基本的に自社所有資産なのでデータ入手は可能ですが、オペレーションは相手方に委ねているためScope1,2には含めずScope3で報告します(対照的に、借りる側は前述のカテゴリ8に該当)。このカテゴリはレンタル業やリース業、フランチャイズ本部などで重要であり、貸与先との協力による省エネ推進が排出削減策となります。
カテゴリ14: フランチャイズ
自社がフランチャイズ展開するビジネスにおいて、フランチャイズ加盟店の事業活動で排出されるGHGが対象です。例えば飲食チェーン本部にとって、自社ブランドで運営される加盟店の厨房設備からのガス使用や電力使用による排出がこれに該当します。要するにフランチャイズ加盟先のScope1,2排出をまとめて自社のScope3として計上する形になります。算定は、各加盟店舗からエネルギー使用量データを収集するか、店舗当たり平均排出量×店舗数といった推計で行います。フランチャイズ先は独立した事業者ですが、ブランドオーナーとして全体のカーボンフットプリントを把握し、支援するために算定・報告されます。多店舗展開企業ではこのカテゴリ14がScope3の主要部分を占めることもあり、加盟店への省エネ設備導入支援や運営ガイドライン策定など、排出削減に向けた連携が求められます。
カテゴリ15: 投資
企業が行う出資や融資など投資ポートフォリオに係る排出を指します。特に金融機関(銀行・保険・資産運用会社など)にとって極めて重要なカテゴリで、自社が融資・出資している先で発生するGHG排出(いわゆる「金融ポートフォリオの間接排出」)が該当します。例えば銀行であれば融資先企業の排出、ベンチャーキャピタルであれば出資先企業の排出、電力会社などが出資する発電プロジェクトでの排出などを、自社の投資に比例配分して計上します。算定方法は投資形態によって異なりますが、一般的には投資先企業のScope1,2排出量に持分比率や融資比率を乗じて算出します。株式投資であれば投資先企業の排出量×(持株比率)、融資であれば融資先企業の排出量×(融資額/企業価値)などの方法です。また、金融セクター向けにはPCAF(パートナーシップ・フォー・カーボンアカウンティング・ファイナンシャルズ)という国際的な基準があり、6種類の資産クラスごとに具体的な算定ガイドラインが提供されています。金融機関はこれを活用して投融資ポートフォリオ由来の排出量を精緻に算定することが可能です。非金融企業の場合、カテゴリ15はあまり該当しませんが(関連会社でScope1,2に含めていないものなどがあれば計上)、金融・投資事業を営む企業にとってはScope3排出量の大部分を占める重要カテゴリとなります。
以上、カテゴリ9~15(下流側)の概要と算定の考え方を説明しました。下流カテゴリは自社製品の社会での使われ方や、金融上の影響に関わるため、自社単独では管理しきれない部分も多いですが、製品設計の工夫や顧客への啓発、投資ポリシーの転換などを通じて間接的に削減へ働きかけることが可能です。また、金融業界では投融資先の脱炭素化を支援することでカテゴリ15の削減を図る動きも活発化しています。各企業は、自社のビジネスモデルに照らして重要な下流カテゴリを特定し、長期的な環境戦略に組み込むことが求められます。

6. 第三者保証とは?その必要性と方法
自社で算定したGHG排出量(Scope1,2,3)の信頼性を高めるために重要なのが第三者保証です。第三者保証とは、企業が報告するGHG排出量データについて、独立した第三者機関がその算定方法や結果を検証し、正確性を保証するプロセスを指します。専門の検証機関(監査法人や認証機関など)が企業の用いた基準や算定手法が適切か、データに誤りや偏りがないか、報告内容が透明性・一貫性を持っているかをチェックし、問題がなければ「第三者保証報告書」等の形でお墨付きを与えます。これにより、企業が開示する温室効果ガス排出量の数字について、投資家や取引先をはじめとする利害関係者は信頼性の高い情報として受け取ることが可能になります。
第三者保証が求められる背景と重要性
近年、企業のGHG排出量データに第三者保証を付与することが重視されるようになったのは以下のような理由によります。
データの信頼性向上
独立第三者による検証を経たデータは、企業の自己申告のみのデータに比べて格段に信頼性が高まります。内部チェックだけでは見落としや恣意的な操作の懸念が残りますが、外部の専門家が関与することで、透明性・客観性が担保されるためです。特に環境報告書や統合報告書で排出量を開示する際、保証付きであることは読み手に安心感を与えます。
ステークホルダー要求・規制への対応
投資家や顧客はサプライチェーン全体を通じて環境負荷の小さい企業を支持する傾向が強まっており、排出量データの正確さが資金調達や評価に直結しています。さらに各国で企業の気候関連情報開示の義務化が進む中、開示されるデータに対する保証は規制遵守上も重要となっています。例えばCDP(気候変動の情報開示プログラム)では、Scope1,2およびScope3排出量に第三者検証/保証が付与されている企業の方がスコア評価が高くなる仕組みです。実際、第三者機関による検証はCDPにおける開示やマネジメント、リーダーシップ各スコアの向上に寄与することが公表されています。また、SBTやTCFD提言に沿った目標管理においても、データの正確性担保は前提条件となります。
継続的な改善と戦略支援
第三者保証を受ける過程で、データ管理上の課題点や改善点が指摘されることは、企業にとって逆に有益です。例えば、一部の排出源データ漏れや算定ミスがあれば是正でき、以降のモニタリング精度が向上します。また保証意見を得ることで、自社の排出削減目標に対する進捗が客観的に裏付けられ、サプライチェーン全体での削減施策の計画策定にも役立ちます。このように第三者保証プロセス自体が企業の環境マネジメントを成熟させ、ステークホルダーとの信頼関係構築や持続可能な成長につながる経営情報を提供してくれます。
第三者保証の手法と国際基準
第三者保証は通常、専門の検証機関(例えばISO認定検証機関、会計監査法人のサステナビリティ部門など)に依頼して実施します。保証業務にはいくつかの国際標準が存在し、代表的なものに以下があります。
ISO 14064-3
国際標準化機構(ISO)が定めるGHG検証のための規格で、組織のGHG報告に対する第三者検証プロセスを詳細に規定しています。ISO14064-1が算定基準、ISO14064-3が検証基準となっており、これに則った検証はグローバルに通用する信頼性を持ちます。
ISAE 3410
国際監査基準(IAASB)が策定した保証業務基準で、GHG報告に対する保証業務に特化した基準です。公認会計士や監査法人がGHGデータ保証を行う際によく用いられ、合理的保証(Reasonable Assurance)と限定的保証(Limited Assurance)の2つの保証レベルが定義されています。合理的保証は詳細な検証で高い確信度を提供し、限定的保証はそこまで踏み込まずに「大きな誤りがないこと」を確認するもので、企業のニーズやコストに応じて選択されます。
その他の基準
上記のほか、AA1000AS(AccountAbilityが定めるサステナビリティ保証基準)や、製品のカーボンフットプリント検証に特化したISO14067、カーボンニュートラル達成を証明するPAS2060などがあります。
いずれも第三者によるデータ信頼性の確保を目的としたフレームワークであり、企業は自社の開示目的に適した基準を採用します。例えば欧州では財務監査と一緒にISAE3410ベースの保証を受ける企業が多く、日本国内ではISO14064-3に基づく検証報告書を環境報告書に添付する例が一般的です。
第三者保証のプロセス(検証の流れ)
第三者保証(GHG排出量検証)は、概ね以下のステップで進められます。
契約・計画策定
まず企業は検証機関と契約を結び、保証範囲(対象とする年度や排出源範囲:Scope1,2およびどのScope3を含むか)、採用基準(例えばISO14064-3に基づく限定的保証など)、スケジュールを取り決めます。事前に企業側の算定方法やデータ準備状況についてヒアリングが行われ、検証計画書が策定されます。
予備評価
検証人は提供資料の事前レビューを行い、算定方法の妥当性チェックやデータの概要把握を実施します。
ここでリスク評価(どの部分に誤りが潜みやすいか)を行い、重点的に検証すべき項目を洗い出します。
現地調査(オンサイト審査)
検証チームが必要に応じて現地(サイト)訪問を行い、実際の排出源や計量計測の状況を確認します。例えば工場を訪問して燃料使用記録やメーター類をチェックし、報告されたデータと齟齬がないか検証します。複数拠点がある場合は排出量の大きい拠点を抽出してサンプリング調査することが多いです。現地では担当者への聞き取りや、証憑資料(請求書、計量ログ等)の確認も行われます。こうしたフィールドワークによって、報告書上の数字と実態が整合しているかを確かめます。
データ検証・解析
収集したエビデンスに基づき、各排出量算定が正確に行われているか詳細に検証します。チェック項目は多岐にわたりますが、例えば「組織の境界設定は適切か(漏れている事業所や子会社はないか)」「算定に使用した排出原単位は信頼できるか」「算定式や集計シートにミスがないか」「前年との差異が大きい場合は合理的な理由があるか」などが挙げられます。またScope3については推計の前提やデータソースが妥当かも確認対象です。必要に応じて企業側に追加質問やデータ修正の依頼が行われます。
検証報告書の発行
すべての検証手続きを終え、大きな誤りや問題がないと判断されれば、第三者保証報告書(検証意見書)が発行されます。そこには検証範囲・基準、保証の程度(限定的/合理的)、および「報告された排出量には重要な虚偽の表示がないと判断した」旨の意見が記載されます。企業はこの保証報告書を環境報告書やウェブサイトで公開したり、CDP回答に添付したりします。仮に検証で不備が見つかった場合は、修正を経たうえで意見書が作成され、重大な不備が解消されない場合は保証見解を出せない(否定的意見や意見不表明)こともあり得ます。
以上が第三者保証の一般的な流れです。第三者保証を実施することで、企業のGHG排出データは透明性と信頼性が飛躍的に向上します。これは社内管理だけでなく、社外への説明責任を果たす上でも大きなメリットです。投資家や顧客、社会に対し「当社の排出量データは信頼できる」というお墨付きを示すことで、ESG評価の向上やレピュテーション向上につながります。

7. まとめ
ここまで、企業のGHGプロトコルに基づく排出量区分であるScope1,2,3の概要と、それぞれの算定・管理手法、さらに算定結果の信頼性を高める第三者保証の重要性について解説しました。自社の直接排出(Scope1)とエネルギー間接排出(Scope2)、そしてサプライチェーン全体の間接排出(Scope3)を網羅的に把握し、公表し、継続的に削減していくことが、脱炭素経営の土台となります。そして、その情報の正確性を裏付ける第三者保証は、ステークホルダーからの信頼を得てESG経営を推進する上で不可欠なプロセスです。各企業の状況によって重点となるScope3カテゴリや取り組み方は様々ですが、まずは現状の排出量を正確に測定・開示し、課題を洗い出すことがスタートラインです。