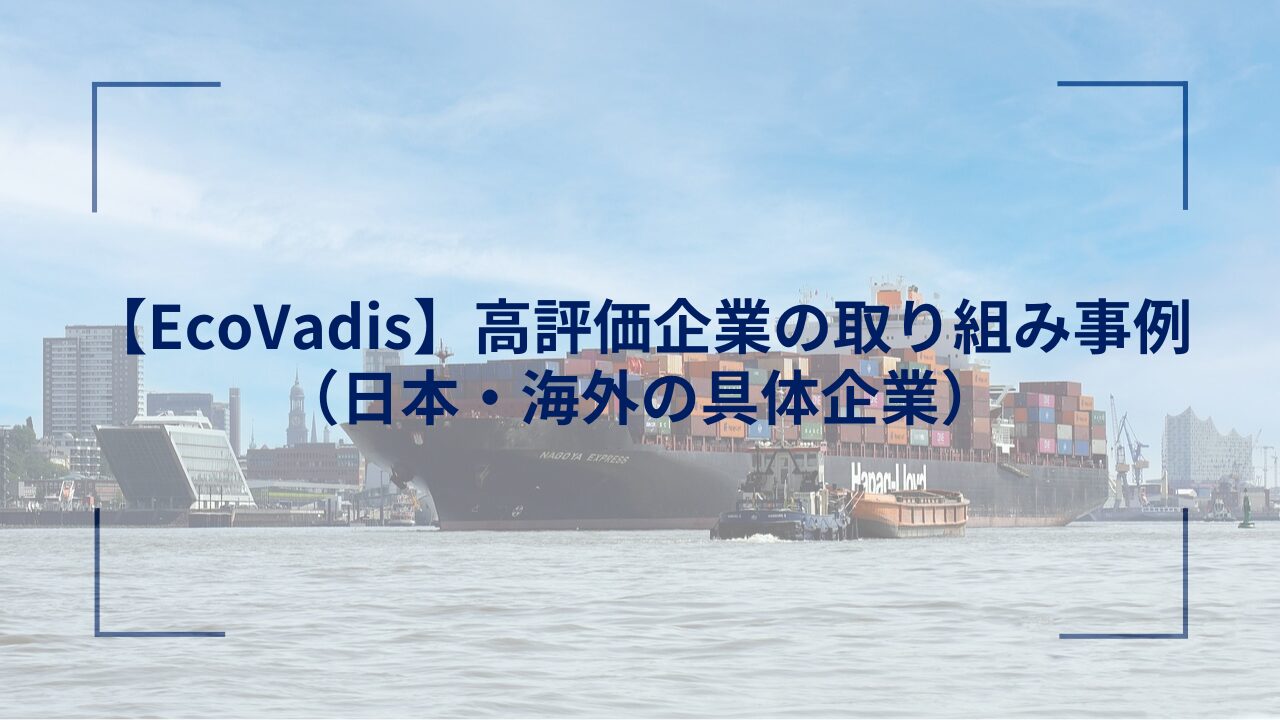EcoVadisで高スコアを獲得している企業は、どのようなサステナビリティ施策を展開しているのでしょうか。本記事では、日本および海外の具体的企業を例に、EcoVadis評価でプラチナやゴールドといった高評価を受けるに至った取り組み内容を紹介・分析します。先進企業の事例から、持続可能性経営のベストプラクティスを学びましょう。


1.日本企業の高評価事例
花王株式会社(Kao) – プラチナ評価の背景
花王は長年CSRに積極的に取り組んできた日本を代表する日用品メーカーです。特に花王グループの花王チミグラフ(印刷インキを扱う子会社)は、EcoVadisで最高位のプラチナメダルを獲得した実績があります。2023年の評価では、環境・労働と人権・倫理・持続可能な調達の全分野で卓越したスコアを収め、インキ製造業界において上位1%という評価を受けました。この高評価の背景には、花王グループ全体で推進するKirei Lifestyle Planという包括的なサステナビリティ戦略があります。具体的な取り組みとして
環境面
2030年に向けたCO2排出削減目標を掲げ、工場で再生可能エネルギーの活用や省エネ投資を積極化。製品設計でも環境負荷低減(詰替えパック普及や生分解性素材の活用)を推進しています。こうした努力が評価され、花王はCDPの気候変動・水・森林の3分野でオールA評価を獲得するなど外部評価も高いです。
労働と人権面
「花王人権方針」を策定し、国内外の全従業員に人権尊重教育を実施。安全衛生については各事業所で専門委員会を設置し、労災ゼロを目指す活動を継続しています。また多様性推進にも力を入れ、18年連続で「世界で最も倫理的な企業」に選出されるなど倫理・人権面の評価も高水準です。
倫理・ガバナンス面
グループ全体でコンプライアンス教育を年次実施し、内部通報制度の整備や腐敗防止の厳格なルール運用を行っています。花王は企業倫理に関する国際指標でも高く評価され、Ethisphereの「世界で最も倫理的な企業」に常連となっています。
サプライチェーン面
調達先には花王グループ購買行動指針を提示し、主要サプライヤーに対するCSR監査や支援を実施。例えば紙パルプの持続可能な調達ではFSC認証紙の調達比率向上を図るなど、環境・社会に配慮した調達を推進しています。その結果、花王はサプライチェーン領域でもEcoVadisから高いスコア評価を受けました。
以上のような総合力が、花王チミグラフのプラチナ評価につながったと考えられます。経営トップのコミットメント(花王は社長直轄でESG部門を設置)や、長期ビジョンに基づく戦略的な取組みが高スコアの原動力と言えるでしょう。
パナソニック ホールディングス – ゴールド常連企業の施策
パナソニックはグローバル電子機器メーカーとして、サステナビリティ経営においても先進的な企業です。EcoVadis評価は2013年頃から継続受審しており、毎年安定してゴールド(上位5%)評価を維持してきました。直近では2023年12月発行のスコアカードで総合68点を獲得し、全企業中90位=上位10%という高評価でした(ゴールド基準には若干届かないものの、シルバー上位・ゴールド目前の水準)。パナソニックの主な取り組みとして
環境
「Panasonic GREEN IMPACT」という環境ビジョンを掲げ、2050年カーボンニュートラルに向けたロードマップを策定。製造拠点での再エネ導入、省エネ商品開発、サーキュラーエコノミー推進(家電リサイクルなど)を強力に推進しています。2019年には科学的目標イニシアチブSBT認定も取得し、Scope1,2,3全てで削減目標を公表しています。こうした気候変動対応が評価され、CDPでもAリスト常連となっています。
労働人権
パナソニックは人権尊重宣言を早くから制定し、グローバルで従業員の人権デューデリジェンスを実施しています。安全衛生面では「ゼロアクシデント」目標の下、KY(危険予知)活動や労働安全マネジメントシステムの導入を進めています。またダイバーシティ&インクルージョンでは女性管理職比率向上や障がい者雇用など具体的目標を掲げ達成状況を開示しています。
倫理・ガバナンス
「パナソニックグループ行動基準」に基づき、贈収賄禁止や独禁法遵守の教育をグローバルで展開。内部監査・内部統制システムも充実しており、取締役会直属の監査役会やコンプライアンス委員会が機能しています。腐敗行為防止については高リスク国での贈答ガイドラインなど詳細規定を持ち、研修も頻繁に実施しています。情報セキュリティ面でもISO27001取得やCSIRT設置など万全を期しています。
調達
サプライチェーンCSRにおいて、日本企業で初期からEcoVadisを採用した一社です。主要仕入先に対しEcoVadis評価取得を働きかけ、自社だけでなくサプライヤーの評価向上にも取り組んでいる点が特徴です。実際、パナソニックは取引先と協働で環境データの開示や人権リスク低減策を進めるプログラムを運営しています。また「グリーン調達ガイドライン」を定め、調達先の環境負荷低減にも注力しています。
これらの取り組みによって、パナソニックはEcoVadis各テーマでバランス良く高スコアを維持しています。特筆すべきはサプライチェーン全体へのアプローチで、単に自社対応に留まらず取引先も巻き込んで持続可能性向上を図っている点です。この姿勢が国際的にも評価され、ゴールド常連企業としての地位を確立しています。
引用:https://news.panasonic.com/jp/topics/144058#
2.その他の日本企業例
上記以外にも、EcoVadisで高評価を受けている日本企業は多数あります。
セイコーエプソン
2020年より2年連続プラチナを獲得。環境ビジョン実現やRBA監査の推進などグローバルなCSR戦略が高く評価されました。エプソンは2019年までゴールド3年連続で、2020年新設のプラチナに移行して以降も最上位を維持しています。
引用:https://www.epson.jp/osirase/2021/211027_3.htm
味の素
2014年から評価を受け、直近ではスコア81でゴールド評価(2年連続)を取得。食品業界の中でも環境・社会貢献への取組みが進んでおり、特に栄養改善やコミュニティ支援の活動がユニークな点です。スコア81はかなりの高得点で、味の素グループのESG経営の成果が反映されています。
引用:https://news.ajinomoto.co.jp/2025/06/20250612.html
住友化学
2021年にゴールド評価を取得。気候変動や製品安全への取り組み、そして医薬・農薬分野での社会課題解決(マラリア防止蚊帳の提供など)が評価されたと言われます。経団連の企業行動憲章実践やSDGs推進にも熱心なことで知られ、総合化学メーカーとして初のゴールド獲得はニュースとなりました。
引用:https://www.sumitomo-chem.co.jp/news/detail/20230630.html
これらの企業はいずれも自社のコア事業とサステナビリティ課題を統合した戦略を持っており、その成果がEcoVadisスコアに表れている点が共通しています。
3.海外企業の高評価事例
ユニリーバ(Unilever)
ユニリーバは英国・オランダに本拠を置く世界的な消費財メーカーで、サステナビリティのリーダー企業として有名です。EcoVadis評価では具体的なスコアこそ公表していませんが、常にトップクラスの評価を維持していると見られます。ユニリーバの特徴は、自社だけでなくサプライチェーン全体で持続可能な慣行を根付かせていることです。
同社は「責任ある調達方針(Responsible Sourcing Policy)」を策定し、1次サプライヤーから農産物の生産者に至るまで包括的な基準遵守を求めています。その方針履行状況を監査・評価するツールの一つとしてEcoVadisを活用しており、取引先のEcoVadisスコア向上に取り組んだ功績で表彰も受けています。具体的には、調達部門が取引先にEcoVadis評価受審を奨励し、その結果を共有しながら弱点分野での改善を支援しています。ユニリーバのチーフサプライチェーン責任者は「EcoVadisは我々とサプライヤーの協力関係を深化させ、環境・社会コミットメントの向上に役立っている」と述べています。つまり、ユニリーバにとってEcoVadisはサプライヤーエンゲージメントのプラットフォームなのです。
サプライチェーン全体での持続可能性追求
ユニリーバ自身の社内施策も非常に先進的です。例えば気候変動対策では2039年までにバリューチェーン全体カーボンゼロを目標に掲げ、再エネ100%化(RE100)や物流の低炭素化を推進。労働人権ではILOの中核的労働基準順守を誓約し、人権報告書を毎年公表。倫理面では1870年代創業以来の企業理念「信頼できる企業であること」を掲げ腐敗行為を許さない文化を維持。これらが相まって、ユニリーバは各種サステナビリティランキングで常に上位を占めています(GlobeScan調査では十数年にわたり持続可能な企業ランキング1位または2位)。EcoVadisでも当然高い評価となっており、プラチナ相当であることは間違いありません。
引用:https://resources.ecovadis.com/sustain-conference/unilever
マイクロソフト
米国のIT大手マイクロソフトはEcoVadisプラットフォームの初期から参画しており、自社の主要サプライヤーに対しEcoVadis評価取得を求めてきました。自社自身もサステナビリティにおいてリーダー格であり、環境面では2030年までにカーボンネガティブ(排出より除去が多い状態)を宣言するなど攻めた目標を設定。労働人権ではサプライヤーへの労働基準遵守監査を徹底し、倫理面ではAI倫理ガイドライン策定など最先端の課題にも取り組んでいます。
EcoVadisにおいてマイクロソフトのスコアは公表情報が限られますが、ある年のサステナビリティレポートでは「当社はEcoVadis評価でゴールドを獲得し、上位5%企業に入った」と記載されていました(年次不明ながら概ね2010年代後半の実績)。テック企業はScope3(製品使用時排出)など課題も多い中、マイクロソフトはクラウド事業の効率化やデータセンターの省エネなどに投資し、他社をリードしています。こうした取り組みが評価され、EcoVadisでも高スコア帯に位置しています。さらに、業界全体への影響としてサプライヤーに高いCSR基準を課し変革を促す点が特筆されます。マイクロソフトは多数の部品メーカー・サービス企業と取引がありますが、EcoVadisや自社監査を通じてそれら企業の改善を後押しし、サプライチェーン全体での責任ある企業行動を推進しています。
引用:https://www.unilever.com/sustainability/responsible-business/sustainability-ratings-and-rankings/
これら海外企業に共通するのは、自社の事業特性に沿ったサステナビリティ重点課題を見極め、先進目標を掲げて実行している点です。さらに、その取り組みを透明性高く開示し、ステークホルダーと協働していることも高評価の要因でしょう。EcoVadisはあくまで評価結果ですが、その背後には企業ごとの創意工夫ある活動があります。高スコア企業の事例から学ぶことで、自社の持続可能性戦略のヒントを得ることができるはずです。
4.事例分析からの学び
以上、日本と海外の高評価企業のケースを見てきました。いずれの企業も、EcoVadisが評価する4テーマすべてにおいてバランスよく優れた対策を講じています。高得点を獲得するには、一部分だけ突出して良くても難しく、環境・社会・倫理・調達の全方位で一定水準以上を達成する必要があります。そのためには経営戦略にサステナビリティを組み込み、組織横断で継続的に取り組む姿勢が不可欠です。
また、トップランナー企業ほどサプライチェーン全体を視野に入れ、自社だけでなく取引先や業界全体のサステナビリティ向上をリードしています。EcoVadis評価はそうしたリーダーシップも間接的に反映される仕組み(360°ウォッチ等)になっており、単なる社内対策に留まらない影響力の大きさも高スコアの秘訣と言えます。高評価企業の取り組み事例は、これからEcoVadis対応を強化しようとする企業にとってロールモデルとなります。自社の業界でプラチナやゴールドを取っている企業があれば、そのCSR報告書やケーススタディを研究し、自社とのギャップを分析してみましょう。そこから、自社に足りない施策(例:科学的目標の設定、外部認証の取得、人権デュー監査の実施など)が見えてくるはずです。 EcoVadis高評価企業は、サステナビリティをコアバリューに据えて先進的な経営を行っています。彼らの実例に学びつつ、自社の持続可能性活動を深化させることで、EcoVadisスコア向上のみならず持続的な企業価値の向上を実現していきましょう。