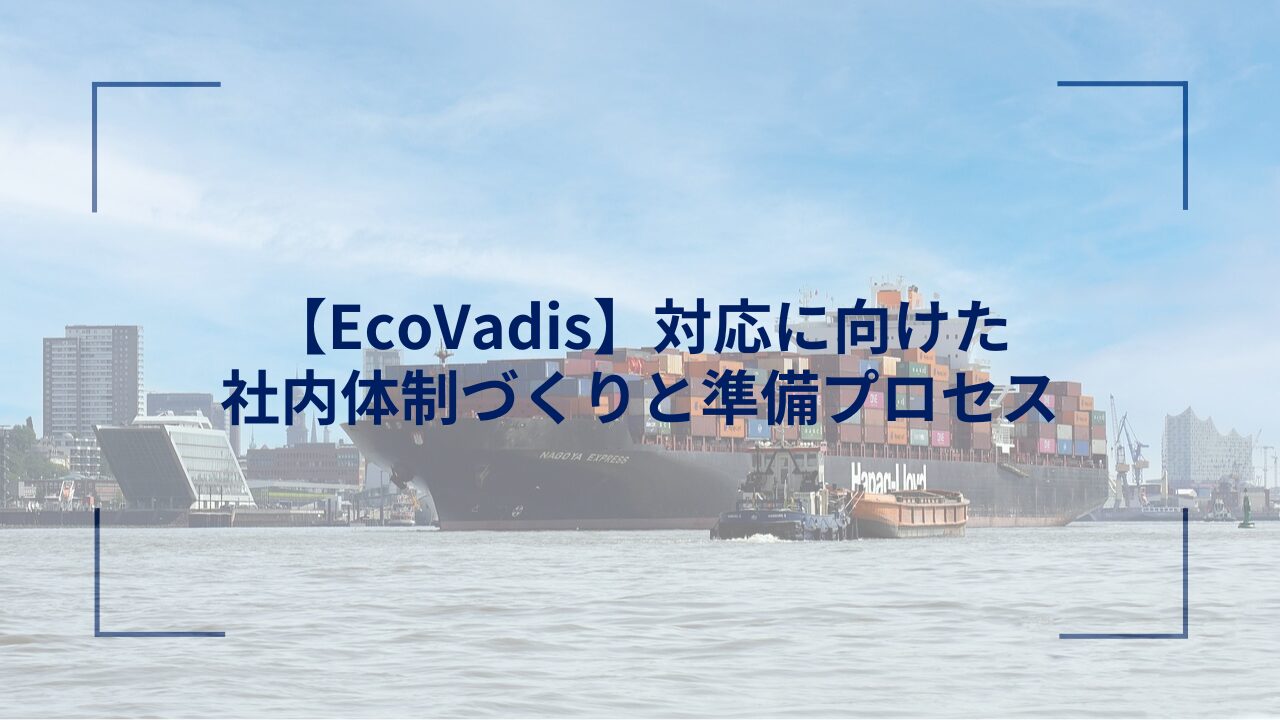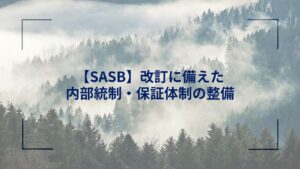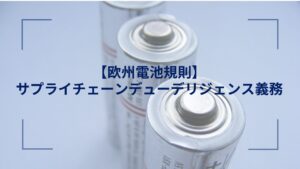EcoVadisの高評価を得るには、評価項目への対応を確実に行う社内体制の整備が不可欠です。内部監査の仕組みづくりや社員教育、部門横断のデータ収集体制、そして継続的な改善サイクルの構築など、組織として準備すべきポイントがあります。本記事では、EcoVadis評価に備えるための社内体制づくりと具体的な準備プロセスについて詳しく解説します。


1.EcoVadis評価に備える内部体制の重要性
EcoVadis対応は一部署だけで完結できるものではなく、企業全体での取り組みが求められます。評価項目は環境・人事・法務・調達など多岐にわたるため、関連する各部門が協力して情報を提供し、必要な施策を講じる体制を構築する必要があります。例えば、環境部門は温室効果ガスや廃棄物に関するデータを用意し、労務・人事部門は労働安全衛生や人権研修の記録を整え、調達部門はサプライヤーコードや監査方針を策定する、といった具合です。またCSR推進やサステナビリティ担当部署が中心となり、各部門の取り組みを統合・管理する横断的なプロジェクトチームを編成すると効果的です。
トップマネジメントのコミットメントも重要な要素です。経営層がEcoVadis評価を企業戦略に位置付け、社内に明確な目標(例:次回評価でシルバー以上取得)を示すことで、全社的な協力体制を引き出しやすくなります。実際、評価スコア向上に成功した企業は、必ずと言っていいほど経営トップが主導してサステナビリティ方針を掲げ、進捗管理を行っています。このように、EcoVadis対応は組織全体の協働とリーダーシップが鍵となる取り組みなのです。
2.サステナビリティ方針の策定と内部監査の整備
まず取り掛かるべきは、各テーマに関する基本方針やルールを明確にすることです。EcoVadisの評価では「企業がサステナビリティに関する方針を定めているか」が重視されます。環境方針、人権方針、倫理規程、調達ガイドラインなどを策定・整備し、社内外に公表しておきましょう。既にISO14001やISO45001等の認証を取得済みであれば、それらの方針を活用できます。また未策定の場合も、業界のベストプラクティスや国際規範(例:国連グローバルコンパクトの原則)を参照してポリシーを定めることが重要です。
内部監査や自己評価の仕組み
次に、内部監査や自己評価の仕組みを構築します。EcoVadis質問票への回答を準備する過程で、自社の体制を点検する「模擬監査」を実施すると効果的です。例えば内部監査部門やサステナ担当者が中心となり、環境・労務・倫理・調達の各領域で必要な資料が揃っているか、手順は運用されているかをチェックします。これはいわばEcoVadisスコア向上のための社内デューデリジェンスと言えます。もし内部チェックで不足が見つかれば、本番評価前に是正措置を講じることができます。特に証拠書類(ポリシー文書や記録類)が未整備だった箇所は急ぎ作成・蓄積する必要があります。EcoVadisでは「回答には証明書類が必要なため、取組みを文書化する体制づくりが欠かせない」と指摘されています。つまり、良い取り組みをしていても記録や文書がなければ評価されません。「書類に残す文化」を醸成し、社内ルールや活動実績をきちんと文書管理する仕組みを整備しましょう。
具体的な準備としては、以下のような内部監査チェックリストを作成すると良いでしょう:
内部監査:環境
環境方針の制定・周知状況、環境目標(CO2削減等)の設定と進捗データ、廃棄物・エネルギー管理記録、環境教育の実施履歴など
内部監査:労働と人権
労働安全衛生方針と委員会活動記録、労働時間・労働条件の管理状況、ハラスメント防止策、人権研修の実施状況、従業員からの苦情処理体制など
内部監査:倫理
企業倫理規程と従業員への周知(研修受講記録)、腐敗防止の社内規定(贈答接待ルール等)、内部通報制度の運用状況、情報セキュリティポリシーと事故記録など
内部監査:調達
サプライヤー行動規範の有無と告知状況、重要仕入先へのCSR調査や監査の実施記録、取引基本契約へのサステナ条項盛込、紛争鉱物調査等の実施など
こうした点を点検し、漏れがあれば是正します。特に証拠書類の裏付けが重要なので、監査チェック後には関係部門に証拠資料を提出させファイル化しておくと、評価回答時にスムーズです。
3.社内教育と部門横断的なデータ収集体制
EcoVadis対応を機に、社員教育・意識啓発にも力を入れましょう。サステナビリティやCSRに関する基礎知識、なぜEcoVadis評価が必要なのか、社内で各部署が何をすべきか、これらを社員全体に共有することで協力体制が強まります。具体的には、社内説明会やeラーニングでEcoVadisの概要と評価項目を説明し、自社の目標(例:「来年度ゴールド評価取得」)を周知すると良いでしょう。特に各部署の担当者レベルまで理解を浸透させることが重要です。現場の一人ひとりが自分の業務とEcoVadis評価の関連性を理解すれば、日常の中で必要なデータや記録を意識的に残すようになります。
部門横断的なデータ取集
例えば工場部門であればエネルギー使用量や事故発生件数、総務部門であれば社員研修やボランティア活動の記録、調達部門であれば仕入先アンケートの回答結果など、部署ごとのデータ収集が不可欠です。これらを集約するため、共通の社内データベースや共有フォルダを用意し、定期的に更新してもらう仕組みを作ります。「環境」「労働安全」「コンプライアンス」「調達」などカテゴリごとにフォルダを分け、証拠書類や数値データを年度ごとに蓄積していくとよいでしょう。将来的に再評価を受ける際にもこのデータ蓄積が役立ちます。
コンサルティング活用
なお、中小企業などでは専任担当者が限られるケースもあります。その場合は外部の力を借りるのも一案です。EcoVadis認定トレーニングパートナーやCSRコンサルタントに相談し、社内研修の講師を務めてもらったり、評価回答のコツを指南してもらう企業も増えています。自社だけで難しい場合は、こうした専門家の支援サービスも検討すると良いでしょう。
4.継続的改善のサイクル設計
EcoVadis評価は1回受けて終わりではなく、継続的な改善サイクルを回すことが大切です。初回評価で出たスコアカードの「改善点」に基づき、次回評価までにどのような対策を取るか計画を立てましょう。例えば「環境で得点不足だったので再生可能エネルギー導入を検討」「労働人権で指摘を受けたのでサプライチェーン人権方針を策定」といった具体策をKPI化し、進捗を管理します。
このPDCAのサイクルを社内に定着させるため、定期的なサステナビリティ委員会やCSRワーキンググループを開催するのも有効です。四半期ごとに各部署の取組み状況とデータをレビューし、改善すべき点を洗い出していきます。EcoVadisは年次アップデートで評価手法が変更される場合もあるため、最新情報のキャッチアップも必要です。その意味でも定期会合を設け、情報共有と対応策検討を継続することが望ましいです。
ギャップ分析
さらに、EcoVadis評価後にはアナリストからのコメントが各設問に付されます。これには「証拠書類が十分」「○○が未整備」といった具体的フィードバックが含まれるため、詳細を確認し次のアクションにつなげます。EcoVadisでは評価後に改善に向けたガイダンスも提供しており、優先的に始めるべきことが示唆されます。例えば「CO2算定を開始しましょう」などの提案があるので、ギャップ分析を実施しそれらを社内計画に反映させます。
5.まとめ
EcoVadis対応には、社内規程類の整備、データ収集・文書管理の徹底、社員教育と意識改革、そしてPDCAによる継続改善という一連のプロセスが欠かせません。これらを通じて企業内部にサステナビリティマネジメントの仕組みが構築されれば、EcoVadisで高スコアを得られるだけでなく、事業運営そのものがより持続可能で強靭なものとなります。社内体制づくりへの投資は、長期的な企業価値向上に直結する重要なステップと言えるでしょう。
引用
EcoVadis公式サイト「EcoVadisが与える影響」
https://resources.ecovadis.com/sustain-conference/unilever
三菱商事ケミカル事例「評価受審がもたらした意識変革」
https://resources.ecovadis.com/ja/suppliers-customer-stories/how-the-ecovadis-assessments-ignited-a-company-wide-mindset-shift-for-mitsubishi-shoji-chemical-corporation