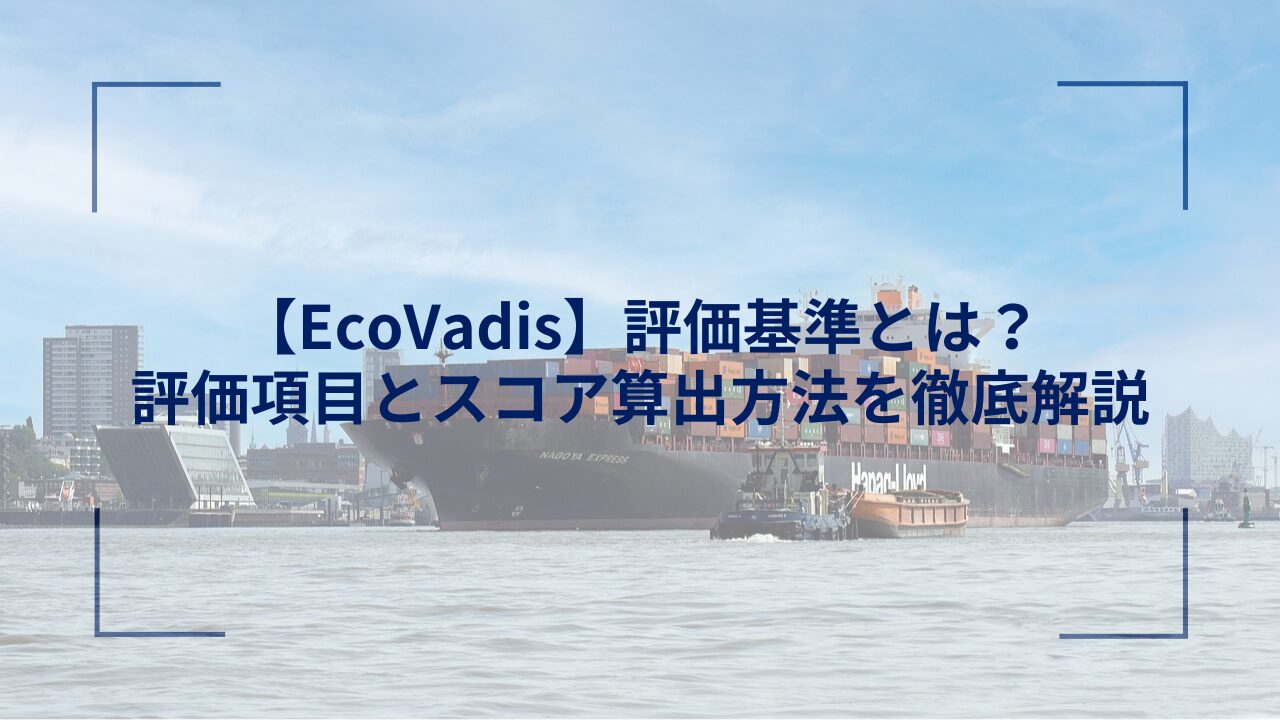企業のサステナビリティ活動を評価するEcoVadisでは、環境・労働と人権・倫理・持続可能な調達の4つのテーマにわたる詳細な評価基準が設けられています。本記事では、EcoVadisの評価カテゴリと具体的な評価項目、評価スコアの算出方法(加重平均による総合スコア算出やメダル判定基準)、さらに評価プロセスにおけるエビデンス検証や監査の仕組みまでを徹底解説します。


1.EcoVadisの4つの評価カテゴリと評価指標
EcoVadisは、企業のサステナビリティ(企業の社会的責任=CSR)への取り組みを「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な資材調達」の4つのテーマで評価します。これら4テーマの下に合計21の評価指標が設定され、企業の活動内容が多角的にチェックされます。各テーマの主な評価項目は次のとおりです。
環境(Environment)
温室効果ガス排出量とエネルギー消費、水資源の使用量・汚染防止、生物多様性への配慮、大気汚染防止、有害物質管理・廃棄物管理など、事業活動による環境影響と資源利用の取組み状況。また製品ライフサイクルにおける環境配慮(製品使用時の環境負荷削減や廃棄後リサイクル、顧客の健康安全確保、環境に優しいサービス提供など)も評価されます。
労働と人権(Labour & Human Rights)
従業員の労働安全衛生の確保、適切な労働条件の提供、労使間の対話推進、人材育成(教育訓練・キャリアマネジメント)といった労務管理面、および児童労働・強制労働の禁止、人身取引の防止、従業員の多様性・公平性の推進、コミュニティや取引先など社外ステークホルダーの人権尊重といった取り組みが対象です。
倫理(Ethics)
贈収賄や汚職の防止、利益相反の回避、独占禁止法順守、公正な取引慣行の維持など企業倫理・コンプライアンス体制が評価されます。また責任ある情報管理として、サイバーセキュリティや個人情報保護などデータ管理の適切性も含まれます。
持続可能な資材調達(Sustainable Procurement)
調達方針・プロセスにおいてサステナビリティがどの程度組み込まれているかを評価します。具体的にはサプライヤー選定基準やコードオブコンダクトの有無、サプライヤーに対するCSR評価・監査の実施状況、取引先との協働体制などです。特に「サプライヤーの環境慣行・社会慣行」に関する管理が問われ、企業が自社だけでなくバリューチェーン全体で持続可能性確保に取り組んでいるかが評価のポイントとなります。
評価指標
各企業には、上記テーマごとに関連する質問が網羅されたオンライン質問票が提供されます。質問票の内容は企業の業種・規模・所在地に応じてカスタマイズされ、例えば製造業とサービス業、従業員数が多い企業と少ない企業では設問や要求される詳細度が異なります。企業は質問に対する回答と裏付けとなる証拠書類(各種ポリシー文書、手順書、データ記録、認証書類など)をプラットフォーム上に提出し、それらに基づいてEcoVadisのアナリストが評価を行います。
2.評価プロセスとスコア算出方法
EcoVadisの評価プロセスは大きく3段階に分かれます。
登録と質問票への回答
まず評価を受ける企業はEcoVadisのオンラインシステムに登録し、自社の基本情報(業種、規模、所在国など)を入力します。登録後、先述のカスタマイズされた質問票にオンラインで回答します。質問は「環境」「労働と人権」「倫理」「持続可能な調達」の4テーマにグループ化されており、自社のサステナビリティに関する取り組み(方針・体制・実施内容・実績データなど)を報告します。回答時には証明書類(エビデンス)の添付が求められます。例えば「環境」なら環境方針書やISO14001認証、「労働」なら安全衛生マニュアルや研修記録、「倫理」なら行動規範やコンプライアンス研修資料、「調達」ならサプライヤー行動規範や監査報告書、といった具体的文書を提出します。これらエビデンスは評価の信頼性を担保する重要な要素です。
専門家による分析
EcoVadisの社内アナリストチームが、提出された回答内容と証拠書類を精査し、各テーマについて0~100のスコアを算出します。評価は7つの基本原則に基づき行われ(国際専門家による評価、多様な情報源の活用、証拠に基づく評価等)、また独自の7つのマネジメント指標(方針、実施措置、認証取得、取組みの範囲、報告、360°ウォッチ等)で企業のマネジメント体制の成熟度を多角的に評価しています。さらにEcoVadisは「360°ウォッチ」と称して、提出情報以外にNGOやメディア、労組、公的データベースなど数千に及ぶ外部情報源をモニタリングし、企業の評判や不祥事情報もスコアに反映させています。例えば提出書類に現れない環境事故や人権問題の報道があれば減点要因となり、公正な評価を期す仕組みです。
結果(スコアカード)
分析完了後、評価結果はオンライン上でスコアカードとして公開されます。スコアカードには各テーマの点数(0~100点)と総合スコア、さらにテーマ毎の評価コメント(強み・改善点)や競合比較のための業界内順位(パーセンタイル)が示されます。このスコアカードは評価日から12か月間有効で、取引先とも共有可能な形で提供されます。
総合スコアの算出方法
EcoVadisでは4テーマのスコアを加重平均して総合スコア(0~100)を計算します。テーマごとの重み(ウェイト)は業種・企業規模に応じて設定され、環境リスクの高い業界では「環境」ウェイトが高く、人的リスクの高い業界では「労働と人権」ウェイトが高くなるなど調整されています(公表されている標準では4テーマすべてを同等に25%ずつではない)。なお、2025年から算出方法に一部変更があり、従来は各テーマ詳細スコアを10点刻みに丸めてから加重平均していましたが、今後は丸めずに実際の点数で計算するよう改善されました。これにより少数点以下の努力も総合得点に反映されやすくなり、より正確で透明性の高いスコア算出が実現します。
例えば従来は「倫理」詳細スコアが45点だと50点に切り上げ計算されていたものが、変更後は45点のまま計算されます。一方「労働と人権」で64点だったものは60点に切り下げられていたのが、64点として計算されるようになります。この変更によって総合スコアが小幅に動くケースもありますが、企業にとっては1点刻みでの継続改善の成果が反映される前向きな改訂といえます。
3.監査・エビデンス検証の仕組み
EcoVadisの評価は提出情報の信頼性確保にも重点を置いています。質問票への回答だけでなく、裏付けとなる証拠書類の提出が必須である点がその表れです。EcoVadis内部には不適切な文書提出(偽造やデタラメな資料)を検知するメカニズムもあり、提出物に不審な点があれば評価プロセス内でチェックされます。評価対象企業は、自社が提示する情報が最新かつ正確であるよう社内でしっかり準備する必要があります。
また前述の360°ウォッチにより、企業の評判リスクも監査的に管理されています。EcoVadisは外部データソースから環境事故、法令違反、労働問題などのニュースを収集し、評価スコアに反映します。仮に企業が提出資料上は完璧でも、直近で重大な不祥事が報じられていればその分スコアは減点されます。このように内部自己申告情報と外部監査情報を組み合わせた評価となっているため、評価される企業は日頃から実態として優れたCSR経営を行うことが求められます。
異議申し立て制度
さらにEcoVadisでは、評価結果に納得がいかない場合の異議申立て制度も用意されています。企業はスコアカード公開前に評価内容に対する質問や修正依頼を出すことが可能で、EcoVadisのアナリストが再確認のうえ対応します。これにより評価プロセスの透明性と公正性が担保され、被評価企業との信頼関係も築かれています。
4.スコアカードとメダルの評価体系
EcoVadisの評価結果はスコアカード上でメダルランクとしても表彰されます。メダルにはブロンズ・シルバー・ゴールド・プラチナの4段階があり、総合スコアの順位(パーセンタイル)に応じて以下のように付与されます。
プラチナ(Platinum): 評価対象全企業中 上位1% に入った企業に授与(99パーセンタイル以上)
ゴールド(Gold): 上位5% に入った企業に授与(95パーセンタイル以上)
シルバー(Silver): 上位15% に入った企業に授与(85パーセンタイル以上)
ブロンズ(Bronze): 上位35% に入った企業に授与(65パーセンタイル以上)
例えば総合スコアが全企業中90位(トップ10%)であればシルバーメダル相当となります。実際には各メダルのボーダーは年次で微調整される場合がありますが、2024年時点では上記基準が適用されています。プラチナ評価は特に難易度が高く、持続可能性先進企業の証しとして国際的にも注目されます。日本では花王グループ企業やエプソンなどがプラチナを獲得した実績があります。
各種コメント
スコアカードにはメダルの他、各テーマ別の詳細得点と「強み・改善点」のコメントが記載されます。企業はこのフィードバックを基に、次回評価に向けて弱点を補強する計画を立てることができます。なおスコアカードの有効期間は1年間で、継続して高ランクを維持するには毎年評価を更新し続ける必要があります。したがって企業は一度高評価を得ても安心せず、次回評価に向けた持続的な改善努力が求められる点に留意が必要です。
まとめ
EcoVadisの評価基準は非常に体系立てられており、網羅的な質問と厳格なエビデンス審査によって企業のサステナビリティへの取り組みを定量評価します。そのスコア算出方法やメダル判定も透明性が高く、結果は企業の課題発見と改善に直結する有益な情報となります。評価される企業側は、評価内容を正しく理解し、自社のCSR活動強化に活かすことで、持続可能な経営水準の底上げにつなげていくことが重要です。
引用ecovadis公式
https://ecovadis.com/ja/