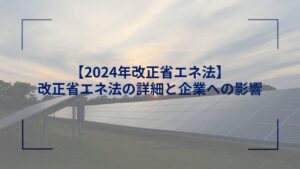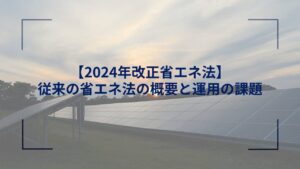1. 食品サプライチェーンが抱える排出の全体像
食品業界は、原材料の生産から加工・流通、消費、さらには廃棄・リサイクルに至るまで、極めて広範なサプライチェーンを持っています。とりわけ農業・畜産・水産分野では、土地利用や肥料・飼料の投入、家畜の消化過程で発生するメタンなど、多様な温室効果ガスが排出されます。食品メーカーが自社工場で削減努力を重ねても、サプライチェーン全体に占めるScope1とScope2の割合は一割にも満たないのが一般的であり、実際には調達段階や消費段階を含むScope3が総排出量の九割前後を占めるケースが珍しくありません。したがって、カーボンフットプリント(以下CFP)を正確に把握するためには、農場から食卓に至る「ファーム・トゥ・フォーク」の全工程を視野に入れたライフサイクルアセスメント(LCA)が欠かせません。
2.規格とガイドラインの位置付け
製品単位の排出量算定にはISO 14067が国際的な拠り所となります。
ISO 14067
ISO 14067はライフサイクル全体を対象に、算定境界やデータ品質、報告書作成のポイントを示しており、多様な食品製品にも適用可能です。ただし食品特有の変動要因 -気象条件による収穫量の差異、畜産における飼料配合変更、シーズンごとの生産地域移動などはISOだけでは詳細に定義されていません。そのため、国連食糧農業機関(FAO)のLEAPガイドラインや、国際食品LCAコンソーシアムのPCR(製品カテゴリルール)、さらには各国農業省が公開する排出係数集などを組み合わせ、品目別に妥当な前提を設定する必要があります。
サプライチェーンCO₂算定ガイドライン
国内では農林水産省が「フードサプライチェーンCO₂算定ガイドライン」を整備し、農作物・畜産品を対象とした排出係数の標準化を進めています。企業は国際規格のフレームワークを土台に、こうした補助的ガイドラインを参照しながら、自社商品のCFPを算定・開示する流れが主流になりつつあります。
3.データ収集の難所と解決策
食品業界における第一の課題は、原材料生産段階の一次データ不足です。
1次データ
農家や漁協は排出量報告の義務を負っていない場合が多く、肥料投入量や温室効果ガス排出に関する詳細なモニタリングも限定的です。したがって、企業は統計データやメタ解析に基づく代表値を使わざるを得ない局面が頻繁に生じます。こうした不確実性を低減するには、主要原料を産地別に区分し、サプライヤーと協働して土壌改良・飼料転換・省エネ機器導入などの実地調査を行うことが有効です。対象農場を抽出してサンプル分析を重ね、係数のアップデートに活かす手法はいわゆる「デジタルMRV(計測・報告・検証)」の先駆けと位置付けられます。
加工・製造段階
蒸気ボイラーや冷凍冷蔵設備のエネルギー消費が主な排出源となります。最新の工場管理システムでは、ラインごとに電力・蒸気流量をリアルタイムで計測し、品種別エネルギー原単位を自動算出する機能を備えるものも増えてきました。これにより製造工程のCFP算定精度は飛躍的に向上しています。
流通段階
低温物流の拡充に伴い、倉庫・トラック・コンテナの複合輸送が温室効果ガス排出に与える影響が大きくなります。輸送距離、積載率、アイドリング時間などの変動要素を踏まえた排出量計算は煩雑ですが、物流データプラットフォームを使って拠点間輸送の詳細データを取得し、ルート最適化と合わせて排出量低減策を検討する企業が増加しています。
4.消費・廃棄段階をどう扱うか
食品の消費段階排出は、家庭・業務用での調理エネルギーや冷蔵保管時の電力消費が中心となります。これをCFPに含めるかどうかは製品戦略に依存しますが、近年は「食べ方」や「保管方法」まで含めた環境影響情報を消費者に提供する動きが活発です。例えば冷凍食品メーカーがパッケージに「電子レンジ調理時のCO₂排出量」を併記し、湯煎より電子レンジ利用を推奨することで排出削減を訴求するケースがあります。また、廃棄段階では食品ロス削減と有機性廃棄物のメタンガス化対策が大きなテーマです。企業は賞味期限延長技術やリパッケージ、バイオガス施設との連携などで廃棄由来排出を低減し、CFPの最終値を押し下げる仕組みづくりを進めています。
5.算定プロセスの実際
算定手順は大きく五つのフェーズに分かれます。
第一フェーズは目的と範囲の設定です。ここでは「製品一単位あたりの排出を把握し消費者に開示する」「取引先からの要求に対応する」など明確な目標を掲げ、システム境界を定義します。第二フェーズはデータ収集で、原料投入量、エネルギー使用量、輸送実績、廃棄率などをできる限り一次情報で集め、信頼性を高めます。第三フェーズがLCA解析であり、投入・産出フローを整理し排出係数を当てはめ、ライフサイクルの各段階ごとにGHG排出量を算出します。第四フェーズは結果の統合と検証です。ここでは感度分析を実施し、特定の前提値を変更した際の振幅を検討するほか、第三者機関によるISO 14064-3準拠の検証を受けることで透明性を担保します。最後の第五フェーズでは、算定結果をステークホルダー向けに報告し、削減計画へ落とし込みます。ここで重要なのは、単なる情報開示に留まらず、排出源分析を通じて優先度の高い削減策を抽出し、サプライヤーや物流事業者を巻き込んだ改善サイクルを回すことです。
6.進む開示義務と消費者ニーズ
EUのCSRD(企業サステナビリティ報告指令)は2028年までに多くの非EU企業にも食品サプライチェーン排出の開示を求める予定であり、日本でも金融庁がIFRS S1/S2を基準とした開示項目を策定中です。こうした規制の後押しに加え、消費者の環境意識向上がCFP情報の需要を押し上げています。調査会社ニールセンIQの最新レポートでは、Z世代の65%が「食品を購入する際に炭素ラベルを参考にしたい」と回答しており、CFPをマーケティング要素として活用する余地が広がっています。
7.事例にみる競争優位の可能性
大手飲料メーカーは、コーヒー豆の調達段階で排出量最大三〇%の削減が可能であることをCFP算定で把握し、産地と連携して日陰栽培への転換、バイオ炭施肥プログラムを共同実施しました。それにより排出量削減にとどまらず、豆の品質向上と生産者の収入増にもつながり、ブランド価値が上昇しました。また、冷凍食品メーカーは包装サイズの最適化とルート配送網の見直しで物流起因排出を一五%削減し、商品のCFPラベル掲載によって小売バイヤーとの取引成約率を高めています。これらの事例は、CFP算定が単なる環境対応のコストセンターではなく、原価低減やブランド強化を通じて競争優位を生む戦略的ツールであることを示しています。
8.今後の展望と企業が取るべきアクション
食品業界においてCFP算定の高度化は不可逆的な潮流です。まず、自社原料の排出係数を随時更新可能なデータプールを整備し、サプライヤーとリアルタイムで共有できるプラットフォームを構築することが求められます。次に、農場・工場・物流・小売の各段階でIoTセンサーを導入し、デジタルMRVを実装することで、従来ブラックボックスだった排出源を可視化し、削減施策をスピーディに検証する体制を整える必要があります。
排出量の見える化
また、CFPラベルの消費者認知が拡大する中、コミュニケーション戦略として「排出量の見える化」を積極的に取り入れ、環境配慮型商品の価値を訴求することが差別化につながります。さらに、規制動向に合わせてTCFDやISSBの開示フレームワークへの統合を進め、投資家や金融機関との対話において裏付けあるデータを提示することが資金調達面の優位性を生むでしょう。
食品業界のカーボンフットプリントは今後、企業経営の指標としてますます重みを増します。排出量を測定し、削減策を実行し、その成果を評価・公開する一連の循環を確立できる企業こそが、サステナビリティと収益性を両立させ、未来の市場をリードする存在になるのではないでしょうか。
引用
GHG Protocol “Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions
https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf?utm_source=chatgpt.com
FAO LEAP Partnership “LEAP Guidelines
https://www.fao.org/partnerships/leap/resources/publications/fao-leap-guidelines/en?utm_source=chatgpt.com
3Degrees “What are Scope 3 emissions and how can you manage them?
https://3degreesinc.com/insights/what-are-scope-3-emissions-and-how-can-you-manage-them/?utm_source=chatgpt.com