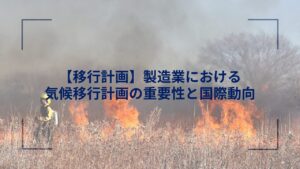企業が報告する温室効果ガス排出量の信頼性を高める手段として第三者保証(第三者検証)があります。これは、前述したScope1,2,3の算定結果について、独立した専門機関が検証を行い、「適正に算定・報告されている」ことを保証するプロセスです。ここでは第三者保証の概要とその手法、実施までの流れについて詳しく説明します。


1. 第三者保証の目的とメリット
第三者保証(Third-party assurance)とは、企業自身ではない第三者(一般には公認会計士や認証機関)が、企業のGHG排出量報告を審査し、データの正確性・網羅性・透明性にお墨付きを与えることです。その主な目的とメリットは以下の通りです。
データ信頼性の向上
第三者のチェックを経たデータは、信頼性が飛躍的に高まります。
企業による自己申告だけでは、「見たい数字に寄せていないか」「ミスがないか」という疑念が残る可能性がありますが、独立機関の検証によって誤りや不正のリスクが大幅に低減します。その結果、投資家や顧客、社会は報告値を安心して受け取ることができ、企業への信頼が増します。
規制や枠組みへの対応
海外を中心に、企業の気候関連開示に保証を付けることが求められる動きがあります。例えばEUのCSRD(サステナビリティ報告指令)では開示情報への保証が義務化の方向です。またCDPではScope1,2,3に第三者検証が付いている企業にスコア加点します。こうした規制・評価に対応するため、第三者保証は事実上必須になりつつあります。
ESG評価・資金調達での有利性
第三者保証を受けている企業は、ESG投資家からの評価が高まる傾向にあります。なぜなら保証付きデータは環境パフォーマンスの信頼できる証左だからです。また、グリーンボンド発行時やサステナビリティリンクローン契約時にも、GHGデータの保証が求められるケースがあります。信用力向上に繋がり、市場競争力の維持・向上に寄与します。
内部改善への寄与
検証プロセスで専門家から指摘・助言を受けることで、データ管理体制の弱点や算定上のミスが明らかになります。企業はそれを改善し、翌年以降より精度の高い算定が可能になります。また、保証人から見た第三者の視点を知ることで、排出削減目標の進捗や課題を客観視でき、気候戦略の見直しに役立つ場合もあります。このように第三者保証プロセス自体が企業の温室効果ガスマネジメントを成熟させる効果があります。
以上の理由から、現在多くの先進企業が毎年のGHG排出量(特にScope1,2)に第三者保証を付与しています。日本においても、大企業の環境報告書では保証付きが一般的になりつつあります。
2. 第三者保証の範囲と基準
第三者保証を行う際には、その範囲(Scope)と基準を明確に定めます。
保証の範囲
例えば「2024年度のScope1およびScope2排出量(CO2, CH4, N2O)」のように期間・対象ガス・対象範囲を特定します。Scope3まで含めるか、含めるとしてどのカテゴリまでかも決めます。一般的にはまずScope1,2が保証範囲に入り、大きなカテゴリ3やカテゴリ11など主要なScope3も含める企業が増えています。
保証のレベル
先に少し触れましたが、保証には限定的保証(Limited assurance)と合理的保証(Reasonable assurance)の2段階があります。限定的保証はチェックのサンプル数などを絞り「特に問題は見つからなかった」というネガティブ保証(消極的表明)です。一方、合理的保証は監査に近い徹底検証で「ほぼ正確である」というポジティブ保証(積極的表明)を行います。多くの企業はコスト等の理由から限定的保証を採用していますが、近年は合理的保証を目指す動きもあります。
適用する基準
検証をどの標準/基準に則って行うかを決めます。
代表的な国際基準には、
ISO 14064-3
温室効果ガスの検証プロセスに関するISO規格。日本ではこのISOに基づく検証報告書がよく使われます。
ISAE 3410
国際監査保証基準の3410号「GHG声明に対する保証業務」。監査法人系がこの基準で保証報告書を発行します。
AA1000AS
AccountAbilityが定めるサステナビリティ保証基準。GHGのみでなく全般的なCSR情報保証に用いる枠組みですが、GHGにも適用可能です。
国内ガイドライン
日本独自には環境省が「GHG検証・認証ガイドライン」を策定しています。また業界団体が独自基準を持つケースもあります。
基準を明示することで、どういった手順・原則で検証したかがわかります。例えばISOなら透明性・関連性・完全性・正確性などの原則に基づき検証しています、という説明が付きます。
3. 第三者保証の実施プロセス
第三者保証(検証業務)は、大まかに次のようなステップで進みます。
検証計画の策定
検証機関と契約を結び、まず初めに企業から算定結果の概要や算定プロセスの説明を受けます。検証チームはそれを基に、重点的に確認すべきポイント(例えば排出量の大部分を占める工場や、計算ルールが複雑なScope3カテゴリなど)を洗い出し、検証アプローチを計画します。ここではリスク評価に基づきサンプリング計画も立てます。
データ提供・書面審査
企業側は算定に用いたデータ一式(活動量データ、計算シート、使用した排出係数や資料根拠など)を検証人に提出します。検証人はそれらを精査し、数値に飛び抜けた異常値がないか、計算は指針通りか、基礎データと報告値がトレースできるか、といった書面でのチェックを行います。疑問点があれば質問事項としてまとめられ、企業に問い合わせがあります。
現地訪問(オンサイト検証)
必要に応じて、検証チームが実際に事業所や工場などを訪問します。現地では、エネルギー計量システムの様子や、データ記録の原本(電力使用量のメーター値や請求書、燃料納入伝票など)を確認し、提出されたデータとの一致を確かめます。また担当者へのヒアリングにより、算定境界に漏れがないか、運用上のミスがないかも検証します。
例えば「ここには非常用発電機があるが燃料使用を計上していますか?」などの確認です。現地調査は全拠点でなく主要拠点をサンプリングして行われます。
不備修正・追加資料対応
検証の過程で、もしデータの不備や誤りが見つかれば、企業に対して修正が求められます。例えば単位換算ミスや一部未集計のデータが判明した場合、企業側は速やかに再集計し修正版データを提出します。また、エビデンスが不足していた部分について追加資料を提出するなど、キャッチボールが行われます。この過程で疑義事項がすべて解消され、合理的に正しいと判断できれば次のステップに進みます。
保証報告書の作成・発行
検証チームは最終的な検証結果をまとめ、経営者宛の保証報告書(Assurance Statement)を発行します。報告書には、検証の範囲・基準・手続きの概要と、意見(Conclusion)が記載されます。限定的保証の場合、「我々の検証で重大な虚偽表示は認められませんでした」といった表現になり、合理的保証なら「適正に報告されているものと意見します」とポジティブ表現になります。また、Scope3を部分保証した場合はその旨明記されます。企業はこの保証書をそのまま報告書に掲載したり、Web開示します。検証期間はデータ規模により様々ですが、大企業で1~3ヶ月程度が一般的です。年度決算監査と並行して行われることも多く、財務監査と連携して効率化する例もあります。
4. 検証機関がチェックする主なポイント
第三者検証において、検証人が重点的に確認するチェックポイントをいくつか挙げます。
組織境界の妥当性
どこからどこまでの事業・拠点を含めたか。連結範囲と照合し、漏れている子会社や事業がないかを確認。
算定範囲・カテゴリーの網羅性
Scope1,2,3で報告すべき対象が全て含まれているか。特にScope3は算定対象を選択している場合、その選択理由が合理的か(排出量が小さいカテゴリを省略していないか)をチェック。
基準適合性
算定方法がGHGプロトコルや各種ガイドラインに沿っているか。例えば電力排出係数は所在地国の公表値を使っているか、Scope2はロケーション・マーケット両方計算しているか、GWPsは最新版か等。
データの完全性・正確性
活動量データが一次資料(メーター記録や請求書)から正しく集計されているか、ヒューマンエラーがないか。エクセル計算式の検算や、データ転記漏れの有無チェック。
期間整合性
データがちゃんと対象年度(会計年度等)に対応しているか。月ずれや重複計上が起きていないか。
推計の合理性
推定やサンプリングで算定している部分について、その手法や前提が妥当か。業界平均などの使用は根拠出典を確認。
比較検討
前年値や他社値と比較して不自然な乖離がないかを俯瞰チェック。大きな増減には企業に理由説明を求め、その説明が合理的か検証。
再計算ポリシー
過去年度算定方法変更時の遡及修正ルールや、組織変更時のベースライン調整ルールが決まっているか。SBT目標などがある企業は重要。
これらのチェックを経て、整合性が取れていれば「保証可能」となります。もし重大な欠陥が発見され企業が修正に応じない場合、保証範囲から外すか意見不表明となる可能性もありますが、実際にはほとんどのケースで修正対応がなされます。
5. 第三者保証報告書の読み方
最後に、実際に発行される第三者保証報告書(意見書)の内容について触れておきます。典型的な保証報告書には以下の項目が含まれます。
対象
「当社の2024年3月期におけるScope1, Scope2および一部Scope3排出量」
基準
「GHGプロトコルおよび環境省ガイドラインに準拠」
保証レベル
「限定的保証」
手続き
「算定過程のインタビュー、リスク評価、データ突合、現地調査(主要工場)等の手続きを実施」
結論(意見)
「我々は上記対象について検証を行った結果、重大な虚偽の表示が認められないとの結論に至った」
強調事項
必要に応じ、「Scope3は推計に依拠しており不確実性が高い」等のコメントや、良好事例として「目標達成に向けた内部統制がしっかりしている」等の所見が書かれることもあります。
発行者情報
検証会社名、責任者サイン、発行日。
この報告書を確認することで、どの範囲が保証済みか、どの基準に則ったかが第三者にも分かります。報告書の有無や内容はCDP回答や統合報告書の信頼性評価に大きく影響します。
以上、第三者保証の詳細を解説しました。要約すれば、第三者保証は企業のGHG排出量データに対する「信頼の保証書」です。適切なプロセスで検証を受けることで、企業は透明性の高い情報開示を実現し、投資家や顧客からの信頼を獲得できます。脱炭素経営を推進する上で、自社の取り組みや成果を正当に評価してもらうためにも、第三者保証は今後ますます重要性を増していくと予想されます。
引用先
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.5.0
https://www.env.go.jp/press/press_02717.html
サプライチェーン排出量算定に関する基本ガイドライン Ver.2.7(2025年3月)
https://chatgpt.com/c/681f0504-1d30-800d-9941-fc9bcfc3788c
1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド Ver.1.0(2025年3月)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/1ji_data_v1.0.pdf
排出原単位データベース(環境省 Green Value Chain Platform)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/