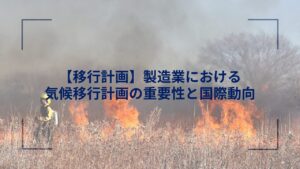Scope3の下流に分類されるカテゴリ9~15について、それぞれの定義と算定アプローチ、管理上のポイントを詳しく解説します。下流カテゴリは自社が提供した製品・サービスが市場で使われたり、最終処分されたり、あるいは投資によって引き起こされる排出であり、顧客や投資先など事業のアウトプット側に起因する排出となります。


1. カテゴリ9 輸送・配送(下流)
自社の出荷後に発生する輸送・流通に伴うGHG排出です。典型的には、商品を卸売業者から小売店へ配送するトラック輸送、流通倉庫での商品保管に伴う電力消費、小売店舗での商品陳列にかかるエネルギーなどが該当します。また広義には、消費者が店舗まで商品を買いに行く際の交通も含まれ得ますが、一般にはそこまで詳細には算定しません。
対象例
メーカー→卸→小売店への配送(自社がメーカーとして負担しない場合)。
小売店での商品保管時の冷蔵・冷凍設備エネルギー(ただし店舗運営そのものはカテゴリ11やフランチャイズカテゴリ14に近い考え方)。
Eコマース企業なら、配送センターから顧客宅への配達(宅配便)に伴う排出。
算定方法
基本的にカテゴリ4(上流輸送)と同じ方法論を適用できます。すなわち、輸送区間ごとの貨物輸送量または輸送距離 × 排出原単位で計算。もしくは物流業者から提供される配送CO2データを集計。
自社が直接関与しない配送も多いため、推計が中心になります。例えば、自社製品○トンが小売店まで輸送される想定で、平均輸送距離×トン数×輸送係数で算出します。また、流通倉庫での電力使用などは、その倉庫の床面積当たりエネルギーから自社製品が占める比率を割り当てるといった手法も考えられます。
留意点
自社がコントロールできる配送(自社負担の配送)はScope1,2またはカテゴリ4に入っている場合があるため、カテゴリ9ではそれ以降のフェーズを対象とします。例えば工場→倉庫の輸送はカテゴリ4、倉庫→店の輸送はカテゴリ9など明確に切り分けます。
Eコマース企業ではカテゴリ4と9の切り分けが曖昧になりがちなので、全配送を一括でScope3輸送として報告し「上流/下流の区別なし」とすることもあります。店舗や倉庫のエネルギー使用は厳密には輸送ではないですが、GHGプロトコル上はカテゴリ9に「流通(Distribution)」も含むため、商品保管・陳列のためのエネルギーも含めて良いです。ただ店舗運営全体はカテゴリ11やフランチャイズ14にまたがるので二重計上に注意します。
カテゴリ9の削減策としては、流通効率の向上が挙げられます。上流物流と同様、モーダルシフトや共同配送の拡大、配送ルート・荷姿の最適化による輸送回数減少、などが有効です。また、自社製品の流通チャネルをシンプルにする(中間流通業者を減らす)ことも輸送総量を減らすことにつながります。ただし、多くは自社外の活動なので、自社単独ではコントロールしづらい領域です。
2. カテゴリ10 販売した製品の加工
自社が販売した中間製品や部品が、他社によってさらに加工・組み立てられる際の排出です。主にBtoB企業に関連するカテゴリであり、自社製品(中間財)が顧客企業の工場で使用される際のエネルギー消費やプロセス排出を意味します。
対象例
素材メーカーが出荷したスチール板を、自動車メーカーがプレス加工・溶接する際の排出。
化学メーカーが出荷した樹脂ペレットを、成形メーカーが射出成形するときの電力使用による排出。
半導体メーカーが販売した半導体を、電子機器メーカーがプリント基板実装するときのハンダ付け工程の排出。
算定方法
顧客側のプロセス情報が必要になるため難易度は高めです。アプローチは、可能であれば顧客企業からエネルギー使用量データをもらう。例えば自社材料○kgを加工する際に電力△kWh使った、といった情報。
難しければ、業界平均データで推計。例えば「鉄板1トンをプレス加工するのに必要なエネルギー量」を文献から調べ、それを自社販売量に乗じます。LCAデータベースに「中間製品Xを最終製品Yに加工するプロセス」単位プロセスが載っていれば、それを使うこともできます。
具体例
自社がタイヤ向けゴム材料を1000トン販売→タイヤメーカーでの加工排出を推計。文献より「タイヤ1本(10kg)の製造エネルギー=50 MJ、CO2換算約3kg」と知れば、1000トン=100万kg分のタイヤ10万本相当 → 排出=3kg*10万=300トンCO2と推定する、など。
留意点
自社製品がどのように使われるかを把握する必要があります。同じ素材でも顧客によって加工工程が違う可能性もあります。その場合主要用途ごとに分けて算定します。最終製品が輸出されている場合、加工場所が海外になりエネルギー事情も異なるでしょう。その点まで考慮するのは困難なので平均値で計算せざるを得ません。カテゴリ10と11(製品使用)の境界は明確です。カテゴリ10は企業が顧客(事業者)による加工、カテゴリ11は最終消費者による使用です。
カテゴリ10は、素材・部品メーカーが顧客企業と協働して削減に取り組む余地があります。例えば、自社素材が加工しやすいよう改良し、顧客側の加工温度を下げてエネルギー削減につなげる、といったエコな提案です。また、顧客に省エネ設備を紹介するなど間接的支援も可能でしょう。もっとも削減分は顧客側のScope1,2に表れるため、自社のScope3削減としては表に出づらいジレンマはあります。
3. カテゴリ11 販売した製品の使用
自社が販売した最終製品が使用される際に排出されるGHGです。これはScope3の中でも非常に重要なカテゴリで、特にエネルギー消費型製品を扱う企業(自動車、家電、電子機器、化石燃料等)では自社サプライチェーン排出の大部分を占めることがあります。
対象例
自動車メーカーの場合: ユーザーが車を運転する際に燃焼するガソリンからのCO2。
家電メーカーの場合: エアコン、冷蔵庫、テレビなどが使用される際の消費電力に伴う発電所のCO2。
IT機器メーカーの場合: データセンター等で自社製サーバーが稼働する際の電力使用に伴う排出。
石油会社の場合: ガソリンや天然ガスなど販売した燃料が顧客により燃焼される際のCO2(これは化石燃料由来CO2なのでScope3でも最大級の排出源になります)。
算定方法
製品ごとに使用段階の排出量を見積もります。ポイントは、「どのくらいの期間/頻度で使われ、その間にどれだけエネルギーや燃料を消費するか」をモデル化することです。
耐久消費財(車・電機等): 製品の平均寿命と年間使用量からライフサイクル全体の使用エネルギーを算定し、それにエネルギーの排出係数を掛けます。
例: 車1台=10年間で10万km走行、平均燃費15km/L → 燃料約6,667L消費 → CO2約15.5t排出(ガソリンCO2係数2.31 kg/L)と計算し、当年販売台数に乗じます。家電なら、例えばエアコン1台=1日8時間×年間120日×10年間=9600時間使用、平均消費電力1kW→総消費電力量9600kWh→CO2約4.3t(0.45 kg-CO2/kWh仮定)などとし、販売台数分積算します。
燃料等の使い切り製品: 顧客が購入後すぐ燃焼/使用する商品(ガソリン、天然ガス、石炭など)は、その燃焼排出量そのものがカテゴリ11排出です。単純に販売量×燃焼排出係数で算定します。これはScope1排出のスコープ外排出とも言われ、例えば石油会社のScope3カテゴリ11=顧客による燃料燃焼CO2です。
留意点
製品寿命や使用条件の仮定は慎重に設定します。実態調査や統計データがあればそれを使い、なければ業界標準の値(例えば乗用車平均走行距離など)を用います。SBTなどでは「平均的使用時シナリオで見積もること」とガイドされます。
エネルギー排出係数は将来変動しうる(電力のCO2係数は将来下がる可能性など)ため、寿命全期間を現在の係数で計算すると過大になるかもしれません。しかしGHG算定上は基本現行の係数で計算します。科学的には将来のグリッドクリーン化を加味してもよいですが、そこまでのルールはないのが現状です。製品からの間接GHGも場合によっては含めます。
例: エアコンの冷媒が使用中徐々に漏洩するなら、それはカテゴリ11のフロン排出として加算します。ただし通常フロン漏洩はScope1の他社排出扱いになるため任意です。
カテゴリ11は多くの企業にとって自社が提供する価値とトレードオフの関係にある排出です。特に自動車や化石燃料などは、この使用時排出をいかに低減する製品に転換するか(電気自動車への移行、代替燃料開発等)が脱炭素戦略の柱となります。また、電機メーカーも省エネ製品の開発競争が進んでおり、高効率家電・機器の普及がカテゴリ11削減に直結します。最近では「製品使用時排出を売上高あたりで何%改善」といった目標を掲げる企業も多く、まさにカテゴリ11は顧客とともに達成する脱炭素の象徴的領域です。
4. カテゴリ12 販売した製品の廃棄
自社の製品やその梱包材が使用後に廃棄・処理される際の排出です。製品そのものが寿命を迎えて捨てられるとき、あるいは使い終わったパッケージが捨てられるとき、それを処理する過程のCO2やCH4が該当します。
対象例
耐久消費財(車、電化製品)の廃棄処理:シュレッダー処理の電力、残渣の焼却などによる排出。
消費財(食品・日用品)の容器包装廃棄:プラスチック容器焼却CO2、紙パッケージ焼却CO2等。
製品のリサイクルに伴う排出も厳密にはありますが、通常廃棄カテゴリでは最終処分(焼却・埋立)由来だけ扱います。
算定方法
製品組成や廃棄シナリオから推計します。
製品の材質別重量を把握します。例えば自動車1台 = 金属1000kg, プラスチック100kg, ゴム50kg, ガラス20kg, その他30kg 等。
廃棄処理方法の想定
各材質がどの程度リサイクルされ、どの程度焼却/埋立されるか仮定します。上記自動車例だと金属80%リサイクル・20%埋立、プラ50%焼却・50%再資源化など。処理別排出量計算: 焼却部分→炭素含有量からCO2排出算定。
埋立部分→分解して発生するCH4のCO2換算量算定。リサイクル部分はゼロ(または別途考慮)。
製品1単位あたりの廃棄時排出を算出し、当該年の販売数量に乗じます。ただし、耐久財の場合、実際に廃棄されるのは販売から何年も後なので、その場で計上するか、年次排出として推計するかポリシーが分かれます(GHGプロトコル上は販売時に将来廃棄分も計上する)。
例えば、飲料メーカーが今年販売したペットボトル飲料1000万本について、1本当たりプラ重量30g、そのうち焼却率60%なら、焼却炭素排出0.09 kgCO2/本(仮)×1000万本=900tCO2と見積もる、など。
留意点
製品寿命が長いものは将来の廃棄排出を現時点で算定するため、不確実性があります。が、Scope3標準上は販売時点でフルライフサイクル考慮して報告することになっています。
実際の廃棄方法は地域・時代で変わるため、平均的シナリオを設定します。例えば先進国なら高リサイクル率、途上国なら埋立多め、など国別に検討する企業もありますが、多くは一律シナリオです。バイオ系素材(紙や木)は燃焼してもカーボンニュートラルとされ、CO2計上しません。ただ埋立時に発生するCH4は化石由来でなくとも温暖化寄与するためカウントします。製品に内蔵されていた冷媒や特殊ガスが廃棄時放出される場合も含めます(例えば冷蔵庫のフロン回収漏れによる排出)。
カテゴリ12の削減策は、製品の終末処理を見据えた設計とリサイクル推進です。例えば素材をリサイクルしやすくする、解体容易にする、バイオ由来素材にすることで焼却してもネットゼロCO2にする、といったDesign for Environmentが求められます。また、自社製品のリサイクルプログラム(回収してリサイクル)を展開すれば廃棄時排出削減につながります。こうした循環型経営の取り組みは、Scope3削減と資源循環の一石二鳥の効果があります。
5. カテゴリ13 リース資産(下流)
自社が貸し出した資産(リース、レンタル提供したもの)の使用に伴うGHG排出で、Scope1,2に含めていないものです。つまり、自社がオーナーで他社(顧客)が使用する資産からの排出を、自社のScope3として計上します。
対象例
自動車メーカーのファイナンスリース車両:ユーザーが運転して出す排ガスCO2はカテゴリ13。
IT機器レンタル会社:貸与中のサーバー機器が消費する電力起源CO2。
不動産会社:テナントに賃貸している建物で消費されるエネルギーのCO2(ただしフランチャイズとの境界注意)。
算定方法
基本的にカテゴリ11(製品使用)と同じ考え方で、その資産の使用時排出を計算します。ただし対象は自社オーナーの資産のみです。
例えば、リース車両なら走行距離や平均燃費からCO2算定(自動車メーカーであればカテゴリ11との二重計上に注意。通常、自社製品であっても貸し出した分はカテゴリ13に振り替え、11から控除します)。
賃貸建物なら、テナントの光熱費に基づきCO2算出。テナント個別のデータがなければ建物全体のエネルギーのうち賃貸部分割合で按分したりします。
注意点
このカテゴリ13は、自社が資産オーナーである点がポイントです。もし単に自社製品を販売しただけならカテゴリ11に入りますが、リース契約等で貸し出している場合は、使用排出がこちらに来ます。バウンダリ基準によりますが、会計的にはオンバランスのリース資産です。運用上Scope1,2に入れていない理由は、オペレーションコントロールが自社にないから、といった判断でしょう。GHGプロトコルでは両方式認めていますが、二重計上にならないよう一貫性を持って決めます。
賃貸不動産の場合、フランチャイズ(カテゴリ14)かリース資産(カテゴリ13)か迷うことがあります。自社ブランドで運営されるフランチャイズ店なら14、単純にオーナーとして貸しているだけなら13です。カテゴリ13の削減は、貸出資産自体の省エネ化・高効率化です。例えばレンタカー会社なら低燃費車やEV車を貸し出す割合を増やす、不動産会社なら省エネビル(断熱強化や高効率設備導入)を建設してテナントのエネルギー需要を減らす、といった策です。また、リース契約時にユーザーに対し省エネ運用を促すガイドラインを提供するなど、貸し手としての責務を果たす動きも考えられます。
6. カテゴリ14 フランチャイズ
自社がフランチャイズチェーン展開する事業において、加盟店の事業活動から排出されるGHGが対象です。フランチャイズ加盟店は法的には独立した企業ですが、自社ブランドの下で営業しているため、その排出も広義には自社のバリューチェーン排出とみなします。
対象例
ファストフードチェーン本部にとっての加盟店舗のエネルギー消費や廃棄物排出。
コンビニ本部にとっての加盟店店舗の電力・ガス使用。
塾フランチャイズ、本部にとっての教室運営に伴う排出など。
算定方法
加盟店それぞれのScope1,2排出を集計する形になります。具体的には、加盟店数、業態ごとの平均エネルギー使用量データ(例えば1店舗あたり年間○kWhの電力、○m3のガス等)を把握し、それに排出係数を掛け全店舗分算出。
可能であれば加盟店から個別の環境データ報告を受けて積み上げます。大手チェーンでは環境負荷データを本部集約しているところもあります。範囲としては、店舗の電気・ガス・燃料使用によるCO2、および店舗から出る廃棄物の処理CO2などを含めます(後者はカテゴリ12との関係ですが、加盟店の廃棄物はフランチャイズ運営上本部が関与度高ければ含めるケースも)。
留意点
フランチャイズ店舗は独立事業者なので、データ収集には本部の強い働きかけが必要です。環境報告協力を契約上義務化したり、システムで自動収集するなどの仕組みがあると望ましいです。直営店舗は自社Scope1,2に入っているので、フランチャイズカテゴリでは当然除きます。報告時には「直営店○店は自社Scope1,2に含む、加盟店×店分をカテゴリ14で算定」と明記すると透明性が高まります。
フランチャイズ事業では、本部がエネルギー効率基準や設備仕様を定めていることが多いです。したがって加盟店排出も本部次第で左右できる部分が多く、本部が率先して削減策を講じるべき領域と言えます。
カテゴリ14の削減は、加盟店と一体となった省エネ・削減活動です。本部が統一した省エネ機器(LED照明、インバーター冷蔵庫等)を加盟店に導入促進する、店舗スタッフ向けに省エネ研修を行う、さらには営業方針(例えば深夜営業短縮)を見直すことでエネルギー需要自体を下げるなどのアプローチがあります。また、本部が再生可能エネルギー電力を一括調達し加盟店に供給する仕組みを作れば、加盟店のScope2排出削減に大きく貢献できます。いずれにせよ、チェーン全体での協調した気候変動対策が重要です。
7. カテゴリ15 投資
企業が行う投融資先の活動に起因する排出、すなわち金融ポートフォリオから発生するGHG排出です。これは主に金融機関(銀行、保険、投資会社)向けのカテゴリですが、事業会社でも関係会社への投資などがあれば該当します。
対象例
銀行の融資先企業が出す排出(融資ポートフォリオの間接排出)、投資ファンドの出資先企業の排出、自社の持つ株式ポートフォリオの企業排出。
保険会社の運用資産に組み込まれた社債発行体やプロジェクトの排出。
一般事業会社が一部出資する関連会社(連結外)の排出。
算定方法: 金融資産ごとに、その投資先の排出量を按分して計上します。GHGプロトコルではカテゴリ15の算定について詳しく述べており、PCAFなどの標準も整備されています。
代表的な方法
株式投資
投資先企業のScope1+2排出量×(自社の持株比率)を計上。上場企業ならCDPやサステナビリティレポートから排出量データを取得可能。不明な場合、売上や業種から類推。
企業融資
融資先企業の排出量×(融資額/企業価値)で按分。企業価値には株式時価総額+負債を用いるなどします。これも相手企業の排出データ前提ですが、なければ業界平均を資産額比例で推計します。
プロジェクトファイナンス
プロジェクト自体の排出量×(ファイナンス額/プロジェクト総投資)で按分。例えば再エネ発電所なら建設・運営排出を按分計上。ただし再エネはむしろCO2削減に寄与するので、その扱いは議論があります。
社債保有
債券発行企業の排出量×(保有額/企業価値)で按分(基本は融資と同じ考え方)。
電力購入契約等(広義の投資ではないがPPP的なもの)はScope2で扱うので含みません。
事業会社の場合、例えば持分法適用会社(20~50%出資)の排出を持分比率で計上するケースがあります。GHGプロトコルでも、自社Scope1,2に含めない投資先はカテゴリ15で計上するよう推奨しています。
留意点
データ収集が最大の課題です。上場株式は情報がありますが、非上場や中小融資先は直接問い合わせるか推計に頼ることになります。ダブルカウントになりますが、投資家同士で重複計上は避けられません。Scope3は本来ダブルカウントしてもよい領域(それぞれのバリューチェーンに属する)なので問題ありませんが、同じ排出が複数の金融機関のScope3に計上される点は認識しておく必要があります。
投資ポートフォリオ全体のGHG強度(例えば投融資額1億円あたり排出量など)をKPIとして開示する例が増えています。これはカテゴリ15の結果をまとめて指標化したものです。
カテゴリ15の削減は、金融機関にとっては融資・投資先の脱炭素化支援とポートフォリオの組替えの二本柱です。高炭素産業への投融資を減らし、グリーン分野への投融資を増やすことでポートフォリオ全体の排出量を減らす戦略が取られています。また、既存投融資先に対しては、気候関連目標の設定を働きかけたり、技術支援・融資条件の工夫によって排出削減を促します。これはエンゲージメント投資とも呼ばれ、金融セクターの重要な役割となっています。事業会社にとっても、カテゴリ15は通常大きくはないですが、ESG投資の一環として自社の投資先について気候リスク評価を行い、必要に応じて脱炭素型にシフトすることが求められる時代になりつつあります。
引用先
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.5.0
https://www.env.go.jp/press/press_02717.html
サプライチェーン排出量算定に関する基本ガイドライン Ver.2.7(2025年3月)
https://chatgpt.com/c/681f0504-1d30-800d-9941-fc9bcfc3788c
1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド Ver.1.0(2025年3月)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/1ji_data_v1.0.pdf
排出原単位データベース(環境省 Green Value Chain Platform)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/