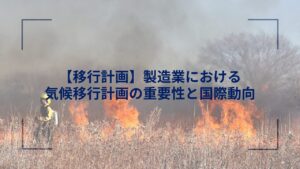Scope3のうち、サプライチェーン上流(アップストリーム)に分類されるカテゴリ1~8について解説します。これらは企業が調達・利用する製品やサービスに関連する排出で、サプライヤーや従業員の活動に影響されます。本記事では、Scope3カテゴリ1~8の定義、算定方法、削減策について紹介します。


1. カテゴリ1 購入した製品・サービス
自社が購入するすべての物品・サービスで排出されたGHGです。
原材料、部品、包装材、消耗品、オフィス用品、外部委託したサービス(例えば清掃サービス等)の提供に伴う排出も含みます。言い換えると、自社の支出に対応する相手先の排出を網羅するカテゴリです。多くのメーカーにとってこのカテゴリ1がScope3で最も排出量が多く、サプライチェーン全体のカーボンフットプリントの中核となります。
算定方法
基本式は「購入物量(または金額) × 排出原単位」です。
手法として大きく2つあります。
数量ベース算定
購入した各品目の数量や重量に、その生産に伴う排出原単位(例: 1kgあたりのCO2排出量)を掛けて積み上げる方法。
例えば、鉄鋼1000kg購入×製鋼時排出2.1 kg-CO2/kg = 2100 kg-CO2といった具合に計算します。必要な排出原単位は、製品ライフサイクルデータベース(IDEAやecoinventなど)や環境省の供給網排出原単位集から取得します。
金額ベース算定
購入金額に基づき、金額当たり排出原単位(経済投入産出表等から算出された産業平均値)を掛ける方法。
例えば「電子部品の購買100万円 × 電子部品製造業の排出原単位 5 t-CO2/百万円 = 5 t-CO2」と計算します。品目ごとに細かく数量データがない場合や、数が多い消耗品類などはこの方法を用いることがあります。
多くの企業では主要な原材料・部品については数量ベースで算定し、それ以外は金額ベースの粗い推計で網羅する、という組み合わせを行っています。重要なのは自社の調達品全体を漏れなくカバーすることです。また、サプライヤーから特定製品のカーボンフットプリント情報(一次データ)を直接入手できる場合は、それを使用して精緻に算定することもあります。
算定上のポイント・注意点
購買品を出来るだけカテゴリー別(原材料、包装材、設備、サービス等)に分類し、それぞれ適切な排出係数を当てはめます。一律の係数にしない方が精度が上がります。
設備投資による購入(資本財)はカテゴリ2との重複に注意します。通常、資本的支出はカテゴリ2、経常的な部品・材料購入はカテゴリ1に区分します。
自社グループ内からの調達品(社内取引)は、連結グループ全体で見ればScope1,2に計上済みの可能性があります。その場合Scope3では除外するか、重複を明示します。
購入した電力・燃料自体はScope3カテゴリ3やScope2で扱うため、カテゴリ1からは除きます。
サービス購入(例えばコンサル費用や清掃委託費用)も金額ベースで排出推計できます。産業連関表ベースの排出原単位に「サービス業」「専門職業」の係数があります。
カテゴリ1の排出削減には、主要サプライヤーとの協働が不可欠です。省エネや再エネ転換による製造時の排出削減努力を共有したり、低炭素素材への切替検討などバリューチェーン全体での取り組みが求められます。また、グリーン調達ガイドラインを策定し、調達先選定にCO2排出原単位の低さを考慮する企業も増えています。
2. カテゴリ2 資本財(設備・資産)
自社がその期に取得した資本財の製造段階での排出です。資本財とは繰延資産的に扱われる耐久財で、典型例は建物、建設資材、大型機械設備、生産ライン、車両、オフィス什器などです。カテゴリ1との違いは、減価償却資産となるような購入物はこちらに含める点です。会計上は設備投資として処理されるもの、と考えるとわかりやすいでしょう。
算定方法
基本的にはカテゴリ1と同様に、「購入した資本財ごとの数量または金額 × 排出原単位」で算定します。例えば、新工場建設に使用したコンクリートや鋼材の量にそれぞれの製造時排出係数を掛けます。または工場建設コスト○億円に建設業の排出原単位を掛ける、といった金額ベース推計も可能です。機械設備については、設備メーカーからLCA情報を入手できればそれを使います。情報が無い場合、機械重量や材質から推計したり、産業平均データ(機械製造業の排出原単位)を用いて計算します。
注意点
資本財は一度に大きな支出となるため、その年だけカテゴリ2排出が突出して多くなることがあります。経年比較する際は資本財購入の変動要因を注記するとよいでしょう。
リース資産の新規取得は、会計上オンバランスであれば資本財購入と同等に扱います。オフバランスのレンタル調達はカテゴリ1または8扱いとなります。原則として資本財は購入時点の最終年に計上します。つまり複数年かけて建設した場合も完成引渡し年にまとめて計上する形です。
減価償却期間に渡って按分計上する手法も理論上はありえますが、GHGプロトコル上は購入時一括計上とされています。その方が排出の発生年と対応するためです。
カテゴリ2は設備メーカー側の脱炭素化(製造時の省エネや素材転換)に依存します。自社で直接削減するのは難しい領域ですが、例えば木造建築や低炭素コンクリート採用など調達先の選択・仕様の工夫で間接的に削減できます。また将来的に、「製品のカーボンフットプリント情報を提供できるメーカー」から優先的に資本財を購入する、といった動きも広がるでしょう。
3. カテゴリ3 燃料・エネルギー関連の上流排出(非Scope1/2)
自社が使用した燃料やエネルギーに関して、Scope1およびScope2には含まれない上流工程での排出です。具体的には、使用燃料の採掘・精製・輸送で出た排出、使用電力を発電するための燃料採掘・精製排出および送電損失に伴う追加発電排出を指します。
例えば、自社で使ったLPGについて、その製造プラントでのエネルギー消費や輸送時の排出がカテゴリ3になります。
また購入電力についても、発電時の排出はScope2に計上済みですが、その発電用燃料(石炭・ガスなど)の採掘や精製に伴う排出、および送電中にロスした電力分を補うための発電排出がカテゴリ3となります。
算定方法
自社の燃料・電力使用量データをベースに、それぞれの上流排出原単位を掛けます。
ガソリン
使用量(L)× ガソリンの上流排出係数 (kg-CO2e/L)。
天然ガス
使用量(Nm<sup>3</sup>)× 採掘・パイプライン輸送の排出係数。
電力
使用量(kWh)× 電力上流係数 (発電用燃料採掘排出 + 送配電ロス分排出)。
日本では環境省の基本ガイドラインに、主要燃料・電力の上流排出係数が示されています。またGHGプロトコルのTechnical Guidanceや産油国のLCAデータ等からも取得可能です。例えば、ガソリン1MJあたり0.015 kg-CO2e程度の上流排出がある、といったデータが利用されます。
留意点
発電に伴う送電ロスは、単に使用電力量に一定率を上乗せして計算します。日本の送電ロス率(数%)などを考慮します。再生可能エネルギー由来の電力についても、上流排出はゼロではありません(太陽光パネル製造時の排出など本来含まれるべきですが、Scope3カテゴリ3では運用上の燃料がないためゼロと見做すのが一般的です)。したがってカテゴリ3は主に化石燃料使用量に比例した値となります。
カテゴリ3の排出削減は、根本的には化石燃料使用量の削減に他なりません。Scope1,2の直接排出を減らせば必然的に上流排出も減ります。また、燃料の調達先(例えば同じ天然ガスでも上流排出の小さいガス田から購入するなど)を選べれば効果がありますが、通常そこまでのコントロールは難しいため、削減策=エネルギー使用削減と考えて差し支えありません。
4. カテゴリ4 輸送・配送(上流)
自社が調達する物資の輸送や、自社間移送など上流サプライチェーン上の物流に係る排出です。自社のスコープ1に入らない輸送活動が対象となります。典型的には以下が含まれます。
調達物流
原材料や部品を仕入れる際に、サプライヤーから自社工場/倉庫までトラック輸送や船舶輸送が行われる場合の排出。
自社内物流
工場間・倉庫間の横持ち輸送で、他社に委託している分の排出(自社トラックならScope1)。
製品出荷物流(前半)
製品を出荷する際、顧客のもとに届くまでの輸送のうち、自社が費用負担する最初の区間(例えば自社倉庫から一次代理店倉庫まで)で他社輸送業者が排出する分。
算定方法
可能な限り具体的な物流データを用いて算定します。アプローチは2通りあります。
燃料ベース
委託物流業者から当該輸送に使った燃料量(または排出量)情報を提供してもらい、それをそのまま集計。または輸送距離・トン数から燃料消費量を推定。
距離×重量ベース
物流モード別(トラック、船舶、航空など)に貨物輸送量(トンキロ)を算出し、モード別の排出原単位(g-CO2/トンキロ)を掛ける。例: トラック輸送 500トンキロ × 150g-CO2/トンキロ = 75,000g = 75kgCO2。
自社で物流ネットワーク図を把握し、主要ルートについて距離と重量(または出荷量)を掛け合わせます。貨物重量が不明な場合、製品単位個数から換算したり、容量ベースを重量に換算するなど推計を行います。排出係数はトラック(積載率○%前提)、海上輸送、航空貨物、日本国内鉄道貨物など、一般的な値が環境省データなどで公開されています。
注意点
インコタームズによって、自社が負担する輸送と顧客が負担する輸送の境界が変わります。
小口配送や複合輸送など、細かいデータ取得が難しい場合はサプライヤーや物流業者からCO2排出報告書をもらう方法もあります。
カテゴリ4排出削減は、輸送効率化(積載率向上、輸送ルート短縮、輸送モード転換=例: トラックから鉄道・船舶へ)、燃費の良い車両の活用等によって実現できます。荷主として物流業者と連携し、共同配送や中継輸送の導入などで省エネ化する動きが進んでいます。また、調達先を地理的に近い企業に切り替えると輸送距離が減り排出削減につながるケースもあります。
5. カテゴリ5 事業から出る廃棄物
自社の事業活動で生じた廃棄物の処理に伴う排出です。工場廃棄物、事務所廃棄物ともに対象ですが、有価物(リサイクルに回されて収益が出るもの)は除外するのが通常です。含まれる排出は、廃棄物の焼却によるCO2、埋立によるメタン等です。
算定方法
廃棄物の種類ごとの年間排出量=「排出量(重量) × 処理方法別排出係数」の合計で求めます。
具体的手順は、
・廃棄物の種類ごとに年間発生量(処理量)を集計(産業廃棄物マニフェストや排出業者の月報などから、紙くず○ton、木くず○ton、可燃ごみ○tonなど)。
・それぞれの処理方法を把握(焼却、焼却発電、リサイクル、埋立など)。一部不明な場合、一般的な処理率で仮定。
・焼却処理される量×焼却の排出係数(kgCO2/ton)、埋立処理量×埋立の排出係数(CH4</sub>換算含むCO2e/ton)を計算。
リサイクルや堆肥化などCO2排出が少ない処理は基本ゼロカウント。ただしリサイクル工程のエネルギーはカテゴリ1や他社Scope1になるためScope3には入れません。
例えば、一般可燃廃棄物の場合は焼却されることが多いので「重量×焼却係数(プラスチックなら燃焼炭素分CO2、生ごみなら分解時CH<sub>4</sub>換算など)」を適用します。産業廃棄物(汚泥や金属くず等)は処理法で排出が異なるので個別係数を使います。廃棄物処理由来排出係数は環境省のデータやIPCCガイドラインに基づき設定可能です。例えば一般ごみ焼却1トン当たりCO2排出量、埋立1トン当たりCH4排出量(地域のメタン回収率考慮)など。
注意点
リサイクル(有価売却)された廃棄物は排出源ではなくむしろ資源回収なので、原則カテゴリ5には含めません。ただしリサイクル工程でエネルギー使用はあるため厳密には排出ゼロではありませんが、Scope3ではスコープ外扱いです。焼却時のCO2排出は、化石起源カーボンのみカウントします。木くずや紙などバイオ起源はカーボンニュートラルとします。排出係数は地域の廃棄物処理事情により差があります。日本の場合、多くの一般廃棄物は焼却されていますが、海外では埋立主体の国もあります。グローバル企業は国別に処理方法を推計するか、全社一律の仮定を置くことになります。
カテゴリ5の削減策は、廃棄物発生抑制とリサイクルです。廃棄物そのものを減量すれば処理時のCO2も減りますし、焼却ではなくリサイクルに回せばカテゴリ5からは除外できます(もっとも排出が他システムに移動するだけですが、資源有効利用の観点では有益です)。多くの企業がゼロエミッション(廃棄物埋立ゼロ)などを掲げていますが、これもScope3削減に寄与する取り組みと言えます。
6. カテゴリ6 出張
従業員による出張業務に伴うGHG排出です。具体的には、航空機、鉄道、バス、レンタカー、自家用車利用など、出張移動手段の燃料起源CO2が中心です。宿泊に伴う排出(ホテルのエネルギー使用)を含める場合もありますが、通常Scope3では移動に伴う排出のみを対象とすることが多いです。
算定方法
出張の旅程データから算定します。
方法は2つのステップです。
活動量の取得
出張の移動距離または輸送手段ごとの利用量を集計。社内の出張精算システムや travel agency から年間の出張一覧を取得し、フライト区間・本数、新幹線区間・本数、車利用距離 等をまとめます。もし詳細データがなければ出張費用を手がかりに推計(例: 航空券代合計から大まかな距離を推定)することもあります。
排出量計算
それぞれの移動手段に対し、移動距離あたり排出係数を掛けます。例えば航空機なら1人1kmあたりのCO2(クラスや距離帯で異なる)を掛け、鉄道なら電力由来CO2係数を掛け、自動車移動なら車種平均燃費からCO2換算します。航空機は距離帯別係数(長距離ほど座席あたり効率良い)や座席クラス(エコノミー vs ビジネスで占有面積が違う)を考慮します。自家用車出張は走行距離 × 車の燃費 × 燃料排出係数で算出します。
例: 東京-大阪の出張(新幹線)往復=500km × 0.02 kg-CO2/人km ≈ 10kgCO2、東京-ニューヨーク出張(飛行機往復)=約20,000km × 0.11 kg-CO2/人km (長距離エコノミー係数) ≈ 2.2 tCO2 といった計算になります。
注意点
日当や宿泊の排出(ホテルでの電気・暖房)は算定対象外にすることが多いですが、包括的に「出張」の排出と考える場合、宿泊1泊あたりのCO2(ホテル業の平均値など)を掛けるケースもあります。業務上の社用車運転はScope1に含まれるので、ここでは社員が自家用車やレンタカーで出張した場合のみを対象にします。
飛行機の放射強制力指数(RFI)による上乗せ(高高度排出の影響)については、GHGプロトコル上は考慮任意です。多くの企業はCO2のみで計算していますが、先進企業はRFI=2倍など係数を掛けて報告する場合もあります。
カテゴリ6の排出は、出張規模を減らすことが直接の削減策です。昨今はオンライン会議の普及で出張自体を削減でき、カテゴリ6排出も大幅に減った企業が多くあります。また必要な出張でも、近距離は鉄道に切り替える(飛行機より排出が低い)、カープールや公共交通を使うなど移動手段の工夫で削減可能です。一部企業では社員にカーボンオフセット出張(出張時に排出枠購入で相殺)を推奨する動きもあります。
7. カテゴリ7 雇用者の通勤
従業員が通勤する際の交通手段から発生するGHG排出です。自家用車・バイク通勤、バス・電車通勤、それぞれの燃料や電力消費に伴うCO2が該当します。出張と異なり日常的な移動です。
一般的な手順と算定方法
通勤手段と距離のデータ収集
社員アンケートや人事部門の通勤手当申請情報から、各社員の通勤手段(車/電車/バス/自転車/徒歩など)と片道距離、通勤日数(週何日)を取得します。全社員分困難ならモデル社員で推計したり、平均値×社員数で概算します。
排出量計算
交通手段別に排出係数を掛けます。自動車通勤者については「片道距離×2(往復)×年間勤務日数 × 車のCO2排出係数(kmあたり)」を計算します。公共交通については「鉄道利用者延べ人数×平均通勤距離×鉄道CO2係数」「バス利用距離×係数」等で算定します。鉄道やバスのCO2係数は旅客1人キロ当たりCO2排出量として国土交通省などが公表しています。自転車・徒歩は排出ゼロ扱いです。
例えば、社員100人の会社で、車通勤20人(平均片道10km)、電車通勤50人(平均片道20km)、バス通勤10人(平均片道15km)、残り20人徒歩/自転車だとします。車: 20人×(102240日)×0.2 kg-CO2/km = 20×4800×0.2 = 19,200 kgCO2、電車: 50人×(202240)×0.03 kg-CO2/km = 50×9600×0.03 = 14,400 kgCO2、バス: 10人×(152240)×0.1 kg-CO2/km = 10×7200×0.1 = 7,200 kgCO2、合計約40 t-CO2といった計算になります。
注意点
在宅勤務日がある場合、その日は通勤排出ゼロなので、年間勤務日数を適切に調整します。
会社支給の通勤手当データから推定する場合、手当額→区間距離を逆算できます(鉄道定期代から距離推定など)。海外拠点では従業員の通勤手段が違う(社用バス提供など)こともあるので、国別にモデル化することもあります。
カテゴリ7の削減は、通勤形態の見直しです。テレワーク推進で通勤日数を減らす、社宅・寮の活用で通勤距離を減らす、公共交通利用を促進する(駐車場利用を制限しバス定期券支給等)、自転車通勤を奨励する(駐輪場整備、手当支給)などの施策があります。社員の行動変容が必要な領域ですが、健康経営や働き方改革とも絡めて工夫している企業もあります。
8. カテゴリ8: リース資産(上流)
自社がリースまたはレンタルで借り受けて使用している資産に関する排出で、Scope1,2に含まれていないものです。バウンダリ基準にもよりますが、オペレーショナルコントロールが自社にあればたとえリース品でもScope1,2に計上すべきですが、そうでないケース(会計上は賃借扱いだが実質的支配が無い等)や、便宜上Scope1,2に含めなかったものをここで報告する可能性があります。例として、自社が借りているオフィスビル(賃貸オフィス)の電力使用に伴う排出や、リース契約で借用している車両の燃料排出などです。
算定方法
ケースバイケースですが、そのリース資産のエネルギー使用量を把握し、Scope1,2と同様に計算します。もし貸主からエネルギー使用量の情報提供があればそれを使います。例えば貸ビルのテナントとしての電力・ガス使用量がわかれば、電力量×係数でCO2算定します。不明な場合、床面積あたりの平均エネルギー使用量(ビルの平均原単位など)から推計します。またリース車両であれば走行距離や燃料購入記録から排出量を算定します。
注意点
環境省ガイドラインによれば、算定・報告・公表制度(温対法)ではリース資産の排出は基本Scope1,2に含めることになっており、結果としてカテゴリ8に計上するケースはほとんどないとされています。つまり実務的には該当なしの企業が大半です。ただ国際基準では、会社の境界設定によってはリース資産をScope3扱いすることも認められているため、海外投資家向けなどに包括的に報告する場合カテゴリ8を使用することがあります。
具体例として、本社が賃借しているビルの排出をScope3扱いする事例があります。算定そのものは難しくありません(エネルギーデータさえ入手できればよい)が、入手権限が自社に無いケースが多いです。貸主からの環境データ開示が望まれます。カテゴリ8は影響の小さい企業が多いですが、不動産を大量に借りている企業(サービス業など)では見逃すとそれなりの排出規模になる可能性があります。将来的には不動産オーナーとテナント間でエネルギー情報を共有し、テナント側もScope3で積極的に管理する動きが広がっています。
以上、カテゴリ1~8について詳細に見てきました。上流カテゴリはサプライヤーや従業員など自社の外部ステークホルダーの協力が欠かせない領域です。データ収集や排出削減には社内だけでなく取引先・社員とのコミュニケーションが重要になります。次の子記事では、下流カテゴリ9~15について同様に解説します。
引用先
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.5.0
https://www.env.go.jp/press/press_02717.html
サプライチェーン排出量算定に関する基本ガイドライン Ver.2.7(2025年3月)
https://chatgpt.com/c/681f0504-1d30-800d-9941-fc9bcfc3788c
1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド Ver.1.0(2025年3月)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/1ji_data_v1.0.pdf
排出原単位データベース(環境省 Green Value Chain Platform)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/