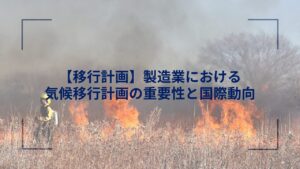企業の温室効果ガス(GHG)排出量は「Scope1」と「Scope2」に分類されます。Scope1は、工場や社有車の燃料使用、冷媒の漏洩など企業が直接排出するGHGを指します。Scope2は、電力や蒸気など購入したエネルギーの使用による間接的な排出を指します。これらの排出量を把握し、省エネや再生可能エネルギーの活用などで削減することが、カーボンニュートラル達成の鍵となります。本記事では、Scope1,2の定義や算定方法、削減対策について紹介します。


1. Scope1(直接排出)の定義と範囲
Scope1とは、前述の通り企業が自らの活動で直接的に排出する温室効果ガスのことです。
具体的には、自社が所有または運用する設備からの燃料燃焼排出、工業プロセスで発生する排出、社有車など移動体の燃料排出、化学物質(冷媒等)の漏洩排出などがすべて含まれます。例えば、製造工場のボイラーで燃料を燃やした際に出るCO2や、事業所の非常用発電機の排ガス、営業車・配送車の排出ガス、工場工程で発生する副生ガス、空調機器から漏れた代替フロン(温室効果ガス)などがScope1に該当します。要するに「自社で発生する排出はすべてScope1」と捉えることができます。
Scope1に含まれる主な排出源のカテゴリーを整理すると以下のようになります。
固定燃焼源
ボイラー、炉、加熱炉、焼却炉、自家発電機など、固定設備での燃料燃焼に伴うCO2やN2O、CH4排出。
例:工場ボイラーのガス燃焼、ビルの暖房用ボイラーの灯油燃焼など。
移動体燃焼源
自社所有または支配下の車両・船舶・航空機等の燃料燃焼による排出。
例:社有車のガソリン、営業用バンの軽油、フォークリフトのLPG、これらの燃焼。
プロセス排出
化学的・物理的プロセスからのGHG発生。
例:セメント製造時の石灰石分解に伴うCO2、肥料製造時の反応生成物としてのN2O、製鉄高炉の排出ガスなど。
漏洩排出(逸散排出)
機器から漏れ出す冷媒や温室効果ガスの排出。
例:冷凍冷蔵庫や空調機器からのHFC(代替フロン)ガス漏洩、天然ガス設備からのメタン漏洩など。
これらScope1排出は、企業が直接管理可能な排出であるため、エネルギー消費削減や設備改善によって比較的取り組みやすい領域です。
多くの企業はまずScope1排出の把握と削減から着手します。
2. Scope2(エネルギー間接排出)の定義と範囲
Scope2は他社から購入したエネルギーの使用に伴う間接的なGHG排出を指します。
典型的には、電力会社から購入した電気の使用により発電所で排出されたCO2が該当します。また、購入した蒸気や熱(地域熱供給や他工場からのスチーム受給など)、冷水の利用に伴う排出もScope2に含まれます。ポイントは、排出そのものは自社の外(他社設備)で発生しているものの、それを引き起こした原因(電力等の需要)は自社にあるということです。具体例を挙げると、オフィスや工場で使用する電力が火力発電によって供給されている場合、その発電時のCO2はScope2排出となります。また工業団地で集中供給される蒸気を工場プロセスに使っている場合、その蒸気ボイラーで生じたCO2もScope2です。自社で直接燃料を燃やしていなくても、他社のエネルギーに頼っていれば間接的にGHGを発生させているという考え方です。
Scope2排出の代表例と活動データ源は下記となります。
購入電力
使用電力量 (kWh) に基づき算定。電力の排出係数(kg-CO2/kWh)は国別・電力会社別に公表されています。日本では環境省から電力排出係数が毎年提供されており、また国際的にはIEAや各国電力グリッド係数を使用します。
購入蒸気・熱
使用量 (MJやトン) に基づき算定。供給元から熱供給のCO2排出係数(または燃料投入量あたりCO2)が提供されることもあります。
購入冷水
使用量に基づき、冷水製造に要した電力等からCO2を推計します(多くの場合購入冷水は電力由来なので電力換算します)。算定方法は前述の通り、「使用量×排出原単位」が基本です。電力の場合、「使用kWh × 電力CO2排出係数」で計算します。注意点として、GHGプロトコルではScope2の報告にロケーションベースとマーケットベースの2種類を用いることが推奨されています。
ロケーションベースとは国や地域の平均的な電力排出係数(例えば全国平均0.x kg-CO2/kWh)で計算する方法、一方マーケットベースは企業が調達した特定の電力メニューの実排出係数(例えば再エネ電力なら0に近い値、石炭火力メインの契約なら高い値)で計算する方法です。両者を併記することで、企業努力(再エネ調達)の効果を示しつつ、その国地域の電力構造の影響も把握できます。
3. Scope1,2排出量の算定方法
Scope1,2排出量を算出する際の一般的な手順は次の通りです。
組織の排出範囲の確定
自社(連結範囲など)のどの事業所・設備が対象か決定します。通常は温対法報告対象範囲や財務会計上の連結範囲に準じます。国内・海外子会社を含めるかもポリシーを定めます。
排出源の特定
Scope1であれば各事業所の燃料使用設備や保有車両、プロセス等を洗い出し、Scope2であれば購入電力・熱の契約を洗い出します。
活動量データ収集
各排出源について、該当年度の燃料使用量(種類ごとに)、電力使用量、熱使用量、発生ガス量などを集計します。これはエネルギーの購入記録やメーター値、請求書などから得ます。
排出原単位の適用: 集めた活動量に対し、それぞれ適切な排出係数を適用します。例えば燃料なら環境省公表の燃料別CO2排出係数(例: 軽油1kLあたり2.64トンCO2など)、電力なら電力会社公表のCO2係数を使用します。
CO2換算
メタンやN2O、HFC等CO2以外のGHGについては、それぞれCO2換算係数(GWP:地球温暖化係数)を掛けてCO2e(CO2相当量)に換算します。例えばHFC-134aならGWP1300程度なので、漏洩量1kgあたり1.3トンCO2eとなります。
集計とダブルカウント防止: 全排出源のCO2eを合計します。同じ排出を二重に計上していないかチェックします(例えば自家発電機の燃料使用CO2をScope1で計上したら、その電力はScope2から除く等)。
検証とドキュメンテーション
内部または第三者による算定プロセスの確認を行い、算定結果や使用した係数、データソースを文書化します。
このように、基本はエネルギー収支にもとづいたボトムアップ集計になります。企業によってはエネルギー管理システムを導入し自動で排出量をモニタリングしているところもあります。また、複数サイトがある場合はサイト別に集計し、本社で取りまとめることが多いです。
算定上の留意点
Scope1,2算定において注意すべき点としては、排出係数の年度更新(電力係数など毎年変わるものを最新にする)、バイオマス燃料由来CO2はカーボンニュートラルとみなし排出量から除外する扱い、
冷媒漏洩は年初残量・年末残量・追加充填量から推計する方法、自家発電の排出をScope1に計上し、その電力はScope2には含めない(ダブルカウント防止)、他社へ供給したエネルギーがある場合はそれもScope1に含まれるが、情報開示上は別掲することが多い、 等があります。
4. Scope1,2排出量の 管理と削減に向けて
Scope1と2は自社の努力で比較的削減しやすい領域です。管理手法としては、まず定期的なモニタリングとKPI化が基本です。エネルギー使用量やCO2排出量を月次・四半期ごとにトラッキングし、前年同期比や売上原単位あたり排出量などを指標化して管理します。
削減施策の例
省エネ改善
高効率設備への更新(ボイラー、空調、照明LED化など)、生産プロセスの省エネ改善、従業員の省エネ意識向上。
燃料転換
重油・石炭からガスへの転換、EV車導入によるガソリン削減、将来的には水素やバイオ燃料への切替。
再生可能エネルギー導入
太陽光発電設備の設置、自家消費型電源の活用。購入電力の再エネ化(グリーン電力証書、非化石証書、PPA契約、再エネ電力メニューへの切替)。
オペレーションの効率化
物流最適化による燃料削減(配送ルート見直し等はScope1の車両燃料に効く)、生産計画調整によるエネルギーロス低減。
こうした取り組みによって、Scope1,2排出量の絶対削減や原単位改善が実現できます。近年は多くの企業が2050年カーボンニュートラル、2030年頃の中間目標を掲げていますが、その達成にはまずScope1,2の徹底削減と残余排出のオフセットが出発点となります。さらに、削減目標の達成状況や取り組みは環境報告書や統合報告書でステークホルダーに報告され、CDPやSBT評価にも反映されます。その際、可能であれば第三者保証を付与してデータ信頼性を高めることが推奨されます。Scope1,2はデータ源が明確で検証もしやすいため、多くの企業が第三者検証を受けており、投資家にも信頼される情報開示が進んでいます。
引用先
温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.5.0
https://www.env.go.jp/press/press_02717.html
サプライチェーン排出量算定に関する基本ガイドライン Ver.2.7(2025年3月)
https://chatgpt.com/c/681f0504-1d30-800d-9941-fc9bcfc3788c
1次データを活用したサプライチェーン排出量算定ガイド Ver.1.0(2025年3月)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/tools/1ji_data_v1.0.pdf
排出原単位データベース(環境省 Green Value Chain Platform)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/estimate_05.html
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイト
https://eegs.env.go.jp/ghg-santeikohyo-result/