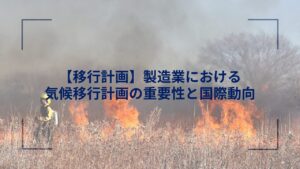本記事では、EUDR違反による罰金・市場排除リスクと遵守がもたらす競争優位、サプライチェーン可視化・リスク評価・デューデリジェンスの実務ステップ、サプライヤー協働によるリスク緩和策、農産品・畜産・木材など品目別の管理ポイント、そして施行後を見据えた規制動向モニタリングと企業の具体的準備策を下記にて解説します。


1. 規則遵守の重要性と企業へのリスク
EUDRに違反した場合の「売上高最大20%の罰金」「製品没収・EU市場からの排除」といった重大リスクと、森林破壊ゼロの証明によって「環境配慮型の顧客獲得」「ESG投資家からの評価向上」など競争優位を得る機会について、下記で詳しく紹介します。
違反リスクの深刻性
EUDR違反は巨額の罰金(売上高の最大20%)や違反製品の没収措置につながり、EU市場から排除されるリスクがあります。コンプライアンス違反による事業停止だけでなく、サステナビリティに反する企業との評価が定着すればブランドイメージの失墜や投資家の信頼喪失にも直結します。特に環境意識の高い欧州市場では、規則遵守は企業の参入券とも言えるほど重要です。各社はこのリスクの深刻さを経営層で共有し、トップダウンで対応方針を打ち出す必要があります。
サステナビリティ戦略上の機会
一方で、EUDR遵守への取り組みは単なるコストではなく企業価値向上の機会とも捉えられます。例えば、自社製品が森林破壊ゼロであることを証明できれば、環境に配慮する顧客や調達基準の厳しい企業から選ばれやすくなります。また投資家や金融機関もESG重視の観点からサプライチェーン環境リスクに対応する企業を評価する傾向があります。規則対応を契機にサプライチェーンの透明性を高め、持続可能性を経営戦略に統合することは、長期的には競争優位につながるでしょう。
2. EUDR対応の実務ステップ
農園・林業地まで遡るトレーサビリティの構築(サプライヤー調査や衛星画像・ブロックチェーンによるデジタル管理)と、国・地域別に森林破壊リスクを判定し低リスク国の簡易手続き/高リスク国への強化策を検討するプロセスについて、下記で詳しく紹介します。
原材料供給源のトレーサビリティ確立
まず取り組むべきは、自社が扱う原材料・製品の供給源を徹底的に洗い出すことです。調達先の農園・林業地レベルまでサプライチェーンをマッピングし、生産地の地理座標や農場名など必要情報を収集します。この作業にはサプライヤーからの聞き取りやアンケート、契約上の情報提供義務化など協力が不可欠です。可能であれば衛星画像プラットフォームやブロックチェーン技術なども活用し、サプライチェーン上の位置情報と物流経路をデジタル管理します。属人的な管理を排しシステム化することで、大量のデータを効率よく扱い将来的な監査にも備えます。
リスク評価と国・地域分析
集めた情報をもとに、各サプライヤーや生産地域の森林破壊リスク評価を行います。森林カバーの減少が著しい地域や、違法伐採が横行している国からの調達品はハイリスクと判断されます。EUDRでは低リスク国からの輸入に簡易手続が適用される一方、高リスク国からの調達には強化策が必要とされています。自社の調達地域がどのリスクカテゴリーに該当しそうか、公開情報や専門機関のデータを活用して分析します。また供給者毎の過去のコンプライアンス履歴(違法伐採の関与有無など)や、現地法遵守状況も評価に含めます。リスクが高いと判定されたサプライチェーンには後述の緩和策を講じ、必要に応じて調達先変更も検討します。
文書化とデューデリジェンス報告
データ収集と評価の結果、自社のデューデリジェンス手続を文書化します。各製品について「いつ・どこで・誰が生産した原料か」「森林破壊の有無をどう確認したか」「リスクに対し何を講じたか」を記録し、所定のフォーマットでデューデリジェンス声明書を準備します。EUの主管当局から求められた際や、取引先への説明用に備えるとともに、社内規程として手順を明文化しておくことで対応漏れを防ぎます。また関連文書やエビデンス(例えば森林管理認証書、衛星画像の解析結果、現地監査報告書等)は一定期間保管し、追跡調査に協力できる体制を整えます。
3. サプライヤーとの協働とリスク緩和策
サプライヤーへの無森林破壊条項の設定・是正措置・技術研修などの協力要請と、認証材優先調達・調達先多角化・衛星監視によるリスク低減策について、下記で詳しく紹介します。
サプライヤーへの要求事項と支援
サプライチェーン上流に位置する農園主や素材供給企業に対しては、EUDR遵守のための協力要請と支援が不可欠です。具体的には、契約に無森林破壊条項を追加し、森林破壊が判明した場合の是正措置や取引停止条件を明示します。同時に、サプライヤー側が遵守できるよう技術的支援や研修提供も検討します。例えば、小規模農家には衛星データ提供や農法改善の指導を行い、森林を伐採せず生産性を向上する取り組みを支援します。サプライヤーとの定期的なコミュニケーションを図り、データ提出のフォローアップや現地訪問による状況確認を続けることで、リスクを事前に把握し是正できる関係性を築きます。
リスク緩和のための措置
リスク評価で中〜高リスクと判定されたサプライチェーンに対しては、追加のリスク緩和策が求められます。一例として、該当地域からの調達量を減らし他地域へ切り替える、多角的な調達先を確保して依存度を下げる、といった戦略があります。また、公認された森林管理認証制度の活用も有効です。FSC認証木材やRSPO認証パーム油など第三者認証を取得した原料を優先調達することで、違法・無計画な森林伐採リスクを低減できます。もっとも、EUDR上は認証があってもデューデリジェンス義務は免除されないため、認証はリスク低減の補完手段と位置付けます。さらに最新の技術として、人工衛星によるリアルタイム森林監視サービスを契約し、自社の調達地域で新たな森林消失が起きていないか継続モニタリングする企業も出始めています。こうした手法を組み合わせ、リスクを可能な限り低減したうえで最終的なデューデリジェンス判断を下すことが重要です。
4. 対象品目別のポイントと事例
農作物(大豆・パーム油・カカオ等)セクター、畜産(牛肉・皮革)セクター、木材・紙・ゴム製品セクターについての例を取り上げます。
熱帯農産品のサプライチェーン管理
大豆やパーム油、カカオ、コーヒーといった熱帯農産品は、プランテーション開発による森林転換が大きな課題です。これらの業界では既にサステナビリティ認証(例:RSPO、RTRS、レインフォレスト・アライアンス等)が普及しつつあり、企業は認証取得原料の調達やサプライヤー監査を強化しています。例えばパーム油大手では、自社調達先の農園を衛星監視し森林伐採ゼロを確認するシステムを導入しています。またチョコレートメーカー各社はサプライチェーン上流でカカオ農家と直接連携し、森林保護と生計向上を両立するプログラムを展開しています。EUDR対応にあたって、こうした既存の取り組みを活用・拡大しつつ、より厳格な地理情報の把握と小規模生産者への関与強化が求められるでしょう。
家畜生産における森林リスク管理
牛肉や革製品のサプライチェーンでは、飼育地拡大のための熱帯林開墾が問題視されています。特に南米産牛肉は牧場開拓による森林破壊との関連が指摘されてきました。この分野では、大手食肉加工会社が衛星データやGPSを活用して牧場の位置特定と植生変化の監視を行い、不適切な牧場からの調達停止措置を講じ始めています。また皮革については、なめし業者から最終製品メーカーまでの追跡が必要です。畜産分野では農産品以上にサプライチェーンが長く複雑な場合もあるため、各段階の業者と情報共有体制を構築し、一貫してトレーサビリティを担保することが重要です。
林産資源の合法性・持続可能性確保
木材・紙製品は以前よりEU木材規則(EUTR)により違法伐採木材の規制対象でしたが、EUDRでは違法でない伐採や転用も含めた森林劣化そのものを防ぐ厳しい基準が課されます。林業企業や木材取引業者は、伐採許可証だけでなく、その木材が2020年以降に森林転換された土地から産出されていないことを証明する追加責任を負います。FSCやPEFC認証材の利用は有効な手段ですが、前述の通り証明責任は残るため、原木の産地情報やサプライチェーン上の加工・流通経路を細かく把握する必要があります。同様に、天然ゴムについてもプランテーション造成による森林伐採が対象となります。タイヤメーカー各社は森林保護方針を打ち出し、サプライヤー農園の監査や代替素材の研究に取り組んでいます。木材・ゴム製品分野では、自社およびサプライヤーが遵守すべき森林管理基準を明確化し、現地での監査や第三者検証を組み合わせて対応することが重要です。
5. 今後の展望と企業への提言
2025年末の本格施行に伴う監査強化・要件拡大の動向と、経営体制整備・調達リスク対策・社員教育など企業が今から進めるべき準備策について、下記で詳しく紹介します。
EUDR施行後の動向予測
2025年末からのEUDR本格施行により、まず対象となる主要分野でサプライチェーンの変革が加速すると見込まれます。施行後の初年度には各国当局による監査や違反摘発事例が出始める可能性があり、企業はそれらの事例分析から教訓を得て対策をアップデートすることが求められます。EUは数年ごとに規制の有効性をレビューし、必要に応じて対象品目の拡大や要件強化を行うことも考えられます。例えば、森林以外の生態系(サバンナや湿地)の保護まで範囲が広がる可能性も指摘されています。常に最新情報をモニタリングし、自社のコンプライアンス体制を継続的に見直す仕組みが不可欠です。
企業が今から準備すべきこと
規制開始まで残された時間を有効に活用し、今からでも準備を加速させることが重要です。第一に、経営陣のコミットメントを明確にし、全社横断のEUDR対応プロジェクトを立ち上げましょう。法務・コンプライアンス部門だけでなく、調達・サステナビリティ・IT部門など関係部署が連携する体制を整備します。第二に、リスクが高い調達先の特定と代替案の検討を早期に行います。場合によってはサプライヤーの入れ替えや在庫戦略の見直しなど、事業計画にも影響する意思決定が必要です。第三に、取引先や業界団体と情報交換しベストプラクティスを共有します。他社の先行事例から学び、自社の対応計画に反映させることも有益です。最後に、従業員教育や意識啓発を実施し、現場レベルで規則の趣旨を理解した行動を促します。これらの準備を着実に進めることで、EUDR施行後も安定して事業を継続しつつ、持続可能な社会への貢献を果たしていくことが可能となるでしょう。
6. まとめ
EUDRへの実務対応とリスク管理は、企業にとってチャレンジであると同時に、新たな持続可能経営への転換点とも言えます。本記事で述べた手順や対策を参考に、自社のサプライチェーンを再点検し、必要な体制整備を計画的に進めてください。規則対応を単なるコストと捉えるのではなく、自社の商品価値を高め市場での信頼を獲得する機会と位置付けることが重要です。森林破壊を防止する取り組みは気候変動や生物多様性保全にも寄与し、ステークホルダーからの評価にもつながります。EUDR対応を契機に、一歩進んだサプライチェーン・マネジメントを実践し、レジリエントで責任ある企業経営を実現していきましょう。