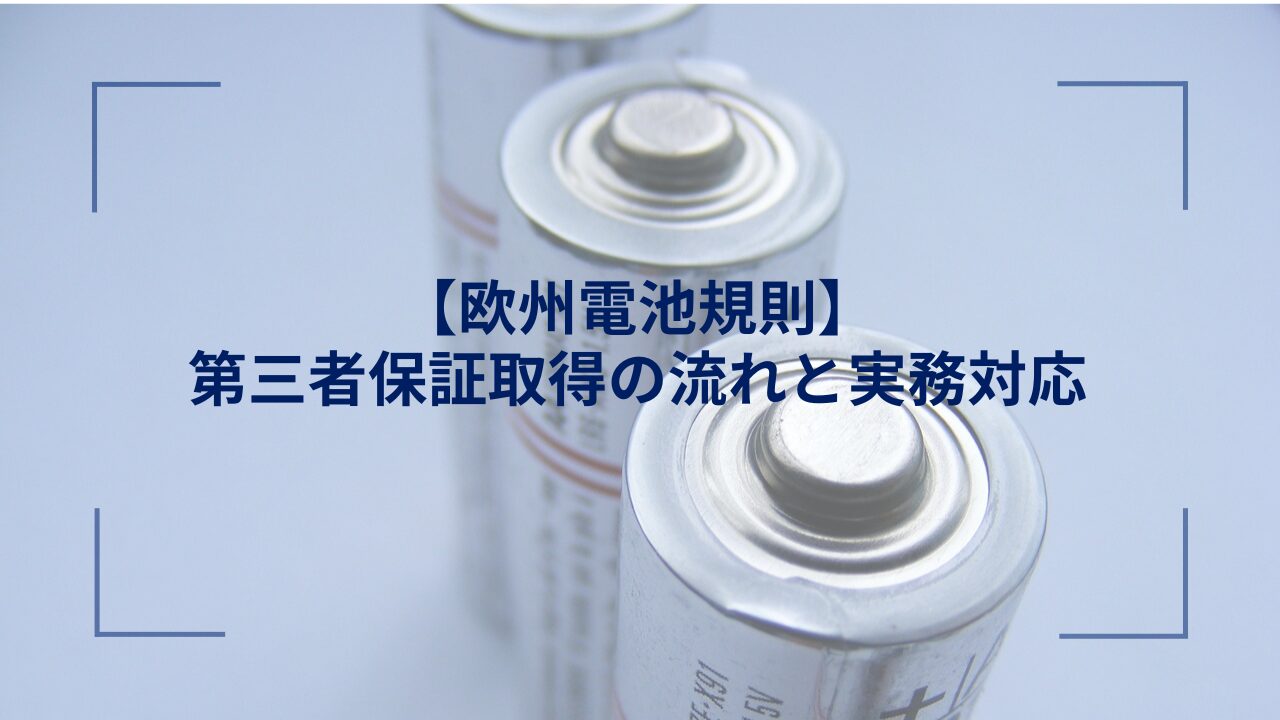欧州電池規則では、電池の環境性能やサステナビリティ情報の透明性を確保するため、第三者保証が求められます。企業が開示するカーボンフットプリント(CFP)やデューデリジェンス(DD)手続きなどの情報を、独立した認証機関(Notified Body)が審査し、その正確性を保証する仕組みです。適切な認証取得には、書類整備やデータ管理、認証機関の選定などの準備が重要です。特に2025年以降、申請の集中が予想されるため、早めの対応が求められます。
本記事では、欧州電池規則の第三者保証の要件や認証取得の流れ、企業の実務対応ポイントを解説します。


1. 第三者保証とは
第三者保証(Third-Party Assurance)とは、企業が開示・申告する情報について、利害関係のない独立した機関がその正確性や信頼性を検証し保証することです。
欧州電池規則における第三者保証
第三者保証が重視される背景には、企業が提供する環境情報の透明性と信頼性を確保する狙いがあります。電池の環境性能やサステナビリティ情報は、製造者自らが評価・報告するだけでは客観性に欠け、場合によっては過小報告や恣意的な解釈が入り込む余地があります。そこで、公平な第三者がルールに基づきデータや手順をチェックし、「この報告内容は妥当である」と保証することで、ステークホルダー(規制当局、消費者、ビジネスパートナー)の信頼を得ることができます。第三者保証を実施する機関としては、各国の認定を受けた試験認証機関(Notified Body)が該当します。
Notified Bodyについて
欧州委員会は欧州電池規則に基づき各国から適任機関の通知を受け、それらが電池規則に関する適合性評価業務を担うことになります。製品認証や環境認証の実績がある組織が想定されますが、これらの機関は規制の要求事項に沿って評価手順やチェックリストを持ち、企業からの申請に基づき審査・検証を行います。
2. 欧州電池規則で求められる認証
欧州電池規則に関連して、企業が第三者機関から取得すべき認証・検証は多岐にわたります。
主なものは以下の通りです。
カーボンフットプリント(CFP)検証
電池ごとのCFP算定結果について、独立検証機関の妥当性確認を受ける必要があります。
これは、ISO 14064-3(温室効果ガス報告の検証)などの基準に則り、算定プロセス・データ・計算結果が正確かを審査してもらうものです。検証に合格すると、CFP検証報告書や声明書が発行され、それをもって規制当局へのCFP宣言が有効となります。
デューデリジェンス(DD)手続きの認証
サプライチェーンにおける人権・環境デューデリジェンス方針とその運用について、第三者の監査を受け認証を取得する必要があります。具体的な規格名があるわけではありませんが、既存の鉱物調達の認証(例:RMIのRMAPやOECDデューデリジェンス・ガイダンス等)が参考になるでしょう。
認証機関は企業の方針策定、リスク評価手順、是正措置、情報開示まで一連のプロセスを評価し、規則の定める要件(第47条~第62条)に適合しているか判断します。
適合なら適合声明書(または証明書)が発行されます。
再生材料含有率の検証
電池の技術文書に記載するリサイクル材の使用率について、数値の裏付けとなるデータや計算を第三者が検証します。例えば、「この電池のコバルト20%はリサイクル由来である」ことを証明するには、サプライヤーからの原料証明やマテリアルフローの追跡などが必要です。検証機関はそれらエビデンスをレビューし、宣言値に偽りがないことを確認します。このプロセスはCFP検証に似ていますが、対象が物質フローになる点が異なります。
性能・耐久性試験の認証
電池の性能(容量や出力特性)や耐久性(サイクル数、カレンダー寿命)について、規則が定める基準を満たしているかどうか試験成績書を用意する必要があります。これ自体は第三者認証とは少し異なりますが、独立試験機関に試験を委託し、その報告書を技術文書に含めることで客観性を確保します。将来的に規則に適合した性能認証マークのような仕組みができる可能性もありますが、現時点では各社が試験データを示す形です。
CE適合宣言とNotified Body関与
前述の通り、電池規則はCEマーキング制度に組み込まれるため、対象電池ではEU適合宣言書を作成しCEマーク表示が必要です。高リスクカテゴリの電池(EV用や大型産業用)は、この適合性評価プロセスに第三者(NB)の関与が義務付けられます。すなわち、自社で全て自己宣言できるのではなく、認証機関による審査(工場監査や技術文書審査)を経てCEマーキングを行う形になります。電池規則の場合、CFP宣言やリサイクル含有率宣言が関与要件となるため、それらをきちんと第三者検証していることがCEマーキングの前提になります。
3. 欧州電池規則の取得プロセスと必要書類
第三者保証(認証・検証)を円滑に取得するためには、企業は事前に必要な書類を整備し、認証機関とのコミュニケーションを図ることが大切です。一般的な取得プロセスと必要となる書類は次のようになります。
1. 申請書類の提出
審査に先立ち、企業側で揃えた書類一式を認証機関に提出します。
CFP検証用
CFP算定報告書(LCAレポート)、算定に用いたデータリスト、算定結果のExcelシート等
DD認証用
デューデリジェンス方針書、リスク評価表、サプライヤーコードオブコンダクト、過去の監査記録、体制図、従業員教育資料等
リサイクル含有率検証用
原材料リスト、サプライヤーからのリサイクル材含有証明書、材料分析結果、集計表等
性能試験
試験報告書、製品仕様書、試験に用いたサンプル情報等
などが挙げられます。それぞれ規格・規則で要求される内容に応じて必要書類が異なりますが、要は「自社でこれだけきちんとやっています」というエビデンスを全て揃えることになります。
2. 書面審査と現地審査
認証機関は提出書類を精査し、不明点や追加資料要求があれば質問します。
CFP検証では計算ミスがないか、データの信頼性は十分かを詳細に確認します。
DD認証では書面上の手続きが実践されているかどうか、場合によっては現地訪問して従業員への聞き取りやサプライヤー先の監査などを行うこともあります。
このプロセスでギャップが見つかれば、企業側は是正措置(例:不足データの補充、手順書の改訂など)を行い、再提出します。
3. 認証書・検証報告書の発行
全ての審査工程をパスすると、最終的に第三者保証報告書が発行されます。
例えば「CFP検証報告書」には検証意見として「申告されたCFP値XX kg-CO₂eは、規定の基準に照らし正確であると確認した」等が記載されます。DD認証の場合は「適合証明書(Certificate)」が発行され、規則要件に基づくデューデリジェンスシステムを備えている旨が証明されます。これらの文書は、EU市場へ製品を出す際に当局要求があれば提示することになりますし、一部はバッテリーパスポート経由で公開される可能性もあります。
4. 維持審査と更新
認証は取得して終わりではなく、有効期限や定期検証が設定されます。例えばCFPは製品や製造条件が変われば値も変わるため、ロットごと・年ごとのアップデートが必要でしょう。DD認証も年次のフォローアップ監査が課されるのが一般的です。企業は継続的にデータを蓄積し、改善を図りながら、認証の維持に努めます。
4. 欧州電池規則に向けて企業が準備すべきこと
以上のプロセスを踏まえ、企業が第三者保証取得のために準備すべき事項を整理します。
内部ドキュメントの整理
認証取得には、まず自社の取り組みを文書化することが前提です。環境管理やサプライチェーン管理の社内ルール、手順書、記録類を体系立てて整備します。。例えば「CFP算定マニュアル」「デューデリジェンス手順書」などを作成し、現場への教育も実施しておきます。これらは審査時にそのまま提出資料や現場対応力として効果を発揮します。
データの検証と保管
CFPやリサイクル含有率など数値データは、その出典や計算根拠を明確にしておく必要があります。第三者から質問されたときにすぐエビデンスを示せるよう、データソース(例えばサプライヤー提供の環境データならそのメールや報告書)を保管しておきます。また計算シート類はダブルチェックを行い、ケアレスミスがないよう事前に検証しておきます。
模擬審査の実施
可能であれば、実際の認証前にコンサルタント等によるギャップアセスメント(模擬審査)を受けるのも有効です。第三者の視点で不足点を指摘してもらい、本番までに是正できます。特にDD認証など初の仕組みの場合、見落としがちな点を教えてもらえるでしょう。
社内関係者の調整
認証プロセスでは、審査員とのインタビューに複数部門が対応する場面もあります。環境データは環境担当者、人権リスクは調達担当者、といった具合に、事前に誰がどの分野を説明するかを決め、リハーサルしておくとスムーズです。審査中に戸惑わないよう、想定問答集を用意して共有する企業もあります。
スケジュール管理
各種認証取得には思った以上に時間を要するため、早急な対応が必要です。特に2025年以降、対象企業が一斉に認証機関へ依頼を始めると、審査の予約が取りにくくなる可能性があります。自社に関連する期限を逆算し、遅くともその半年前には審査を開始するくらいの計画で動きましょう。例えば2025年8月のDD義務開始なら、2025年春までに認証取得完了を目指し、2024年内には準備を終えるスケジュール感です。
以上を踏まえて準備を進めれば、第三者保証取得は決して難しいものではありません。欧州電池規則対応はハードルが高い印象もありますので、適切に対応をしていく必要があります。認証を得ることで企業の管理水準も上がり、社内外の信頼も向上します。準備期間に余裕を持ち、計画的に取り組んでいく必要があります。
引用元
欧州委員会:CEマーキング/適合性評価に関する総合案内
https://ec.europa.eu/growth/single-market/ce-marking_en
ISO 37301:2021(コンプライアンスマネジメントシステム)
https://www.iso.org/standard/75080.html