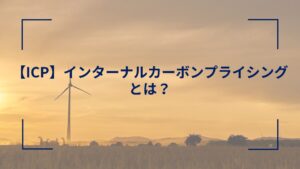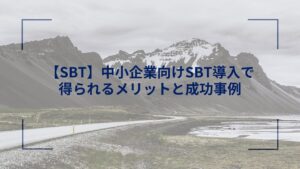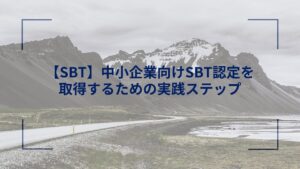GX-ETS(自主参加型国内排出量取引制度)では、企業への排出枠割り当てにおいて、ベンチマーク方式とグランドファザリング方式という2つの主要な計算手法が採用されています。本記事では、これらの方式の基本概念から具体的な計算プロセス、さらには制度の将来展望まで、企業が理解すべき割当量計算の全体像を詳細に解説します。

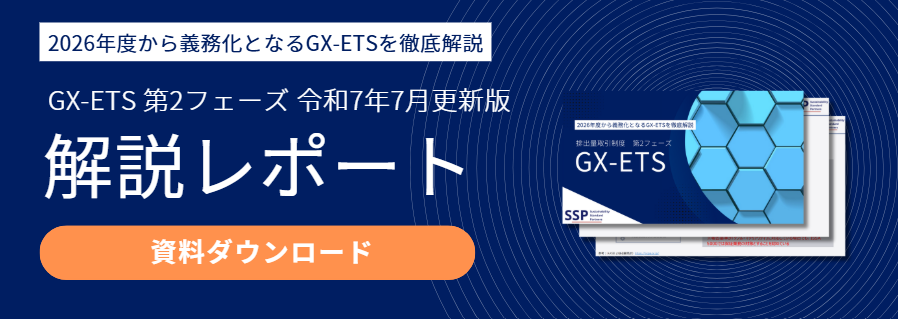
1.ベンチマークとグランドファザリングの基本概念と重要性
GX-ETSにおける排出枠の割当方式は制度の公平性と実効性を左右する重要な要素です。ベンチマーク方式は業界内の効率的な事業者の排出原単位を基準とし、グランドファザリング方式は過去の実績排出量を基準として削減率を適用します。業種や企業の特性に応じた適切な選択により、制度全体の受容性と削減効果の両立が図られています。
2.GX-ETSにおける割当方式の位置づけ
GX-ETSでは、参加企業に対する排出枠の割当において、主にベンチマーク方式とグランドファザリング方式の2つの手法が採用されています。ベンチマーク方式は、業界内の効率的な事業者の排出原単位を基準として割当量を決定する方式で、技術的な改善余地が大きい業種に適用されます。一方、グランドファザリング方式は、過去の実績排出量を基準として削減率を適用する方式で、業界特性や技術的制約を考慮した柔軟な対応が可能です。これらの方式は、EU-ETSをはじめとする国際的な排出量取引制度の経験を踏まえて設計されており、日本の産業構造や技術水準に適合した形で導入されています。
業種特性に応じた割当方式選択の意義
割当方式の選択は、各業種の技術的特性や競争環境を十分に考慮して行われます。例えば、電力業界のように技術革新の余地が大きく、効率性の差が明確に現れる業種では、ベンチマーク方式が効果的に機能します。この方式により、効率的な事業者が適切に評価され、技術革新へのインセンティブが強化されます。一方、製造業の中でも技術的制約が大きい業種や、プロセスの標準化が困難な業種では、グランドファザリング方式が採用されることがあります。この方式は、企業の過去の努力を適切に評価しつつ、段階的な削減を促進する効果があります。適切な方式選択により、制度全体の受容性と削減効果の両立が図られています。
3.ベンチマーク方式による割当量計算の詳細プロセス
ベンチマーク方式は業界内の効率的な事業者の排出原単位を基準として排出枠を配分する手法です。各業種における上位企業の排出効率を参考に技術的に達成可能な水準を設定し、企業の生産活動量に応じて割当量を決定します。最終的な割当量は「ベンチマーク値×基準活動量」の計算式で決定され、効率改善への取り組みが直接的に評価される構造となっています。
上位X%水準の設定方法
ベンチマーク方式における基準値の設定は、業界内の排出効率上位企業のデータを基に行われます。具体的には、対象業種の事業者を排出原単位(生産量あたりのCO2排出量)で順位付けし、上位10%から20%程度の企業の平均値をベンチマーク値として採用します。例えば、鉄鋼業界では粗鋼1トンあたりのCO2排出量を基準とし、効率的な高炉や電炉を持つ企業の実績を参考にベンチマーク値を設定します。この際、技術的制約や設備の特性も考慮し、現実的に達成可能な水準となるよう調整が行われます。設定されたベンチマーク値は定期的に見直され、技術進歩に応じて段階的に強化される仕組みとなっています。
基準活動量の算定と割当量への反映
基準活動量は、企業の生産実績や事業規模を示す指標として用いられ、過去3年間の平均値や直近年の実績値を基に算定されます。鉄鋼業では粗鋼生産量、セメント業ではセメント生産量、電力業では発電量といった具合に、各業種の主要な生産活動を反映する指標が選定されます。最終的な割当量は「ベンチマーク値×基準活動量」の計算式で決定されます。この仕組みにより、生産量が多い企業ほど多くの排出枠を受け取る一方で、効率改善への取り組みが直接的に評価される構造となっています。また、新規参入企業や事業拡大を行う企業に対しては、別途調整メカニズムが設けられ、公平性の確保が図られています。
4.グランドファザリング方式による割当量計算の実務
グランドファザリング方式は企業の過去の排出実績を基準として割当量を決定する手法です。基準年における実際の排出量から一定の削減率を適用することで各年度の割当量を算定します。過去3年間の排出実績を基に基準排出量を設定し、年次削減率を適用して段階的に割当量を減少させる仕組みにより、企業の過去実績を尊重しながらも確実な排出削減を促進します。
基準排出量の算定方法
グランドファザリング方式における基準排出量の算定は、対象企業の過去3年間の排出実績を基に行われます。具体的には、2019年度から2021年度の排出量データを収集し、異常値を除外した上で平均値を算出します。例えば、ある製造業企業の年間排出量が2019年度100万トン、2020年度95万トン、2021年度105万トンの場合、基準排出量は100万トンとして設定されます。この算定プロセスでは、設備の大幅な変更や事業規模の変化があった場合の調整も考慮されます。企業は排出量データとともに、生産量や稼働状況の変化を詳細に報告する必要があり、これらの情報を基に適切な基準排出量が決定されます。
削減率の適用と年次進行による割当量変化
基準排出量が確定した後、年次削減率が適用されて各年度の割当量が算定されます。GX-ETSでは、第1フェーズ(2026-2030年)において年率1.67%の削減率が設定されており、この率に基づいて割当量が段階的に減少します。前述の企業例では、2026年度の割当量は基準排出量100万トンから削減率を適用し、約98.3万トンとなります。2027年度はさらに削減が進み、約96.7万トンの割当となります。このように、グランドファザリング方式では企業の過去実績を尊重しながらも、確実な排出削減を促進する仕組みが構築されています。企業は年次進行に伴う割当量の減少を見据えた長期的な削減計画の策定が求められます。
5.GX-ETSの割当計算方式の今後の展望と企業の対応戦略
GX-ETSは2026年度の本格運用開始に向けて段階的な制度設計が進められています。現在の割当量計算方式は制度の初期段階における基盤となりますが、長期的には更なる強化と精緻化が予定されています。企業には精密な排出量管理システムの構築、中長期的な削減計画の策定、クレジット調達戦略など、戦略的な対応が求められる重要な局面を迎えています。
割当基準の段階的強化と技術革新の促進
GX-ETSにおける割当基準は、制度の成熟とともに段階的に強化される方針が示されています。ベンチマーク方式では、現在の上位10%水準から、将来的にはより厳格な上位5%水準への移行が検討されており、これにより企業の削減インセンティブが一層強化されます。また、グランドファザリング方式においても、年間削減率の段階的な引き上げが予定されており、2030年度以降は現在の1.67%から2%以上への強化が想定されています。このような基準強化は、企業の技術革新を促進する重要な役割を果たします。特に製造業においては、省エネ設備の導入や生産プロセスの効率化、さらには水素やアンモニアなどの新燃料への転換が加速されることが期待されています。
企業に求められる排出量管理と戦略的対応
企業は今後、より精密な排出量管理システムの構築が不可欠となります。具体的には、リアルタイムでの排出量モニタリング体制の整備、データの透明性と信頼性の確保、そして中長期的な削減計画の策定が求められます。また、割当量の不足に備えたクレジット調達戦略や、余剰分の売却による収益化戦略も重要な経営課題となります。さらに、サプライチェーン全体での脱炭素化への取り組みや、他社との連携による共同削減プロジェクトの推進など、従来の企業単体での対応を超えた包括的なアプローチが必要となっています。
引用
ベンチマーク・グランドファザリングによる割当量の計算方法
2025年8月7日 経済産業省 GXグループhttps://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/sangyo_gijutsu/emissions_trading/pdf/002_03_00.pdf