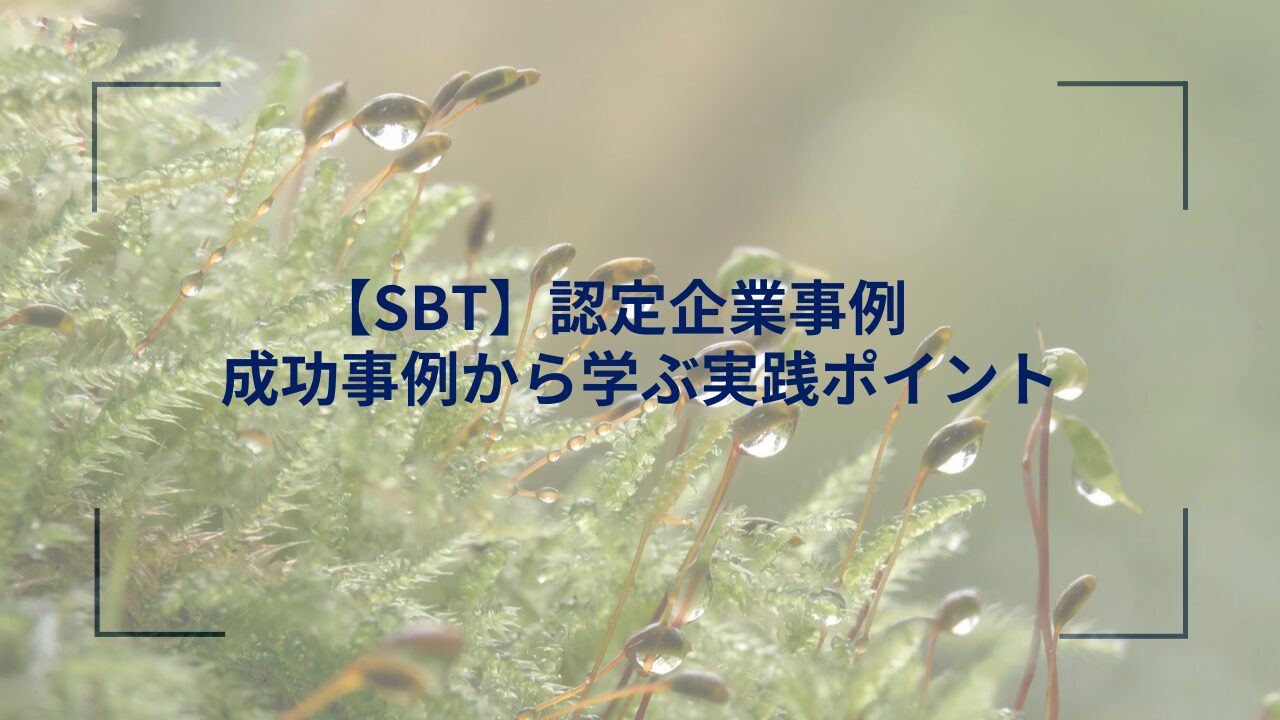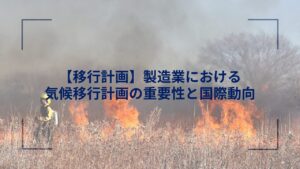ソニー、パナソニック、イケアなどSBT導入企業の成功事例をもとに、経営トップのコミットメントやバリューチェーン全体での排出削減、革新的技術投資などの実践ポイントについて解説します。


1. ソニーのSBT導入と成功要因
ソニーグループは、日本企業の中でも早くから科学的な気候目標に取り組んできたリーダー企業です。同社は2010年に「Road to Zero」と呼ばれる長期環境ビジョンを策定し、2050年までに自社の環境負荷(温室効果ガス排出や資源消費)をゼロにすることを掲げていました。その中間マイルストーンとして、2020年度までに自社事業(Scope1・2)排出を2000年度比42%削減する目標を設定し、これを着実に達成しています。その後、国際的なSBTの動きに合わせて目標水準を引き上げ、2017年には「well-below 2℃(産業革命前比2℃未満)」水準でSBTiの認定を取得しました。
ネットゼロ目標の前倒しと1.5℃認定
さらにソニーはパリ協定後の気候リーダーシップを示すため、2050年としていたバリューチェーン全体のネットゼロ達成目標を2040年に前倒しし、Scope1・2については2030年までに実質ゼロを達成するという非常に野心的な目標を打ち出しました。この新目標は2022年にSBTiから承認を受けており、ソニーは「1.5℃目標」および「ネットゼロ目標」を併せ持つ企業として業界をリードしています。
経営トップの強力なコミットメント
ソニーの成功要因の一つに、経営トップの強力なコミットメントがあります。同社では気候変動対策が経営の重要課題と位置づけられ、CEO自らが科学的目標の策定に深く関与しました。「CEOが他の経営陣を巻き込むのに非常に重要な役割を果たした。彼にとってこれはソニーの存在意義そのものだ」という社内の声があるほどで、トップダウンで社内合意を形成した点は見逃せません。CEOの後押しにより各事業トップも同調し、全社的に「排出削減を大胆に進める」という共通認識が醸成されました。また社員レベルでも、グリーンマネジメント目標に関するeラーニング研修が提供されるなど意識啓発が徹底され、社内のモメンタムを維持しています。
革新的技術開発 SORPLASの活用
こうした体制の下、ソニーは具体的なイノベーションを次々と実現しました。代表的な成果が、自社開発した再生プラスチック素材「SORPLAS(ソープラス)」です。このプラスチックは廃棄光ディスクや廃棄ウォーターボトルなどを原料に最大99%まで再生樹脂を用いて製造され、製造時のCO2排出を約80%削減できます。現在ではソニーのテレビやカメラなど多くの製品部品にSORPLASが採用されているほか、ソニーグループ外にも素材供給されています。
製品の省エネ性能向上 ブラビアテレビ
また、製品の省エネ性能向上にも積極的で、新開発のブラビアテレビでは独自のバックライト技術によりフレーム単位でLED明るさを最適制御し、従来モデル比で20%の消費電力削減を実現しました。これは画質を維持しつつエネルギー効率を高めた例で、「高性能化と脱炭素の両立」を追求した成果と言えます。
経営上のメリットとブランド価値向上
ソニーはこれらの取り組みを通じ、経営上のメリットも享受しています。同社は「気候変動対策はお客様が望む製品を提供しながら地球規模で排出削減にも貢献できるウィンウィンの関係だ」と述べています。省エネ製品はユーザーの電気代削減やCO2削減にもつながるため、環境価値がそのまま製品価値として顧客に提供でき、ブランド価値の向上に寄与します。また「科学的に裏付けられた目標をグローバルなイニシアチブから承認されたことで、社内的にも自信と権威を得た」とし、COP21後に高まった気候意識の中でソニーの目標が業界や規制当局に対する一種の「お墨付き」になった点を挙げています。さらに、エネルギー効率改善はコスト削減効果も生み、「ステークホルダーの期待を上回る目標を掲げることで競合より先んじて有利な立場に立てる」とも分析しています。事実、ソニーはCDPの気候変動Aリスト常連企業として評価され、株主や投資家からの支持も高めています。
以上のように、ソニーの事例からはトップのリーダーシップ、全社的な巻き込み、革新的技術開発、そして目標達成がもたらす事業上の価値という成功要因が浮かび上がります。科学的目標を据えることが単なる環境対応に留まらず、自社製品・サービスの競争力やブランド力強化につながっている好例と言えるでしょう。
2. パナソニックのバリューチェーン全体での取り組み
パナソニックホールディングスは、自社のバリューチェーン全体を網羅した長期気候目標を掲げ、その達成に向けた包括的な戦略「Panasonic GREEN IMPACT(PGI)」を推進しています。
非常に高い目標
パナソニックのSBTは、まず2023年に1.5℃水準の削減目標としてSBTiの承認を取得し、続いて2024年には2050年ネットゼロ目標の検証に世界で初めて合格した日本企業となりました。同社のネットゼロ長期目標は、「2019年度比で2050年までに自社のバリューチェーン(Scope1・2・3)由来のGHG排出を少なくとも90%削減し、残る10%未満を自社の技術による炭素除去で相殺する」という非常に高い水準のものです。この目標には、自社の工場・事業所だけでなく、製品の使用やサプライチェーン上流の排出まで含めた全体最適が盛り込まれており、まさにバリューチェーン全体での脱炭素を目指しています。同社は短期目標としては「2030年までに自社事業(Scope1・2)で実質ゼロ」を掲げており、こちらもSBTiにより1.5℃に整合するものと認定されています。
ソリューションと社会貢献
パナソニックの気候戦略の特徴は、自社の直接排出削減と製品・ソリューションによる社会貢献の双方に力点を置いている点です。同社は長期ビジョンPGIにおいて、まず自社オペレーションから排出ゼロを目指すと同時に、自社の製品・技術によって社会全体でのCO2削減に貢献する目標を掲げています。具体的には、エナジーソリューション事業(蓄電池や水素技術等)や省エネ家電製品の普及によって、2050年までに累計3億トン超のCO2削減に貢献することを目標としています。3億トンという削減量は、現在の世界年間排出量(約330億トン)の約1%に相当し、企業単体としては極めて大きな社会貢献目標です。このようにパナソニックは、自社の排出そのものを減らす「直接的貢献」と、自社製品・サービスを通じて他者の排出削減を支援する「間接的貢献」の両面から気候変動対策に取り組んでいます。実務面でも、同社は様々な施策を並行して進めています。
自社拠点の脱炭素化
まず自社拠点の脱炭素化では、世界各地の工場・オフィスで再生可能エネルギー電力の導入やエネルギー効率化投資を加速しています。例えば欧州では再エネ100%化を達成済みで、国内外の他地域でも2030年100%を目指し太陽光発電設備の設置やPPA(電力購入契約)の活用を推進中です。また、製造プロセスの改善(省エネ改造やIoT活用による生産効率向上)や物流網の最適化にも取り組み、事業活動全体での排出削減を図っています。
サプライチェーン対応
サプライチェーン対応も重要な柱です。パナソニックはScope3排出の大部分を占める購入部品・原材料および製品使用時の排出に対応するため、主要サプライヤーや顧客との連携を深めています。サプライヤーに対しては、温室効果ガス排出量データの提供や削減計画の策定を働きかけるとともに、省エネ素材の共同開発や調達先の見直しなども進めています。製品の使用段階では、エアコンや冷蔵庫など家電の省エネ性能向上を継続的に行い、買い替え促進策と組み合わせてユーザー側の省CO2効果を狙っています。さらに、顧客企業向けには省エネソリューションや創エネ(エネルギー創出)技術を提供し、顧客のSBT達成も支援するビジネス展開を強化しています。これらパナソニックの取り組みは、日本企業がバリューチェーン全体でSBTを実践する好例と言えます。同社は2021年にTCFD(気候関連財務情報開示)に沿ったリスク・機会分析を実施し、炭素価格リスクやレピュテーションリスクを定量評価するなど、気候変動が事業に与える影響を経営戦略に統合しています。こうした動きを踏まえ、投資家からは「実行力のある脱炭素戦略」として評価され、環境株価指数への組み入れやESG投資の受け入れにもつながっています。
パナソニックの事例は、長期ビジョンに基づき自社と社会双方に価値を生み出す気候戦略のモデルケースといえるでしょう。
3. イケアのサプライチェーン全体での気候戦略
イケア(IKEA)は、グローバルな家具メーカー・小売業としてその大規模なサプライチェーン全体で気候変動対策をリードしている企業です。イケアはパリ協定の目標達成にコミットし、2016年度比で2030年までにバリューチェーン全体のGHG排出量を50%削減、2050年までにネットゼロ(実質ゼロ)を達成する目標を掲げています。この目標はSBTiによって1.5℃目標として承認済みであり、特に2030年に向けた削減目標はオフセットに頼らず絶対排出量を半減するという非常に挑戦的な内容です。さらに、2050年のネットゼロ達成に向けては、イケアの自社バリューチェーン内で森林経営や農業を通じた炭素吸収を行い、排出の残余を打ち消す計画で、少なくとも90%の削減と残余の相殺というSBTiネットゼロ基準を満たすものとなっています。この野心的目標を達成すべく、イケアはサプライチェーン全体にわたる包括的な気候戦略を推進しています。
その柱は大きく3つあります。
自社バリューチェーンの排出削減
イケアはまず、自社のバリューチェーン上で徹底的な排出削減を図っています。具体策としては、製品に使用する原材料をできるだけ低炭素なもの(持続可能な木材、リサイクル素材、植物由来素材など)に転換すること、事業モデルを使い捨て前提からリサイクル・リユース前提の循環型経済に変革すること、事業運営で利用するエネルギーを100%再生可能エネルギーに切り替え物流や店舗運営の電化を進めること、などがあります。特に原材料はイケアのバリューチェーン排出の中核であり、木材や金属、プラスチックといった素材由来排出が最大の割合を占める(イケア全体のフットプリントで材料生産が最も寄与)ため、サプライヤーと連携して材料生産時の排出削減に注力しています。実際、イケアは「原材料からの排出を2030年までに半減する」という目標を掲げ、森林管理の改善や代替素材の研究開発を進めています。
カーボンリムーブとストレージ(炭素の除去と貯蔵)
排出削減だけでなく、大気中のCO2を除去・吸収する施策にも取り組んでいます。具体的には、イケアの製品原料となる森林での持続可能な森林経営を通じて追加的な炭素吸収を図ったり、農業部門で土壌炭素を増やす手法を模索したりしています。イケアは以前「Climate Positive(気候ポジティブ)」を掲げていましたが、科学の進展や業界基準の変化を踏まえ「Net Zero and Beyond(ネットゼロとその先)」というアプローチに更新しました。これには、自社バリューチェーン内での炭素除去策を追求しつつ、炭素クレジットなど外部オフセットには依存しない方針が含まれています。もっとも、将来的にネットゼロ達成後はバリューチェーンを超えた除去も視野に入れる可能性に言及しており(例えば自社製品に炭素貯蔵する木材を使い、製品として長期貯蔵する等)、こちらは今後の技術・ガイドラインの進展に合わせ目標設定するとしています。
バリューチェーンの外への働きかけ(Beyond IKEA)
イケアの気候戦略の第三の柱は、自社の枠を超えて社会全体の脱炭素を後押しする取り組みです。具体例として、イケアは自社が関与しない領域でもGHG削減が進むよう政策提言や再エネ投資を行っています。再エネ分野では、自社消費用だけでなく地域社会向けの風力・太陽光発電プロジェクトに出資し、電力グリッドの脱炭素化に貢献しています。また企業連合を通じて各国政府に気候政策強化を働きかけ、より野心的な産業規制や再エネ補助政策を求める活動も展開しています。イケアはサプライチェーン外のGHG削減策(Beyond Value Chain Mitigation)も気候目標の一環と位置づけており、これらはSBTiがネットゼロ到達企業に推奨する自主的努力でもあります。
イケアの具体例から浮かび上がる成功ポイントは、「サプライチェーン全体での徹底した排出削減」と「企業の枠を超えた気候アクション」です。原材料調達から製品使用・廃棄に至るまでバリューチェーンを俯瞰し、各段階での排出削減策を統合的に講じている点は他企業の模範となります。また、自社だけでなく業界全体・社会全体の変革を促す姿勢(政策提言や協働)は、気候問題が一企業では解決し得ないとの認識に基づくもので、システム全体を変革しようとするリーダーシップが感じられます。これらの戦略により、イケアは2021年度までに2016年度比で既に約30%のGHG排出強度削減を達成しており(売上高あたり排出量ベース)、「成長しながら排出を減らす」道筋を実証しつつあります。イケアの事例は、サプライチェーン全域にわたる包括的な気候戦略が企業価値と両立しうることを示す好例と言えるでしょう。
4. 他の先進企業の成功ポイント
上述の他にも、世界にはSBTを活用して気候変動対策と競争力強化を両立している先進企業が数多く存在します。そうした企業の成功事例からは、共通するいくつかの実践ポイントが見えてきます。
バリューチェーンでの取組み
まず、バリューチェーン全体に目を向けることです。多くの企業では、自社の直接排出よりもサプライチェーンや製品使用時の排出(Scope3)の方がはるかに多く、平均すると直接排出(Scope1)の11倍・総排出量の70%以上を占めるとも言われます。そのため、先進企業は例外なくScope3削減に本腰を入れています。具体的には、主要サプライヤーに対して排出削減目標の設定を働きかけたり、サプライヤー向けのカーボンフットプリント管理支援プログラムを提供したりしています。例えばH&Mグループは、自社のサプライチェーン排出を減らすためサプライヤー支援策を実施し、協働での脱炭素化に取り組んでいます。
また、ユニリーバは主要原料サプライヤーとの契約条件に持続可能な慣行を組み込むなど、バリューチェーン全体で目標共有を図っています。こうしたサプライチェーン・エンゲージメントはSBT達成のカギであり、先進各社は自社だけでなく取引先も巻き込んだ削減努力を展開しています。
ガバナンスと社内制度の工夫
次に、ガバナンスと社内制度の工夫です。野心的な目標を掲げても現場で実行されなければ絵に描いた餅となります。先進企業はSBTを経営の中に組み込むための仕組みを整えています。例えば取締役会レベルで気候目標の進捗が定期議題に上げられ、経営陣が直接レビューする体制を敷いたり、気候関連KPIの達成状況を経営幹部の報酬に反映させたりするケースが増えています。実際、欧州の大手企業ではCEOや役員報酬の一部をSBT達成に連動させる動きが広がっており、これにより経営層のコミットメントとアカウンタビリティ(説明責任)が一層明確になります。さらに従業員に対しても、業績評価項目に温室効果ガス削減や省エネ改善を組み込んだり、全社OKR(Objectives and Key Results)に気候目標を織り交ぜたりする企業もあります。要するに、「目標のための仕組みづくり」が成功には不可欠であり、先進企業ほどそれを徹底しているのです。
技術革新と投資
第三に、技術革新と投資です。SBTという高い目標を達成するためには、現状からの延長線上の施策だけでは不十分な場合もあります。そこで先進企業は、将来を見据えた技術投資やイノベーションにも積極的です。例えば、マイクロソフトは2030年までにカーボンネガティブ(排出より除去が多い状態)を目指し、大気からCO2を直接回収するDAC技術への投資や革新的なカーボンリムーブ企業とのパートナーシップを進めています。デンマークのオーステッド(旧DONGエナジー)は化石燃料主体の事業からいち早く風力発電事業へと舵を切り、大胆なビジネスモデル転換でSBT達成と企業成長を同時に成し遂げました。これらに共通するのは、長期視点の戦略的投資を行い脱炭素と事業機会創出を両立させている点です。SBTをチャンスと捉え、自社の強みを活かせる技術領域でリードする姿勢は、先進企業に学ぶべき重要なポイントでしょう。
透明性の高いコミュニケーション
最後に、透明性とコミュニケーションも成功に欠かせません。先進企業は進捗や課題を積極的に開示し、社内外の声を取り入れながら軌道修正しています。例えば、ある企業では「計画より削減が遅れている」と率直に開示した上で原因分析と対策を説明し、投資家からの理解を得ました。またステークホルダーとの対話を通じ、新たな協働プロジェクトが生まれるケースもあります。こうしたオープンな姿勢が企業の信頼を高め、ひいてはブランド価値向上や優秀な人材の惹きつけにもつながっています。以上、先進企業の事例から浮かび上がるポイントを総括すると、「野心的な目標を全社とバリューチェーンに浸透させ、ガバナンスとイノベーションで支え、透明性ある進捗管理で信頼を得る」ことが肝要と言えます。SBTは単なる目標設定イニシアチブではなく、企業変革のフレームワークでもあります。成功企業はいずれもSBTを企業戦略の中核に据え、このフレームを最大限活用しています。その姿勢と取り組みは、これからSBT達成を目指す企業にとって貴重な示唆とノウハウの宝庫となるでしょう。
引用
ソニー企業事例
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/technology/packaging
https://www.wwf.or.jp/corp/info/923.html
https://www.sony-semicon.com/ja/products/sorplas/index.html
パナソニック企業事例
https://holdings.panasonic/jp/corporate/panasonic-green-impact.html
サステナビリティレポートFY23|IKEA
https://www.ikea.com/jp/ja/files/pdf/6f/2e/6f2e0f92/ikea-sustainability-report-fy23_ja_jp.pdf
ユニリーバ企業事例
https://www.unilever.co.jp/sustainability/climate-action/