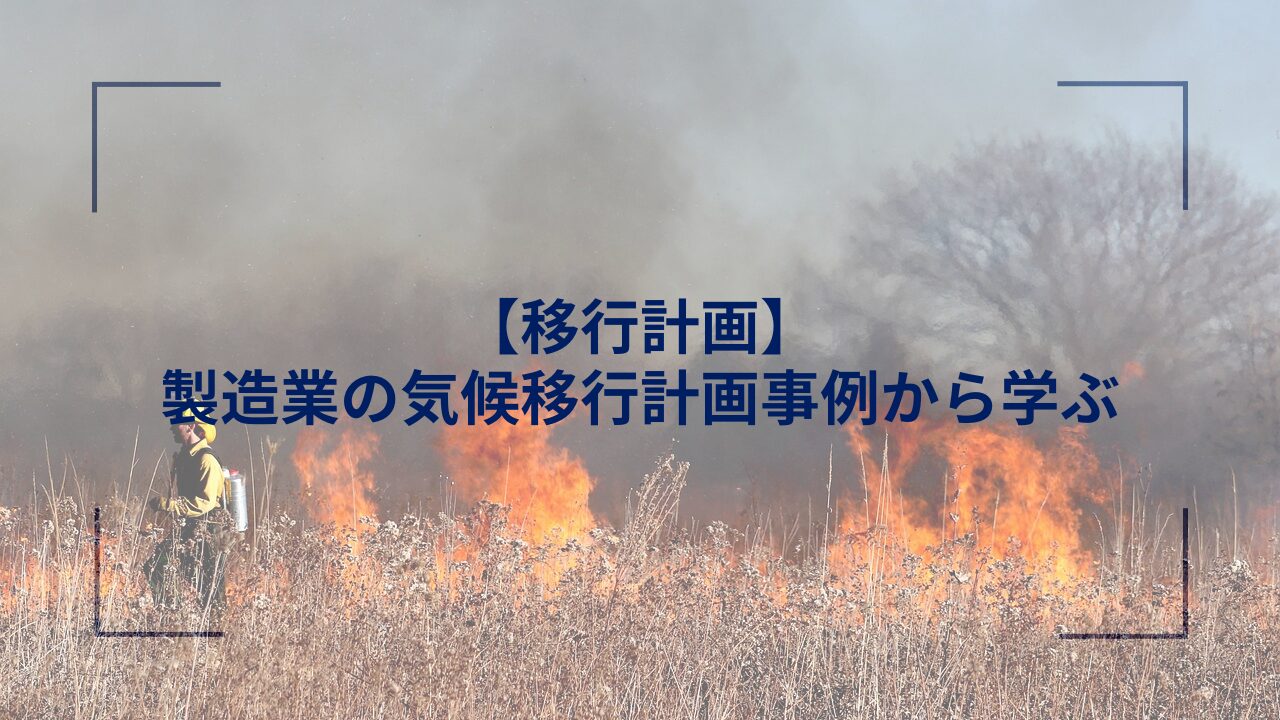気候変動に対する移行計画を実際に策定・実行している製造業企業の事例を紹介し、その成功要因を分析します。また、製造業に共通する移行計画の実現上の課題(技術面・資金面・バリューチェーン対応など)について考察し、課題克服に向けたポイントを示します。


1.製造業における先進企業の移行計画事例
実際に気候移行計画を策定し積極的に取り組んでいる先進企業の例を見てみましょう。いずれも自社の特性に合わせた独自の戦略で脱炭素と事業成長の両立を目指しており、製造業に有用な示唆を与えてくれます。
ユニリーバ
グローバルに展開するユニリーバは、自社バリューチェーン全体での温室効果ガス排出削減目標を掲げています。具体的には、自社の製造拠点だけでなく原料供給の段階から製品使用・廃棄に至るまで、あらゆる段階での排出削減を目指す包括的な「気候移行行動計画」を公表しています。サプライヤーとの協働による原材料調達の低炭素化や、消費者の行動変革(製品使用時の省エネ促進など)まで含めた取り組みを進めており、まさにバリューチェーンを巻き込んだ戦略が特徴です。このようにScope3まで視野に入れた計画は高い難度ですが、同社の強力なブランド力とイニシアチブにより実行に移されています。
引用:https://www.unilever.com/sustainability/climate/our-climate-transition-action-plan/
ソニー
日本の製造業からはソニーグループの取り組みが挙げられます。ソニーは「Road to Zero」という長期環境計画を掲げ、2050年までに環境負荷ゼロを目指すビジョンを打ち出しました。中間目標として2030年までに自社事業所でのCO2排出実質ゼロ(再エネ100%化)などを設定し、毎年その進捗を環境報告書で開示しています。特徴的なのは、グループ全体で統一した方針のもと各事業部門が具体的な計画を策定している点です。製品の省エネ設計から物流の効率化、さらには従業員一人ひとりの環境意識向上策まで、多角的なアプローチで取り組んでいます。こうした努力が評価され、ソニーは国際的なCDP気候変動ランキングでも高スコアを獲得するなど、投資家からも高い評価を得ています。
引用:https://www.sony.com/ja/SonyInfo/csr/eco/RoadToZero/gm.html
キリンホールディングス
キリングループは2050年に温室効果ガス排出量ネットゼロの目標を掲げています。同社は自然資本の保全を重視し、水資源管理や農産原料の持続可能調達、容器包装の軽量化・リサイクル推進といった事業戦略と排出削減を一体化させています。製造工場では再生可能エネルギー電力100%利用を進めるなど、着実に施策を実行中です。またTCFD提言に沿った情報開示に早期から取り組み、経営戦略に気候変動対応を組み込んでいることを示しています。具体的には「環境KPIの達成状況を役員報酬に連動させる」など経営層のコミットメントを明確化し、投資家から高く評価されています。
引用:https://www.kirinholdings.com/jp/investors/files/pdf/environmental2024_03.pdf
オムロン
オムロンは2019年にTCFD支持を表明後、2022年には自社およびサプライチェーン排出量削減目標をパリ協定の「2℃シナリオ」からより厳しい「1.5℃シナリオ」に引き上げました。統合報告書において移行計画の基盤となる詳細なシナリオ分析のプロセスを開示し、経営計画と気候対策との整合性を明確に示しています。この点が投資家から高く評価され、「脱炭素と事業成長を両立するには移行計画が不可欠」との日経新聞の評価記事でも好例として紹介されています。同社はハードウェア製造企業として、自社製品や生産工程の電力効率化に加え、サプライヤーの協力を得た調達改革なども進めています。
引用:https://www.omron.com/jp/ja/sustainability/environ/climate_change/response/
上記の他にも、日本企業では味の素がグループTCFD会議を設置してシナリオ分析や各社の進捗管理を行っていたり、ENEOSがカーボンニュートラル推進委員会を設置して脱炭素ロードマップを開示し高い評価を受けたりする事例があります。製造業と一口に言っても業種によってアプローチは様々ですが、共通して言える成功要因は「経営トップ主導による明確な長期ビジョン設定」「自社の強みに基づく具体策の実行」「進捗とシナリオの透明な開示」にあります。企業ごとの創意工夫を凝らした移行計画から学べる点は多いでしょう。
引用:https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/sustainability/
引用:https://www.hd.eneos.co.jp/esgdb/environment/tcfd.html
2.移行計画実現における主な課題
移行計画の策定・実行には、特に製造業ならではの困難も存在します。最後に、製造業が直面しやすい主要な課題とその対応策について整理します。
技術面の課題
製造業では高温の熱エネルギーを要する工程が多く、ボイラーや炉などで安価な化石燃料を大量使用しているケースが一般的です。このためプロセス自体の脱炭素化(電化や水素燃料への転換など)は大きな技術的課題となります。現時点で代替技術が確立していない「ハードトゥアベート(削減困難)」分野もあり、製鉄業などでは水素還元製鉄やCCUS(炭素回収・貯留)など超革新的技術の開発に取り組んでいます。例えば日本製鉄は「2030年に2013年比30%のCO2削減、2050年カーボンニュートラル」を掲げ、世界に先駆けて水素製鉄等の技術開発・実用化ロードマップを推進中です。技術面の課題解決には自社開発だけでなく、産官学連携でのイノベーション創出や、既存技術の組み合わせによる効率向上など、長期視点での取組みが必要です。
資金面の課題
脱炭素化対応には往々にして巨額の設備投資や研究開発費が伴います。老朽設備の更新や燃料転換、新エネルギー設備の導入など、初期コストの高さが壁となり、すぐに全施策に着手するのは難しい企業も多いでしょう。特に中堅・中小の製造業では投資余力が限られるため、国や自治体の補助金・支援策を活用しながら効率的に進める工夫が不可欠です。幸い日本では環境省や経産省による製造業向けの脱炭素化支援事業(設備導入補助や技術実証支援など)が拡充されつつあります。また、近年は金融機関もグリーンボンドやサステナビリティ・リンク・ローンなどグリーンファイナンスの商品を提供し、企業の移行計画達成を資金面から後押ししています。移行計画を明確に示せば投資家や銀行からの資金調達もしやすくなるため、計画策定自体が資金面の課題緩和策とも言えます。
バリューチェーン全体への対応
製造業のGHG排出は自社工場だけでなく、サプライチェーン上流(原材料の生産・輸送)や下流(製品使用時のエネルギー消費)に多く存在します。このScope3領域の削減は、自社単独では完結せず取引先企業や消費者の協力が必要となるため、大きな挑戦です。例えば原材料メーカーに省エネ・再エネ導入を促したり、物流業者と協力して輸送効率を上げたり、場合によっては製品の使い方まで工夫してもらう(省エネ家電や省エネ操作の啓発など)といった対応が求められます。
このように多岐にわたる関係者を巻き込むには相応の時間と調整が必要ですが、逆に言えば他社を巻き込んだ取り組み自体が企業のイニシアチブ発揮の場にもなります。成功事例で見たユニリーバのように、サプライヤーと連携し消費者行動にも働きかける包括的計画は理想的ですが、実現には自社の強い発信力と支援策が欠かせません。まずは自社の主要サプライヤーに対し、自社目標を共有して削減努力を要請することから着手し、必要に応じて技術面・資金面で協力する関係を築くことが現実的な一歩となるでしょう。また、移行計画にはこうした他者への働きかけ戦略も盛り込むべきとされており、自社だけでなく業界全体・社会全体の低炭素化にどう貢献するかという視点が重要です。
以上の課題に加え、社内意識改革やデータ整備(排出量の正確な把握・管理システム構築)といった課題も指摘できます。しかしこれらは裏を返せば、移行計画を推進する中で必然的に取り組むべき事項でもあります。国の支援策や産業界の連携も活用しつつ、計画達成への障壁を一つ一つ乗り越えていくことが肝要です。政府によるルール形成や技術革新のスピードは企業側で完全に制御できるものではないため、将来の不確実性も織り込んだ柔軟な計画とすること、そして一度立てた計画も定期的にアップデートしていく姿勢が重要です。
3.移行計画まとめ
製造業の企業が気候変動における移行計画を策定・実行する意義と難しさについて、事例と課題を通じて見てきました。移行計画は単なる環境対策に留まらず、企業の長期成長戦略そのものです。脱炭素社会への移行は困難な挑戦ではありますが、それを乗り越えた企業には新たな競争力と持続的成長の機会が待っています。実際、非財務情報の開示を積極的に行った企業の株価に良い影響が見られるとの報告もあり、気候対応と企業価値向上は両立し得ることが示唆されています。
製造業に携わる皆様も、自社の未来像を描く移行計画にぜひ取り組んでください。脱炭素方針を明確化し事業戦略と整合させること、バリューチェーン全体を巻き込んで持続可能な道筋を示すこと、そして不確実な未来に備えて計画を継続的に磨き上げることが成功のポイントです。移行計画を実践することで、貴社は持続可能な社会の実現をリードするとともに、自らも次世代に選ばれる強い企業へと進化できるでしょう。共に脱炭素への移行を推進し、カーボンニュートラル社会で輝く未来を築いていきましょう。
引用
移行計画ガイドブック
https://tcfd-consortium.jp/pdf/news/24083001/Transition_Plan_Guidebook_J.pdf