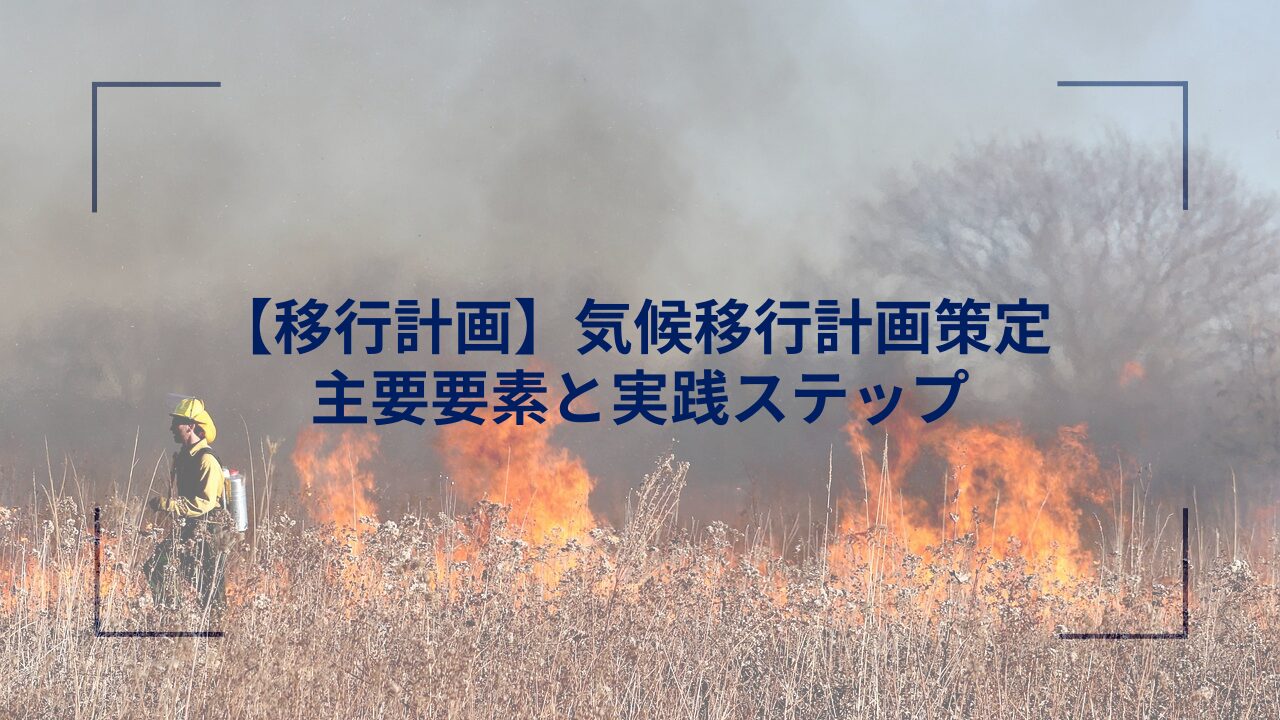製造業企業が効果的な気候移行計画を策定する方法を解説します。移行計画に盛り込むべき主要な構成要素(ガバナンス、戦略、リスク・機会、指標・目標)と、現状分析から目標設定、行動計画の立案・実行、進捗モニタリングまでの具体的なステップを示し、計画策定のポイントについて論じます。


1.移行計画の主要構成要素
気候移行計画を策定する際には、どのガイドラインを参照する場合でも共通して求められる重要な要素があります。それは主に次の4つです。
ガバナンス
気候変動対策を推進するための社内の統治体制です。経営層の関与と責任を明確にし、取締役会レベルで気候変動対応を監督する仕組みが求められます。例えば専門の気候戦略責任者(CCRO=Chief Climate Risk Officer)を任命したり、各部門の代表者からなる気候変動委員会を設置して定期協議することで、全社横断的な対策を進める体制を構築します。経営トップのコミットメントとリーダーシップは不可欠であり、気候変動への対応姿勢が企業文化に根付くようなガバナンス強化が重要です。
戦略
脱炭素に向けてどのような事業戦略を描くかという部分です。複数の気候変動シナリオ(例えば産業革命前比+2°Cシナリオや+4℃シナリオ等)を用いて、将来の政策・市場・技術動向を見据え、自社事業への影響を分析します。このシナリオ分析に基づき、低炭素社会でも競争力を維持・向上できる戦略を策定します。具体的には、製品ポートフォリオの見直し(低炭素製品やサービスへの転換)、必要な技術開発や設備投資、新規事業機会の探索などを計画に盛り込みます。また、分析結果に応じて事業の脆弱性や機会を洗い出し、移行リスク(規制強化や技術革新による影響)と物理的リスク(気候変動による災害等)が自社に与える財務インパクトも評価します。戦略面では「脱炭素への野心」と「事業成長」の両立が鍵となります。
リスクと機会の評価
上記戦略策定と並行して行うべきなのが、自社にとって重要な気候関連リスク・機会の特定とその評価です。製造業では業種特有のリスク(例:炭素集約型の工程が規制強化されるリスク、原材料価格高騰)や機会(例:低炭素製品市場の拡大によるビジネスチャンス)があります。こうした項目を洗い出し、発生確率や影響度を評価した上で、優先度をつけて対策を検討します。必要に応じて専門家の知見を借りたり、同業他社のベストプラクティスを参考にすることも有効です。このプロセスを通じて、移行計画に盛り込むべきリスク緩和策や機会追求策が明確になります。
指標と目標
計画の進捗を測定し目標達成度を評価するための定量的な指標(KPI)と、削減目標値の設定です。温室効果ガス排出量(GHG)の削減目標は不可欠で、Scope1(自社直接)、Scope2(購入エネルギー由来)、Scope3(バリューチェーン全体)にわたる削減目標を設定します。これら目標は科学的根拠に基づいた野心的な水準である必要があり、SBT(Science Based Targets)イニシアチブなど国際的枠組みに整合したものとすることが望ましいとされています。例えば「2050年までにネットゼロ」「2030年までに2010年比○%削減」など長期・中期目標を掲げ、それを実現するための中間マイルストーン(5年毎などの区切り目標)も設定します。さらにGHG以外にも、省エネ率や再生可能エネルギー比率、環境関連投資額、新製品売上高割合など、自社の進捗管理に有用な指標を定めます。長期目標から逆算して現在何をすべきかを決めるバックキャスティング手法を用い、各指標に対する具体的行動計画を策定すると、実効性の高い計画となります。
以上の4要素は相互に関連し合っています。例えば、ガバナンス体制がしっかりしていなければ戦略や目標が絵空事に終わる可能性がありますし、指標・目標が不明確ではリスク評価もうまく機能しません。網羅的でバランスの取れた計画とするために、これら構成要素を一体的に検討することが大切です。
2.移行計画策定の手順
移行計画を策定する際は、上記の構成要素を踏まえて段階的に進めると効果的です。一般的には次の5つのステップで計画を作り上げます。
現状分析
まず自社の現状把握から始めます。自社の事業活動によるGHG排出量(スコープ1・2、および可能ならスコープ3の主要項目)を算定し、排出源の特定とベースラインを確立します。また気候変動に関連する自社のリスクと機会を洗い出し、影響度を評価します(前述のリスク評価)。さらに関連する法規制の動向、業界標準や競合他社の取組状況も調査し、自社の強み・弱みを分析します。こうした分析により、何を優先すべきかの方向性が見えてきます。
目標設定
現状分析を踏まえ、削減目標を短期・中期・長期で設定します。長期目標としては例えば「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、中期目標(2030年や2040年時点の削減率)や短期目標(今後数年のKPI)を定めます。目標は科学的根拠にもとづき野心的な水準とする必要があります。社内外の信頼を得るため、SBTi認定など科学的に妥当と認められた目標にするのが望ましいでしょう。製造業では自社設備からの直接排出のみならず、原材料調達や物流などバリューチェーン全体での削減目標も検討します。
行動計画の立案
設定した目標を達成するための具体的な行動計画(アクションプラン)を策定します。ここでは、「何を、いつまでに、誰が、どの程度の予算で」実施するかを明確にします。例えば「〇〇工場で2025年までに太陽光発電設備を導入」「製造工程の廃熱回収を2028年までに全拠点で実装」など、施策ごとに担当部署・責任者、実施期限、期待される削減量や必要投資額を記載します。また各施策の進捗を測るKPIも設定し、定期的なモニタリング方法を決めます。行動計画には技術導入だけでなく、社内教育や組織体制整備(例:前述のガバナンス強化策)、取引先との協働(サプライヤーへの支援や調達基準設定)などソフト面の施策も含めます。実現可能性を高めるため、施策ごとに優先度をつけローンチ時期を調整するなど、リソース配分計画も検討します。
実行
策定した行動計画に基づき、各施策を社内外で実行に移します。計画の実行フェーズでは、必要に応じて組織や業務プロセスの変更を行い、計画推進に適した体制を整えます。例えば専門プロジェクトチームの設置、関連部署への権限委譲や予算配分の見直しなどです。従業員への教育・啓蒙活動も重要で、全従業員が自分事として脱炭素目標に取り組めるよう意識改革を促します。社内だけでなく社外パートナーとも協力し、技術提供やノウハウ共有を受けながら施策を着実に実行していきます。
モニタリング・見直し
計画の実施状況を定期的にフォローアップし、進捗と成果を評価します。例えば四半期ごと・年度ごとにGHG排出量やエネルギー使用量をモニタリングし、目標値とのギャップを検証します。目標達成が危ぶまれる場合は原因を分析し、必要に応じて計画を修正します。外部環境の変化(新技術の出現、予想以上の規制強化等)にも柔軟に対応し、移行計画自体をアップデートする体制が重要です。このPDCAサイクルを回すことで、移行計画は単なる書面上の計画でなく生きた戦略として機能し続けます。
以上のステップを順に踏むことで、網羅的で実効性の高い移行計画を策定できます。
3.計画策定成功のポイント
移行計画を策定・実行するにあたり、押さえておくべきポイントをいくつか挙げます。
経営層のコミットメント
計画を机上の空論に終わらせず全社的な取り組みにするには、トップマネジメントの強い意思表明とリーダーシップが欠かせません。経営陣自らが気候変動対応を企業戦略の最優先課題の一つと位置付け、率先してメッセージを発信することで社内の意識改革を促します。例えば脱炭素目標の達成状況を役員報酬に連動させるといった仕組みも有効でしょう。
全社横断の取組み
サステナビリティ推進部門や環境担当だけでなく、経営企画、財務、人事、調達、生産、営業など関連する全ての部署が自分ごととして関与する体制が重要です。部門間のサイロを排し、共通の目標に向けて協力する文化を醸成します。各部署の業務計画と移行計画とを連携させ、現場レベルの改善活動(省エネ活動や工程見直し等)を積み上げることで大きな成果につながります。
ステークホルダーとの対話
移行計画の策定・実行には、投資家、顧客、サプライヤー、地域社会など外部ステークホルダーの理解と協力も欠かせません。投資家には計画の進捗や達成見込みを誠実に開示しフィードバックを得る、サプライヤーには脱炭素化の要請とともに技術支援や協働の場を提供する、自治体とは補助金活用やインフラ面で連携するといった取り組みが考えられます。情報開示を通じて積極的に自社の努力を発信し、信頼関係を構築することが計画成功の一助となります。
最新情報の収集と専門家連携
気候変動に関する科学知見や脱炭素技術、政策動向は日進月歩で変化しています。常に最新動向をウォッチし、自社計画に反映させる姿勢が必要です。例えば新しい画期的技術が登場したら投資を検討する、国の補助金制度ができれば活用する、といった柔軟性を持ちます。また社内に知見が不足する部分は専門家の力を借りるのも有効です。コンサルタントや学術機関、業界団体などと連携し、ベストプラクティスを取り入れながら計画の精度を高めましょう。
以上のポイントを踏まえることで、策定した移行計画の実効性と社内外からの信頼性を高めることができます。移行計画はゴールではなくスタートです。計画策定後も継続的に改善を図り、企業文化として低炭素への取り組みを根付かせていくことが、製造業が持続的成長を遂げる鍵となるでしょう。
引用
移行計画ガイドブック
https://tcfd-consortium.jp/pdf/news/24083001/Transition_Plan_Guidebook_J.pdf