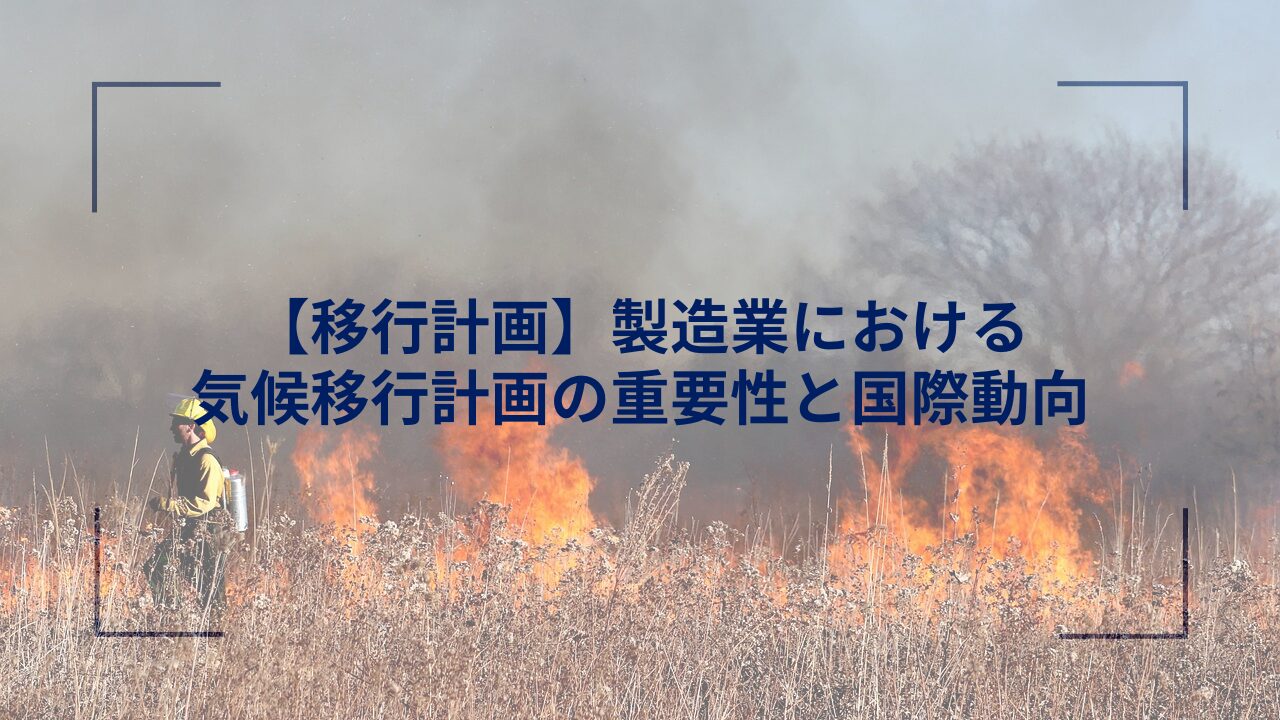製造業における気候変動への「移行計画」の重要性について解説します。本記事では、移行計画の定義や背景、国際的な潮流を整理し、企業にとってのメリットや策定しない場合のリスクを考察します。


1.移行計画とは何か
移行計画(トランジションプラン)とは、企業が脱炭素社会に向けて「現在の姿から将来の目標に至るまでどのように変化していくのか」を示す長期的な行動計画のことです。簡単に言えば、温室効果ガス排出削減の目標を定め、その達成に向けた具体的な施策や資源配分を示す企業戦略の一部です。たとえば国際会計基準のIFRS S2では、移行計画を「温室効果ガス排出量の削減などを含む、低炭素経済への移行に向けた目標・行動・リソースを示す企業の全体戦略の一つ」と定義しています。この計画には、自社の現状から目標達成に至るまでの道筋が含まれ、経営戦略に組み込まれていきます。
移行計画が注目される背景
近年、多くの国・地域が2050年カーボンニュートラル(温室効果ガス排出実質ゼロ)目標を表明し、2030年の中間目標も迫っています。そうした中、「企業がどのように脱炭素に取り組むか」という情報開示への投資家や社会の関心が急速に高まっています。特に金融機関や機関投資家は、気候変動リスクへの対応を企業評価の重要な要素としており、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言では気候リスク開示の一環として移行計画の開示が推奨されています。2021年にTCFDはガイダンスを改訂し、従来の戦略開示項目に「指標・目標・移行計画」を追加するなど、移行計画の重要性が一段と強調されました。また、国際サステナビリティ基準であるISSBのIFRS S2「気候関連開示」でも、事業計画と整合した移行計画が重要な開示項目の一つに挙げられています。
規制強化と国際動向
政策面でも企業に移行計画を求める動きが進んでいます。例えばEUでは企業サステナビリティ・デューデリジェンス指令案(CSDDD)において、パリ協定の1.5℃目標と整合した脱炭素移行計画の策定と実行を企業に義務付ける方向です。英国でも2022年に財務省主導で移行計画タスクフォース(TPT)が設立され、2050年ネットゼロに向けた移行計画の開示フレームワークを策定しています。国際会計基準のIFRS S2では前述のように企業が移行計画を持つ場合、その内容開示を求めており、こうしたグローバル基準の整備により「移行計画」は今後ますます重要な経営課題となる見込みです。
2.製造業における移行計画の必要性
投資家・金融機関からの要請
製造業は他産業に比べ温室効果ガス排出量が多く、気候変動対応へのプレッシャーが大きい分野です。投資家は製造業企業に対し、長期的な脱炭素ビジョンと具体的な移行計画の提示を強く求めています。移行計画を策定・開示することは、企業の気候変動対応への本気度を示すシグナルとなり、ESG投資の観点から重要視されています。実際、移行計画を明確に示すことで国内外からの資金調達機会や企業価値の向上につながる可能性があります。特に製造業では設備投資や技術開発に多額の資金が必要なため、投資家の信頼を得て資金調達を円滑にするためにも説得力ある移行計画が不可欠です。
企業価値と競争力への影響
適切な気候移行計画を有する企業は、投資家からの評価が向上し資金調達コストの低減が期待できるだけでなく、気候変動リスクの軽減や事業継続性の確保にもつながります。さらに、脱炭素に向けた革新的製品やプロセスの開発を通じて新たなビジネス機会を創出でき、市場競争力の強化にも寄与します。例えば省エネルギー技術や再生可能エネルギーの活用はコスト削減と環境対応の一石二鳥となり得ますし、環境意識の高い顧客層からの支持獲得にもつながります。また、気候対応に積極的な姿勢を示すことは自社ブランドのイメージ向上にも貢献し、優秀な人材の確保・社員のモチベーション向上といった効果も期待されています。
策定しない場合のリスク
他方で、移行計画を持たない企業は様々なリスクに直面し得ます。まず、気候対策に消極的と見做されれば投資家や金融機関からの評価が低下し、将来的に資金調達コストの上昇や投資機会の減少を招く恐れがあります。また各国で炭素税や排出規制が強化される中、対応の遅れは規制違反リスクや事業機会の損失につながります。さらに消費者や取引先からの信用低下(レピュテーションリスク)により製品が選ばれなくなる可能性もあります。実際、移行計画の有無は企業評価に直結しつつあり、「描いただけ」の曖昧な目標ではなく具体的行動計画を示さなければ厳しい目が向けられる時代になっています。持続可能な経営の道筋を示せない企業は、将来的に市場から淘汰されかねないという危機感が必要でしょう。
3.国際潮流と製造業への影響
世界の企業の取り組み状況
移行計画の策定・公表は世界的な潮流となっています。ある調査によれば、世界51か国・地域の大手企業1,536社中、約53%が具体的なネットゼロ戦略や移行計画を開示済みであり、さらに25%の企業が1.5℃目標に沿った気候移行計画を策定済みと回答しています。加えて約36%の企業が「今後2年以内に計画を作成する予定」としており、今後ほぼ全ての主要企業が何らかの移行計画を持つ時代になることが予想されます。製造業企業にとってもこれは他人事ではなく、自社が属するバリューチェーン全体で脱炭素化戦略を示すことが求められるでしょう。
ステークホルダーからの圧力
こうしたグローバルな動向を受け、日本の製造業も対応を迫られています。欧州連合のCSRD(企業サステナビリティ報告指令)や米国SECの気候関連開示規則案など、海外市場で事業を展開する企業は気候関連情報開示の厳格化に直面しています。サプライチェーン上位に位置する日本の製造業は、取引先や多国籍企業から排出削減計画の提示を求められるケースも増えています。さらに、国内でも金融庁の開示指針や環境省のTCFDガイダンス等で移行計画の開示が推奨され、主要企業では統合報告書やサステナビリティレポートに移行計画を組み込む動きが一般化してきました。要するに、移行計画は単なる環境対応ではなく企業の中長期的な競争戦略として不可欠であり、特に製造業ではその影響が大きいと言えます。
4.移行計画まとめ
移行計画は企業の未来を左右する重要な戦略です。製造業にとって、脱炭素への対応は避けて通れない課題である一方、うまく取り組めば競争優位性や企業価値向上のチャンスにもなります。2030年という中間目標の期限が近づく中、投資家や社会からは「持続可能な道筋」を示すことが強く求められています。移行計画をしっかりと策定・実行することで、製造業企業は脱炭素時代においても信頼され持続的に成長する存在へと進化できるでしょう。企業のサステナビリティ推進担当者は、移行計画を自社の成長戦略の一環と捉え、積極的にその策定・推進に取り組む必要があります。
引用
移行計画ガイドブック
https://tcfd-consortium.jp/pdf/news/24083001/Transition_Plan_Guidebook_J.pdf