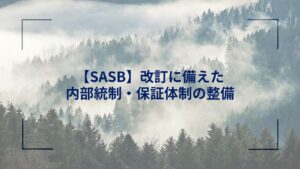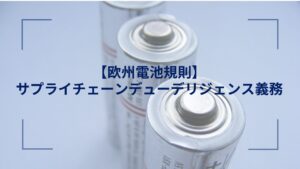環境データに対する第三者保証とは、企業が開示する環境関連のデータ(例:温室効果ガス排出量、水使用量、廃棄物排出量など)の正確性と信頼性を、独立した専門機関が検証し保証することを指します。本記事では、環境データ第三者保証の重要性とそのメリット、一般的なプロセス、そして水資源管理から廃棄物処理、エネルギー使用量、大気汚染物質、土地利用・生物多様性、資源消費、製品ライフサイクルに至る各分野で、第三者保証の適用とポイントを解説します。第三者保証の導入によって環境情報の信頼性が向上し、ステークホルダーや投資家からの信頼獲得につながるため、サステナビリティ経営を推進する企業にとって重要な取り組みとなっています。


1.環境データ第三者保証の重要性とメリット
環境データは企業のESG報告やサステナビリティ報告において重要な要素であり、その信頼性確保が求められています。第三者保証を受けることで情報の透明性と信頼性が飛躍的に向上し、ステークホルダー(投資家や取引先、地域社会など)からの信頼を得ることができます。特に、ESG投資の拡大に伴い非財務情報の正確性への関心が高まっており、欧州のCSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)のようにサステナビリティ情報開示への第三者保証が制度的に求められる動きも進んでいます。
第三者保証のメリット
第三者保証の主なメリットとしては、開示情報の正確性担保によるステークホルダーからの信頼向上、それに伴う投資家評価の向上と企業価値の長期的な向上、および内部管理プロセスの改善(データ収集・管理体制の強化)などが挙げられます。単に社内でデータを報告するだけでは「本当に正しいのか?」という疑念が残り得ますが、独立した専門家の検証を経ることで情報の信ぴょう性が担保されるのです。
環境パフォーマンス改善
また、第三者保証は企業の環境パフォーマンス改善にも寄与します。検証プロセスにおいてデータ算定方法や管理体制についてのフィードバックを受けることで、データ計測手法の精度向上や報告プロセスの是正が図れます。結果として、環境対策のPDCAサイクルが強化され、持続的なパフォーマンス改善につながります。さらに、保証付きのデータは国際イニシアチブ(CDPやGRIなど)への回答や評価において有利に働きます。実際、CDPは企業が報告する環境データを独立第三者により検証することを推奨しており、適切な基準に沿った検証を経た企業は高い評価(スコア)を得られるとしています。このように、第三者保証の取得は企業の環境リーダーシップを示すものとも位置付けられています。
2.第三者保証の枠組みとプロセス
第三者保証は通常、国際的に認められた基準に従って実施されます。代表的なものに、IFAC(国際会計士連盟)が定めるISAE 3000(財務情報以外の保証業務に関する基準)や、GHG排出量検証に特化したISO 14064-3(温室効果ガス主張の検証基準)などがあります。保証業務には「限定的保証」と「合理的保証」のレベルがあり、サステナビリティ報告では一般的に限定的保証(限られた手続きで否定的表明を行う形式)が採用されることが多いです。保証人(監査法人や第三者検証機関)は、企業と合意した範囲・手法で検証を実施し、最終的に保証報告書(独立保証報告書)を発行します。検証プロセスの一般的な流れは次のとおりです。
事前準備
検証計画の策定と、必要資料の事前提出・確認を行います。
文書レビュー
データ算定ルールや組織のデータ管理体制について文書ベースで審査します。
現地検証
工場や事業所等をサンプリング訪問し、現場でのデータ計測方法や記録の管理状況を検証します。そこで不備や矛盾があれば指摘し修正を依頼します。
データ確認・再計算
提出された環境データの集計方法や根拠資料を精査し、必要に応じて元データとの突合や再計算を行います。
修正対応の確認
検証過程で発見された不備(算定誤りや不明瞭な点)について、企業が修正・改善した内容を再確認します。
テクニカルレビュー
検証機関内部で、担当検証人とは別のレビューアが保証意見の妥当性をチェックします。
保証報告書の発行
最終的な検証結果にもとづき、第三者保証報告書を作成・発行します。
この報告書には保証範囲、使用基準、保証レベル、対象データ、基準からの逸脱の有無などが記載されます。
保証の対象となるデータ範囲は、企業のニーズやステークホルダー要請に応じて決定されます。一般的には、環境分野では温室効果ガス(GHG)排出量、水使用量、廃棄物排出量などが主要な検証対象データとなっています。近年ではこれに加え、エネルギー消費量や再生可能エネルギー利用量、VOC等の大気汚染物質排出量、また一部企業では労働安全や社会データまで含めて保証を受けるケースもあります。実際に、日本の大手企業でも「環境データ(GHG、エネルギー、水、廃棄物)および一部社会データについて独立保証を取得」する例が増えています。
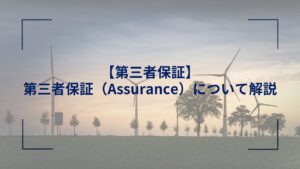
3.水使用量・水資源管理データの第三者保証
水資源は事業継続や地域環境に直結する重要な資源であり、企業は取水量(withdrawal)や排水量(discharge)、水消費量(使用して蒸発等で失われた水量)などのデータを管理・報告しています。特に水ストレスの高い地域で操業する企業にとって、水使用量の削減や循環利用は重要な課題です。この分野の代表的指標には、総取水量、排水量、再生水利用率、水循環率などがあります。第三者保証を受けることで、こうした水使用データの正確性や算定プロセスの適切性が確認され、社内外への信頼性が高まります。
第三者保証
第三者保証の過程では、各事業所のメーター測定値や水道使用量の請求書、水再利用の記録などがサンプリングされ、その集計手順が点検されます。CDPウォーターセキュリティやGRI 303(水と排水)などの開示基準に沿った報告がなされているかも確認点となります。第三者保証を付与された水使用量データは、開示情報への信頼性付与だけでなく、水リスク対応の実効性を示す指標として投資家にも評価されます。例えば楽天グループでは、全社の廃棄物と水データを収集し第三者保証を取得することで、水取水量削減の取り組みを裏付け、社内啓発にも活用しています。

4.廃棄物処理・循環型経営データの第三者保証
循環型経営の推進において、事業活動から生じる廃棄物の総排出量やリサイクル率等のデータ管理は不可欠です。企業は一般廃棄物・産業廃棄物の排出量、再資源化量、最終処分量(埋立量)などを計測・報告し、廃棄物削減やリサイクル率向上の目標管理を行います。これらの廃棄物データに第三者保証を受けることで、データが正確に算定・集計されていることが裏付けられ、ステークホルダーに対し循環型社会への貢献度合いを信頼性高く示すことができます。
第三者保証
保証プロセスでは、廃棄物量の算定根拠(マニフェスト集計や処理業者からの報告値)、リサイクル率の計算方法、範囲(事業所範囲やグループ会社範囲)が検証対象となります。たとえば廃棄物処理法に基づく産業廃棄物区分ごとの量が適切に集計されているか、リサイクル量に過大・過小計上がないか、といった点をチェックします。第三者保証によって確認されたデータは、社内では廃棄物管理のPDCA強化に活かされ、社外には循環経済へのコミットメントの証として提示できます。

5.エネルギー使用量・再生可能エネルギー利用量データの第三者保証
エネルギー使用量(燃料や電力の消費量)は、気候変動対策やコスト管理の観点から企業にとって重要な環境データです。また、再生可能エネルギー(再エネ)利用量・率は脱炭素経営の指標として注目されています。エネルギー消費量データはGHG排出量算定(スコープ1・2)とも密接に関連するため、その正確性保証は気候関連情報の信頼性確保に直結します。第三者保証では、購入電力量や燃料使用量の記録が正しく集計され、適切な排出係数の適用など算定ルールが遵守されているか検証されます。
第三者保証
再生可能エネルギー利用量に関しては、再エネ電力の購入証書(非化石証書など)の確認や、自社発電再エネの計量などが検証ポイントになります。企業が「電力使用量のうち再エネ比率XX%」と主張する場合、その計算根拠(電力使用総量と再エネ由来量)が正しいか、二重計上や属性の齟齬がないかを保証人がチェックします。保証を受けた再エネ利用データは、RE100やCDP気候変動の評価において説得力を持つ数字となります。総じて、エネルギーデータへの第三者保証は、脱炭素に向けた実績報告の信ぴょう性を高め、気候関連財務情報開示(TCFD報告等)の質を向上させる効果があります。
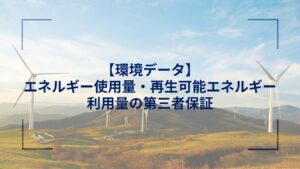
6.大気汚染物質排出量データ(VOC・NOx・SOx等)の第三者保証
大気汚染物質(揮発性有機化合物VOC、窒素酸化物NOx、硫黄酸化物SOx、粉じんなど)の排出管理は、工場等を有する企業では法規制順守および環境影響低減のための重要課題です。排出量データは主に環境省や自治体への報告(PRTR制度や大気汚染防止法の届け出)を通じて公表されるケースが多いですが、サステナビリティ報告の中で自主的に開示する企業も増えています。こうした大気汚染物質排出データについても第三者保証を付与することで、環境コンプライアンスおよび公害防止の取り組み状況に関する情報の信頼性を高めることが可能です。
第三者保証
大気汚染物質データの検証では、排出濃度測定結果の集計や、燃料使用量からの排出推計手法などが対象となります。例えばNOx排出量であればボイラーや焼却炉の燃料消費と係数による算出が正しいか、VOC排出量であれば有機溶剤の購入・使用量からの推計に漏れがないか、といった点です。もっとも、GHGやエネルギー・水と比べて大気汚染物質データに保証を付ける企業はまだ限定的で、どちらかと言えば法令遵守としてのモニタリングデータ公開にとどまるケースもあります。しかし環境報告の高度化に伴い、一部では自主的にこれらデータも保証範囲に含める動きが出ています。第三者保証が付いた大気汚染物質排出データは、地元コミュニティや環境NGOへの説明責任を果たす上で強い裏付けとなり、企業の環境リスク管理姿勢を示す材料となります。

7.土地利用・生物多様性への影響データの第三者保証
企業活動による土地利用(敷地面積、開発面積)や生物多様性への影響(生態系への配慮状況、植樹本数、保全エリア面積など)は、定量化が難しい分野ではありますが、自然資本の開示として徐々に重視されてきています。例えば操業拠点の土地面積や、そのうち自然保護区画面積などのデータ、事業で喪失・創出された生息地面積、植林や生物種モニタリング数値などが該当します。これらの自然資本・生物多様性データについて第三者保証を得ることは現時点ではそれほど一般的ではありませんが、非財務情報の信頼性向上の観点から徐々に検討が進んでいる分野です。
第三者保証
今後、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の枠組み整備や、生物多様性クレジット制度の登場により、企業の自然資本データ開示の重要性が増すと予想されます。その際には、温室効果ガス排出量と同様に、土地利用や生物多様性指標に関しても信頼性確保のため第三者保証の需要が高まるでしょう。第三者保証人は、生物多様性の専門知見を有するコンサルタント等が務め、保全活動の成果指標(例えば植樹本数が記録と一致するか、保全面積測定の根拠)を評価すると考えられます。もっとも数値化が難しい領域ではあるため、「確認可能な定量データ」に絞って保証を付ける(例:敷地面積や植樹本数など確実に測定できるもの)形が現実的です。

8.資源消費・原材料使用データの第三者保証
製造業などでは、投入した原材料の重量や、製品中の再生材使用率、包装材料使用量などの資源消費データを管理することがサステナビリティ上重要です。たとえば「年間○○トンの原材料を使用し、そのうち△△%がリサイクル材」や「プラスチック包装材使用量〇〇トン削減」といった情報です。これらの資源消費データについて第三者保証を受けることで、企業の資源効率向上や循環経済への取り組みに関する主張に信頼のお墨付きを与えることができます。第三者保証では、原材料購入記録や生産量データをもとにした投入量計算の検証、再生材利用率の算出根拠の確認(サプライヤー提供情報のトレースなど)、包装材重量のサンプリング計測確認などが行われるでしょう。

9.製品ライフサイクルにおける環境影響データの第三者保証
製品やサービスのライフサイクル全体での環境影響評価(LCA: Life Cycle Assessment)は、近年製品の環境ラベルや環境宣言(EPD: Environmental Product Declaration)などで活用されています。製品ライフサイクルにおけるカーボンフットプリント、水フットプリント、資源採掘から廃棄までの総環境負荷といったデータは、その算定プロセスが複雑なため、第三者による検証が推奨される分野です。例えばEPDはISO 14025に基づく環境宣言であり、その発行には独立第三者の検証が必須となっています。企業単位のサステナビリティ報告でも、自社製品のLCA結果を掲載する場合に、その計算手法や結果について専門家の第三者検証を受けることがあります。
第三者保証
第三者保証プロセスでは、LCAの前提条件(システム境界、機能単位、データ品質)、インベントリデータの正確性、影響評価手法の適切性が検証されます。具体例として、業界団体が作成する製品カテゴリルール(PCR)に則って計算された製品環境フットプリントを、外部検証員が再現検証し、問題がなければ認証を与えるという流れです。企業の環境報告においてLCAに関する記述がある場合、可能であれば第三者のレビューコメントや保証声明を添えることで、読者に対してそのデータの信頼性を明示することが望ましいでしょう。
以上、環境データの第三者保証の概要と各分野への適用可能性について概説しました。環境データの正確性と透明性を担保する第三者保証は、ステークホルダーからの信頼獲得、企業価値向上、さらには地球環境課題の解決への実効性を高める上で重要な役割を果たします。サステナビリティ推進担当者にとって、自社のどの環境データを保証対象とすべきか、どの基準・機関で検証を受けるべきかを戦略的に検討し、信頼性の高い情報開示を行っていくことが求められています。