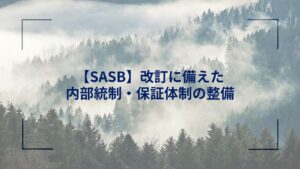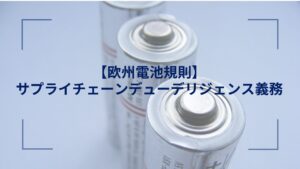製品ライフサイクル全体での環境影響評価(ライフサイクルアセスメント, LCA)は、原材料の採取から製造、流通、使用、廃棄・リサイクルに至るまでの各段階における環境負荷を定量化する手法です。企業はLCAに基づく製品の環境プロファイル(カーボンフットプリントやウォーターフットプリント等)を開示し始めており、その信頼性を確保するために第三者保証や検証を受けるケースが増えています。本記事では、製品ライフサイクル環境影響データの概要、評価上の課題、第三者保証の意義、関連基準、国内企業の事例、将来展望を論じます。


1.製品ライフサイクル環境影響評価(LCA)データの概要
LCA(Life Cycle Assessment)は製品やサービスに関連する環境影響を定量化する包括的手法であり、気候変動への影響(CO₂排出量)だけでなく資源消費量、エネルギー使用量、排水・廃棄物、その他大気汚染物質排出量など多岐にわたる環境負荷指標を網羅します。LCAによって得られる代表的なデータとしては、製品1単位あたりのカーボンフットプリント(CFP: CO₂換算排出量)、ウォーターフットプリント(WF: 水使用量)、一次エネルギー消費量、大気汚染物質排出量(NOx, SOx等)、廃棄物発生量などが挙げられる。
開示
企業が開示する場合、特定製品のライフサイクルCO₂排出量(例えば自動車1台あたりの製造〜廃棄までのCO₂総排出量)や、建材1kgあたりのCO₂とSOx排出量、食品1包装あたりの水使用量などといった形で公表されることが多いです。近年はこれらを標準化した環境製品宣言(EPD: Environmental Product Declaration)として公開する動きも盛んであり、EPDはISO 14025に準拠した国際的な枠組みの下で製品ごとの環境影響データを公開する仕組みです。
TOTO株式会社
たとえば、TOTO株式会社は自社の主力製品(温水洗浄便座、陶器衛生器具、水栓金具)の4カテゴリについて、それぞれ製品ライフサイクル全体のCO₂排出量・エネルギー使用量・水資源への影響などを算定し、EPDとして開示しています。このようなデータは製品環境性能を示す指標として、顧客や調達先にも提供され、サステナブルな製品選択を促す材料となります。
2.LCA評価の課題と不確実性
製品ライフサイクル環境影響データの算定には高度な専門知識と膨大なデータが必要であり、いくつかの課題と不確実性要因が存在します。
システム境界の設定
ライフサイクルをどこまで含めるか(原材料採掘から排気まで全て含む “Cradle to Grave” か、製造出荷までの “Cradle to Gate” か等)によって結果が変わるため、明確なルール設定が必要です。EPD作成時にはプロダクトカテゴリールール(PCR)が用意され、各業界で統一の境界・算定方法を定める努力がなされているが、全ての製品で網羅されているわけではありません。また新規性の高い製品では適切なPCRが存在しないこともあり、個別に前提条件を設定する必要があります。
データ取集の困難さ
ライフサイクル各段階の環境負荷を算出するには、多数の工程や部材のデータが必要です。自社製造工程のデータは比較的揃えやすいですが、サプライヤー工程や使用段階、廃棄段階のデータは推計に頼る部分が大きいです。一般的にLCAソフトウェアやデータベース(e.g. Ecoinventなど)の平均データを使用して補完しますが、それらが自社実態と乖離しているケースもありえます。例えば海外製の部材を使っている場合、その製造電力の炭素強度(CO₂排出係数)をどう設定するかで結果が変動します。
影響評価モデルの選択
LCAではインベントリデータ(物質収支データ)を集計した後、潜在的環境影響量に換算するステップがある(例:メタンをCO₂換算するなど)。この際、どのインパクトカテゴリを評価対象に含めるか、評価手法はTRACIかReCiPeかなど、様々な選択肢があります。結果として、同じ製品でも評価手法の違いで数値が変わることがあるため、報告時には手法を明記する必要があります。
前提条件の扱い
例えば「使用段階」はユーザーがどう使うかで環境負荷が大きく変わる。自動車なら走行距離や燃費、エアコン使用有無、食品なら冷蔵期間、洗剤なら使用量、建材なら使用寿命など、仮定を置かなければなりません。この仮定が実態と異なると数字の信ぴょう性が疑われてしまいます。したがって業界標準に合わせる、あるいは複数シナリオを提示するなどの工夫が求められます。
以上のような不確実性を内包するLCAデータを公表するには慎重さが必要であり、第三者保証の重要性が際立っています。
3.第三者保証(検証)の意義
製品ライフサイクル環境影響データへの第三者保証(厳密には「検証」と称されることも多い)は、LCAの専門家が計算手法やデータをレビューし、妥当性を確認するプロセスです。
前提条件・ルールの適合性確認
その意義は、まず前提条件・ルールの適合性確認にあります。保証人(第三者検証人)は、そのLCAが該当するISO標準(ISO 14040/44など)やPCRに沿って行われているかを詳細に検証します。例えば境界の設定が適切か、カットオフルール(無視した小さな要素はないか)が標準通りか、代替シナリオの必要性はないかなどがチェックされる。これにより、企業独自の都合で有利な前提を置いていないことが保証されます。
データ品質の確認
次にデータ品質の確認である。検証では、主要なインプットデータについて信頼できる出所かどうか確認します。自社計測値であれば計器校正状況や記録のトレーサビリティを、外部データベース値であれば最新版かつPCR推奨のものか、といったイメージです。TOTOの事例では、国際EPDシステムの枠組みで厳格な第三者検証を経てEPDが発行されており、ここでは日本・ドイツ・イタリアの専門家チームがデータをクロスチェックしたと報じられています。このように多角的な検証により、データエラーや古い係数の使用、計算ミスなどが是正される効果があります。
透明性・再現性の担保
第三者検証済みのLCA結果は、その計算書一式を一定期間公開することが多いです(EPDの発行に際しては裏付けとなるLCAレポートがまとめられる)。検証人はその報告が再現可能なレベルで記述されているか確認するため、恣意的なブラックボックス計算になっていないことが保証されます。この透明性確保により、利用者は結果を信頼し、自分の製品や他社製品と比較する際も公平に判断できます。
第三者保証(検証)付きLCAデータを保有することは、企業にとって国際競争力の強化にもつながります。欧州では建築分野でEPD取得が入札要件となる例も出てきており、検証済みの環境情報がない製品は市場機会を逃す可能性がある為、検証済みCO₂排出量を提示できるか否かが差別化要因となるでしょう。
4.関連する標準と基準
製品LCAデータの第三者保証(検証)は主にISO 14025(環境ラベルIII型=EPD)およびISO 14040/14044(LCA手法)に基づき実施されます。
ISO 14025
ISO 14025ではEPDプログラム運営者による第三者検証を義務付けており、製品カテゴリごとにPCRを定め、そのPCRに則ったLCA結果を独立検証人が審査した上でEPDを発行する仕組みになっています。この検証プロセス自体が事実上の第三者保証です。
国際的に著名なEPDプログラムとして、スウェーデン発祥のInternational EPD System、ドイツのIBU、フランスのPEP、日本のエコリーフなどがあり、それぞれISO14025適合の検証プロセスを有しています。例えばInternational EPD Systemでは、登録された検証人(第三者)がLCAレポートとEPD原稿を審査し、適切なら発行承認します。テュフズードはこのInternational EPD Systemの下でTOTOの製品4カテゴリの検証を行ったとされ、そのEPDには「このEPDは第三者検証済み」と明記されています。
参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000205.000017062.html
ISO 21930
その他の関連基準としてISO 21930(建築製品のサステナビリティ指標)もあります。これは建材EPDの指針で、ISO14025を補完するものだが、検証手順も含まれています。各国でEPD制度が広がる中で、検証基準はISO14025+PCRという形でほぼ標準化されつつあると言えます。
一方、任意の企業が独自に発行するLCA報告書に対して第三者保証を付ける場合は、ISAE3000に則った保証業務として行われる場合もあります。例えば自動車メーカーが自社車種のLCA結果(CO₂, NOx排出量など)をアニュアルレポートに載せ、その一部として監査法人が限定的保証する、といったケースです。この場合、ISO準拠かどうかといった技術的部分だけでなく、開示情報としての一貫性や重要なミスの有無をチェックする視点が加わります。ただ、製品単位のLCA結果は複雑であるため、一般的には専門のLCA検証スキーム(EPD等)に乗せる方が多いです。
5.日本企業の事例と保証機関
日本では、TOTO株式会社が前述の通りウォシュレット等の製品でEPDを取得し、第三者検証を受けた例が注目されます。同様にLIXILやパナソニックなど住宅設備・家電系でも、欧州市場をにらんで製品EPD取得と検証を進めています。建設・建材分野では、大成建設や積水化学工業などがエコリーフ環境ラベルを活用し、自社製品・工法のLCA結果を検証付きで公表しています。またトヨタ自動車は自社のサステナビリティ報告で主要車種のライフサイクルCO₂排出量を開示し、独立検証済みであることを示しています。
6.今後の展望
製品ライフサイクル環境影響に対する第三者保証の需要は、今後飛躍的に高まると見込まれます。
主な要因は以下の通りです
政策と市場の要請
欧州のグリーンディール政策やカーボンニュートラル方針の中で、製品段階での環境情報開示(デジタル製品パスポート等)の制度化が進んでいます。例えばEUは一定製品についてライフサイクルCO₂排出強度の表示を求める方向であり、その裏付けとして第三者検証されたLCAデータが不可欠となります。また国際的な大手企業はサプライヤーに対し製品CFP情報の提供を求めるようになってきており、その真実性を保証する第三者証明がないと信頼してもらえない可能性があります。
消費者意識の高まり
消費者が環境性能を比較して購入する動きが見られる中で、いわゆるグリーンウォッシュ(環境メリットの誇張)を避けるために第三者認証ラベルを活用する例が増えています。例えばフランスではファッション製品に環境スコア表示義務が検討され、嘘の表示には罰則も検討されています。その対応としても、企業は第三者が検証したLCAに基づくスコアを使う必要が出てくるでしょう。
LCAの自動化・効率化
製品設計段階から部品のLCAデータを組み込んでおき、完成品LCAを瞬時に計算できるツールが進化している。またブロックチェーン等でサプライチェーンの環境データを共有する試みもあり、将来的には製品ごとにリアルタイム更新される環境データが手に入るかもしれません。そうなれば第三者保証人も、継続的監査に近い形でデータ流を監視・検証する体制に移行する可能性があります。
標準化
標準化の面では、現在はEPDが製品別保証の主流ですが、企業単位での製品ポートフォリオ全体のLCA保証という考え方も出てくるかもしれません。例えば「当社の全製品群のライフサイクルCO₂排出総量を第三者保証済みで算定し、2030年までに○%削減」といった目標管理が考えられます。これはScope3(製品使用・廃棄段階)排出の実質算定であり、企業の気候目標との連携も進むでしょう。
総じて、製品ライフサイクルにおける環境影響の第三者保証は、環境配慮型経営を総合的に支える重要な仕組みとなっていきます。企業は高品質なLCAデータを蓄積しつつ、独立した専門家の知見を借りてその信頼性を確保し、持続可能な製品・サービスを胸を張って提供できる体制を築くことが求められます。