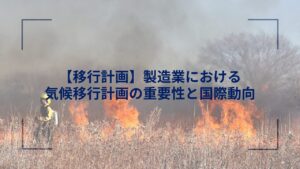CDP水セキュリティは、水資源リスクの高まりを背景に、企業の持続可能な水管理を評価する国際的な開示枠組みです。企業には水使用量や排水、地域連携、水リスクへの対応策などの情報開示が求められ、高スコア獲得はESG評価やレジリエンス強化に直結します。本記事では、CDP水セキュリティが注目される理由と、企業が取るべき水リスク管理戦略について解説します。


1. CDP水セキュリティが重視される理由
水セキュリティ(水安全保障)とは、企業や社会が安定的に必要な水資源を確保し、水関連リスクを適切に管理できる状態を指します。近年、世界的に水資源を巡る課題が深刻化しており、企業経営においても水の問題は無視できないものとなっています。CDPが2010年後半から気候変動に加えて「水セキュリティ」分野の情報開示プログラムを開始した背景には、以下のような理由があります。
物理的リスクの顕在化
気候変動や人口増加、経済発展に伴い、地域によっては深刻な水不足(渇水)や水質汚染が発生しています。また一方で、洪水や豪雨といった水害リスクも増大しています。こうした水の過不足や質の問題は、企業の生産活動に直接影響を及ぼします。工業プロセスに多量の水を必要とする産業では、生産拠点での取水規制や水不足は事業継続の脅威となり得ますし、洪水被害で工場が操業停止に追い込まれるケースもあり得ます。CDPはこれら水関連リスクを企業が正しく認識し、対策を講じているかを明らかにするために水セキュリティ情報の開示を促しています。
経済的影響の大きさ
CDPの試算によれば、水リスクが企業の財務に与える潜在的損失額は世界全体で3,360億米ドルにも上るとされています。一方で、水リスクに対して行動を起こすことで得られるビジネス機会も存在し、CDPに報告された水関連の商機の総額は7,110億米ドルに達すると報告されています。つまり、水問題への対応次第で、企業は巨額の損失を被る可能性もあれば、逆に新たな価値創造の機会を掴む可能性もあるということです。この経済インパクトの大きさから、投資家も企業の水リスク管理に注目し始めており、CDPの水プログラムは投資家に有用な情報を提供する役割も果たしています。
社会的責任と規制強化
水は地域社会の共有資源であり、企業による過剰利用や汚染は地域住民との摩擦や評判リスクを引き起こします。近年は各国政府や自治体も水資源の保全に向けた規制を強める傾向にあります。例えば工場排水の水質規制強化、地下水採取量の規制、水使用に対する課金制度導入などです。企業がこうした動きに対応しないと、事業許可の維持や新規プロジェクトの承認が得られない可能性も出てきます。CDP水セキュリティプログラムは、企業の水利用状況や方針の透明性を高めることで、社会や規制当局との建設的な対話を促す側面もあります。
以上を踏まえ、CDP水セキュリティ質問書は2018年頃から本格的に多くの企業へ送付されるようになり、2023年には全世界で約1,200社が回答を提出しました。特に投資家からの回答要請が年々増加しており、2023年の要請企業数は前年から122%も増えたというデータがあります。これは、水問題への関心が急激に高まっている証左と言えます。CDP水セキュリティプログラムでは、企業に対し自社の水使用と管理状況、水リスクおよび対応策、さらに機会や目標設定まで一連の情報開示を求めています。次章では、その内容を概観しつつ、企業が具体的にどのような水リスクに直面し、どのような対応戦略を取るべきかを解説します。
2. 企業の水リスクとその種類
企業が直面する水リスクは大きく分けて3種類あります。物理的リスク、評判(レピュテーション)リスク、そして規制・財務リスクです。これらは相互に関連し合い、複合的に企業活動へ影響を及ぼします。
物理的リスク
文字通り水資源の物理的な不足や過剰、劣化に起因するリスクです。代表的なものが水不足(渇水)です。工場や発電所など大量の水を使う施設では、渇水により取水制限がかかると生産量の低下や操業停止に直結します。例えば半導体工場では超純水が不可欠ですが、渇水時に地域のダム貯水率が低下すると給水カットの恐れがあります。また逆に洪水・浸水被害も物理的リスクです。大雨や河川氾濫で工場や倉庫が浸水すると設備損害や在庫商品の喪失が発生します。さらに、水質の悪化(例えば上水源の汚染)もリスクです。飲料メーカーや食品工場では、水質基準を下回ると生産に支障が出ますし、追加の浄化コストがかかります。近年の気候変動で降雨パターンが変化し、渇水と洪水の振れ幅が大きくなっているため、多くの企業が複数拠点で物理的水リスクに晒されつつあります。
評判リスク
企業の水利用や排水処理に関する社会的評価が下がることで生じるリスクです。たとえば、ある工場が地下水を過剰に汲み上げ周辺住民の井戸枯れを起こした場合、地域社会から強い非難を浴び企業イメージが損なわれます。あるいは工場排水による河川汚染が発覚すれば、SNS等で瞬く間に悪評が広がり不買運動に発展することも考えられます。また投資家も企業の水関連不祥事には敏感で、そうした評判悪化は株価下落や投資引揚げに繋がる可能性があります。水は生命に直結する資源であり、企業が「水を汚している」「地域の水を奪っている」と見られることは深刻な評判リスクとなります。
規制・財務リスク
水に関する法律規制や経済的な影響によるリスクです。典型例は水使用に係る規制で、地域行政が取水許可量を減らしたり、水源からの取水に料金を課すようなケースです。そうなると事業コストが増大したり、生産可能量が制限されます。また排水規制の強化により新たな高度処理設備の導入を迫られる場合もあります。さらには、水関連のトラブルで訴訟を起こされ賠償金支払いが発生するといった法的・財務的リスクもあります。こうした直接的なものだけでなく、投資家がESG評価の一環で水リスクの高い企業への投資比率を下げる、融資銀行が大規模水使用プロジェクトに融資を渋る、といった資金調達上のリスクも潜在的に存在します。
CDP水セキュリティ質問書では、企業が自社に関連するこれら水リスクを特定し、重要度の評価を行ったかどうか、またそのリスクにどう対処しているかを回答することになっています。つまりまず「自社の水リスクマップ」を作成する必要があります。多くの企業はWRI(世界資源研究所)のAqueduct等のツールを用いて各拠点の水ストレスを評価したり、気候変動シナリオに基づく水供給リスクの将来予測を行っています。またステークホルダーとの関係性も分析し、地域コミュニティやNGOから懸念が提起されていないかをチェックします。
サントリーホールディングス
飲料業界のサントリーホールディングスでは、全工場で水リスク評価を行い、各事業所ごとに水資源保全計画を策定しています。その根底には「水理念」というグループポリシーがあり、「水循環を知る・大切に使う・水源を守る・地域社会と共に取り組む」という柱のもと、2030年・2050年に向けた具体的目標を掲げています。その結果として、同社は2023年に全世界の自社工場において2015年比28%の用水削減を達成しました。このように、自社の水リスクを定量・定性の両面から把握し、長期ビジョンと短期行動計画を結び付けることが重要です。
https://www.suntory.co.jp/company/csr/env_water
CDPへの報告では、「識別したリスク」「その潜在的影響額や深刻度」「発現可能性の評価」などを記載し、それぞれについて「対策・対応状況」を問われます。企業はここで、自社に特に重大な水リスクは何か(渇水なのか洪水なのか水質か等)、そのリスクが顕在化した場合どの程度の財務インパクトが予想されるか、そして事前・事後にどのような緩和策を講じているか、といった情報を開示する必要があります。例えば製薬会社の塩野義製薬では、「事業継続に欠かせない水のリスクを最小限に抑える取り組み」を実施しており、研究開発・製造拠点に排水処理施設を併設して厳格な排水中の化学物質管理を行っています。具体的には、排水中の薬品濃度が環境に影響を与えないレベルであることを常時監視し、法規制より厳しい社内基準を設定して遵守しています。これは水質汚染リスクへの対応例ですが、同社はこれにより評判リスクと規制リスクの低減を図っています。
このように各社が抱える水リスクは業種や立地によって千差万別です。重要なのは、それを他人事ではなく自社事として捉え、科学的かつ網羅的な評価を行い、リスク低減のための計画を策定・実施することです。それがCDP上での高評価にもつながりますし、ひいては企業のレジリエンス強化にも直結します。
3. 水リスクへの企業の対応策と持続可能な管理戦略
水リスクを認識した企業は、次にそれに対する対応策を講じなければなりません。ここでは、企業が取るべき代表的な水管理戦略をいくつか紹介します。CDPの水セキュリティ質問書でも、これらの対応策の有無や効果について詳しく問われています。
用水の削減と効率向上
「使う水の量を減らす」ことは、渇水リスクへの最も直接的な対策です。多くの企業が生産プロセスや施設運営での節水に取り組んでいます。
具体例としては以下です。
リサイクル・再利用
工場で使用した水をそのまま捨てずに処理・浄化して再利用する仕組みを導入します。例えば冷却水は閉鎖循環系にして繰り返し使う、排水を逆浸透膜などで処理してボイラー給水等に回す、といったものです。積水化学工業では、製造工程で使用する冷却水を循環利用することで新規取水量を削減し、2022年度には国内外の生産拠点におけるリサイクル水使用率を大幅に向上させました。
プロセス改善
工程そのものを見直し、必要水量を減らします。例えば、洗浄工程でのすすぎ回数を減らすための技術開発や、ドライプロセス化(液体を使わない製造法への転換)、空冷式設備への変更などが考えられます。花王は家庭用洗剤分野で、洗濯時のすすぎ回数を1回で済ませられる超濃縮洗剤「アタックZEROパーフェクトスティック」を開発し、水使用削減に貢献する商品として展開しました。このように商品面での革新を通じて、顧客の水使用量削減にも寄与する取り組みも評価に値します。
日常管理の徹底
漏水対策や従業員の節水意識向上も地味ながら重要です。水道や配管の漏洩箇所を無くし、不要な流水を止めるだけでも削減効果があります。従業員教育で節水の重要性を周知し、小さな改善提案を積み上げていくことも有効です。
こうした節水努力は、CDPの質問書では「水使用量の絶対削減目標または原単位削減目標」「前年からの削減実績」として問われます。サントリーHDのように「グローバルで2015年比水使用原単位35%削減(2030年目標)」など明確な数値目標を掲げる企業は高く評価されます。実際同社は工場での節水改善を重ね、前述の通り28%削減を達成しています。定量目標+実績データをセットで開示することが肝要です。
水源保全とコミュニティ連携
企業の取水先である水源環境を健全に維持することも、持続的な水利用には欠かせません。特に地下水や河川水に依存する企業は、地域の水生態系保全に貢献する取り組みを進めています。
水源涵養活動
工場の水源となっている森や山地で植林や下草刈り、間伐などを行い、森林の保水力を高める活動です。
サントリーは「天然水の森」プロジェクトと称し、全国各地の水源地域で森林整備活動を自治体や林業関係者と協働で行っています。「水源を守る」取り組みとしてこれは非常に象徴的で、CDPでもコミュニティとの協働事例として強調されています。
地域社会との協働
水資源は一企業の単独努力では守りきれないため、地域の利害関係者との協働が重要になります。企業が主体となって流域協議会に参加したり、地域住民向けの水環境教育・啓発活動に協賛することも意義があります。サントリーの「水の学校」のように、水の大切さを伝える教育プログラムを展開する企業もあります。また、トヨタやキリンなどは工場周辺で清掃活動や河川モニタリングを地元と一緒に行うなど、社会貢献も兼ねた活動を実施しています。
共同水インフラ整備
一部の地域では、複数企業や行政が連携して上下水道インフラを整え、水の有効利用を図る例もあります。例えば工業団地で下水の共同処理場を設置し再生水を各社で再利用する、雨水貯留設備を共同管理して防災に備える等です。
CDPでは「地域社会やNGOと協働した水プロジェクトがあるか」「流域単位での管理に参加しているか」なども問われます。積極的に関与している場合は、プロジェクト名や成果を具体的に記載しましょう。これらは企業の評判向上にもつながり、水問題に対する前向きな姿勢として高評価につながります。
排水管理と水質保護
水質汚染の防止も企業の重要な責務です。特に化学物質や有害物を扱う業界では、排水処理を徹底し環境への悪影響を最小化する必要があります。
高度排水処理設備
法令で定められた排水基準よりも厳しい水質で放流できるよう、最新の排水処理技術を導入します。具体例として活性炭処理やメンブレンろ過、生物処理の多段階プロセスなどに投資し、排出負荷を極限まで下げます。塩野義製薬は各製造・研究所内に排水処理施設を備え、排水中の薬剤濃度を常時監視して法規制より厳しい基準で管理していると報告しています。このような自主基準を設け、違反が起きていないことを示せれば安全管理の成熟度として評価されます。
緊急時対応策
万一の汚染事故に備える策も必要です。薬品流出時に排水口を閉鎖する仕組みや、有害物質のモニタリングシステム、自社による環境影響調査のフローなど、事故対応計画を整備し訓練しておくことで、リスク低減努力をアピールできます。
水質改善への貢献
自社のみならず地域全体の水質改善に寄与する活動もあります。例えば自社技術を活かして下水処理の効率化に協力したり、農家と連携して肥料流出を抑制するプログラムに参加するなどです。花王はインドネシアの小規模パーム農園への支援を行い、持続可能な農業普及とともに周辺の水環境保全にも寄与しています。こうしたサプライチェーン上流での取り組みも含め、水質保護への広範な関与を示すことができます。
排水や水質に関する法令遵守は最低限ですが、CDPではさらに自主的なコミットメントが評価されます。例えば「当社は2025年までにすべての製造拠点で排水中の特定有害物質濃度を検出限界未満に抑えることをコミットしている」などの宣言をし、それに向けた進捗を示すとよいでしょう。最近ではTNFDの議論も進んでおり、水質・生態系保全は気候変動以上に注目される可能性があります。先進企業はその動きを先取りして対策を強化しています。
ガバナンスと目標設定
気候変動分野と同様に、水セキュリティについても社内のガバナンスと目標管理が重要です。CDP水質問書の後半では、組織体制(取締役会の関与、責任者の有無)、社内ポリシー、水関連の中長期目標、およびその達成度などが問われます。有効な戦略の一つは、定量的な目標を設定することです。例として「2025年までに全拠点の取水量を2018年比で30%削減」「2030年までに水リサイクル率を50%に引き上げ」といった目標があります。サントリーは2030年までに製品1kL当たりの水使用量を前年比35%削減するという目標を掲げています。塩野義製薬も水リスク低減をCSR目標に組み込み、年次で進捗を開示しています。こうした数値目標+期限を明記することが、計画性とコミットメントの強さを示します。
責任ある体制を築くこと
例えば環境管理責任者の下に「水プロジェクトチーム」を設け、各工場からメンバーを集めて節水アイデアの横展開を図る、あるいは経営会議に年1回以上水リスク評価の結果を報告する、といったガバナンスを構築します。取締役会レベルで水関連課題を扱う企業はまだ多くありませんが、気候変動同様に経営課題化していることをアピールできればベストです。最後に、ステークホルダーとのコミュニケーションも戦略の一部です。CDPに回答し公表することで、水リスクへの取組み状況を投資家や取引先に示すこと自体が、信頼性の向上と競争優位性につながると期待できます。CDP日本窓口の分析でも、CDP水セキュリティに回答する企業はサプライチェーンの強靭性(レジリエンス)が向上し、競争上のメリットを享受できると指摘されています。回答を通じて得られるベンチマーク情報(業界平均との比較など)も、自社の戦略見直しに役立つでしょう。
以上、企業が講じるべきリスク対応策と管理戦略を概観しました。要点を整理すれば、「自社の水使用実態とリスクを把握し、明確な目標を立て、節水・水質対策を実行し、地域社会と協調しつつ、進捗をモニタリングして経営にフィードバックする」というPDCAサイクルを回すことです。CDPの質問書はまさにその各ステップで何をしているかを問うものになっています。従って、ここで述べたような施策を着実に講じていけば、CDP上の評価も自ずと高まり、ステークホルダーからの信頼も増していくでしょう。
4. CDP水セキュリティスコア向上のためのポイント
CDPの水セキュリティ質問書に効果的に回答し、高いスコアを得るためのポイントを最後にまとめます。
全設問に回答する
気候変動分野と同様、未回答項目を残さないことが基本です。自社で当てはまらない項目も「該当なし」や「未実施」と明記し、理由を補足しましょう。例えば「当社は農業原料を使用していないため、灌漑用水の直接使用はありません」といった記述です。空欄提出はスコアに大きく響くので避けます。
定量データと目標を明示する
年間総取水量、総排水量、水リサイクル率などのデータは漏れなく記載します。さらに削減目標(%削減や絶対量削減)と達成状況をセットで示します。目標年度と基準年度も忘れずに。具体的な数値は評価の判断材料となるため、可能な限り開示してください。
リスク評価プロセスを説明する
自社がどうやって水リスクを特定・評価しているか、プロセスを書くことが有益です。例えば「年1回、全製造拠点について水ストレス評価ツールを用いて分析し、上位5拠点を重点管理」といった手順を述べます。さらに、リスクごとに発生確率や影響度のスコアリングをして優先順位付けしている場合、その概要も書くとよいでしょう。
対策の具体例と効果を示す
節水や水質対策の取り組みは、単に「実施している」ではなく、具体的な施策名・技術名、その結果得られた削減効果量などを盛り込みます。「冷却水循環システムを導入し年間〇万トンの取水削減」「排水再利用で年間×千トンの上水使用削減」などです。STAR法を用いて背景・行動・成果を整理すると記述が充実します。
サプライチェーンや流域レベルの対応も記載
可能であれば、自社の外まで視野を広げた対応も言及します。サプライヤーへの水リスク調査依頼や、流域の合同プロジェクト参加などは積極的に書きましょう。これはリーダーシップ要素としてプラス評価になり得ます。
目標達成に向けた進捗管理
水使用量や水強度(原単位)が前年と比べどう変化したか、その理由は何かも分析して回答します。もし増加してしまっている場合でも、原因(生産拡大等)と今後の改善策を述べることで、真摯な姿勢が伝わります。
外部評価・認証の活用
例えば、AWS(Alliance for Water Stewardship)の認証取得や、水関連賞の受賞歴などがあれば書き添えます。NGK日本ガイシのようにCDP水セキュリティでAリストを取得した実績があればニュースリリースで公表し、社内外のモチベーションにつなげるとよいでしょう。
経営計画
直近の取り組みだけでなく、今後予定している投資や計画も記載します。「2024年に新たな水再生設備を導入予定で、完了すれば年間△トン削減見込み」のように、未来志向の回答は前向きな印象を与えます。
CDP水セキュリティのスコアリングは、基本的には気候変動分野と同じく「情報開示の質」「認識」「管理」「リーダーシップ」の度合いで評価されます。したがって、ポイントは「いかに具体的で包括的な情報を開示できるか」「問題を把握し管理しているという証拠を示せるか」にかかっています。社内の水管理担当者だけでなく、経営層や他部門とも連携し、会社全体の知見を集めて回答を作成することが理想的です。水は気候変動以上に地域性が強く、一律の解決策がない難しいテーマですが、その分、各企業の創意工夫が発揮できる領域でもあります。CDPへの回答準備を通じて自社の水戦略を練り上げることで、リスク低減とコスト削減、新たな技術導入や協働関係構築など多くの副次的なメリットも得られるでしょう。実際、CDPの調査でも「水リスクへの対策を講じた場合の経済効果は、講じなかった場合のコストの5倍の価値がある」とされています。
総じて、CDP水セキュリティへの対応は、企業の持続可能な水管理の成熟度を測る良い指標となります。高スコアを目指すことは、水に関する自社の弱点を改善し強みを伸ばすプロセスに他なりません。その結果として得られる評判向上や投資家評価の改善は、企業価値へも跳ね返ってくるでしょう。水という貴重な資源を守りつつ事業を繁栄させるために、CDPのフレームワークをぜひ積極的に活用していきましょう。
引用
CDP 水セキュリティ レポート 2023: 日本版
https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/009/003/original/CDP_Water_Security_Japan_2023_0319.pdf