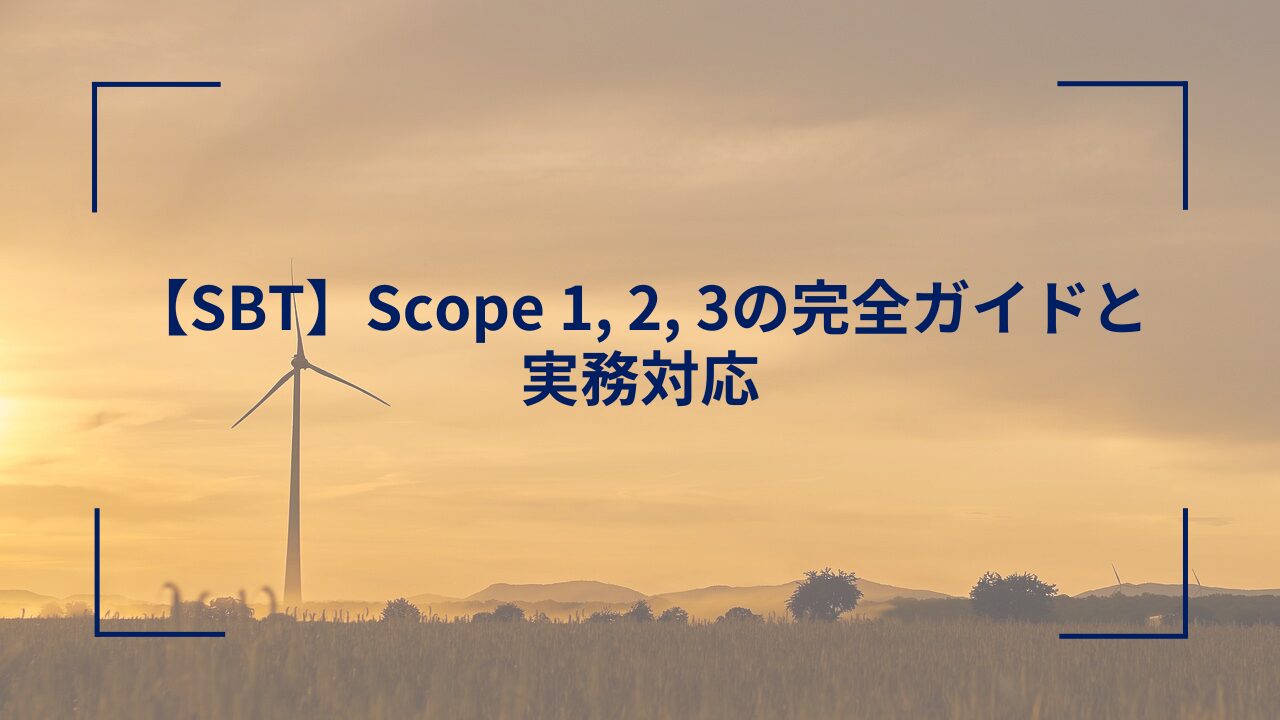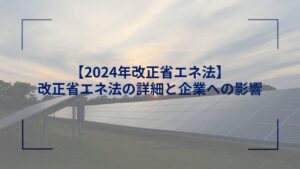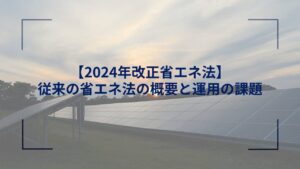Science Based Targets (SBT) は、企業が温室効果ガス排出削減目標を科学的根拠に基づいて設定するための国際的なイニシアチブです。パリ協定で定められた「産業革命前からの気温上昇を1.5℃に抑える」という目標を達成するため、世界中の企業が自主的にSBTに取り組んでいます。近年では日本企業の参加も急増しており、2023年末時点で世界で4,000社以上がSBT認定を取得し、そのうち768社は日本企業で世界最多となっています。本記事では、SBTの基本から実務での対応方法までを網羅し解説します。


1. SBT(Science Based Targets)とは何か?
SBTとは、企業の温室効果ガス(GHG)排出削減目標を最新の気候科学に照らして設定・検証する枠組みのことです。国連やWWFなどが共同で2015年に設立したSBTイニシアチブによって運営されており、企業がいつまでにどの程度GHGを削減すべきかを科学的に示すことで、気候変動対策の野心度を確保します。パリ協定の目標に沿った1.5℃未満シナリオを前提にしているため、SBTを採用することは気候変動の深刻化を防ぐための国際的に認められたアプローチです。
SBTの定義と目的
科学に基づいた削減目標”であり、気候変動の最悪の影響を避けるため企業に明確な削減ロードマップを提供します。
設立の経緯
2015年にCDP、国連グローバル・コンパクト、WRI、WWFの共同で開始され、企業の気候行動を加速するために発足しました。
グローバルな動向
2020年代に入りSBT認定企業数は急増し、日本政府も2017年から企業のSBT設定を支援するなど各国で政策的後押しが進んでいます。
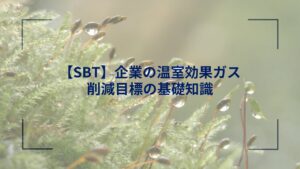
2. SBTを企業が導入するメリット
気候変動対策としてSBTを導入することは、単に環境への責任を果たすだけでなく、企業経営上も多くのメリットがあります。
将来リスクへの対応
SBTに沿った目標は将来の規制強化や炭素税導入などに対するレジリエンス(耐性)を高めます。科学的根拠にもとづく目標設定により、不確実な気候関連リスクへの備えが可能です。
コスト削減と効率向上
エネルギー効率の改善や省資源化を促進するため、長期的にはエネルギーコスト削減や業務効率の向上に繋がります。実際に、ソニーではSBTによる省エネ施策でコスト削減効果も得られたと報告されています。
ステークホルダーからの信頼獲得
SBT認定は国際的に信頼される基準であり、達成意欲を社内外に示すことで投資家や取引先からの評価が向上します。消費者にも具体的な気候アクションを示せるため、ブランド価値の向上にも寄与します。
競争力の強化
競合他社に先駆けて野心的な気候目標を掲げることで、市場や業界内でのリーダーシップを発揮できます。ソニーの事例では「SBTの採用により競合他社や規制当局に対して有利な立場を得た」とされています。
これらの理由から、単なるCSR活動の一環に留まらず、経営戦略としてSBTを位置付ける企業が増えています。
3. Scope 1・2・3とは?GHGプロトコルの基本とデータ精度
企業のGHG排出量はその発生源に応じてScope 1、Scope 2、Scope 3の3つに分類されます。これはGHGプロトコル(温室効果ガスプロトコル)という国際標準で定められた分類法で、企業が排出量を網羅的かつ一貫して算定・報告するための基盤です。
Scope 1(直接排出)
自社が所有・支配する施設や車両などからの直接的な排出(燃料の燃焼や工業プロセス等)。
Scope 2(間接排出)
自社が購入して使用する電気・熱・蒸気などのエネルギー起源の間接排出(発電所等からの排出)。
Scope 3(その他の間接排出)
バリューチェーン全体(川上から川下まで)で生じるそれ以外の間接排出。原材料の調達から製品の使用・廃棄に至るまで、サプライチェーンや製品ライフサイクルでの排出が含まれます。
GHGプロトコルはこのように網羅的な排出量算定ルールを提供し、「漏れなくダブりなく」企業の排出量を把握することを可能にします。SBTにおいても、GHGプロトコルに準拠したデータ算定が要求されており、これにより各企業の排出データの精度と信頼性が担保されています。例えば、SBTイニシアチブではGHGプロトコルを排出量算定の基盤として採用し、企業が一貫性・正確性・信頼性のある方法で排出量を測定・報告していることを確認しています。この仕組みにより、SBTの目標値は企業間で比較可能かつ実効性のあるものとなり、第三者から見ても透明性の高いものとなります。
※ポイント: SBTiは企業にScope 1・2だけでなくScope 3にも目標設定を求めることで、バリューチェーン全体の削減を促しています。従来の自主的枠組みでは見落とされがちだったサプライチェーンの排出にも目を向ける点がSBTの特徴です。
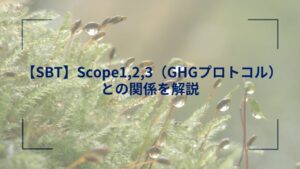
4. SBTとGHGプロトコルの関係
SBTイニシアチブとGHGプロトコルは切り離せない関係です。SBTiはGHGプロトコルを土台に企業の排出量データを評価し、各社の目標設定が科学的に正当かつ厳格であることを保証します。GHGプロトコル準拠のデータであれば、業種や国を超えて一貫した基準で比較・評価できるため、SBTのターゲットとなる削減量や達成度合いも信頼性が高まります。
データの一貫性
すべての企業が同じプロトコル(GHGプロトコル)に従って排出量を算定するため、SBTの目標値は横並びで比較可能です。
精度管理
GHGプロトコルには正確性の原則が含まれており、過大または過小な見積もりを避けるよう定めています。SBTiはこの原則に沿って各社のデータ精度をチェックし、目標設定の土台となる排出インベントリが信頼できるものかを検証します。
検証プロセス
SBTiへの目標申請時には、GHGプロトコルに基づいた排出インベントリと算定手法の提出が必要です。専門家による審査でデータ不備や不整合がないか確認され、必要に応じて修正・再計算が求められます。
このように、SBTはGHGプロトコルによる厳密なデータ算定を前提としているため、企業の温室効果ガス削減目標の信頼性が高く保たれます。言い換えれば、GHGプロトコルの精度があるからこそSBTの信憑性が成り立っているのです。
5. SBT導入の手順
自社でSBTを導入するには、目標設定のプロセスを正しく理解し、社内体制を整備することが重要です。
一般的なSBT導入までのステップは次のとおりです。
社内準備・コミット意思表明
まずSBTiの公式サイトでアカウント登録を行い、自社が対象となるか(一般企業か金融機関か、中小企業か等)の確認をします。必要に応じてコミットメントレター(誓約書)を提出し、科学的目標設定へのコミットを公表します(中小企業の場合コミットメント段階をスキップして直接目標提出も可能)。
GHG排出量の算定と目標策定
自社のScope1・2・3排出量の現状をGHGプロトコルに従って算定し、削減シナリオを検討します。業種別ガイダンスやSBTiの基準を参考に、何年までにどの程度削減するかの目標案を作成します。この段階では社内の関連部門(環境担当や経営企画等)で合意形成を図り、現実的かつ野心的な目標値を設定します。
目標の申請と検証
設定した目標をSBTiに提出し、公式の検証プロセスを受けます。SBTiサービスのポータルサイトから所定のターゲット提出用フォーマットを送信すると、SBTiの専門チームが内容を審査します。通常数週間~数ヶ月の審査期間を経て、目標が科学的に妥当であれば認定(Validated)されます。不備があればフィードバックを受け再提出する仕組みです。
目標の公表と社内展開
SBTiから認定を受けたら、社名がSBTi公式サイトに掲載され「Targets Set(目標設定済み)」企業として公表されます。プレスリリースや自社ウェブサイト等で目標を社内外に公表し、従業員やステークホルダーと共有します。社内では経営層のコミットメントを再確認し、部署ごとの具体的な削減施策に落とし込んでいきます。
削減施策の実行と進捗開示
目標達成に向けた具体的アクションを実施します。省エネ投資、再生可能エネルギー導入、サプライチェーンの協働など、Scope別・部門別の計画を推進します。毎年の温室効果ガス排出量を開示し、CDP報告や統合報告書、TCFDレポート等で進捗を公開します。これにより社内外のチェックを受けつつ、必要に応じて戦略の軌道修正を行います。
上記が基本的な流れですが、企業規模や業種によって細部は異なります。例えば中小企業向けには簡易な「SBTi Target Setting Letter」で迅速に目標認定を受けるプロセスもあります。また目標は一度設定して終わりではなく、科学のアップデートや事業変更に応じて定期的な見直しも必要です。
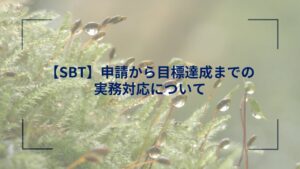
6. SBTと関連する法規制・イニシアチブ
SBTはあくまで自主的な取り組みですが、昨今の法規制や国際イニシアチブとも深く関連しています。
パリ協定と国別目標
パリ協定の下で各国政府が長期戦略を策定する中、企業のSBT設定はその達成を下支えする役割を果たしています。
日本政府も長期戦略で企業のSBT活用を明記し、世界で初めて企業のSBT設定を公式に支援しています。
国内の温暖化対策法
日本では2006年から温室効果ガス排出量算定・報告制度(Mandatory GHG Accounting and Reporting System)が施行され、大企業に年次報告が義務付けられています。こうした法制度により企業の排出量データ基盤が整備されてきたことが、SBT導入の土台となっています。さらに2023年には気候関連財務情報の開示(いわゆる「TCFD開示」)がプライム企業を対象に、企業は気候目標や戦略を開示することが求められつつあります。SBTはその具体的な目標として位置づけることができます。
イニシアチブとの連携
SBTにコミットすることは、同時に国際的なキャンペーンへの参加も意味します。例えば「Business Ambition for 1.5°C」キャンペーンに賛同してSBTを設定すれば、自動的に国連のRace to Zeroキャンペーンにも参加企業として位置付けられます。
このように、SBT達成へのコミットはESG投資の文脈や国際イニシアチブからも評価される傾向にあります。今後はEUをはじめ各国で企業の気候目標に関する開示ルール強化や、カーボンプライシングの導入が本格化する見込みです。その中でSBTの採用は先手を打った対応策となり、規制遵守だけでなく競争優位の観点からも重要性を増すでしょう。
7. SBT認定企業の事例と成功のポイント
既に多くの先進企業がSBTに基づく脱炭素経営に踏み出しており、その成功事例から学べることは少なくありません。ここでは、SBTを採用した企業の具体的な取り組みと得られた効果、成功の秘訣を簡単に紹介します。
ソニー株式会社 – 「1.5℃目標」に世界で初めてコミットした日本企業(2015年)
ソニーは自社の長期環境ビジョン「Road to Zero」の一環としてSBTを設定しました。SBT認定により社内の意識統一が進み、経営トップのコミットメントの下で大胆なイノベーションが推進されています。顧客からの信頼やブランド価値向上に加え、省エネによるコスト削減などビジネス上のメリットも享受しています。特に「グローバルな第三者基準で承認された目標」を持つことで、社内外への説得力が増し、競合他社に対する優位性にもつながったといいます。
パナソニック株式会社 – バリューチェーン全体での大幅削減目標
パナソニックは製造業としては難易度の高いScope3(製品使用時排出)まで含めた野心的目標を設定しました。自社製品の省エネ性能向上や再エネ100%利用を掲げ、サプライヤーとも協働して削減を進めています。SBTを通じて得た教訓は、「社内外のステークホルダーを巻き込み、技術革新と事業戦略を両立させる」ことの重要性です。目標達成には従業員の意識改革からパートナー企業との連携まで包括的な取り組みが鍵となりました。
海外企業の例
イケア (IKEA) – サプライチェーン全体での気候インパクト低減: 欧州発のイケアは、自社だけでなくサプライヤーや顧客の行動変容まで視野に入れた気候戦略を展開しています。SBT認定目標を掲げて以降、物流の効率化や持続可能な素材への転換、製品のエネルギー効率改善などを実施し、大幅なGHG削減を達成しました。イケアの成功のポイントは、事業モデルそのものを環境対応型に再構築した点にあります。トップダウンの目標設定とボトムアップのイノベーション創出を両立させ、SBTを企業文化に根付かせました。
これらの事例から学べるのは、経営戦略と一体化した気候目標の重要性です。SBTという明確なゴールがあることで、企業全体が方向性を共有し、イノベーションの加速やステークホルダーとの協働が進みます。課題は業種ごとに異なりますが、共通しているのは「トップの強力なコミットメント」と「社内外の連携による実行力」です。成功企業はこれらを両輪として、SBT達成に向けた取り組みを着実に前進させています。
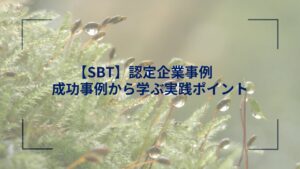
8. SBTまとめ
SBT(科学的根拠に基づく目標)は、気候変動という地球規模の課題に企業が主体的に取り組むための強力なフレームワークです。企業のCSR担当者にとってSBTを理解し実践することは、単なる環境対応を超えて自社の持続可能な成長戦略を描くことに他なりません。SBTの基本から実務対応までを総覧するとともに、各トピック別の詳細解説(本記事内のリンク先の子記事)を活用して、自社の状況に合った取り組みを進めていきましょう。
グローバルではSBTが事実上のスタンダードとなりつつある今、競争優位の確保やリスク管理の観点でもその重要性は増しています。ぜひ本記事をきっかけに、貴社の気候変動対策を次のステージへと高めてください。科学に裏付けされた目標設定と着実な実行によって、持続可能な未来への一歩を踏み出しましょう。