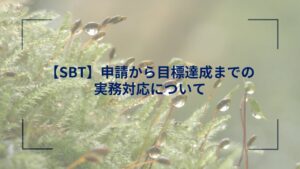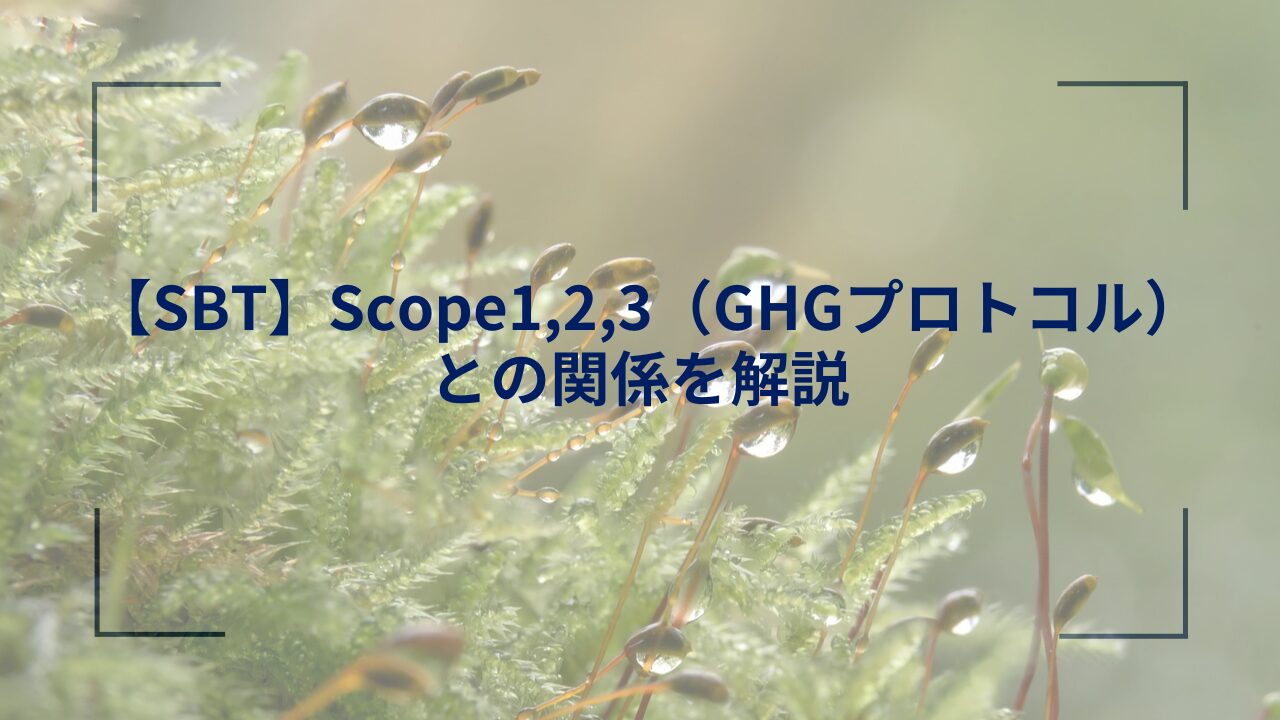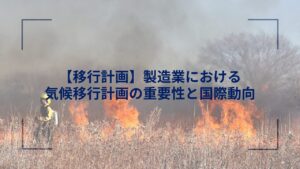正確なGHG排出量データの把握は、効果的な削減計画と持続可能な戦略策定の要です。本記事ではScope1~3の分析ポイントや指標選定、進捗管理、比較の重要性について解説します。


1. GHGプロトコルとは何か
GHGプロトコル(温室効果ガスプロトコル)とは、企業や組織が温室効果ガス(GHG)排出量を測定・報告し、管理するための包括的な国際基準です。世界資源研究所(WRI)と世界経済人会議(WBCSD)が共同で開発したもので、2000年代以降多くの企業が採用しています。GHGプロトコルは、組織のGHG排出をScope1、Scope2、Scope3という3つの区分に分類し、排出源に応じて標準化された算定・報告手法を提供します。この標準化により企業間で排出情報の比較が容易になり、信頼性の高い温室効果ガスインベントリ(排出目録)の構築が可能になります。実際、2016年にはCDP気候変動報告に回答したFortune500企業の92%がGHGプロトコルを直接または間接的に利用していたとの調査もあり、GHGプロトコルは事実上世界で最も広く使われているGHG算定基準と言えます。
2. Scope 1・2・3の定義と具体例
GHGプロトコルでは、企業のGHG排出源を以下の3つのScopeに分類します。
Scope1(直接排出)
企業が自ら所有・支配する施設や資産から生じる直接的な排出を指します。例えば、自社工場のボイラーで燃料を燃焼した際に出るCO2や、自社保有車両のガソリン燃焼に伴う排出がこれに当たります。Scope1は企業の事業活動そのものに由来する排出であり、企業の管理範囲内にあります。
Scope2(間接排出)
他社から購入したエネルギー(電力、熱、蒸気など)の使用に伴う間接的な排出です。典型例として、自社で消費する電力を発電する際に発生したCO2がScope2となります。電力や熱を自社で使うことで間接的に他社の排出(発電所など)を誘発しているため、Scope2として計上します。
Scope3(バリューチェーンの排出)
上記Scope1・2以外で、企業のバリューチェーン上で発生するすべての間接排出を指します。具体的には、原材料の調達や製品の輸送・流通、製品の使用段階や廃棄・リサイクルなど、サプライチェーンの上流から下流までの幅広い活動に由来する排出がScope3に含まれます。例えば、自社が仕入れた原材料を製造する際にサプライヤーで生じた排出や、自社が販売した製品を顧客が使用する際に生じる排出(使用時のエネルギー消費に伴うCO2)などが該当します。GHGプロトコルではScope3排出をさらに15のカテゴリーに細分化して定義しており、企業は自社の事業形態に応じて関連するカテゴリーすべての排出量を算定することが推奨されています。
要約すると、Scope1は「自社から直接出る排出」、Scope2は「買ったエネルギーに由来する排出」、Scope3は「それ以外のあらゆる間接排出(バリューチェーン由来)」です。この分類によって企業は自社の排出源を体系的に把握でき、特にScope3を含めることで自社のバリューチェーン全体に視野を広げた気候変動対策が可能になります。
3. SBTとGHGプロトコルの関係
SBTイニシアチブ(SBTi)では、GHGプロトコルの基準をGHGインベントリ算定と目標設定の根幹に据えています。具体的には、SBTiの求める科学的目標を設定するにあたり、企業はまずGHGプロトコルに従って自社のScope1、2、3排出量を網羅的に算定しなければなりません。GHGプロトコルで定義された組織範囲・運用範囲の下で排出量を把握することで、SBTの対象範囲も明確になります。SBTiはGHGプロトコルを土台に据えることで、企業間で一貫した方法で排出量を算定・報告させ、科学的根拠に沿った目標設定を可能にしています。
例えば「2030年までにScope1,2排出を50%削減」といったSBT目標を掲げる際も、GHGプロトコル準拠の算定に基づく排出ベースライン(基準年排出量)があって初めて、その目標が信頼性のあるものとして評価されます。またSBTiの審査においても、GHGプロトコルに沿った企業の排出インベントリが提出要件となっており、GHGプロトコルはSBTを語る上で欠かせない「共通言語」となっています。このように、SBTとGHGプロトコルは表裏一体の関係です。GHGプロトコルが排出量算定の「ルールブック」だとすれば、SBTはそのルールに則った上で「将来に向けどう排出を減らすか」を示すロードマップと言えるでしょう。SBTiはGHGプロトコルが提供する標準化フレームワークを活用し、各企業に一貫性・信頼性のある方法で気候目標を設定させることで、企業間で公平かつ野心的な気候行動を推進しているのです。
4. 企業に求められるデータ精度の確保
SBTに取り組む上でまず重要になるのが、自社のGHG排出データの網羅性と正確性を確保することです。特にScope3の排出量把握は容易ではなく、多くの企業がデータ収集に課題を抱えています。SBTiの企業調査でも、Scope3インベントリを構築した企業の85%が「必要なデータへのアクセス」が最大の障壁だと報告しています。サプライヤーからの排出情報の入手や排出係数の精緻化など、信頼できるデータを集めるには相当の努力が求められます。そのため、企業にはいくつかデータ精度向上の取り組みが求められます。
データカバレッジ(網羅性)の確保
SBTi基準では、企業が算定するScope3排出量インベントリから「全体の5%を超える排出を除外してはならない」と定められており、裏を返せば少なくとも95%以上の排出源をインベントリに含める必要があります。これにより、都合の悪い(削減が難しい)Scope3排出源を恣意的に除外することを防ぎ、目標範囲の完全性を担保しています。
データ品質の向上
各排出源について、できるだけ実測値や特定の活動量に基づく計算を行い、推計や業界平均値の使用を必要最小限に抑えることが理想です。またデータの出所や算定方法の透明性を確保し、可能であれば第三者による検証・保証(assurance)を受けることで、データの信頼性を高めることができます。GHGプロトコルやISO14064などでは、排出データの精度管理に関するガイダンスも提示されており(不確実性評価やQA/QC手順など)、こうした手法を活用してインベントリ品質を継続的に改善していくことが企業には求められます。
社内の関連部署(調達部門や生産管理部門など)との連携
サプライヤーからの詳細データ取得には調達部門の協力が不可欠ですし、Scope1・2のエネルギーデータは工場や施設管理担当から正確に収集する必要があります。社内外のデータ発生源に働きかけ、データフローを構築する体制整備がデータ精度向上の土台となります。
5. SBT達成に向けたデータ管理のポイント
高い精度の排出データを継続的に管理していくために、体系だったデータマネジメントが不可欠です。先進企業の間では、インベントリ管理の仕組みを社内に定着させるため「インベントリ管理計画(Inventory Management Plan; IMP)」を策定することが推奨されています。
IMPでは、GHGデータをどのように収集し、どの計算方法・排出係数を用い、誰がどのように検証・承認するかといったプロセスを文書化します。これにより排出量算定の方法論が社内で共有され、担当者が異動しても一貫したデータ管理が可能になります。
また、多くの企業が使用している基幹業務システムや環境情報管理システムにGHG排出データを統合し、定期的にモニタリングできるダッシュボードを設ける例も増えています。
あくまでも例ですが、四半期ごとに各工場・事業所のエネルギー使用量と排出量を集計し、SBTの削減軌道と比較する仕組みを作れば、早期に進捗遅れを検知して手を打つことができます。さらに、CDP報告や統合報告書での開示内容を年次でレビューし、データのばらつきや異常値を分析することで、データ品質の改善点を洗い出す取り組みも有効です。要は、SBTという長期目標を支えるのは日々のデータ管理の積み重ねだということです。信頼性の高いデータなくして科学的目標の達成も検証もできません。データ管理計画の策定、社内プロセスへの組み込み、継続的な品質チェックと改善 、これら地道な取り組みが、SBT達成の土台を支えているのです。
引用
GREENHOUSE GAS PROTOCOL
https://ghgprotocol.org/corporate-standard
CDP & Gold Standard – Value Change in the Value Chain: Best Practices in Scope 3 Greenhouse Gas Management
https://www.goldstandard.org
GHG Protocol – Designing a GHG Inventory Management Plan
https://ghgprotocol.org