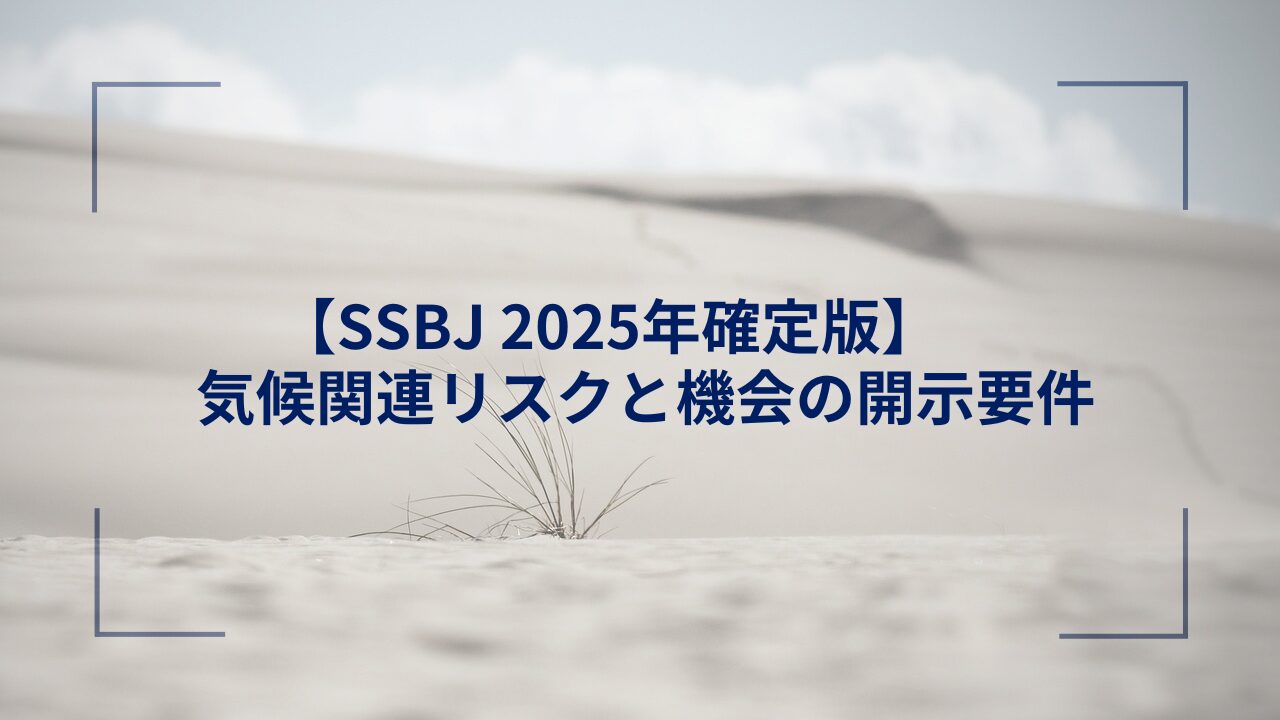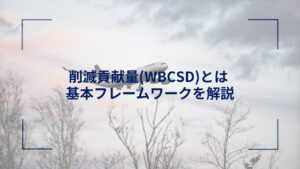近年、気候変動が企業の財務に与える影響について投資家や金融当局の関心が高まっており、気候関連リスクと機会の情報開示はグローバルな潮流となっています。こうした背景を受け、SSBJの「気候関連開示基準」(テーマ別基準第2号)は、企業に対し気候変動に起因するリスクおよび機会に関する詳細な情報開示を求めています。本記事では、まず気候関連リスク・機会の定義と範囲を整理し、それらの開示基準における具体的要件を概説します。また、企業が気候リスクの財務影響をどのように評価・報告すべきか、さらにこれらの開示要件に応じるため企業が取るべき実務上の対応について解説します。読者である財務・サステナビリティ担当者にとって、気候関連情報開示への理解を深め、自社の開示態勢整備に役立つ内容となることを目指します。


1.SSBJ気候関連のリスクと機会の定義
気候関連リスクとは、気候変動が企業にもたらす潜在的なネガティブ影響のことです。気候関連リスクは大きく2種類に分類されます。
リスク
1つは物理的リスクで、これは気候変動そのものによって引き起こされるリスクです。物理的リスクには、台風や洪水・猛暑日といった急性のリスクと、平均気温上昇や海面上昇のような慢性(長期的変化)のリスクの両方が含まれます。もう1つは移行リスクで、低炭素経済への移行の過程で生じる政策・法規制の強化、技術革新の進展、市場需要の変化、そしてレピュテーションへの影響などによるリスクを指します。たとえば、炭素税の導入や排出規制の強化、新エネルギー技術への代替、消費者の環境志向の高まり、企業イメージの悪化などが移行リスクに該当します。
機会
気候関連機会とは、気候変動から企業にもたらされる潜在的なポジティブな影響のことです。気候変動対応はリスクだけでなく新たなビジネスチャンスも生み出し得ます。例えば、再生可能エネルギーや省エネ製品への需要拡大、新規の環境ビジネスの創出、あるいは低炭素技術における競争優位の確立などは機会と言えるでしょう。企業は気候変動に伴い生じるこれらの正の側面にも注目し、戦略に取り入れていく必要があります。
SSBJの気候関連開示基準では、上記のような気候関連の物理的リスク・移行リスクおよび機会の全てが対象範囲に含まれています。企業は自社が直面する具体的な気候リスクと利用可能な機会を洗い出し、それぞれについて重要性の判断を行った上で開示することが求められます。重要性の基準は、「企業の見通しに影響を与えると合理的に見込まれるかどうか」で判断されます。つまり、将来的に自社の財政状態や収益に大きな影響を及ぼす可能性が高い気候関連リスク・機会は必ず開示しなければなりません。一方、その企業の事業にほとんど影響しないと考えられる場合には開示不要となります。この判断は各社の状況に依存するため、業種・地域によって開示すべきリスク・機会の内容や数は異なります。財務・サステナビリティ担当者としては、自社の事業戦略やサプライチェーンを深く理解し、気候変動が及ぼし得る影響の洗い出しと重要性評価を適切に実施することが第一歩となります。
2.SSBJ気候関連リスクと機会の開示基準
気候関連開示基準では、基本的な開示枠組みは一般開示基準と同様に「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」の4つの要素から構成されています。ただし、気候というテーマに特化しているため、各要素において必要とされる開示内容がより具体的かつ詳細に定められています。
ガバナンス
気候関連のリスク・機会に対する組織のガバナンス(監督・経営体制)について開示します。一般開示基準で求められる内容(取締役会レベルの監督体制や経営陣の役割、報告頻度等)に加え、気候変動に特有の事項としては、取締役会や経営陣が気候変動問題に関する十分な専門知識を有しているか、必要な能力向上の計画があるか、などがポイントとなります。また気候関連の業績指標が経営陣の業績評価や報酬にどのように反映されているかも重要です(すでに一般基準でも求められている開示項目ですが、気候という文脈で具体的に説明します)。気候ガバナンスの透明性を確保することで、投資家は経営陣が気候リスク・機会を適切に認識し、意思決定に組み込んでいるかを判断できます。
戦略
気候関連リスク・機会が企業のビジネス戦略や財務計画に与える影響、およびそれに対する戦略的対応を開示します。ここでは、シナリオ分析に基づく事業戦略のレジリエンス評価が中核的な要求事項となっています。企業は、例えば2℃未満シナリオや4℃シナリオなど複数の気候シナリオを用いて、自社の事業モデルや戦略が将来の気候変動下でも持続可能か分析する必要があります。基準では、少なくとも戦略計画サイクルに合わせて定期的にシナリオ分析を実施し、その方法(使用したシナリオの種類と前提)、分析に用いた時点(年度)や頻度、分析に要した能力・リソースなどを開示することが求められます。
さらに、シナリオ分析の結果として判明した自社戦略やビジネスモデルへの影響(例えばあるシナリオでは特定事業の収益性が低下する等)も開示対象です。加えて、気候関連の移行計画(後述)を策定している場合には、その計画の内容や前提条件も戦略情報として開示することが求められます。戦略要素の開示を通じ、投資家は企業が気候変動を念頭に長期ビジョンを描いているか、事業上の脅威や機会に対してどの程度備えているかを読み取ることができます。
リスク管理
気候関連リスクの特定・評価・管理プロセスについて開示します。一般開示基準と同様、プロセスの全社的リスク管理体系への統合状況を含めて説明する必要があります。特に気候リスクの場合、物理的リスクと移行リスクという性質の異なるリスクを扱うため、従来のリスク管理プロセスにこれらを組み込む工夫が重要です。企業は、気候リスク評価の頻度や手法(例えば施設毎の洪水リスク評価やカーボンプライシングを用いた事業影響分析など)、使用データの範囲(自社施設のみかサプライチェーン含むか)等を具体的に開示します。また、気候リスクが全社的なリスク評価でどの程度優先度が高い位置付けになっているか(例:リスクヒートマップで「重大リスク」に分類)や、監督側(取締役会)がその評価結果をどのように把握・議論しているかも含まれます。リスク管理体制の開示によって、投資家は企業が気候リスクを体系的かつ網羅的に管理できているかを判断できます。
指標と目標
気候関連リスク・機会の管理やパフォーマンス測定に用いる指標、および設定している目標の開示が求められます。最も重要なのは温室効果ガス排出量に関する指標であり、基準ではScope1、Scope2、Scope3の排出量合計をそれぞれ区分して開示することが義務付けられています。これらは業種を問わず共通に適用される産業横断的指標として位置付けられており、企業は自らの排出量(直接排出であるScope1、購入電力等の間接排出であるScope2、およびバリューチェーンを通じたその他の間接排出であるScope3)を算定・報告する必要があります。
加えて、内部炭素価格を導入している場合にはその価格と利用方法を開示しなければなりません。内部炭素価格とは、企業が自主的に設定する炭素1トン当たりの価格で、投資判断や事業採算の分析、シナリオ分析等に組み込むものです。基準では、内部炭素価格を経営意思決定に用いている場合にはどのように適用しているか(例えば投資評価や製品価格算定に組み込んでいるか)およびその金額(○ドル/トン)を開示し、用いていない場合にはその旨を明示するよう求めています。この情報により、投資家は企業が将来の炭素コストを織り込んだ経営をしているかを測ることができます。
上記のように、気候関連開示基準は一般的な枠組みを踏襲しつつ、気候変動固有の重要情報(GHG排出量やシナリオ分析結果等)を確実に報告させるための詳細要件を盛り込んでいます。企業はこれらの要件を踏まえて、自社の気候リスク・機会を網羅的かつ定量・定性的に開示することが期待されます。
3.SSBJ財務的影響の評価と報告
気候関連リスクと機会の開示で特に重視されるのが、それらが企業の財務にどのような影響を及ぼすかを評価・報告することです。単なるリスク項目の列挙ではなく、それが現時点および将来の財務数値にどう反映されているかを示す点に、投資家は関心を寄せています。
具体的な開示要求
気候関連開示基準では、この点について具体的な開示要求を定めています。 企業は、当期(現在)の財務的影響と将来(予想される)財務的影響の双方を明らかにする必要があります。当期の財務的影響とは、気候関連のリスクおよび機会が実際に当該報告期間中の財政状態(貸借対照表)、財務業績(損益計算書)およびキャッシュ・フローに与えた影響です。具体例としては、「異常気象により工場が被災し特別損失を計上」「炭素価格上昇に備えたカーボンクレジット購入により費用増加」といった事項が該当します。
こうした影響は可能な限り定量的に報告し、どの勘定科目に影響が表れているか(減収、増加費用、減損など)を説明することが望まれます。 将来の財務的影響については、短期・中期・長期の時間軸ごとに、気候関連リスク・機会が企業の財政状態・業績・キャッシュフローに与えると予想される影響を開示します。
ここでは企業の内部計画に組み込まれた仮定を用いて予測した情報を提供することになります。例えば、「今後5年間でCO2排出削減のために追加CAPEX(資本的支出)○億円を予定、それによりエネルギーコストが年△%削減される見込み」「2030年までにカーボンニュートラルを達成するために必要な累計投資額」といった予測情報が考えられます。
基準では、この将来影響の開示にあたって、企業の財務計画(中期経営計画等)に気候関連要素がどのように織り込まれているかを考慮するよう求めています。これは、気候リスク・機会が単なる環境問題ではなく、実際に財務モデルへ組み入れられていることを示す重要な指標となります。
さらに、開示基準では具体的な開示項目として、以下のような点を挙げています。
当期の財務影響(定量情報)
今期のPL・BS・CFにおいて気候関連事象が与えた具体的な影響額や指標(にあるように、損益・財政状態・キャッシュフローへの影響を定量的・定性的に開示)。
翌期の重要リスク
現在把握している気候関連リスクのうち、翌年度の財務諸表に計上される資産・負債に対して重要な影響を与える可能性が高いリスクがある場合、その内容を開示。例えば、翌期に炭素税導入が確実視され、自社の設備に減損リスクが高まっている場合、その旨を明示します。
長期財務見通しへの影響
企業の気候対応戦略を踏まえ、短期・中期・長期にわたる財政状態および財務業績・キャッシュフローの将来的な変化見込み。ここでは、企業の投資計画や資金計画(資本調達の計画等)も考慮して示します。例えば「2030年時点で高炭素資産が◯%減少し、収益構造がどう転換しているか」といった見通しです。
このように、財務影響の開示項目は多岐にわたりますが、要するに「気候変動が企業価値に与えている現在進行形の影響」と「将来与えうる影響」を、定量面と定性面の双方からしっかり伝えることが重要です。財務・サステナビリティ担当者は、環境部門や経営企画部門と連携し、シナリオ分析や事業計画シミュレーションを通じてこれらの影響を数値化・可視化する取り組みが求められます。その結果得られた知見を適切に報告することで、投資家は企業の財務的な露出度や対応力を評価できるようになります。
4.SSBJにおける具体的な対応
上述の開示要件を踏まえ、企業(特に財務・サステナビリティ担当者)は内部で以下のような具体的対応を進める必要があります。
リスク・機会の網羅的な洗い出しとマテリアリティ評価
自社の事業活動全般を見渡し、気候変動に関連するリスクと機会の候補を洗い出します。これには社内各部署(経営企画、事業部門、設備管理、調達、物流、人事など)との協働が不可欠です。その上で、それぞれが事業・財務に与える潜在的な影響の大きさと発生可能性を評価し、重要なものを特定します。この評価には定性的判断だけでなく、定量的な影響額試算(たとえば売上何%影響、コスト何円増減など)も取り入れると説得力が増します。
ガバナンス体制の整備
洗い出された気候リスク・機会を効果的に管理するためのガバナンス体制を構築・強化します。具体的には、取締役会レベルで気候関連課題を監督する責任者(委員会や担当役員)を明確化し、定期的な報告ラインを設定します。また、経営陣内で気候戦略を統括する役職(チーフ・サステナビリティ・オフィサー等)の任命や、関連部署間の横断的な委員会の設置も有効です。さらに、取締役や経営陣に対し気候変動に関する研修を実施したり、専門知識を持つ人材を登用したりすることで、ガバナンスの実効性を高めます。
シナリオ分析の実施
戦略策定とリスク評価の一環として、気候変動シナリオ分析を行います。国際機関のシナリオ(IPCCのRCPシナリオやIEAの持続可能発展シナリオ等)や自社開発シナリオを用い、将来の温度上昇パスごとに自社事業環境がどう変化するかを分析します。例えば「2℃シナリオ下では炭素価格が2030年に○ドル/トンとなり、当社の製造コストに△%上乗せ」等の定量分析を行います。その際、必要な社内データ(設備ごとの排出量やエネルギーコスト構造等)を収集し、必要なら外部の専門機関の協力も得ます。シナリオ分析結果は経営戦略の検証や移行計画の策定に役立つだけでなく、開示資料において投資家に対する説明材料ともなります。
移行計画および適応策の策定
識別された主要リスクに対処し、機会を捉えるための気候関連の移行計画を策定します。これは後述するガバナンスと戦略の記事で詳述しますが、簡潔に言えば「どのように自社を低炭素型に転換し、気候変動に適応させていくか」のロードマップです。移行計画には、温室効果ガス削減目標や実施施策、必要投資額とスケジュール、達成に必要な技術や前提条件などを含めます。この計画は単なる環境宣言ではなく、事業計画や資本支出計画と一貫したものにすることが重要です。また策定後は定期的に進捗をモニタリングし、状況変化に応じアップデートします。
財務への組み込みとディスクロージャー整備
気候関連の影響評価結果を実際の財務管理に組み込みます。例えば、予算策定プロセスで内部炭素価格を適用してコスト計上したり、投資稟議で炭素コストや規制リスクを考慮させたりします。同時に、開示すべき情報(定量データや説明文)の整備も進めます。GHG排出量については信頼性の高い算定と第三者検証の取得、財務影響の定量化については財務部門と連携して過去データの分析・将来予測モデルの構築を行います。これらのデータをまとめ、年次の統合報告書やサステナビリティ報告書、証券報告書に反映させる作業も必要です。
関係者との連携とステークホルダー対応
気候関連情報開示は企業単独では完結せず、サプライヤーや顧客、投資家など多くのステークホルダーとの関係に影響します。自社の排出量算定にはサプライチェーン(Scope3)の協力が欠かせませんし、逆に自社が顧客から排出データ提供を求められる立場でもあります。したがって、バリューチェーン全体で協調しデータを共有・精度向上させる取り組みが重要です。また、開示した気候情報について投資家や金融機関から問い合わせや要求が増えることが予想されるため、そうした対話に備えエクスポージャー分析の詳細やリスク対応策の説明資料を準備しておくと良いでしょう。
以上のような社内対応を体系立てて進めることで、企業は気候関連開示基準の求める情報を的確に報告できるようになります。それは単にコンプライアンス対応というだけでなく、自社の気候変動に対する耐性強化や戦略見直しにもつながり、長期的な企業価値の向上に寄与するでしょう。
引用元
サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」
https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html