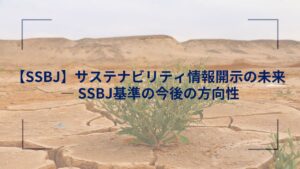SSBJは、日本のサステナビリティ情報開示基準を策定する機関で、国際基準(IFRS S1・S2)と整合性を図る役割を担います。SSBJ基準はユニバーサル基準、テーマ別基準(気候関連など)、産業別ガイダンスで構成され、2026年以降プライム市場の上場企業を対象に段階的に適用されます。企業は財務報告と統合した開示が求められ、データ基盤整備やガバナンス強化が必要です。今後の適用スケジュールや企業への影響について解説します。
※本記事は2025年3月5日にサステナビリティ基準委員会から発表された確定案より以前の内容となっています。
確定案に関しては下記記事を参照してください。



1. SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは?
SSBJは、日本のサステナビリティ情報開示基準の策定を目的に設立され、ISSB基準と整合した独自基準の開発や、国際的な動向を踏まえた基準の更新に取り組んでいます。
そこで設立の背景と目的、役割と責任について解説していきます。
設立の背景と目的
SSBJは「サステナビリティ基準委員会」(Sustainability Standards Board of Japan)の略称で、日本におけるサステナビリティ情報開示基準の策定を担う機関です。2021年12月、財務会計基準機構(FASF)の理事会において2022年7月1日付でSSBJを設立することが決議され、2022年7月に正式に発足しました。これは2021年のIFRS財団による国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の設立を受けた動きであり、国際的なサステナビリティ開示基準への対応を日本でも進める目的がありました。SSBJ設立準備委員会は2022年1月に立ち上げられ、ISSBが公表したプロトタイプ基準や公開草案の検討を行い、国内関係者からの意見収集(アウトリーチ)も実施しました。
役割と責任
SSBJは、企業のサステナビリティ関連情報の開示に関する基準(SSBJ基準)を開発・公表することが主要な役割です。具体的には、国際的なISSB基準(IFRSサステナビリティ開示基準)と整合的な日本独自の開示基準を策定し、国内の制度への組み込みに寄与します。また、ISSBをはじめ海外の標準設定主体との連携も図り、国際動向を踏まえた基準のアップデートを適時に行う責任があります。SSBJはFASF内の組織であり、日本の会計基準を策定する企業会計基準委員会(ASBJ)と同様のガバナンス体制で運営されています。さらに、SSBJには「サステナビリティ基準諮問会議」という助言機関も設置され、幅広いステークホルダーの意見を反映しつつ基準の検討が行われています。総じて、SSBJは日本企業のサステナビリティ情報開示を高品質かつ国際的に比較可能なものとするための基盤整備を担っているのです。
2. SSBJ基準の概要
SSBJ基準は、すべての企業に適用される「ユニバーサル基準」と、特定課題に特化した「テーマ別基準」、国際基準を参照する「産業別基準」で構成されています。さらに、IFRS S1の「コア・コンテンツ」を「一般開示基準」とし、その他の事項を「適用基準」として分割することで、IFRS S1とS2の要求事項を網羅しつつ、可読性の向上を図っています。
一般開示基準・テーマ別基準
SSBJ基準は、大きく「ユニバーサル基準」「テーマ別基準」「産業別基準」のカテゴリに分けられる構成となっています。ユニバーサル基準とは、すべての企業に共通に適用される一般的な開示要求事項を定めた基準で、サステナビリティ情報開示の基本となるものです。一方、テーマ別基準は特定のサステナビリティ課題に特化した基準を指し、現時点では「気候変動」がその代表例です。産業別基準は業種ごとの特有な情報開示事項を定めるものですが、SSBJにおいて独自の産業別開示基準が公表されているわけではなく、SASB(サステナビリティ会計基準審議会)の基準など国際的に整備された産業別ガイダンスを参照する形が取られています。実際、SSBJが公表した公開草案でも、各企業が自社の属する業種に関連する開示事項を識別するためにSASB基準等を参照することが求められていました。このように、ユニバーサル基準で全般的な事項を網羅し、必要に応じてテーマ別基準・産業別ガイダンスで詳細を補完する仕組みになっています。
IFRS S1・S2基準との関係
SSBJ基準は国際的なISSB基準(IFRS S1およびS2)を土台として策定されています。SSBJは「国際的な整合性の確保」を基本方針に掲げ、IFRSサステナビリティ開示基準の要求事項を原則すべて取り入れる方針を明確にしています。実際、2024年3月に公表されたSSBJ基準の公開草案では、IFRS S1「一般的開示要求事項」とIFRS S2「気候関連開示」の全ての要求事項を日本基準に組み込むことが示されました。ただし、一部には日本固有の事情に応じて任意適用できる追加的な取扱いを設ける提案もなされています。これは企業が特定の項目でISSB基準と異なる開示方法を選択できる余地を示すもので、例えば初年度の比較情報の扱いなど技術的な点で選択肢が示される可能性があります(これらのオプションはISSB基準との比較可能性を大きく損なわない範囲に留める意図です)。
また、IFRS S1自体が多岐にわたる要求事項を含むため、SSBJ基準ではIFRS S1を2つに分割して提示しています。具体的には、IFRS S1の中の「コア・コンテンツ(重要な開示項目)」部分を切り出して「一般開示基準」とし、それ以外の基本事項を「適用基準」としてユニバーサル基準に位置付けました。この分割により基準の可読性を高めつつも、両基準を同時適用することで結果的な開示内容はIFRS S1を網羅するようになっています。さらに、IFRS S2「気候関連開示」についてはSSBJのテーマ別基準(気候基準)としてそのまま組み込まれました。
以上のように、SSBJ基準はIFRS S1・S2とほぼ同等の内容を持ち、グローバルなベースラインとの整合性が確保されています。
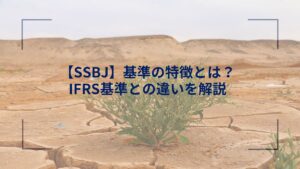

3. SSBJが与える企業への影響
SSBJ基準は、将来的に東京証券取引所プライム市場の上場企業に適用が予定され、2027年3月期から時価総額3兆円以上の企業に義務化が始まります。続いて1兆円以上、5000億円以上の企業へと段階的に拡大し、最終的に全プライム企業が対象となる見込みです。
プライム上場企業への適用
SSBJ基準は将来的に主に東京証券取引所プライム市場上場企業に適用されることが想定されています。金融庁の金融審議会における検討では、企業規模(時価総額)に応じた段階的な適用スケジュールが示されており、まずは時価総額3兆円以上の企業から義務化が始まる見通しです。具体的には2026年3月期までは任意適用期間としつつ、2027年3月期(=2026年度決算)から時価総額3兆円以上の企業に対して開示を義務化する案が有力です。続いて、時価総額1兆円以上の企業は2028年3月期から、5000億円以上の企業は2029年3月期から、それぞれ義務対象に加わり、最終的にはプライム市場の全上場企業へと段階的に適用範囲が拡大される計画です。
この段階導入により、大企業から中堅企業へ順次に対応を促すことで、企業側の準備期間を確保するとともに、市場への影響を緩やかにしていく狙いがあります。また、SSBJ基準は確定公表後すぐに強制適用とはならず、一定の移行期間と任意適用期間が設けられます。例えば2025年3月末までに基準が確定すれば、早い企業は2025年3月期の有価証券報告書から任意で新基準による開示を開始できる見込みです。もっとも、任意適用であっても「一般基準(IFRS S1相当)」と「気候基準(IFRS S2相当)」はセットで適用しなければならず、一部だけ先行適用するといったことは認められない点に注意が必要です。
財務報告との統合
SSBJ基準によるサステナビリティ情報は、財務情報と統合して開示されることが求められます。具体的には、関連する財務諸表と同時期に、かつ同じ報告対象(連結グループ単位)でサステナビリティ情報を開示することが原則となっています。実務上は有価証券報告書内にサステナビリティ情報の専用セクションを設けて記載する形が想定されており、既に2023年3月期から全上場企業に求められているTCFD項目の開示と同様の枠組みです。したがって、今後プライム企業には財務情報と同じタイミングでサステナビリティ関連情報を準備・提供する体制整備が求められます。
もっとも、日本企業の現状では、統合報告書やサステナビリティ報告書を決算後数ヶ月遅れて発行しているケースが多く、決算と同時に詳細な非財務情報を開示するにはハードルがあると認識されています。このため金融審議会のワーキンググループでも、経過措置として「二段階開示」を初年度に認めるかが議論されています。二段階開示とは、まず有価証券報告書提出時に主要項目を開示し、後日追加情報を補完する方法です。ISSB基準自体が初年度のみ同時開示の猶予を認めていることもあり、日本でも初年度は例外的にサステナ情報の遅れた開示を許容し、2年目以降に完全な同時開示へ移行する案が有力です。いずれにせよ、中長期的には財務・非財務情報を一体的に開示することが要求されるため、企業側は内部プロセスの見直しにより開示スピードを上げていく必要があります。
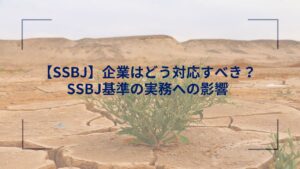
4. SSBJ基準の最新動向
最後に最新動向という観点から、2025年版アップデートのポイントや今後の展望について紹介します。
2025年版アップデートのポイント
2024年3月にSSBJはサステナビリティ開示基準の公開草案を公表し、国内外からの意見募集を行いました。この公開草案は前述のとおりIFRS S1・S2をほぼ忠実に取り入れた3本の基準案(適用基準案・一般開示基準案・気候関連開示基準案)で構成されており、2024年内にパブリックコメントの集約と内容の精査が行われました。
最新の予定では、2025年3月末までにSSBJ基準の確定版が公表される見込みです。仮にスケジュール通り2025年3月中に確定基準が公表されれば、日本企業は2025年3月期決算の有価証券報告書から新基準を早期適用することが可能となります。公開草案から確定版にかけての主なアップデートポイントとしては、ISSBが2023年6月に公表した最終基準との整合を図った点が挙げられます。例えば、ISSBは気候関連開示(IFRS S2)において一部産業に要求していたGHG排出量の区分開示(「ファイナンスド・エミッション」をGICS産業別に報告する要件など)の見直しを議論しており、最終基準では柔軟性が追加されています。SSBJもこれら国際基準の微修正を反映しつつ、日本の開示実務に適合させた表現調整(例えば用語の日本語化やガイダンスの追加)を行っている模様です。2025年版の確定基準が公表されれば、日本版サステナビリティ開示基準の詳細が明らかになりますが、基本的な枠組みは公開草案と大きく変わらないと予想されています。企業にとっては、確定基準の内容を踏まえて具体的な開示項目やガイダンスを確認し、社内の準備状況を最終チェックする段階に入ることになります。
今後の展望
SSBJ基準の公表はゴールではなくスタートです。2026年以降、本格的な適用が順次開始され、2027年~2029年にかけてプライム市場の企業に開示義務が段階的に拡大していく見通しとなっています。義務化の翌年度からは、開示されたサステナビリティ情報に対する第三者保証も段階的に義務づけられる案が検討されています。また、ISSBにおける新たな基準開発にも注目が必要です。気候以外のテーマ、例えば自然や人的資本に関する国際基準策定の動きが今後進めば、SSBJはそれらを速やかに国内基準へ取り込むでしょう。常に国際的な比較可能性を維持することがSSBJの基本方針であり、実務適用後も各国の開示動向をモニタリングし必要に応じて基準の見直しを行う計画です。企業・投資家の視点では、サステナビリティ開示はもはや「任意のCSR情報」ではなく財務情報と一体となった必須開示へと位置付けが変わります。
企業は気候変動や人権といったサステナビリティ課題を経営戦略に組み込み、開示を通じて投資家との対話を図ることが求められます。投資家側も開示情報を活用して企業の中長期的な価値創造力やリスク管理能力を評価する姿勢が一層重要になるでしょう。規制環境の進化に伴い、サステナビリティ経営の実践が企業価値向上の鍵となっていくと考えられます。今後も制度面・実務面で改善を重ねつつ、サステナビリティ情報開示は企業経営の不可欠な要素として定着していくと展望されています。
引用元
サステナビリティ基準委員会(SSBJ)公式サイト
https://www.ssb-j.jp
財務会計基準機構(FASF)公式サイト
https://www.fasf.or.jp
金融庁 ディスクロージャーワーキング・グループ関連資料
https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/disclose_wg/index.html
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)公式サイト
https://www.fsb-tcfd.org/