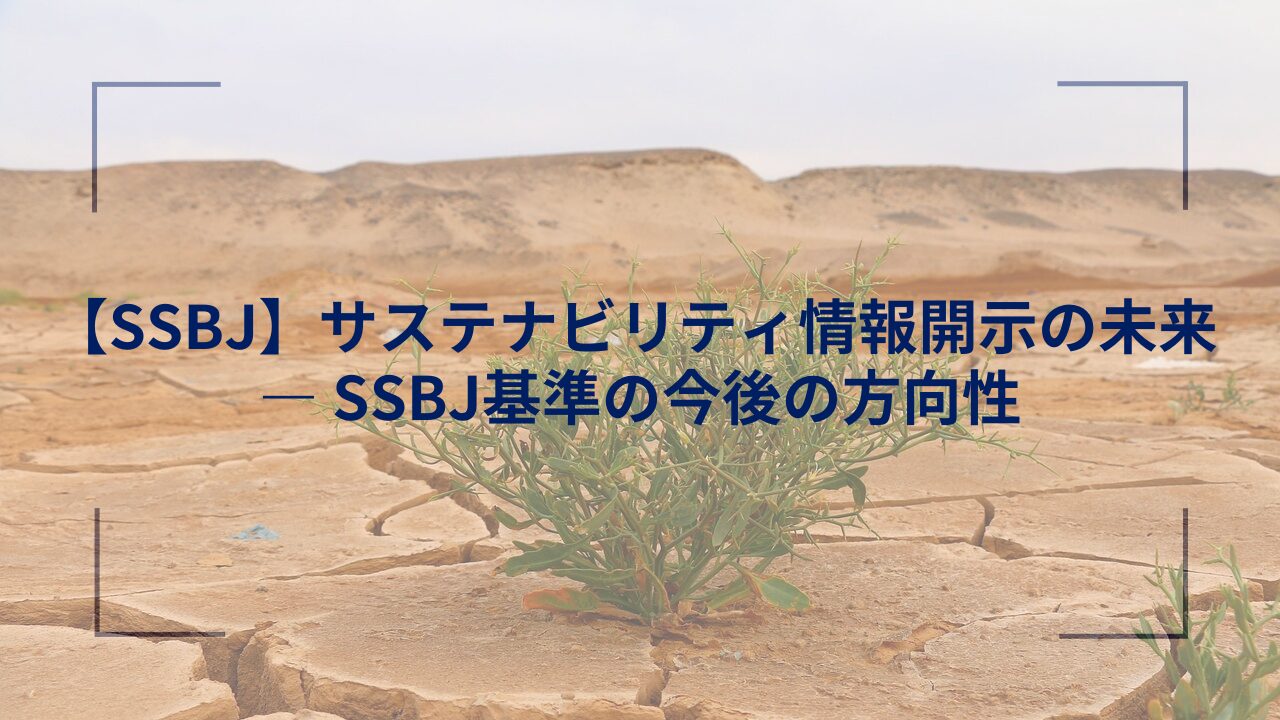SSBJ基準は2026年以降、段階的に適用され、2027年から義務化が始まります。企業はこのスケジュールを見据え、体制構築や試行開示を進める必要があります。また、投資家側も財務情報とESG情報を統合的に評価する視点が求められます。将来的には開示基準の拡充や監査レベルの強化が進み、サステナビリティ経営の標準化が加速するでしょう。企業はこの流れを競争力向上の機会と捉え、どのように対応すべきかを解説します。
※本記事は2025年3月5日にサステナビリティ基準委員会から発表された確定案より以前の内容となっています。
確定案に関しては下記記事を参照してください。



1. 2026年以降の適用スケジュール
2025年にSSBJ基準が確定した後、いよいよ2026年以降に実際の適用フェーズが始まります。
フェーズについて
前述の通り、2026年度は多くの企業にとって任意適用の期間となり、2027年3月期から義務化がスタートします。最初は時価総額3兆円を超える超大企業が対象となり、その翌年以降、段階的に対象範囲が広がります(2028年3月期に1兆円以上、2029年3月期に5000億円以上、2030年3月期には残るプライム企業に順次適応というタイムラインが検討されています)。このスケジュールは現時点での案であり、今後正式に金融庁から規則が公表されれば確定します。
保証の義務付け
また、保証の義務付けもサステナビリティ情報開示義務化の翌期から開始する方向で検討されています。例えば2027年3月期に開示義務となる企業は、2028年3月期から保証報告書の添付が必要になる、といった具合です。さらに、Scope3(サプライチェーン排出量)の開示や保証については他項目より遅れて適用される経過措置も議論されています。海外ではEUが2025年度報告から大型企業への義務適用を始め、米国SEC規則も2024年度ないし2025年度あたりから段階適用される見込みで、日本も2026~2027年にかけて主要国に追随するスケジュールとなります(2024年12月時点)。2026年から数年間は各社が順次新基準での報告に移行する過程となり、投資家やアナリスト側もその情報を受け止め評価手法を磨いていく時期となるでしょう。
企業はこのタイムラインを念頭に、逆算してプロジェクト計画を立てることが重要です。例えば、自社が2028年適用なら、2026年中には体制構築と初回開示項目の把握を終え、2027年には試行開示・問題点洗い出しを行う、といった段取りです。時間軸を見据えた着実な準備が、義務化初年度に慌てない秘訣となります。
2. 企業・投資家に求められる視点
サステナビリティ情報開示の本格化に伴い、企業と投資家双方にパラダイムシフトが求められます。
企業視点
企業側は、サステナビリティ課題を単なるコンプライアンスではなく、自社の価値創造ストーリーに組み込む視点が必要です。気候変動対応や人的資本開発はコストではなく将来への投資であり、その成果を測定し情報開示することは投資家との対話材料となります。財務情報とサステナ情報を結びつけ、「なぜこのESG施策が中長期的に企業価値を高めるのか」を説明できる企業は市場から高い評価を得るでしょう。
逆に、開示ありきで形式的な情報を並べるだけでは、ステークホルダーの支持を得られません。経営トップのリーダーシップの下、サステナビリティ経営を推進し、その進捗と成果を透明性高く開示するという一連の流れを構築することが重要です。
投資家視点
一方、投資家側も視点の進化が必要です。従来の財務諸表中心の分析から、ESG情報を統合的に評価に織り込むアプローチへ移行する必要があります。具体的には、気候変動リスクを考慮した企業の将来キャッシュフロー予測や、人的資本の充実度合いによる競争力評価など、非財務要素を定量・定性の両面で分析に組み込むことが求められます。
ISSB基準は投資家に関連の高いサステナビリティ情報提供を目的としているため、投資家は提供された情報を活用し企業間比較やエンゲージメントを行うことが期待されます。特にアクティブオーナーシップを重視する機関投資家にとっては、新たな開示情報は企業との対話テーマを広げ、経営改善を促すツールとなります。また、サステナ要素はリスクだけでなく投資機会の評価にも直結します。例えば脱炭素関連市場で先行する企業を発掘したり、多様性の高い組織文化を持つ企業への投資判断を下したりする際に、開示情報が重要な裏付け資料となるでしょう。
3. 規制の進化とサステナビリティ経営の未来
サステナビリティ情報開示を取り巻く規制は今後も進化し続けるでしょう。各国政府や規制当局は、気候変動の深刻化や社会課題の顕在化に対応して、開示項目の拡充や基準の高度化を図ると考えられます。例えば、ISSBは将来的に生物多様性や人的資本に関する基準策定に着手すると予想され、SSBJもそれに追随して国内基準を拡張していくでしょう。また、現行では限定的保証に留まっているサステナ情報の監査レベルが、いずれ合理的保証(財務諸表監査と同等レベル)に引き上げられる可能性もあります。
さらに、技術の進展も規制を変える要因です。サステナビリティ報告においてもAIやビッグデータ解析が活用されるようになれば、リアルタイムデータ開示や予測情報の開示といった新たな局面が開くかもしれません。規制強化は企業に負担を強いる側面もありますが、その一方でサステナビリティ経営の標準化を促し企業文化を変革するドライバーともなります。開示項目が明確化し経営者評価に組み込まれることで、経営層もESG課題を無視できなくなり、本業戦略に組み入れる動機付けとなります。実際、「サステナビリティ2026問題」とも呼ばれるこれから数年の対応期を経て、日本企業の経営は大きく変わる可能性があります。財務目標と並んで非財務目標を掲げる企業が増え、報酬体系にもESG指標が組み込まれ、人材採用・ブランド戦略にもサステナ重視が浸透するでしょう。
最終的な未来像としては、サステナビリティと経営が完全に融合し、「持続可能性を追求することが競争力そのものを高める」時代が訪れると考えられます。情報開示はその手段であり、規制はそれを後押しする仕組みです。SSBJ基準はその一端として、日本企業のサステナビリティ経営を底上げし、透明性の高い市場を形成する基盤となっていくでしょう。企業はこの流れをコストではなく機会と捉え、イノベーションや価値創造につなげていく姿勢が求められます。それこそが、開示規制の進化が目指す「持続可能な社会と経済」の実現に寄与するものと言えるでしょう。
引用
Request for Information: Consultation on Agenda Prioritieshttps://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/project/issb-consultation-on-agenda-priorities/ja-rfi-issb-2023-1-consultation-on-agenda-priorities.pdf
経済産業省「GX(グリーントランスフォーメーション)関連情報」https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition/pathways_to_green_transformation.pdf