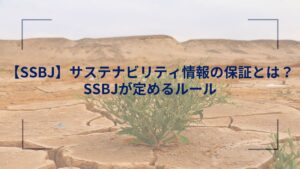SSBJ基準(日本版サステナビリティ開示基準)は、国際的な基準であるIFRS S1・S2を踏襲しながら、日本の法制度や実務に合わせて調整された開示基準です。現在、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)により策定が進められており、2025年3月末までの最終化(確定)が予定されています。
本記事では、現在公表されている「公開草案」の内容に基づき、SSBJ基準の基本構成、IFRS基準との整合性、そして日本独自の基準として検討されている特徴について解説します。
※本記事は2025年3月5日にサステナビリティ基準委員会から発表された確定案より以前の内容となっています。
確定案に関しては下記記事を参照してください。



1.SSBJ基準の基本構成
SSBJ基準は、利用者の利便性を考慮し、以下の3つの基準書で構成される案となっています。
- 適用基準: 「サステナビリティ開示基準の適用(案)」
IFRS S1における「重要性(マテリアリティ)」の判断や報告の一般原則など、共通して適用される事項を定めています。 - 一般基準: 「一般開示基準(案)」
IFRS S1のコア・コンテンツ(ガバナンス、戦略、リスク管理、指標・目標)に関する具体的な開示要求を定めています。 - 気候関連基準: 「気候関連開示基準(案)」
IFRS S2に相当し、温室効果ガス排出量(Scope1, 2, 3)や気候変動リスク分析など、気候関連の具体的な開示事項を定めています。
IFRS S1を「適用基準」と「一般基準」の2つに分割している点が特徴ですが、これは将来的に気候以外のテーマ(自然資本など)が追加された際、共通部分(適用基準)に影響を与えずに拡張しやすくするための工夫です。
2.IFRS S1・S2との整合性と相違点
SSBJ基準案は、IFRS基準(S1・S2)の内容を原則としてすべて取り入れる方針で策定されており、国際的な比較可能性が高く保たれています。一方で、日本の実務に合わせた調整も行われています。
基準の構成方法
前述の通り、IFRS S1を2つの基準に分割する構成案が採用されていますが、開示される内容自体はIFRS基準と実質的に同等となるよう設計されています。
いくつかの任意的な追加取扱いの存在
日本企業の実務負担を考慮し、一部の項目で「選択的な適用(オプション)」を認める方向で検討されています。
例えば、Scope3排出量の算定において、利用可能なデータが限られる場合の経過措置や、産業連関表などの二次データの活用について、実務に即したガイダンスが含まれる見込みです。これらはIFRS基準から逸脱するものではなく、日本企業が円滑に適用できるよう補助する位置づけです。
将来の追加基準の余地
現時点では気候変動が優先されていますが、ISSBにおける次期テーマ(生物多様性や人的資本など)の議論に合わせ、SSBJでも将来的な基準追加が想定されています。
3.日本独自の基準としての特徴
SSBJ基準は、日本の金融商品取引法に基づく「有価証券報告書」での開示を主眼に置いて開発されています。
法定開示との連動
SSBJ基準は、有価証券報告書の「サステナビリティ情報の記載欄」等での使用を前提としています。これにより、財務情報と同じ報告期間(年度決算)で、同じ連結範囲(企業グループ)での開示が求められることになります。これは、従来のサステナビリティレポート(任意開示)とは異なり、法的責任を伴う厳格な開示へとシフトすることを意味します。
ステークホルダーの意見反映
基準策定プロセスでは、日本の企業、投資家、学識経験者などで構成される委員会での議論に加え、パブリックコメント(公開草案への意見募集)を通じて広く意見が反映されています。
例えば、不確実性の高い「財務的影響額」の開示や、シナリオ分析の定量化については、企業の実務負担や訴訟リスクを懸念する声を踏まえ、柔軟な記載を認めるなどの配慮がなされています。
4.まとめ
SSBJ基準は、日本企業がグローバルな投資資金を呼び込むための重要なインフラとなります。
2025年3月末の基準確定後、プライム市場上場企業を中心に早期適用や義務化の議論が本格化します。企業は、公開草案の内容を理解し、有価証券報告書での開示に向けたデータ収集体制(特にScope3や気候リスク分析)の整備を早めに進めることが推奨されます。
引用元
IFRS財団(ISSB)
https://www.ifrs.org/groups/international-sustainability-standards-board/
IFRS S1・S2 最終基準の概要
https://www.ifrs.org/