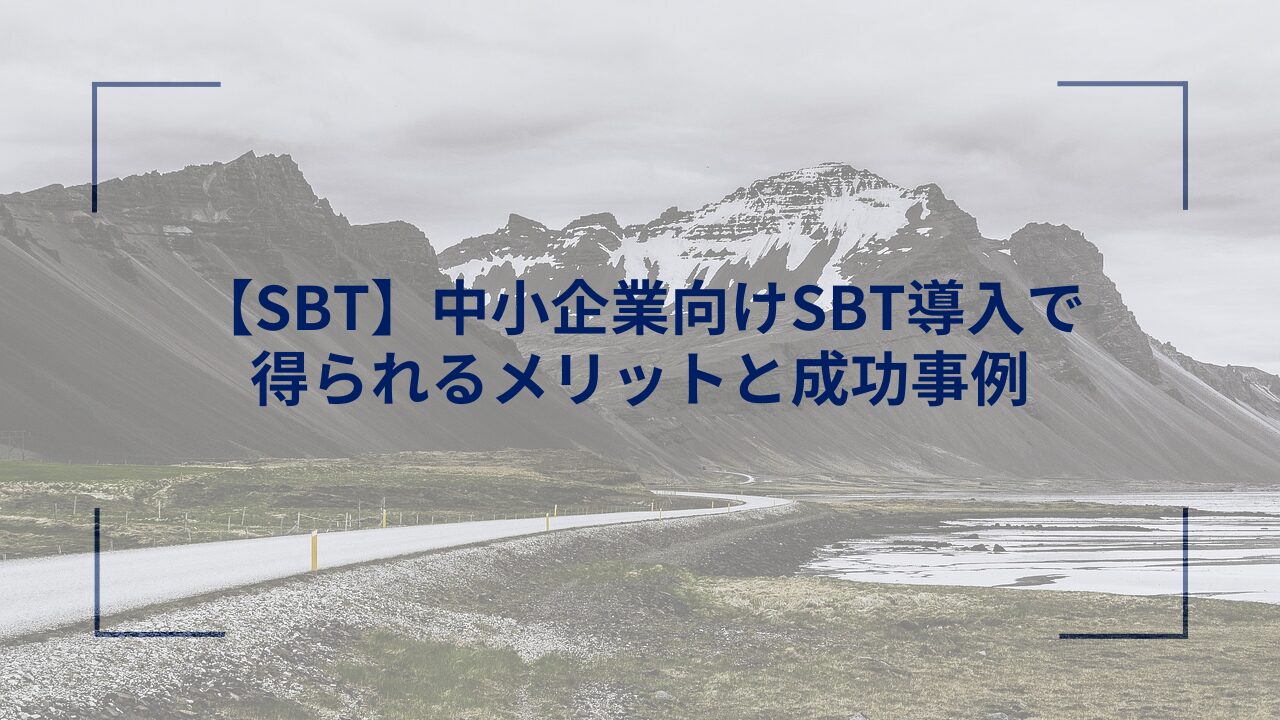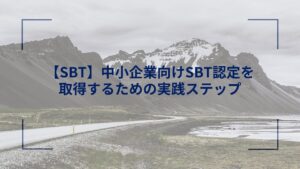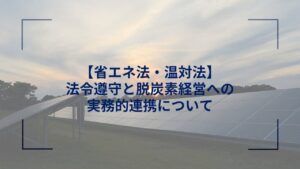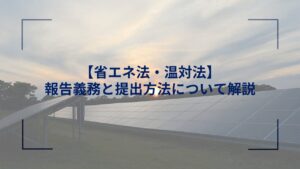中小企業版SBT認定を取得し、脱炭素経営に取り組むことは、環境への貢献のみならず企業経営上の様々なメリットをもたらします。本記事では、中小製造業がSBTを導入することで得られる主な利点を解説するとともに、実際にSBT認定取得によって事業価値を高めた成功事例を紹介します。環境経営の推進は取引先や社会からの信頼向上につながり、コスト削減やイノベーション創出の契機にもなります。先進企業の例に学びつつ、自社の持続可能な成長戦略にSBTを活用するヒントとしていただければ幸いです。

1. 中小企業版SBT導入の主なメリット
中小企業がSBT認定を取得し、科学的根拠に基づく削減目標を掲げることによって得られる代表的なメリットを以下にまとめます。
環境経営のアピールと企業ブランド強化
SBT認定の取得により、自社名がSBTi公式サイトに掲載されるなど、環境に配慮した経営を行っている事実を対外的に示すことができます。これは企業の社会的信用力を高める絶好の機会であり、積極的なCSR実践として顧客や取引先からの信頼獲得につながります。国際的な認証であるSBTは国内外で通用する指標でもあるため、特に輸出企業やグローバル展開を目指す中小企業にとって、自社の環境姿勢を示すブランド力の強化につながるでしょう。また、環境貢献への取り組みは地域社会や業界団体からも評価され、メディアの注目を集めるケースもあります。
取引機会の拡大とリスク回避
SBT認定取得は取引先との関係維持・拡大にも直結します。近年、大手メーカーを中心に「バリューチェーン全体での脱炭素」が重視されており、サプライヤーにもGHG削減努力が求められる傾向があります。この流れの中で、SBT認定を持つことは「取引先の要求に応えられる用意がある」ことを示す証となり、結果的に取引喪失のリスクを減らせます。逆に未対応の場合、温室効果ガス削減要請に応じられずビジネス機会を失う恐れがあります。SBT取得企業であれば、その姿勢自体が新たな顧客から選ばれる要因にもなります。実際、SBT導入企業は環境対応に積極的な取引先から信頼できるパートナーとして評価され、国内外で新規ビジネスチャンスを獲得するケースも増えています。
エネルギー効率化によるコスト削減
脱炭素経営を推進する過程で、省エネルギーの取組みが光熱費・燃料費の削減に直結する点も大きなメリットです。例えばSBT目標達成のために工場設備の電力使用量を最適化したり、高効率な機械に更新したりすることは、同時に電気代や燃料代の節約につながります。このようにコスト削減とCO₂削減の両立が可能となり、浮いた経費を他の成長投資に回すこともできます。事実、SBT認定企業ではエネルギー管理の徹底により運転コストが低減し、収益性が向上した例があります。津田工業のケースでは古い工作機械を省エネ型に置き換え待機電力を削減した結果、光熱費削減と生産効率アップを同時に実現しています。さらに、社内で省エネ改善の文化が根付くことで、日々の業務におけるムダの見直しや改善提案が活発化し、長期的なコスト競争力強化につながる好循環も期待できます。
参照:https://www.tsuda-kogyo.co.jp/news/p5600/
技術革新の促進と従業員エンゲージメント向上
SBTの削減目標は往々にして高いハードルですが、だからこそ新しい技術やプロセスの開発を促す原動力となります。目標達成のために自社製品や製造プロセスの見直しを行う中で、これまでにないイノベーションが生まれる可能性があります。例えばエネルギーを大幅に削減できる新工法の開発や、副産物からエネルギーを回収する仕組みの導入など、SBT達成を契機とした技術開発が競争力向上につながった例も報告されています。
また、社内における従業員の環境意識の向上も無視できない効果です。SBT目標という会社全体のチャレンジがあることで、社員一丸となって取り組む雰囲気が醸成され、現場から省エネや改善のアイデアが次々と出てくるようになります。自社の環境貢献に対する誇りが従業員のモチベーションアップにつながり、人材定着や採用面でのアピールにもなるでしょう。結果的に、環境対応を通じた社内の一体感向上と人材育成という副次的なメリットも享受できます。
資金調達・支援策での優遇
金融機関や行政からの支援を得やすくなる点も見逃せません。多くの銀行が脱炭素経営に積極的な企業に対し、融資条件の優遇やサステナビリティ・リンク・ローンの提供などを行っています。SBT認定の取得は、そうしたグリーンファイナンスを利用する際の有力な信用材料となり得ます。実際に「SBT認定企業であること」を融資審査や金利優遇の判断基準に含める金融機関も出始めています。
また、公的補助金の申請でも有利になる場合があります。自治体によっては、SBT関連の取組みを行う中小企業向けに補助金枠を設けているケースもあり(例:中小企業版SBTのコンサル費用補助)、認定取得企業であることで加点評価を受けられる可能性があります。さらに、先進的な環境認証を持つことで株主や投資家からの評価が高まり、資本調達面でも長期的なメリットが期待できます。このように、SBT導入は企業の財務面にも好影響を及ぼし、持続可能な成長を下支えします。
2. 中小企業におけるSBT導入の成功事例
続いて、実際に中小企業版SBT認定を取得して脱炭素経営を進め、事業上の成果を上げている企業の例を見てみましょう。製造業を中心に、環境と経営の両立を実現した成功事例を3つ紹介します。
協発工業株式会社 – 業界初のSBT認証で取引拡大を実現
協発工業(愛知県、従業員34名)は自動車部品のプレス加工メーカーで、自動車・輸送用機器セクターでは国内で初めてSBT認証を取得した中小企業です。同社は2030年までに2018年比で50%のCO₂削減を目標と定め、主に再生可能エネルギー電力への転換で大幅削減を図っています。具体的には、太陽光発電設備を持つ電力会社とのPPA契約やグリーン電力メニューへの切替えを推進し、購入電力由来の排出を削減しました。また、2021年には従来別々に稼働していた2工場を統合し、生産設備を集約することでエネルギー効率を高める施策も実施しています。これらの積極的な環境投資により、協発工業は業界内で環境先進企業として認知されるようになりました。SBT認定取得を契機に環境への取り組みを積極的にPRした結果、環境意識の高い新規取引先との関係構築が進み、事業拡大にもつながっています。同社は「中小企業でも環境対応をビジネスの核に据え、競争力強化に結びつけられる」ことを実証した好例と言えるでしょう。
参照:https://kyohatu.co.jp/entry02/
株式会社津田工業 – 省エネ改善によるコスト減と信用力向上
津田工業(岐阜県、従業員規模中堅)は機械部品の製造を手掛ける企業で、脱炭素経営の一環として中小企業版SBT認定を取得しました。同社はまず省エネルギーセンターの専門家診断を受け、自社工場のエネルギー使用実態を詳しく分析しました。その結果を踏まえ、特に消費電力の大きい古い工作機械を高効率機種へ更新し、待機時の無駄な電力消費を削減する施策を実行しました。さらに冬場の暖房には廃材を燃料とする薪ストーブを導入し、化石燃料使用量の低減にも寄与しました。これら段階的な取り組みにより、同社はCO₂排出量削減と同時に電力・燃料コストの大幅な節減に成功しています。削減努力の成果は社内外から注目され、地元紙や業界誌からの取材も増加しました。その結果、企業としての信用力や知名度が向上し、既存取引先との関係強化のみならず新たなビジネス機会の創出にもつながっています。津田工業の事例は、中小企業がSBT目標に沿った省エネ投資を行うことで、「環境」と「経済」の双方でリターンを得た成功例と言えるでしょう。
参照:https://www.tsuda-kogyo.co.jp/news/p5600/
株式会社艶金 – 再エネ活用で業界をリードする染色メーカー
艶金(つやがね、岐阜県、従業員132名)は繊維染色加工業の老舗で、業界に先駆けて環境対応を進めてきた企業です。同社は1987年にバイオマスボイラーを導入し、工場内で使用する熱エネルギーの95%をまかなう仕組みを構築しました。木質バイオマス燃料の活用により、石油ボイラーに依存しない環境に優しい染色プロセスを実現し、従業員への環境啓発活動にも力を入れてきました。こうした取り組みが評価され、艶金は国内の染色加工会社として初めて中小企業版SBT認定を取得しています。SBT認定後は、工場の電力を再生可能エネルギー電力に切り替えるなど、更なるCO₂削減策に着手しました。加えて、省エネ投資による生産効率の向上や、環境に配慮した染色技術の開発にも取り組み、経営改善にも結び付けています。艶金はSBT導入を通じて業界内で環境リーダーシップを発揮し、自社のブランド価値を高めるとともに、環境対応をビジネスの強みに変えた好例です。
参照:https://www.tsuyakin.co.jp/archives/1479
企業戦略への統合
以上に紹介した企業に共通するのは、環境対応を企業戦略の中心に据えていることです。それぞれの企業が自社の業態に即した方法でCO₂削減を進め、大きな成果を上げていますが、いずれも「気候変動への取り組み」が単なるコストではなく将来への投資であるという信念を持っています。そしてSBT認定という枠組みを活用してその取り組みを効果的に社内外へアピールし、新たな顧客や取引機会の獲得に結び付けています。環境と経営の両立が実現しているこれらの実例は、同規模の中小企業にとって非常に参考になるでしょう。
3. 環境対応を競争力に変える
中小企業版SBTは、多くの中小企業にとって持続可能な経営戦略の要となり得る取り組みです。認定取得そのものが目的ではなく、そのプロセスで得られる社内外への好影響こそが真の価値と言えます。環境目標の達成に向けて挑戦を続ける中で、自社の効率が高まり、新たな技術やビジネスチャンスが生まれ、ステークホルダーからの評価も向上します。ぜひ先行企業の成功事例から示唆を得ながら、「自社らしいSBT活用」を模索してみてください。環境課題への対応を企業の競争力に転換し、持続可能な未来への道を切り開いていきましょう。