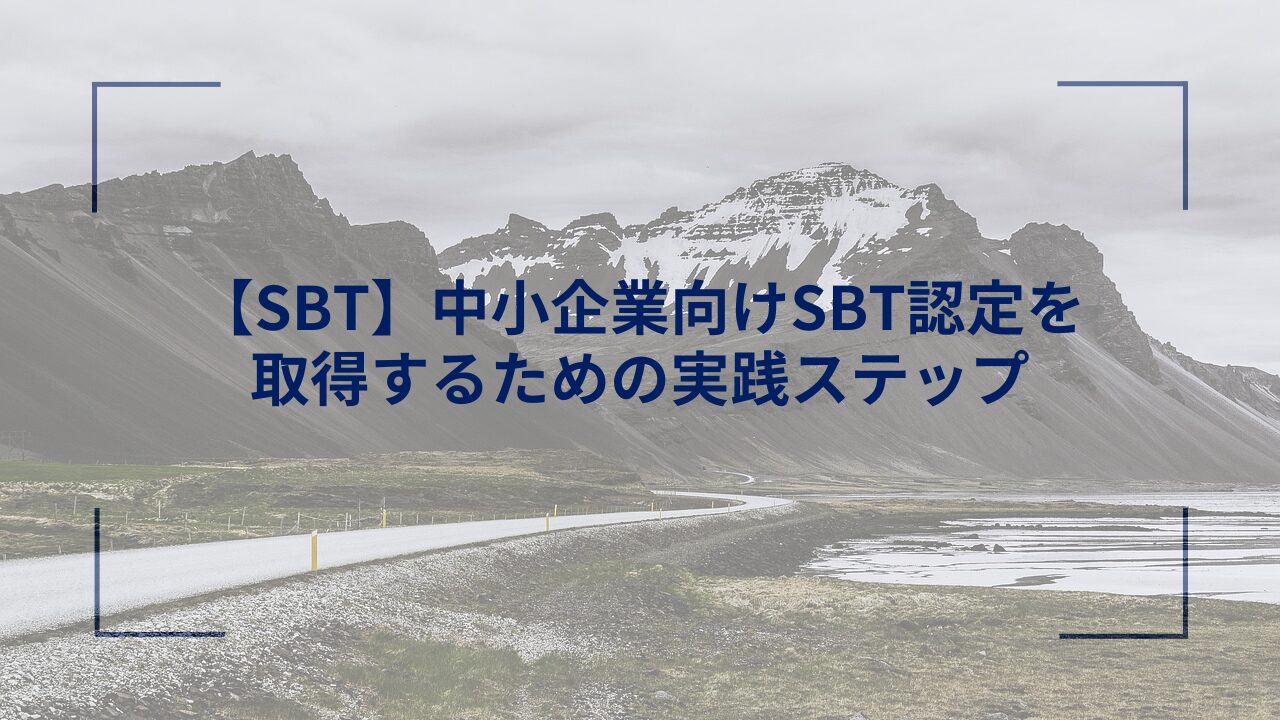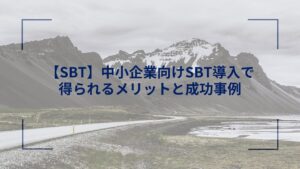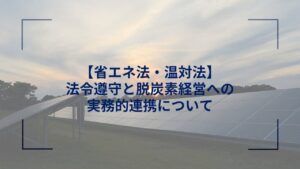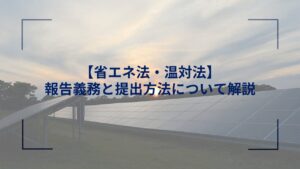中小製造業がSBT (Science Based Targets) 認定を取得するには、事前の準備と明確な手順に沿った取り組みが不可欠です。本記事では、中小企業版SBT認定を取得するための実践的なステップを解説します。具体的には、排出量の現状把握とGHGプロトコルに基づく算定、科学的根拠に沿った削減目標の策定、そしてSBTiへの申請プロセスまで、各段階でのポイントを紹介します。社内リソースが限られている中小企業でも計画的に進めることで、将来的なカーボンニュートラル(2050年温室効果ガス排出実質ゼロ)達成に向けた一歩を踏み出すことが可能です。以下に、そのステップを順を追って解説します。

1. 申請に向けた事前準備
SBT認定取得に取り組むにあたっては、実際の手続きを開始する前にいくつかの事前準備を行っておくことが重要です。
対象要件の確認と社内体制整備
まず自社が中小企業版SBTの申請対象となり得るかを確認します。SBTiが定める所定の基準(従業員数・売上高・排出量規模など)を満たす必要があるため、公式ガイダンスや専門資料で条件をチェックしましょう。同時に、経営陣からのコミットメントを取り付け、環境推進担当者や関連部門でプロジェクトチームを編成します。温室効果ガス削減は全社横断的なテーマのため、生産部門や設備管理部門などからも協力を得られる体制を整えておくことが望ましいです。
必要データの収集と整理
SBT申請には様々なデータ提出が求められます。具体的には、「会社情報(基本的な企業プロファイル)」「財務情報(損益計算書・貸借対照表)」「従業員数の分かる書類」などの企業概要に関する資料のほか、自社の温室効果ガス(GHG)排出量データ(Scope1およびScope2)、そして削減目標値を準備する必要があります。これらを事前に収集し、正確に整理しておきます。特にGHG排出量については、電力会社の電気使用量明細や社用車の燃料レシートといった客観的なエビデンスを集め、それに基づいて算定することが重要です。データに基づく算定方法は後述しますが、証拠となる資料が揃っていないと正確な排出量把握ができず申請プロセスで苦労するため、早めに情報を洗い出しておきましょう。
社内目標と方針の確認: SBT認定取得は単なる環境CSRではなく経営戦略の一環です。自社の中長期経営計画や既存の環境目標との整合性を確認し、SBTで掲げる数値目標が社内の合意を得られるか検討します。トップマネジメントからの支持を明確にし、「なぜSBT認定を目指すのか」「認定取得後にどう活用するのか」を社内で共有しておくと、後のステップが円滑に進みます。
2. 自社のGHG排出量の算定(現状把握)
最初のステップは、現状の温室効果ガス排出量を定量的に把握することです。これはSBT目標を検討する土台になる重要な作業です。
GHGインベントリ(排出量目録)の作成
国際標準であるGHGプロトコルのガイドラインに沿って、自社のGHG排出量を算定します。具体的には、自社の事業活動に伴う直接排出(Scope1)および購入電力などの間接排出(Scope2)について、年間排出量(CO₂換算量)を算出します。製造業の場合、ボイラーや炉などの燃料使用量、社有車の燃料消費量が主なScope1排出源となり、工場や事務所で使用する電力がScope2に相当します。それぞれについて、前年度あるいは基準とする年度の使用実績データを集計し、GHGプロトコルに定められた排出係数を用いてCO₂排出量を計算します。電力使用量については電力会社の月次レポートや電気料金明細から年間消費kWhを把握し、電力のCO₂排出係数を乗じて算定します。燃料についても購入量や使用量からCO₂排出係数を用いて計算します。
Scope3(サプライチェーン排出)の把握
中小企業版SBTでは必須ではないとはいえ、できれば自社のバリューチェーンにおけるその他の間接排出(Scope3)も概算しておくと望ましいです。調達原材料や製品輸送、従業員の出張や廃棄物処理まで含めた排出量は項目が多岐にわたりますが、主要な項目について大まかな数値を掴んでおけば、将来的な削減策の検討に役立ちます。ただし初期段階ではScope1と2の正確な把握が最優先であり、社内リソースに限りがある場合はScope3算定は無理のない範囲で進めましょう。
第三者の診断活用
自社だけで排出量計算を行うのが難しい場合、専門機関の診断サービスや自治体のエネルギー診断を活用する方法もあります。外部の知見も取り入れつつ、まずは現在の排出量の全体像を社内で共有しましょう。
3. 科学的根拠に基づく削減目標の策定
現状のGHG排出量が把握できたら、次に削減目標(ターゲット)を設定します。中小企業版SBT認定を取得するには、この目標がパリ協定に整合した「十分に野心的な水準」である必要があります。
短期(5〜10年程度)の削減目標設定
SBTiでは一般に10年先を見据えた近未来の削減目標を定めます。中小企業版SBTの場合、Scope1・2の排出量について「産業革命前比1.5℃シナリオに沿う水準」、具体的には年間平均4.2%以上の削減率に相当する目標を掲げることが求められます。例えば基準年を2020年とした場合、2030年までにScope1+2排出量を50%以上削減する(年率換算4.2%超)といった目標が一つの目安となります。自社の実情に合わせて達成可能かつ挑戦的な値を検討しましょう。また、可能であればScope3についても自主的な目標を設定すると、サプライチェーン全体の取り組み姿勢として対外的な評価が高まります(中小企業版では必須ではありませんが、自社の主要なScope3排出源に言及した目標があると望ましいでしょう)。
長期目標(ネットゼロ)の視野
近年、SBTiは長期的なネットゼロ(実質排出ゼロ)目標の設定も企業に推奨しています。日本政府も2030年までに2013年度比46%削減、2050年までにカーボンニュートラル達成という国家目標を掲げています。中小企業であっても、2050年頃までに自社の排出量をゼロにするという長期ビジョンを持つことは重要です。まずは2030年前後までの短期ターゲットを明確にし、それを達成した先に2050年ネットゼロへの道筋を描く形で目標体系を構築すると良いでしょう。
社内合意と目標の正式決定
候補となる数値目標が固まったら、経営層の承認を得て社内の公式な目標として設定します。合わせて、目標達成に向けた概略のシナリオも検討します。例えば、「再生可能エネルギーの電力への転換で○○%削減、設備の高効率化で○○%削減」といったように、大まかな施策と寄与率を試算しておくと、目標の現実性が評価できます。SBTiへの申請上は具体的施策計画の提出までは求められませんが、どうやってその目標を達成するのか社内で腹落ちさせておくことが大切です。
4. ステップ3: SBTiへの申請手続き(コミットメント表明と提出)
準備したデータと目標をもとに、いよいよSBTイニシアティブへの公式な申請手続きを行います。
オンラインアカウント登録
SBTiのウェブサイトにアクセスし、検証ポータル上で企業アカウントを作成します。入力項目には基本的な会社情報のほか、前述の要件確認のための質問(従業員数や事業セクター等)が含まれます。アカウント登録後、SBTi側で自社が中小企業版SBTの対象かどうかチェックが行われ、問題なければポータルにログイン可能となります。
排出量データ・目標値の提出
ポータル上で、自社のGHG排出量(Scope1・2)および設定した削減目標をフォームに従って入力・提出します。この際、算定根拠がGHGプロトコルに準拠していること、目標値が求められる水準を満たしていることがポイントです。提出内容はSBTiによるデューデリジェンス(精査)を受け、不備や疑義があれば差し戻し連絡があります。指摘事項があった場合は速やかにデータを修正し再提出します。特に算定ミスや単位間違いが無いよう、念入りにチェックしましょう。
認定費用の支払い
提出データに問題がないと承認の仮通知が届き、続いて請求書が発行されます。中小企業版SBTの申請費用は約1,250ドル(USD)です。指定された方法で海外送金により支払いを完了します(多くの場合、請求書受領から30日以内など期限が定められています)。支払いが確認されると、正式な認定手続きへ進みます。
認定結果の受領
最終的にSBTiから「貴社の目標がScience Based Targetsとして承認されました」という公式レターが届きます。これにより晴れてSBT認定企業の仲間入りです。SBTiのウェブサイトにも自社名と目標概要が掲載されます。同時に、SBTiから提供される認定ロゴやガイダンス資料(ウェルカムパック)を受け取り、社内外への発表準備を進めます。
5.認定取得後の取り組みと継続的な改善
SBT認定は取得して終わりではなく、そこからが本番です。掲げた目標を達成するため、継続的な排出削減の取り組みを社内で推進していきます。
削減アクションの実行
目標達成に向けて、省エネルギー施策や再エネ導入など具体的な削減プロジェクトを実行に移します。工場であれば老朽設備の高効率機器への更新、エネルギー管理システムの導入、照明のLED化や空調の最適制御、工程の効率化によるムダ排除など、多くの対策が考えられます。投資が必要な施策については、補助金の活用や段階的な実施計画も検討し、無理のない範囲で着実に進めます。こうした個々の施策の積み上げが、長期目標の達成に繋がります。
進捗モニタリングと報告
SBTiでは、認定取得後も毎年のGHG排出量を開示し、進捗状況をフォローアップすることが推奨されています。少なくとも社内では年次ベースで排出量を再計算し、削減が順調に進んでいるかチェックしましょう。仮に計画通りに削減できていない場合は、原因を分析し追加対策を講じます。また、これらの状況は統合報告書やサステナビリティレポートにまとめ、ステークホルダーに報告・説明することで企業の信頼性向上にもつながります。
社内への浸透と長期コミットメント
目標達成には現場レベルでの協力が不可欠です。社員一人ひとりに環境目標を周知し、省エネの意識啓発やアイデア提案の機会を設けることで、全社的な取り組みに発展させます。トップマネジメントも定期的に進捗をレビューし、必要なら方針転換や追加投資の判断を行います。SBT認定取得後も定期報告や改善策の継続的実施が求められるため、経営層および従業員の長期コミットメントが重要です。この継続的な努力を怠ると、せっかく取得した認定の意義が薄れ形骸化しかねません。そうならないよう、社内の環境活動を推進する仕組み(例えば環境委員会の設置やKPIへの組み込み)を構築し、長期にわたって改善サイクルを回し続けることが肝心です。
認定の活用(社外アピールとビジネス戦略)
認定を取得したら、プレスリリースや自社ウェブサイトで対外発信し、取引先や顧客に周知しましょう。SBT認定企業であることは、環境に配慮した経営を行っている証として新たなビジネス機会の創出にもつながります。また金融機関からの評価も向上し、脱炭素経営を進める企業への融資優遇策などを受けられる可能性もあります。自社のブランド価値向上と競争力強化に、認定を積極的に役立てていく視点も忘れないようにしましょう。
以上、SBT認定取得に向けたステップを概観しました。リソース不足など中小企業特有の課題もありますが、社内外の協力を得ながら進めることで乗り越えることができます。科学的根拠に裏付けされた気候目標を掲げ、それに挑戦していくプロセスは、自社のイノベーション促進や持続可能な成長にも寄与するはずです。ぜひ計画的に取り組みを進め、貴社の持続可能性戦略にSBT認定を位置付けてみてください。
引用元
環境省『SBT(Science Based Targets)について』(2021年8月、環境省資料)
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/files/SBT_syousai_all_20210810.pdf
SBT等の達成に向けたGHG排出削減計画策定ガイドブック
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/guide/SBT_GHGkeikaku_guidebook.pdf