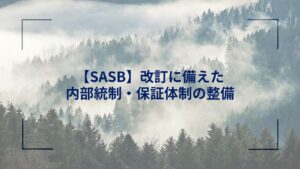1.トランジション・ボンド/ローンの定義と特徴
トランジション・ボンドとは、一般的に「グリーンボンドの基準に適合しないものの、低炭素経済への移行(トランジション)を促すプロジェクト」を資金使途とする債券を指します。企業が温室効果ガス排出削減に向けた移行計画を実行するための設備投資や研究開発などに充当され、重化学工業、発電、運輸など炭素集約型産業での活用が想定されています。実際、石油・ガス、製鉄、化学、航空、海運といった通常はグリーンボンド発行が少ない高排出セクターでの発行例が見られます。
一方、トランジション・ローンも基本的な考え方は債券と同様で、金融機関が借り手企業の移行プロジェクトに対して融資を行うものであり、借入契約上で資金使途を移行関連に限定しグリーンローンの原則にならった管理・報告を行う形態です。
登場背景
トランジション・ボンドの登場背景には、気候変動対策への機運高まりの中で「環境分野への投融資」を促す枠組みにおいて移行がキーワードとして浮上したことがあります。2015年のパリ協定以降、企業の気候関連情報開示(TCFDなど)や経済活動の分類(EUタクソノミー)などで移行リスクや移行活動が重視され始め、2019年には仏大手運用会社AXA IMが独自のトランジションボンド指針を公表、同年クレディ・スイスと気候債券イニシアチブ(CBI)が「サステナブル・トランジション債」に関する提携を発表するなど、市場関係者による新たな取組みが相次ぎました。こうした流れの中、移行分野への資金提供ニーズに応える形でトランジション・ボンドという商品カテゴリーが確立してきたのです。
特徴
トランジション・ボンド/ローンは資金使途特定型(Use of Proceeds)の金融手法であり、調達資金は発行体の定める適格トランジション・プロジェクトに充当されます。グリーンボンドと同様にプロジェクト単位で環境インパクトを把握しやすい利点がありますが、グリーンボンドとの違いは、資金使途が制限される点です。現在は排出量が多い企業であっても、将来の低炭素化に向けた計画と意思が明確であれば、この手法で資金調達が可能です。そのため、トランジション・ボンドはグリーンボンドとサステナビリティ・リンク債の中間に位置づけられるとも言われます。一方で資金使途が「グレー」寄りの領域(化石燃料の効率化など)に及ぶ場合、投資家から厳しい目で見られる可能性もあり、移行計画の妥当性が信用力に直結する点が特徴です。
2.国際的な枠組みとガイドライン
トランジション・ボンド/ローンの信頼性を確保するため、国際的な指針が策定されています。ICMA(国際資本市場協会)は2020年12月に「気候トランジション・ファイナンス・ハンドブック」(CTFH)を発行し、トランジション関連債券で投資資金を調達する際に発行体が満たすべき推奨事項を提示しました。CTFHでは、発行体が自社の気候移行戦略を明確に開示し、事業計画との関連性(ビジネスモデル上の重要性)、科学的根拠に基づく中長期目標、その戦略実行の透明性を示すことが求められます。これら4要素は、既存の気候変動開示フレームワーク(例えばSBTiやTCFD)とも連動し、発行体の移行計画がパリ協定の目標と整合しているかを市場が評価する材料となります。
日本の基本指針
気候トランジション・ファイナンス基本指針も上記ICMAハンドブックの4要素を踏まえて策定されており、移行資金調達に関する具体的な開示項目や第三者評価のあり方を定めています。例えば、発行体は自社の脱炭素移行ロードマップを提示し、業界横断的な2℃/1.5℃シナリオや各国のNDC、国内外のセクター別ロードマップ(日本では鉄鋼や化学など8業種分が策定済)との整合性を説明することが推奨されます。
資金使途
また、資金使途の選定にあたっては、可能な限り既存のグリーンボンド原則に準拠した枠組み(プロジェクト評価・選定プロセス、資金管理、報告)を適用しつつ、「トランジション」として妥当かを検証する外部レビュー(セカンドパーティオピニオン等)を受けることが重要とされています。実務的には、国際的な評価機関による移行戦略の妥当性評価(例:経営計画におけるCO2削減目標の水準や投資計画の合理性の検証)と、個別プロジェクトの環境効果の測定・報告が両輪となります。
3.主な発行事例
初期のトランジションボンドの例としては、2017年に香港の発電事業会社Castle Peak Power社が発行した世界初のトランジションボンドが挙げられます。その後、欧州を中心に石油メジャーや化学メーカー、航空会社などによる発行が相次ぎました。日本では2021年夏にオリエンタルランド社が国内初のトランジションボンドを発行し、設備の省エネ化や再エネ利用拡大に充当しました。また、2022年には三菱重工業が500億円のトランジションボンドを発行し、水素インフラやCCUS(炭素回収・利用・貯留)等のプロジェクト資金に充当しています。同社の債券は経産省の「トランジション・ファイナンス・モデル事業」に選定され、外部レビュー費用補助を受けた典型例です。
さらに2024年には前述のとおり日本政府がGX経済移行債(国債)を発行するなど、ソブリン分野にも波及しています。一方、トランジションローンの分野でも、メガバンク主導で電力・ガス会社向けの移行用途の融資契約が締結され始めています。例えば石炭火力からの転換を目指す発電会社に対し、省エネ改造資金をトランジション・ローンとして貸し付けるケースなどが報告されています(融資契約には基本指針に沿った使途管理や報告義務が組み込まれる)。
4.課題と今後の展望
トランジション・ボンド/ローンは有望な手法である一方、いくつかの課題にも直面しています。
グリーンウォッシング防止
移行計画が不十分なまま「トランジション」の名を借りて実質的に環境悪化に繋がるプロジェクトへ資金が流れることがないよう、ガイドライン遵守と厳格な外部評価が求められます。また投資家側でも、移行債券に対する明確な投資基準を持ち、発行体の長期戦略や目標水準を精査する姿勢が必要です。もっとも近年はSBTi認定のように企業の気候目標の信頼性を評価する仕組みも広がっており、こうした認証取得が移行計画の信憑性を高める一助となっています。
展望
マーケット面では、現状トランジション債の発行額はグリーン債に比べると小規模ですが、日本は重工業中心に世界発行額の約7割を占める主要プレーヤーです。今後は欧州など他地域でもエネルギー転換投資の必要性が高まるにつれ、トランジション金融の裾野が広がると期待されます。国際標準のさらなる整備(例:EUグリーンボンド基準における適格移行プロジェクトの明確化)や、成功事例の共有によって投資家の理解が深まれば、市場拡大に弾みがつくでしょう。一方で投資家需要喚起のためには、「移行債への投資は気候貢献に資する」という納得感を醸成する必要があります。そのためには、発行体は野心的なKPI設定と達成に向けた確かな実行を示し、達成状況を定期的に報告していくことが肝要です。こうした好循環が生まれれば、トランジション・ボンド/ローンはグリーンボンド等と並ぶ主流の資金調達手段として定着し、カーボンニュートラル実現に不可欠な民間資金の動員に大きく貢献すると考えられます。
引用
トランジションボンドの登場とサステナブルファイナスの新潮流https://www.nicmr.com/nicmr/report/repo/2020/2020win15.pdfICMA
https://www.icmagroup.org/
NOMURA https://www.nomuraconnects.com/