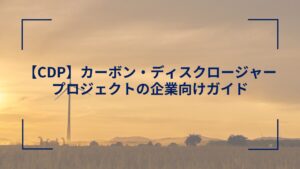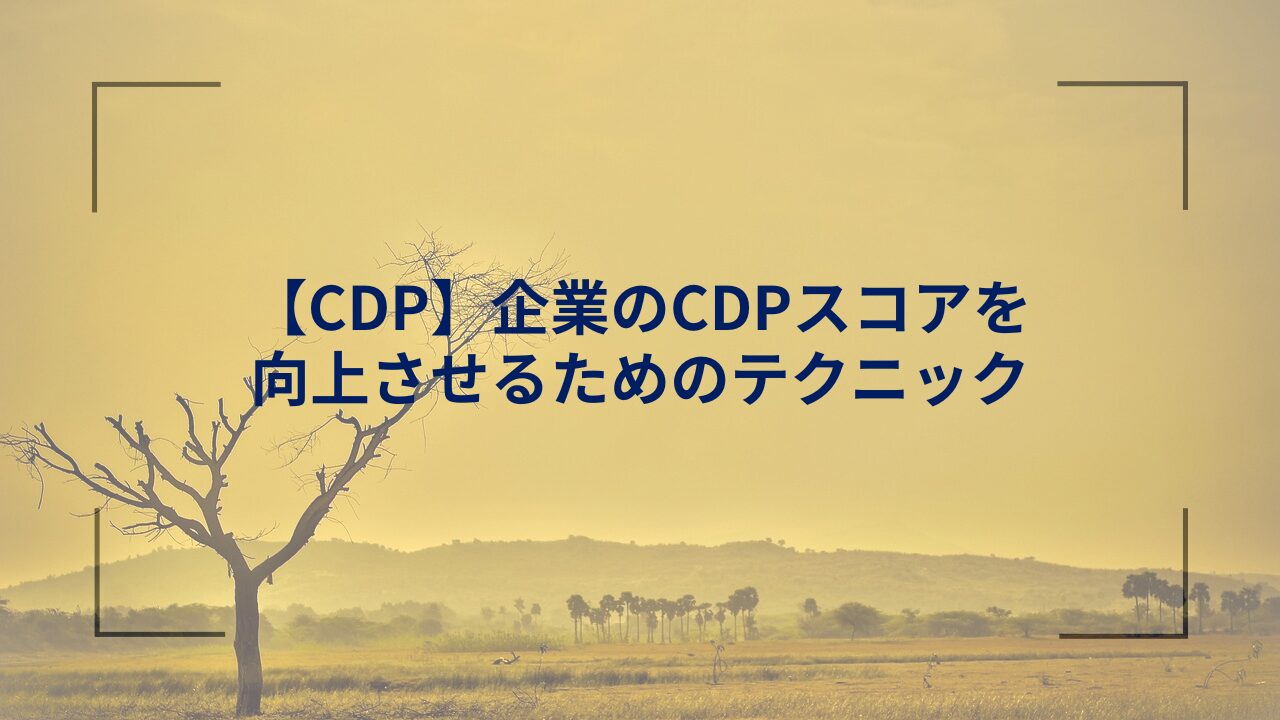企業の気候変動対応を評価するCDP質問書への回答は、単に設問に答えるだけでなく戦略的な工夫が求められます。CDPスコアは企業の環境対応水準や気候リスク耐性を測定する重要指標と位置づけられており、高スコアの獲得・維持は企業経営上大きな意味を持ちます。CDPの評価は情報開示からリーダーシップまで4段階に分類され、最上位のリーダーシップレベル(スコアA/A-)は取締役会レベルの気候ガバナンス、具体的な排出削減目標、1.5℃目標に沿った移行計画の策定・実行、詳細なリスク・機会分析などベストプラクティスを包括的に実践していることを示します。
本稿では、CDP質問書における効果的な回答テクニック(STAR話法の活用、自社固有情報の提示方法、スコア帯ごとの重要項目、スコア向上の具体策)を整理し、さらに第三者保証がCDPスコアに与える影響(有効な保証の種類、検証プロセス、評価基準とスコアへの影響)について、CDP公式情報を基に検討します。


1. CDP質問書回答のテクニック
CDP質問書には自由記述で企業の取り組みを説明する設問が含まれます。効果的な回答にはSTAR話法(Situation, Task, Action, Result)の活用が有用です。
STAR話法の活用方法
具体的なエピソードを記述する際に、状況(課題となる背景)→課題(直面した問題や目標)→行動(講じた対策)→結果(得られた成果)の各要素を盛り込むことで、論理的かつ包括的な説明が可能となります。例えば「気候リスク評価」を述べる場合、まず「自社が直面する気候変動による具体的リスク状況」を述べ(Situation)、次に「そのリスクに対して課題となった点」(Task)を示します。続いて「課題解決のために実行した対策」(Action)を説明し、最後に「対策の結果としてリスク低減や機会創出につながった成果」(Result)を記述します。STAR話法に従えば冗長な説明を避けつつ要点を網羅でき、評価者に分かりやすい回答となります。CDPでは自由記述欄の記載内容もスコアリング評価の一要素となっており、STAR話法によって論理的整合性のある記述を心がけることが高評価につながります。
自社固有の情報の提示方法
自社の実情に即した具体的な情報提示も重要です。汎用的な回答ではなく、自社固有のデータや事例を盛り込み回答の説得力を高めるべきです。例えば「当社は気候変動対策に取り組んでいる」と述べるだけでなく、その施策が必要となった背景や意思決定の根拠を明確に説明し(なぜその対策を講じたか、どのような論理にもとづくか)、具体的な経緯を示す必要があります。さらに可能な限り定量的データや具体例を示すことが望ましいです。例えば温室効果ガス削減目標であれば「2030年までにScope1+2排出量を2019年比30%削減する」など、数値目標や進捗状況を明記します。
また実績についても「2024年末時点で20%削減を達成」といった具体的成果を記載することで、回答の信頼性が増し、評価者に自社の取り組みの有効性を伝えられます。加えてタイムラインを意識し、「いつからいつまでに何を達成したか」を明確にすることも求められます。CDPの設問には、取組の開始年や目標達成年など時間枠の記載が評価ポイントになるものがあるため、例えば「2019年に○○施策を開始し、2023年までに中間目標を達成、2030年に最終目標を予定」といったように時系列で行動と成果を示すと高評価につながります。回答内容は他の設問や定量データとも一貫性と整合性が保たれていなければなりません。自由記述で述べた内容が、別の設問で選択肢として回答した内容や開示した数値データと矛盾していれば信頼性が損なわれ、得点対象とならない可能性があります。従ってCDP回答全体を通じて統一したメッセージとデータ整合性を維持することが重要です。
将来展望
また将来の展望についても触れることが望ましいです。現在の取り組み状況だけでなく、今後の目標や計画、見通しを盛り込むことで、継続的改善へのコミットメントを示せます。これは高スコア維持の一因となると考えられます。さらに回答内容の独自性にも注意が必要です。CDP公式のガイダンスでは、他の質問や他の環境分野(気候変動 vs 水セキュリティ等)で同じ文章を使い回すことへの注意喚起がなされています。仮に類似の質問項目があっても機械的に過去回答をコピー&ペーストすると文脈にそぐわない恐れがあります。
実際、公式には「質問間または環境課題領域間で複製された回答は、それぞれの文脈で意味が通じ、スコアリング基準で要求される具体的情報を提供している場合のみ得点の対象となる」と明記されています。つまり各設問の意図に合わせたカスタマイズが不可欠であり、過去の回答を流用する場合でもそのまま貼り付けるのではなく、設問ごとに適切に言い換え補足することが求められます。自社の状況に即した具体的な情報を盛り込み、汎用的になりすぎない回答とすることで、評価者に「自社の気候対応について十分な理解と開示を行っている」ことを印象付けることができます
スコア帯ごとの重要項目と必須要件への対応
CDPでは回答内容に基づき各質問にスコアが付与され、Disclosure(情報開示)からLeadership(リーダーシップ)まで4段階の評価カテゴリーに集計されます。最上位のリーダーシップ・レベル(A-/Aスコア)に進むためには、単に得点を積み上げるだけでなく各スコア帯の「必須要件」をすべて満たす必要があります。必須要件とは、各評価レベルに上がるために最低限満たさねばならない条件であり、たとえ全体の点数が高くとも必須要件を一つでも欠けばそれ以上の評価段階に進めない関門となります。例えば、認識レベルから管理レベル(CからB)に上がるには設定された複数項目全て、管理レベルからリーダーシップレベル(BからA-)に上がるにはさらに多くの項目全てを満たす必要があります(業種によって項目数は異なります)。
このようにCDPではスコア帯ごとに明確な到達基準があるため、自社の回答が各必須要件を網羅しているかを確認し、不足があれば是正することが高得点への前提条件となります。
リーダーシップレベル(A-/A)
特にリーダーシップレベル(A-/A)に到達するための必須要件には、気候変動対応における先進的な取り組みが含まれます。具体的には、取締役会レベルでの気候変動の監督体制(気候ガバナンス)や経営層へのインセンティブ制度、気候関連リスク・機会を企業戦略や財務計画に統合していること、パリ協定目標に整合した政策提言・公共政策関与、そして1.5℃目標に合致した移行計画の策定が求められます。温室効果ガス排出量の開示はもちろん、排出実績の第三者検証(第三者保証)を受けてデータ信頼性を担保していることも重視されます。実際、Scope1および2排出量の少なくとも95%に対する第三者検証の実施(A-評価要件)、主要なScope3カテゴリの排出量に対する検証の実施、といった条件が設定されています。さらに、自社全体の温室効果ガス排出に関する中長期の削減目標を設定していることも必須であり、とりわけ科学的根拠に基づく削減目標(SBT)の取得が重要視されます。例えば、基準年排出量の95%以上をカバーし5~10年先を目標年とする短期削減目標がSBTイニシアチブ(SBTi)によって認定されていることがA-/A評価の前提条件となっています。
加えて、排出削減目標の達成に向けた具体的行動計画(移行計画)の存在と、進捗をモニタリングする仕組みも要件に含まれます。以上のように、最高評価を得るにはガバナンスから目標設定・計画策定・データ信頼性確保まで網羅的な対応が必要となり、これらを回答中で明確に示すことが求められます。実際、CDP2023では回答企業のうちAリスト企業は約9%と限られており、A評価取得には非常に高度な取り組みが必要であることが分かります。
2. より高いスコアを得るための具体的テクニック
上記の必須要件を満たすことは高スコア獲得の大前提ですが、さらなるスコア向上のためには回答内容の質を高める夫が重要になります。以下に、高評価につながる具体的テクニックをまとめます。
継続的な改善と最新情報への対応
CDPは評価基準を毎年更新しており、企業側の取り組みも年々高度化していく傾向があります。前年と同じ内容を回答するだけではスコアを維持できない可能性があるため、気候変動対策における自社の取組を継続的に強化し、その内容を最新の基準に照らしてアップデートして開示することが必要です。例えば、気候関連財務情報開示の国際基準(IFRS S2)や生物多様性リスク開示フレームワーク(TNFD)など新たな枠組みにも目配りし、自社の情報開示に反映していく姿勢が求められます。常に業界のベストプラクティスや規制動向を把握し、自社の戦略・目標をアップデートすることで、CDP質問書への回答内容も充実し高評価につながります。
サプライチェーンへの取り組み強化
自社排出だけでなくバリューチェーン全体(Scope3)の排出削減にも積極的に取り組む姿勢が重要です。CDPではScope3排出の把握と削減が重視されており、特にサプライヤーエンゲージメント(サプライヤーへの働きかけによる排出削減)が評価される傾向にあります。自社の主要なサプライヤーに排出削減目標設定を促し協働して削減を進めている事例や、購入原材料・製品のライフサイクル排出量の可視化といった取り組みを紹介すれば、気候変動対応をバリューチェーンまで拡大している点で評価が高まります。実際、A評価企業にはScope3排出の削減に向けサプライヤーとの協働を行っているケースが多いと考えられます。
リスクと機会の網羅的な評価
気候関連リスク・機会の評価については、TCFD提言に沿ってシナリオ分析を実施し、企業戦略への影響を定量評価することが望ましいです。CDPでは「気候関連リスク・機会が企業の戦略および財務計画に与える影響」が開示されているかが重要視されます。シナリオ分析の結果、自社の事業ポートフォリオにどのような影響が及ぶか、移行リスクや物理的リスクへの対応策は何か、といった点を詳細に回答すれば、認識レベルを超えたマネジメント・リーダーシップレベルの取り組みとして高評価となります。また機会の側面(低炭素製品やサービスによる収益機会等)についても言及し、気候変動を戦略的に捉えている姿勢を示すことが望ましいです。
取締役会の関与と統治の実証
ガバナンス面では、取締役会が気候変動課題を定期的に審議し監督していることを具体的に示す必要があります。例えば取締役会において年◯回気候変動関連の報告・審議を行っていること、気候変動に関する専門知識を有する社外取締役を任命していること、経営層のKPIにCO₂削減や気候リスク対策を組み込んでいること(業績評価への組込み)など、ガバナンス強化の取り組みを詳述します。A/A-スコア企業には取締役会レベルでの気候ガバナンス実践が求められるため、この点での具体的な説明は必須です。社内規程や取締役会議事録の要約なども活用しつつ、ガバナンス体制の実効性をアピールします。
以上のようなポイントを踏まえ、設問ごとに的確かつ網羅的な回答を作成することが高スコアへの道です。単に質問項目を埋めるのではなく、自社の戦略・目標・実績を総動員して「ストーリー」を示す意識が重要といえます。
3. 第三者保証がCDPスコアに与える影響
第三者保証とは、企業が報告する温室効果ガス(GHG)排出量などのデータについて、独立した外部の専門機関が検証を行い、その正確性・網羅性を保証するプロセスです。ここでいう「第三者」とは、データを算出・提供した当事者から独立し、かつそのデータの利用者からも独立した立場にある組織を指します。具体的には、温室効果ガス検証の専門資格を持ち、国際的に認められた基準に基づいて検証を実施できる公正中立な審査機関が該当します。第三者保証の目的は、企業が開示するGHG排出量などの情報に対して、外部からの客観的なお墨付きを与えることです。これにより投資家を始めとするステークホルダーは、当該データが信頼に足るものであると安心でき、企業の開示する環境情報の信憑性・透明性が向上します。CDP自身も「環境報告におけるグッドプラクティス」として第三者検証/保証の実施を強く支持しており、質問書の該当設問を通じて報告データの精度確保を促しています。つまり、第三者保証は単なるオプションではなく、信頼性の高い気候情報開示に不可欠なステップと位置づけられています。
有効な第三者保証の種類(基準と水準)
第三者保証にもさまざまな基準(スタンダード)や保証レベルが存在しますが、CDPでは国際的に認知された検証基準に沿った保証が有効とされています。一般に温室効果ガス排出量の検証には、以下のような基準が用いられます。
ISO 14064-3
国際標準化機構(ISO)による温室効果ガス検証の標準規格(組織単位のGHG検証手順を規定)
ISAE 3000/3410
国際会計士連盟が定める保証業務基準(3000はサステナビリティ情報全般、3410はGHGアサランスに特化)
AA1000AS
AccountAbilityが策定したアシュアランス標準(ステークスホルダー・エンゲージメントを重視)
The Climate Registry 等
米国や各国のプログラムにおける検証基準 など
第三者検証機関は上記のような基準に基づき、企業との合意に従って限定的保証または合理的保証といった保証水準で検証を実施します。限定的保証は一般的な水準で、主にISO14064-3やISAE3000等に準拠した手続きによって「重大な誤りがないこと」を負担付きで表明します。一方、合理的保証は限定的保証より詳細な検証を行い、高い確信度をもって「正確性を保証する」もので、ISO14064-3やISAE3000による検証でも保証レベルを上げることで合理的保証に該当し得ます。
CDP質問書では検証の有無だけでなく、その保証のレベル(限定的、合理的など)や使用した基準、検証機関名、検証された排出量範囲(割合)等を回答する形式になっており、高水準の保証(例えば合理的保証)を取得している場合には加点要素となります。また検証報告書の提出も求められ、そこに検証範囲や基準、意見などが明記されている必要があります。要するに、独立性・専門性を備えた機関による国際標準にもとづく第三者検証こそがCDP上有効と認められる保証であり、不十分な形式のもの(例えば社内監査のみの「内部検証」や、正式発行前のドラフト保証書など)は認められません。
検証・保証プロセスの概要
第三者によるGHG排出量の検証プロセスは、一般に次のようなステップで進行します。
検証計画の立案
企業と検証機関が協議し、検証の範囲(対象とするスコープや年度)、基準、保証レベル、スケジュールを決定し、組織境界(報告対象となる事業範囲)や算定方法(GHGプロトコルに準拠していることが前提)の確認も行われます。
予備分析と資料要求
検証人は事前に企業から排出原単位や活動量データ、算定計算シート、過去の報告書など関連資料の提供を受けます。これらを分析し、データの一貫性や抜け漏れがないかを予備評価します。また必要に応じて計算方法や前提の合理性をチェックし、リスクの高い領域(エラーや不確実性が生じやすい箇所)を特定します。
オンサイト/オフサイトでの検証作業
検証人は企業の担当者とのインタビューや現地訪問(必要に応じて)を行い、GHGデータの裏付けとなる証拠をサンプリングして確認します。例えば、エネルギー使用量については電力会社の請求書や燃料購買記録、工場のメーター記録を抽出し、報告値と突合せます。また排出係数が適切に適用されているか、集計にミスがないか検算します。社内のデータ管理プロセスや内部レビュー状況についてもヒアリングし、データの信頼性を評価します。
差異の是正と最終評価
検証過程で報告値と証拠との間に有意な差異や誤りが見つかった場合、企業に対して指摘し修正を促します。企業側がデータを修正または追加説明を行った後、検証人はそれを反映して再評価します。最終的に残存する不確実性が許容範囲内か(保証レベルに照らして重大な虚偽表示がないか)判断します。
検証書(保証ステートメント)の発行
検証人は所定の書式に従い検証結果をまとめた報告書を発行します。報告書には対象とした排出量(Scope1,2,3の範囲)、適用基準、保証レベル、検証意見(結論)などが記載されます。この検証書が第三者の「お墨付き」として公表され、必要に応じCDP回答にも添付されます。GHG検証の厳格なプロセスを経て発行された保証声明は、排出量インベントリがGHGプロトコルなどのガイドラインに従い正確かつ信頼性高く算出されていることを示す外部意見となり、企業の開示情報に対する信頼を高める役割を果たします。
4. CDP評価基準における第三者保証とスコアへの影響
第三者保証の有無や範囲は、CDPスコアに直接的な影響を及ぼします。まず、CDP質問書内の該当設問(気候変動: C10.1 など)において「自社のGHG排出量が第三者によって検証されているか」を回答する箇所があり、ここで「はい(実施済み)」と回答し検証の詳細を報告するとポイントが付与されます。一方、「いいえ(未実施)」の場合、その後の詳細設問自体が表示されず得点機会を失います。またCDPのスコアリングでは、排出量の第三者検証は独立の評価カテゴリとして扱われており、リーダーシップスコアの一定割合を占めます。一般業種の例では、リーダーシップ項目点数の約一部が「Verification (incl. Emissions)」すなわち排出量検証に割り当てられているとされ、第三者検証を受けていない場合、その分のリーダーシップ点を獲得できず大きな減点要因となります。さらにスコア帯の上限を左右する要因でもあります。前述した必須要件のうち、排出量の第三者検証はリーダーシップ必須要件に含まれるため、これを満たしていない企業はたとえ他の設問で高得点でもスコアがB止まり(マネジメントレベル止まり)となり、A-以上には到達しません。
保証対象範囲
実際の基準として、CDPではScope1および2排出量の100%が第三者検証されていることがリーダーシップレベルの加点条件となっており、さらにScope3排出量も合計の70%以上が検証済みである場合にScope3についてリーダーシップ加点が与えられます。またスコアA(Aリスト)を得るためには、「Scope1・2が100%第三者保証済み」で「主要なScope3カテゴリで70%以上の排出量が第三者保証されている」ことが必要条件とされており、これらを満たさなければA評価にはなり得ません。CDPの公式FAQでも「気候変動Scope1・2排出量のリーダーシップポイント獲得には100%の検証が必要であり、Scope3についても70%以上の検証が必要。加えてScope1・2が100%かつ少なくとも一つのScope3カテゴリで70%以上検証されて初めてAスコアの資格を得る」と明言されています。このように、第三者保証の有無と範囲はCDP評価において決定的に重要であり、特に最高評価を狙う上では欠かせない要件となります。以上より、第三者保証はCDPスコア向上におけるキー・ドライバーの一つです。
5. まとめ
CDP質問書への回答作成にあたっては、単なるフォーム入力ではなく戦略的な情報開示の場と捉え、企業の気候変動対応の成熟度を的確に示すことが重要です。本稿で述べたように、STAR話法による論理的な記述構成、自社固有のデータと事例に基づく具体的な説明、各スコア帯の必須要件を踏まえた包括的な対応策の提示、そして継続的な改善の姿勢を示すことが高スコア獲得のポイントになります。また、第三者保証の活用によって開示情報の信頼性を高めることは、CDP評価におけるリーダーシップ水準の達成に不可欠です。CDP公式情報でも強調されているように、正確で検証済みのデータ開示は環境経営の「透明性と信頼性」を示すベストプラクティスであり、ひいては投資家や取引先からの評価向上にもつながります。各企業は本稿で整理したテクニックや知見を参考に、自社の気候変動対応状況を余すところなく訴求し、CDPスコアの向上と持続的なレピュテーション強化に結び付けていただきたい。