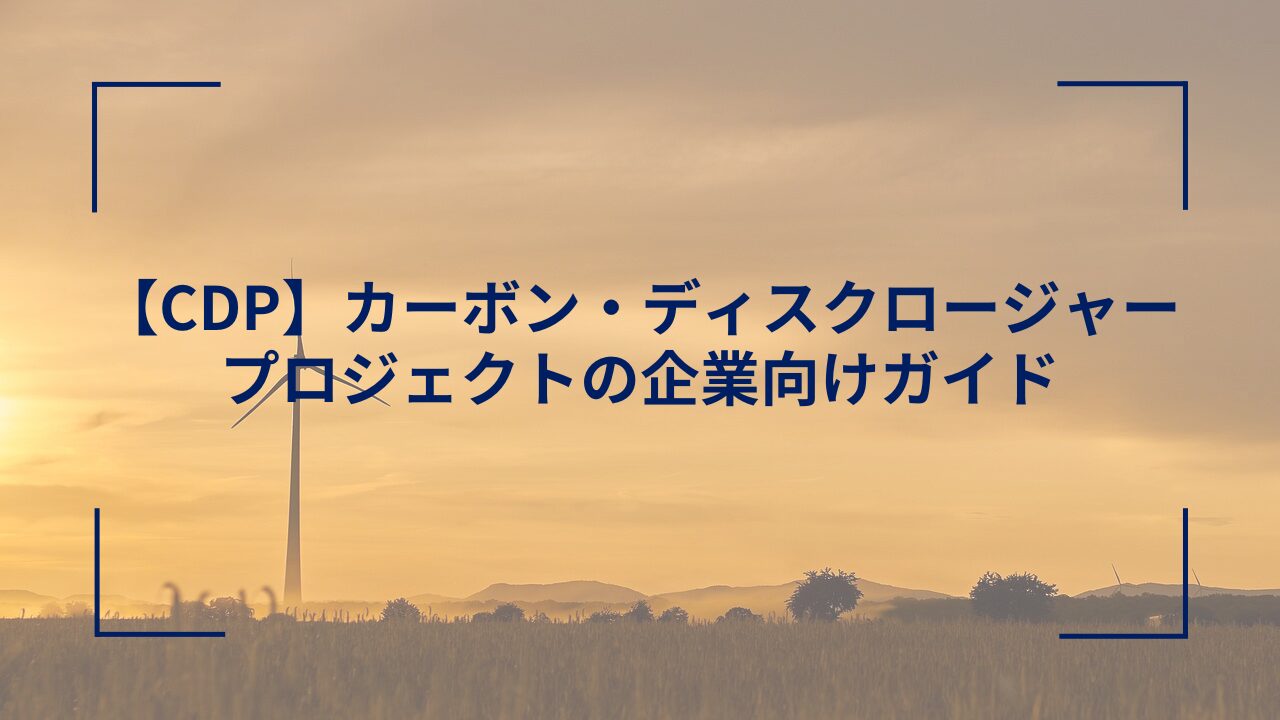CDP(カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト)は、気候変動・水セキュリティ・森林の3分野における企業の環境情報開示を促進する国際的な非営利団体です。CDPへの対応は、ESG投資へのアクセス向上、リスク管理の高度化、企業ブランドの強化といったメリットがあり、企業価値向上にもつながります。CDPスコアは8段階で評価され、投資家や取引先からの信頼獲得に影響を与える重要な指標です。高評価を得るには、詳細で正確な情報開示、ガバナンス体制の整備、定量的目標の設定、継続的な改善と業界への貢献が必要です。本記事ではCDPスコアを上げるための具体的な戦略について解説します。


1. CDPの概要と企業における意義
CDP(Carbon Disclosure Project)は、2000年にイギリスで設立された国際的な非営利環境NGOです。世界中の企業や自治体に対し、温室効果ガス排出量や気候変動対策、水資源管理、森林資源利用などに関する情報開示を毎年求め、それらの回答を分析・評価して報告書を公表しています。CDPは現在、気候変動、森林(フォレスト)、水セキュリティという3つの分野で質問書を展開し、企業の環境への取り組み状況を調査しています。この情報開示の枠組みは、ESG(環境・社会・ガバナンス)における「環境」分野のグローバルスタンダードとなっており、CDPを通じて集められたデータは世界中の投資家や企業、政策立案者の意思決定に大きな影響を与えています。
意義
実際、CDPのスコア(評価結果)は機関投資家や金融機関にとって投資先選定の重要な指標の一つとなっており、高スコアかどうかが企業価値にも大きく影響します。CDPの活動は、莫大な資産を運用するグローバル投資家の支持を受けています。例えば2024年時点で、CDPは運用資産総額136兆米ドルを超える740以上の金融機関を代表して情報開示を促す取組みを行っています。こうした強力な後ろ盾の下、CDPは年々対象企業を拡大しており、情報開示要請(署名投資家からの依頼)を受ける企業数も増加しています。日本でも2005年に活動を開始し、2022年には東京証券取引所プライム市場上場企業の全社(1,841社)に対してCDP質問書への回答が要請されました。
影響
その結果、世界全体では2023年に過去最多となる約23,000社(日本企業約2,000社を含む)がCDPを通じて環境情報を開示し、期限内に回答提出した企業にはすべてスコアが付与されています。CDPの付与するスコアはCDP公式サイトや年次レポートで公表されるだけでなく、金融情報端末(QUICK、Bloomberg)やGoogleファイナンス、ドイツ証券取引所などでも確認でき、機関投資家にも広く共有されています。このように、CDPは企業の環境情報をグローバルな投資コミュニティと結び付け、企業に透明性と行動を促すプラットフォームとしての意義を持っています

2. 企業がCDPに対応することで得られるメリット
企業がCDPの質問書に回答し、情報開示を行うことには多くのメリットがあります。主なメリットとして以下の3点が挙げられます。
ESG投資へのアクセス向上
CDPスコアは投資家が企業を評価する重要な基準の一つとなっており、環境課題への取組みが点数として「見える化」されます。高いスコアを獲得すれば、気候変動や環境対応に積極的な企業として投資家から高く評価され、結果としてESG投資やグリーンファイナンスを呼び込みやすくなります。
リスク管理と戦略立案への活用
CDPの質問項目はTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の提言と整合しており、特に気候変動分野の質問書はTCFDの枠組みに沿った内容になっています。CDPに回答するプロセスを通じて、自社の温室効果ガス排出量や気候変動・水資源・森林に関わるリスクと機会を体系的に把握することができます。それにより、長期的な環境リスクへの適応戦略や事業計画の見直しなど、経営戦略の策定に役立てることができます。実際、CDPへの回答内容はそのままTCFD報告書の作成や社内のリスクマネジメント強化に応用できるとの指摘もあります。
企業ブランドとステークホルダー評価の向上
CDPで高得点を得ることは、企業が環境課題に真剣に取り組んでいる証となります。これは対外的な企業イメージ向上につながり、環境意識の高い企業として顧客や取引先、地域社会からの信頼を得やすくなります。特に近年は消費者の環境意識も高まっているため、CDPスコアを通じて「環境に配慮した企業」としてブランディングできる意義は大きいと言えます。
もっとも、CDPに回答するには相応のコストや労力も伴います(例えば回答には一定の事務手数料や社内リソース投入が必要です)。しかしながら、グローバルに情報開示の重要性が高まる中、これらのデメリットを踏まえても長期的視点で環境情報開示に取り組むことが企業価値向上に資すると考えられます。実際、CDPへの回答をきっかけに社内のデータ管理プロセスが改善されたり、利害関係者(投資家・顧客・従業員等)からの信頼向上につながったケースも報告されています。CDPは単なる評価制度ではなく、企業の環境経営を後押しする有益なフレームワークと位置付けることができます。
3. CDPのスコアリングシステムとその影響
CDPでは、提出された質問書の回答内容に基づき、各企業に対して評価スコアを付与します。そのスコアリングシステムは8段階(A、A-、B、B-、C、C-、D、D-)で構成されており、企業の環境課題への取り組み成熟度を段階的に評価するものです。最も高い評価は「リーダーシップ」レベル(AおよびA-)で、環境リスクの解決に向けて先進的な施策を講じ、自発的かつ包括的に行動している企業が該当します。次いで「マネジメント」レベル(BおよびB-)は、自社の環境リスクや影響を十分に把握し、管理・対策に取り組んでいる企業、「認識」レベル(CおよびC-)は環境上の課題を認識してはいるものの対応が緒についた段階の企業、「情報開示」レベル(DおよびD-)は取り組みは限定的でもまずは情報開示を行っている企業が該当します。なお、質問書に回答を提出しなかった企業は「F(未回答)」という扱いになり評価対象外となります。
客観的指標
このCDPスコアは、金融機関や取引先企業、消費者など幅広いステークホルダーが企業の環境対応度を評価するための指標の一つとして利用されています。特に機関投資家はポートフォリオ企業のCDPスコアに注目しており、スコアが高い企業ほど「環境リスクへの対応力が高い=長期的に持続可能な経営を行っている」と判断されやすくなります。その結果、CDPで高評価を得ることは資金調達面でもプラスに作用し、低評価の場合にはESG投資から外されるリスクもあります。また企業間でも、サプライチェーンを通じた取引先企業からの要求としてCDPスコアが参照されるケースが増えています。例えば大手メーカーが調達先サプライヤーに対しCDP質問書への回答を求め、その結果(スコア)を考慮して調達方針を決めるといった動きも出てきています。
競争力
こうした背景から、CDPスコアは企業の環境経営レベルを示す客観指標として年々重みを増しており、企業価値や競争力にも影響を及ぼす重要な要素となっています。CDPはスコアリングにあたってその基準や方法論の透明性・公平性を重視しています。評価基準(スコアリング基準)はオンラインで公開されており、第三者が統一基準に従って採点し、CDP内の専門チームが品質保証を行っています。評価項目としては、回答内容の詳述の度合い(開示情報の網羅性と詳細さ)、自社の環境課題に対する認識の深さ、課題に対する管理体制・対策(ガバナンスやリスクマネジメント)の有無と充実度、そしてそれらを通じた環境パフォーマンスの進捗(温室効果ガス排出削減の実績や目標達成状況など)といった観点が総合的に評価されます。このように、スコアは単なる情報開示の有無ではなく、企業の環境スチュワードシップ(環境責任経営)への取り組みの成熟度を示すものとなっています。
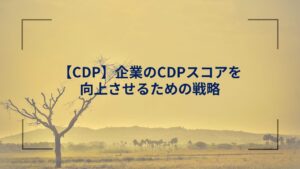
3. CDPがカバーする3つの領域:気候変動・水セキュリティ・森林
CDPの質問書は主に「気候変動」「水セキュリティ」「森林(フォレスト)」の三領域に分かれています。企業は自社の事業内容に応じて該当する質問書に回答することになっており、それぞれの領域で求められる情報や評価の観点が異なります。以下に各領域の概要を説明します。
気候変動
気候変動に関する質問書では、企業の温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1, 2, 3)、温室効果ガス排出削減目標や実績、気候関連のリスクと機会の分析、カーボンプライシング(炭素の価格付け)の活用状況、経営戦略やガバナンス体制への気候変動課題の組み込み状況など、広範な項目について問われます。この質問書は企業が投資に値する気候変動対策を行っているかどうかを示すことを目的としており、前述のとおりTCFDの提言内容とも整合しています。つまり、気候変動分野では排出量データの開示だけでなく、経営層の関与(取締役会による監督など)や戦略的対応(例えば事業ポートフォリオの転換、移行計画)、リスク管理プロセス(シナリオ分析等)、具体的な指標と目標(例:科学的根拠に基づく削減目標=SBTの設定)といった包括的な情報開示が求められます。

水セキュリティ
水セキュリティ質問書では、事業活動が水資源に与える影響や企業が直面する水関連リスクについての情報を収集します。例えば、各事業拠点における年間取水量・排水量、既存または将来的な水不足や水ストレスのリスク評価、洪水や水害による影響、水関連の規制強化による事業への影響、またそれらのリスクに対する対応策などが問われます。水資源管理における目標設定(例:水使用効率の改善目標)や、取水先の流域における利害関係者との協働(例えば地域コミュニティとの水源保全活動)についても開示が求められます。水セキュリティが重視される背景には、近年の気候変動や人口増加に伴って水不足や水災害が深刻化し、企業にとって重大な事業リスクとなっていることがあります。CDPによれば、水関連リスクが企業の財務に与え得る潜在的影響額は全世界で3,360億米ドルにも上り、適切に対応しない場合のコストは対策費用の5倍に達するとされています。こうした理由から、水に関する情報開示とリスク対応は投資家からの要請も年々高まっており、CDPでも気候変動と同等に重視される分野となっています。

森林
森林に関する質問書では、企業の事業活動や調達が森林減少(デフォレステーション)に与える影響、および森林減少が自社の事業に与えるリスクについての情報を開示します。特に、木材・パルプ、パーム油、大豆、畜産(牛肉・革製品)といった森林リスク・コモディティ(森林破壊に繋がりやすい原材料)の生産・使用状況が詳しく問われます。
企業がそれらの原材料を調達・使用する際に、違法伐採や熱帯雨林の開発を招いていないか、持続可能な認証材(例:FSC認証木材、RSPO認証パーム油など)を使用しているか、サプライチェーンのトレーサビリティ(追跡可能性)を確保しているか、そして「ゼロ・デフォレステーション(森林破壊ゼロ)」のコミットメントを掲げているかといった点が評価されます。さらに、森林保全に向けた公的コミットメントへの参加状況(例:企業が世界的な森林保護イニシアチブに賛同しているか)、サプライヤーに対する森林関連方針の浸透・支援、また自社による植林や生態系保全活動などについても報告が求められます。森林は気候変動とも密接に関連するため、森林破壊のリスクは単に原材料調達の問題に留まらず、炭素税や規制強化、企業の評判リスク等、多面的に企業価値へ影響を及ぼし得ます。このためCDP森林プログラムは2013年に設立され、企業のサプライチェーン上の森林破壊リスクを低減し、適切な情報開示を促すことを目的として展開されています。

4. 企業がCDPのスコアを向上させるための具体策
CDPスコアを向上させるには、単に質問書に形式的に回答するだけでは不十分で、質の高い情報開示と実効性のある環境マネジメントの双方で優れた対応が求められます。スコアリングの観点から見た具体的な戦略を、いくつかの重点領域に分けて解説します。
情報開示の充実と正確性
まず基本として、CDP質問書の全ての項目に可能な限り回答し、開示漏れを無くすことが重要です。自社で未実施の事項についても、空欄のまま提出するのではなく「現在未対応である」旨を明記してください。回答が未記入の場合はスコア上「無回答」と扱われ減点対象になりますが、未実施であることを明示すれば最低限のスコアは付与され、空欄よりは評価を確保できます。また、定量データ(排出量や取水量など)はできるだけ網羅的に報告し、第三者機関による検証を受けている場合はその旨を示すことで信頼性を高めることができます。例えば温室効果ガス排出量のデータについては、ISO 14064や保証の取得状況を開示し、検証済みであることを示すと評価につながります。次に、自由記述欄の活用もスコア向上の鍵となります。CDPでは多くの設問で選択肢による回答に加えて自由記述による説明が求められますが、この自由記述部分で具体的かつ説得力のある情報を提供することで、高評価につなげることができます。
STAR話法
効果的な記述方法として、STAR法(Situation, Task, Action, Resultの頭文字)を用いる手法があります。これは例えば「状況:どのような環境課題や事業上のリスクが存在したか」「課題:それに対して何を目標・課題と設定したか」「行動:具体的にどのような対策を講じたか」「結果:その結果どのような成果や改善が得られたか」を順序立てて説明するものです。STAR法に沿って記述することで、背景から施策、成果までを包括的に伝えられるため、回答に具体性と一貫性が生まれ評価につながりやすくなります。ただし、具体的に書くことに加えてデータの正確性や裏付けも重要です。記載した施策の根拠や意思決定に至った理由について、可能な限り定量的な証拠(例えば「ある工場で水リスク対策が必要と判断したのは、その地域の年間降水量が直近10年で20%減少していたため」等)を示すよう心がけましょう。このように、「何をしたか」だけでなく「なぜそれをしたか」「それによって何が起きたか」を数字や事例で示すことが評価アップのポイントです。
環境リスクの認識とガバナンス
CDPの評価体系では、企業が自社の環境リスクと影響をどれだけ正確に認識しているかが問われます。スコア向上には、まず自社にとって重要な環境課題を特定し、そのリスク評価を網羅的に行うことが必要です。具体的には、気候変動に関する物理的・移行リスク、水不足や水害リスク、サプライチェーン上の森林破壊リスクなどを洗い出し、発生可能性と影響度を評価します。その際、シナリオ分析を活用するとより高度なリスク認識を示せます。例えば気候変動ではIPCCの気温上昇シナリオに沿って2050年頃までの事業影響を分析したり、水資源では将来の需要増加や降水パターン変化による各拠点の水ストレスを評価する、といった手法です。実際、CDPで最高評価を得るような先進企業は、気候・水・森林の各分野で入念なシナリオ分析を行い、長期視点でリスクと向き合っています。そうした分析結果やリスクマップを回答に盛り込むことで、企業のリスク認識の深さを示すことができます。さらに、認識したリスクを経営に組み込むガバナンス体制の整備も高スコアには不可欠です。
環境リスクの認識とガバナンスの具体例
具体的には、取締役会や経営委員会レベルで気候変動・水資源・森林など環境課題を定期的に審議する仕組みや、環境担当の役員ポストの設置、社内横断のサステナビリティ委員会の運営などが該当します。CDP質問書でも、気候変動や水リスクについて経営陣に報告する頻度や、役員報酬への環境KPI組み込みの有無などが問われます。これらに「はい」と答えられるよう、社内体制を整備しその内容を詳細に説明することが望まれます。例えば「取締役会において四半期に一度TCFD報告に基づく気候関連リスクのレビューを行っている」などの具体例を示すと良いでしょう。単に方針があると述べるだけでなく、経営陣がどのように環境課題を監督・指揮しているかを具体的に示すことで、スコアリング上もリーダーシップの証左とみなされます。
戦略的対応と目標設定
環境リスクに対処するための戦略と実行計画を持っていることも、高い評価を得るための重要な要素です。単にリスクを認識しているだけでなく、それに対してどのような戦略目標を掲げ、具体的な行動を起こしているかが問われます。まず定量的な目標設定は欠かせません。気候変動分野であれば、温室効果ガス排出削減目標を中長期で設定し、その目標が科学的根拠に整合していること(例えばSBTiによる1.5℃目標の認定取得など)を示すことが重要です。実際、日本企業でも多くが「2050年ネットゼロ宣言」を行い、2030年前後の中期目標についてSBT認定を取得する動きが広がっています。CDPではこうした目標の有無や進捗報告が重視され、SBT認定済みであれば加点要素となります(※CDP気候変動スコアリング基準ではSBT認定の有無が評価に組み込まれています)。水や森林についても、自社の取組みに即したKPIを設定しましょう。
戦略的対応と目標設定の具体例
例えば「2030年までに製品あたりの取水量を2015年比で〇%削減」「2025年までに主要な農産品原料についてゼロ・デフォレステーションを達成」といった具体的な目標を掲げ、その達成状況を測定・開示することが求められます。次に実行計画と施策です。目標を達成するためにどのような戦略を採用し、施策を講じているかを示します。例えば気候変動対策では、再生可能エネルギーへの転換(RE100への加盟や自社施設の再エネ電力100%化)、省エネルギー投資、新技術の導入(製造プロセスの電化や水素利用など)、自社製品・サービスの低炭素化(ZEH住宅やEV製造など)といった取組みが考えられます。一例を挙げれば、積水ハウスは自社が建設する住宅のネットゼロエネルギーハウス(ZEH)化を強力に推進し、2022年時点で戸建住宅の93%をZEH化、2023年以降は分譲マンションも全住戸ZEH仕様とするなど、事業戦略そのものを脱炭素に結び付けています。
他社事例
このような積極的な戦略はCDPでも高く評価され、積水ハウスは住宅業界で初めて気候変動・森林・水の全分野でAリスト(トリプルA)に選定される成果を上げました。他にも、資生堂がバリューチェーン全体でCO₂削減のSBT目標を設定し、2050年ネットゼロを目指すことや、RE100に加盟して国内外の事業所で再生可能エネルギー電力への切替を進めている点、さらにサプライチェーンも含めた持続可能な原材料調達に取り組んでいる点などは、CDPの気候変動・森林分野で高評価(ダブルA)を受ける要因となりました。
森林分野では、例えば花王がパーム油調達に関してトレーサビリティや生産者支援の取組みを徹底しています。同社はパーム油のサプライチェーン情報を可視化する「パームダッシュボード」を公開し、インドネシアの小規模農園からの持続可能なパーム油クレジットの購入量なども開示しています。こうした透明性と具体的行動は、CDPフォレストでの最高評価につながっています。以上のように、自社の環境目標を明確に定め、全社的な戦略の中で具体的な対策を講じ、その進捗をモニタリングしていることを示すことが、CDPスコア向上の肝となります。計画倒れになっていないか、実際のデータ(例えば排出量や水使用量)が改善傾向にあるか、といった成果も併せて示すことで、回答に説得力が増し高スコアにつながるでしょう。

5. 継続的改善と業界リーダーシップの発揮
CDPでトップクラスの評価(AやA-)を得る企業は、単発の対応に留まらず、継続的な改善プロセスを持ち、業界や社会に対してリーダーシップを発揮している点が特徴です。CDP自身も、Aリスト企業について「環境への影響に関して最も正確な情報を有し、それを緩和するための気候及びネイチャーポジティブな行動を最も適切に実行できる企業」であると評価しています。言い換えれば、最高評価を得る企業とは「自社の環境フットプリントを的確に把握し、明確な根拠に基づく野心的な目標を掲げ、計画的な行動で顕著な成果を上げ、それらを外部に積極的に開示している企業」と言えます。その境地に近づくためには、PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)の確立が重要です。環境目標と計画を策定(Plan)し、対策を実行(Do)したら、定期的にデータを収集してモニタリングし(Check)、目標進捗や効果を評価して次の対策に反映させる(Act)という流れを継続します。このサイクルを年次のCDP回答プロセスと連動させることで、毎年回答内容をアップデートしつつスコアの着実な向上を図ることができます。
段階的向上
初年度は情報開示レベル(D相当)でも、翌年には不足していたデータを補完し認識レベル(C相当)へ、さらに2~3年後には新たな方針策定や投資を経てマネジメントレベル(B相当)へ、と段階的にステップアップしていく企業も多く見られます。また、自社内だけでなくバリューチェーン全体や業界横断の取り組みへの貢献も評価されます。CDP質問書でも、サプライヤーや顧客との協働(Scope3削減の取組みや、取引先への情報開示働きかけ等)について尋ねる項目があります。自社がリードとなってサプライチェーン全体の環境負荷削減を推進している場合は、それを具体的に記載しましょう。
自社の枠を超えた前向きな関与
例えば「主要サプライヤー100社に対しCDPへの回答を要請し、低炭素化の支援プログラムを実施」といった取り組みは先進事例として加点材料になります。同様に、気候変動や水・森林の分野での国際イニシアチブへの参画(例:RE100、SCI(サプライチェーン・イニシアチブ)、TNFDパイロットなど)もリーダーシップの証となり得ます。積水ハウスの例では、自社の取り組みだけでなくグローバルABC(建築分野の脱炭素化アライアンス)に参加し業界全体の気候アクションに貢献している点も評価ポイントとなりました。このように、自社の枠を超えた前向きな関与を示すことができれば、CDPスコアで最高位を狙う土壌が整っていると言えます。最後に、高スコア企業の事例から成功要因を学ぶことも有益です。先述の花王は、2040年カーボンゼロ・2050年カーボンネガティブという大胆なビジョンを掲げつつ、工場でのバイオマス燃料活用やプラスチック使用量削減を実現し、さらに森林・水分野でもサプライチェーンの具体策(持続可能なパーム油調達支援や節水型製品の開発)を展開することで4年連続のトリプルAを達成しました。トリプルAは世界でも2023年時点で10社しか存在しない大変難易度の高い評価ですが、裏を返せばこれらの企業は環境経営のあらゆる面で卓越しているわけです。彼らに共通するのは、「経営トップのコミットメントの強さ」「科学的根拠に裏付けられた野心的目標」「全社的な統合戦略」「ステークホルダーとの協働」「透明性の高い開示と検証」という点です。それらが総合的に評価されて初めてAという評価が与えられます。
CDPスコアの向上は一朝一夕には成し遂げられませんが、上記のような戦略的アプローチで取り組むことで、着実に評価を高めていくことが可能です。CDPのスコアリング基準自体、企業が環境上のベストプラクティスへと到達するための「羅針盤」として設計されています。したがって、単にスコアを上げること自体が目的ではなく、自社のサステナビリティ経営を深化させるプロセスと捉え、前向きに活用するとよいでしょう。その結果としてスコアが向上し、投資家や社会からの評価が高まるという好循環を生み出すことが、このガイドの究極的な目標と言えます。
引用
CDP公式 https://cdp.net/ja
CDP 気候変動レポート 2023: 日本版
https://cdn.cdp.net/cdpproduction/comfy/cms/files/files/000/009/502/original/CDP2023_Japan_Report_Climate_0319.pdf
CDP 気候変動質問書スコアリング基準 2023年版
https://www.koei-j.co.jp/cdp-2022/