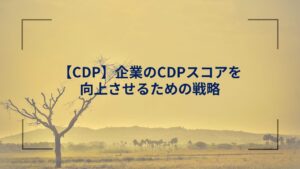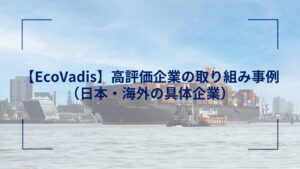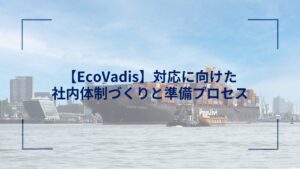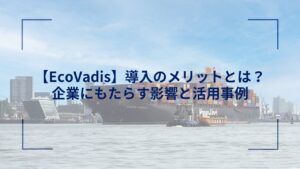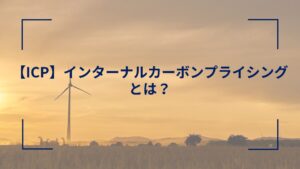CDPフォレストプログラムは、企業がサプライチェーン上で関わる森林破壊リスクにどう向き合っているかを可視化し、持続可能な調達を促す仕組みです。木材やパーム油などの原材料が森林減少に影響することが多く、企業はその対応を怠るとブランド毀損や市場からの排除といったリスクに直面します。一方で、積極的な取り組みは信頼や競争力の向上にもつながります。本記事では、そんなCDPフォレストの背景と企業に求められる対応について解説します。
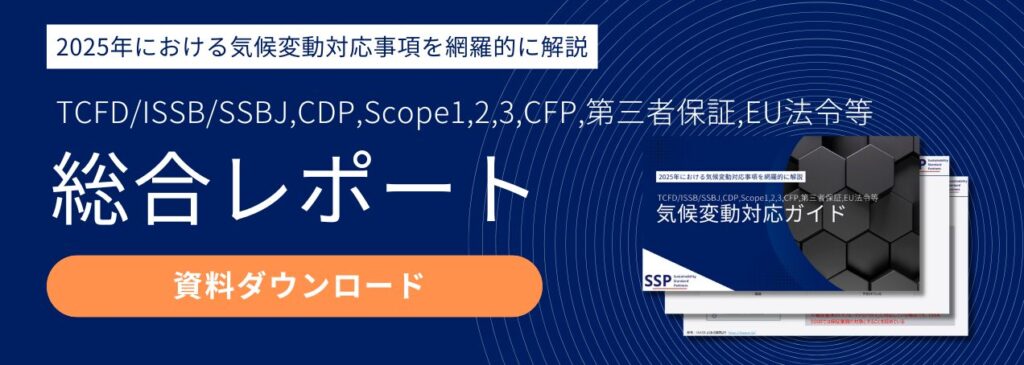

1. 森林テーマでCDP情報開示が求められる背景
森林(フォレスト)は気候変動や生物多様性と並び、地球環境における重要課題の一つです。企業活動は直接・間接に森林に影響を与えることが多く、また森林破壊の進行は企業のサプライチェーンに逆影響を及ぼす可能性があります。こうした背景から、CDPは2013年にCDPフォレストプログラムを立ち上げ、企業の森林関連情報の開示と評価を行っています。CDPフォレストプログラムの焦点は、企業が扱う森林リスク・コモディティ(森林破壊に繋がりやすい主要農産品・資源)の生産・調達による森林への影響です。具体的には、以下の4大コモディティが重視されています
木材・パルプ製品
木材の伐採や紙パルプ生産は、違法伐採や皆伐による森林減少を引き起こすリスクがあります。紙・パルプ、建材、家具などの業界が該当します。
パーム油
パーム油プランテーション開発のために東南アジアなどで熱帯雨林が大規模に転換されています。食品・日用品メーカーが主な消費者です。
大豆
南米などで飼料用大豆畑の拡大が森林やサバンナの減少を招いています。畜産向け飼料・食品産業に関連。
畜牛由来製品
牛肉生産や牛革用の牧畜地拡大が、アマゾン等の森林破壊要因となっています。食品・アパレル(革)産業が該当します。加えて、ゴム、カカオ、コーヒーなど地域によっては森林リスクとなる品目もあります。CDPフォレストは、これらコモディティを扱う企業に対し、サプライチェーン上の森林破壊リスクとその管理状況について情報開示を求めています。
森林破壊における懸念
この情報開示が求められる背景には、ビジネスと森林破壊の関係に対する懸念が高まったことがあります。毎年世界で1,000万ヘクタール以上の森林が減少しており、その主要因の半分以上が農地拡大(商業目的の農林業)だと報告されています。つまり企業活動が森林喪失の一因であり、企業に責任ある調達を促す声が強まっています。とりわけ消費財メーカーや食品チェーンは消費者・NGOからの監視が厳しく、「サプライチェーン上の森林破壊を根絶せよ」との社会的プレッシャーが高まっています。また、投資家も森林問題に注目し始めました。
規制面
熱帯林減少は世界のGHG排出の約10-15%を占めるとされ、気候変動対策として森林保全が不可欠だからです。森林関連リスクを無視する企業は、将来的に規制や市場から排除されるリスクがあるとの認識が広がっています。実際、EUは2023年にEUDRを制定し、森林破壊に関与した産品の輸入を禁止する方向に動いています。このように規制面でも大きな変化が起きつつあります。CDPフォレストプログラムは、企業が自主的に自らのサプライチェーンを見直し、森林への影響を削減することを促す目的で設立されました。情報開示を通じて問題点を浮き彫りにし、投資家やバイヤーが企業を評価・比較できる環境を整える狙いがあります。2013年の立ち上げ以降、年々対象企業が拡大し、2023年には全世界で約1,000社以上がCDPフォレスト質問書を受領し、そのうち271社が日本企業だったと報告されています。回答率はまだ約40%程度ですが、今後投資家要請が増えれば回答企業も増加するでしょう。
質問の全体構成
CDPフォレスト質問書の構成は、気候変動版と同様にガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標、サプライチェーンエンゲージメント、生態系保全といった項目からなります。具体的な質問としては、たとえば「自社が使用する森林リスクコモディティとその量」「サプライヤーに森林破壊ゼロを求める方針の有無」「認証製品(例:FSC、RSPO)の使用率」「森林関連リスクの評価方法と直近のリスク事例」「森林保護に関する公的コミットメントへの参加状況(例:ニューヨーク森林宣言)」などが含まれます。要するに、CDPフォレストプログラムは企業のサプライチェーンにおける森林リスクの透明化と低減を目的としており、これに対応することは持続可能な調達・CSR調達を推進することとほぼ同義です。
2. 企業のサプライチェーンにおける森林関連リスク
前節で触れたように、企業のサプライチェーン上には様々な形で森林破壊リスクが潜んでいます。それを整理すると以下のとおりです。
調達リスク
原材料が森林破壊と関係している場合のリスクです。例えば製紙会社が安価な木材チップを調達しようとすると、違法伐採された木材が混入している可能性があります。仮に違法材が混ざれば、その製品は市場(特に欧米)で排除されるリスクがあり、調達継続も困難になります。またパーム油などではサプライチェーンが複雑で、どこかで違法なプランテーション原料が混入しても企業は気づきにくいという問題もあります。その結果、後に問題が発覚すると供給停止や大規模リコールになりかねません。
規制リスク
前述のEUDRのように、違法伐採や森林破壊に関わる産品の流通を禁止・制限する動きが出ています。こうした規制が施行されると、対応できない企業は主要市場でビジネスができなくなる恐れがあります。例えばチョコレート大手はカカオ豆調達で西アフリカの森林減少問題に直面していますが、EU規制に適合するにはトレーサビリティを確立し「森林破壊に関与していないカカオ」である証明が必要です。対応が遅れた企業は市場アクセスを失いかねません。
評判リスク
森林破壊問題は消費者やNGOの関心が非常に高いため、企業ブランドへの影響が大きいです。有名な例として、東南アジアのパーム油プランテーション開発によるオランウータンの生息地破壊が国際問題化し、欧米の消費者がパーム油ボイコット運動を行ったケースがあります。その結果、大手食品・日用品メーカーは一斉に「持続可能なパーム油(RSPO認証品)のみ調達する」と宣言せざるを得なくなりました。つまり不買運動やメディア報道などで企業イメージが悪化し、市場シェアを失うリスクです。同様にアマゾン森林破壊が報道されれば、そこから牛肉を調達しているハンバーガーチェーンが批判に晒されるかもしれません。このようにサプライチェーン上の森林問題は企業のブランド価値に直結し得ます。
気候変動リスクの増幅
森林は巨大な炭素貯蔵庫であり、森林破壊は温室効果ガス排出を加速させます。そのため森林破壊を放置すると気候変動がさらに進行し、結果的に企業自身の気候リスクも高まります。例えば農業企業にとって気候変動で天候不順が増えれば収穫量が落ちるなど、巡り巡って自らに返ってきます。CDPフォレストプログラムは気候変動対策の一環とも位置付けられており、森林リスク管理は気候リスク管理でもあるのです。
以上のようなリスクを踏まえ、企業はサプライチェーン上の森林リスクを特定・評価し、その影響を低減するための対策を講じる必要があります。CDPの質問書でも「ビジネスの森林破壊リスクを低減し…企業が適切に情報開示に応えることを目的としている」とあるように、まずは自社がどのコモディティでどの程度森林リスクを抱えているかを把握することが肝心です。
ダブルマテリアリティ
CDPでは企業に対し、「自社の事業活動が森林に与える影響」だけでなく「森林減少が自社のビジネスに与える影響」についても分析するよう求めています。例えば違法伐採木材に依存していると将来的に調達不能になるリスク、サプライヤーの森林火災で原料価格高騰のリスク、逆に自社が森林再生プロジェクトに投資することでカーボンクレジットを得る機会、などです。この双方向の視点で森林リスクと機会を洗い出し、重要性を評価することがCDP回答の基礎となります。
日本企業では、紙パルプや食料品、商社、小売などがCDPフォレストの主な対象です。2023年、日本では271社に質問書が送付され、105社(約39%)が回答しました。回答率は気候変動の約55%に比べると低めですが、今後の規制強化を見据え対応を始める企業が増えています。たとえば花王や資生堂は、パーム油や紙容器の持続可能調達方針を打ち出し、進捗をCDP等で開示しています。また積水ハウスは建築資材の木材調達ガイドラインを制定し、違法伐採木材の排除やFSC認証材の使用拡大を進めてきました。これらは、森林リスクを認識した上で対策を講じている例です。次の節では、こうした企業の取り組みも参照しながら、森林リスクに対する具体的な対応策を解説します。
3. 企業の持続可能な森林管理の取り組み
サプライチェーンにおける森林リスクを低減するため、企業は持続可能な森林管理(サステナブル森林調達)の仕組みを構築していく必要があります。CDPフォレスト質問書で評価される主な取り組みをいくつか挙げてみます。
森林方針とゼロ・デフォレステーションコミットメント
まず基本となるのは、企業としての森林調達方針を明確化することです。具体的には「当社はサプライチェーン上のいかなる段階でも違法な森林伐採や持続不可能な森林開発に加担しない」といったポリシーを定め、社内外に宣言します。多くのグローバル企業が、ゼロ・デフォレステーション(No Deforestation)やNo DPE(No Deforestation, No Peat, No Exploitation)といったコミットメントを表明しています。これは「当社の調達活動によって熱帯林の減少も泥炭地開発も人権侵害も引き起こさない」という約束です。
CDPでも、そうしたコミットメントの有無が問われます。企業はこのポリシーをサプライヤー行動基準に組み込んだり、取引契約の条件に入れることで実効性を高めます。積水ハウスの「木材調達ガイドライン」は2007年に制定され、日本産・輸入材問わず合法性と持続可能性を確認する手続きを定めています。その中では違法伐採木材の排除はもちろん、生物多様性保全にも配慮するよう求めています。こうした明文化された方針があるかどうかは、企業の姿勢を測る指標となります。さらに、国際的イニシアチブへの賛同も効果的です。例えば「森林破壊ゼロ企業連合」や「ニューヨーク森林宣言」に署名する、Consumer Goods Forumの目標を支持するといった行動です。これによって社外からの評価も向上し、CDP回答において「公的コミットメント参加」として記載できます。
https://www.sekisuihouse.co.jp/kodate/spec/environment/wood-procurement/
トレーサビリティ
方針を立てても、それが守られているか確認できなければ意味がありません。そのための鍵がサプライチェーンのトレーサビリティです。CDP質問書でも「製品が認証制度に準拠しているか、製品のトレーサビリティが可能か」といった点が評価されます。具体的には、調達している森林リスクコモディティについて、その起源(原料産地)を特定することが重要です。例えば製紙会社なら木材チップがどの国・どの森林から来たか把握する、食品メーカーなら購入しているパーム油がどの製油所・農園由来か突き止めるといったことです。これにはサプライヤーからの情報開示や第三者検証が必要になります。多くの企業が活用している手段の一つが認証取得です。木材であればFSC(森林管理協議会)やPEFC認証、パーム油であればRSPO認証、大豆ならRTRS認証など、独立した認証機関の承認を受けた原料のみを使うことで、ある程度持続可能性を担保できます。CDPでは製品中の認証材使用率などを報告するよう求められます。例えば「当社のパーム油調達量のうち、RSPO認証油が80%を占める」等です。認証品使用率が高いほど評価は向上します。
サプライヤーエンゲージメント
加えて、サプライヤーとのエンゲージメントも不可欠です。サプライヤーに対して森林方針を通知し、遵守を誓約させる。さらにサプライヤー自身にもCDP等で情報開示させたり、定期的に監査することが有効です。先進企業は主要サプライヤーを現地訪問し、森林保護の取組み状況をチェックしています。また、必要に応じて能力開発支援(例えば小規模農家に持続可能農法を指導し、生産性を上げつつ森林へのプレッシャーを減らすなど)を行う例もあります。花王は、パーム油のサプライチェーンについてオンライン上で公開する「パームダッシュボード」を構築し、トレーサビリティ確保に努めています。ここでは自社が購入するパーム油のミル(搾油工場)一覧や、小規模農園から購入したクレジット量などを公開しています。またインドネシアの農家支援プログラムにも参画し、持続可能な農園経営をバックアップしています。このように透明性を高め、サプライヤーと協働する姿勢はCDPでも高く評価されます。
認証制度と社内監査
前述の認証取得は、持続可能な調達を保証する手段ですが、企業自身の努力も欠かせません。社内監査によってサプライチェーンを定期的に点検し、問題があれば改善するPDCAを回します。例えば、木材製品の商社であれば、社員が原産国に出向いて製材所や植林地を視察し、現地の認証状況や違法伐採の有無を確認する、といった監査プロセスを設けます。また疑わしいサプライヤーとは取引停止などの対応基準を決めておきます。さらに、生態系保全の取組みも評価軸です。企業によっては調達先の地域で森林再生活動や自然保護プロジェクトに投資するケースがあります。例えばアパレル企業が自ら植林活動を支援し、将来の持続的な木材供給源を育成するなどです。積水ハウスが参加する「5本の木」計画は、生態系に配慮した植栽を推進するプロジェクトで、住宅建設時に在来種の樹木を植えることで都市の生物多様性回復に貢献するものです。これは直接的な森林保護ではありませんが、緑化推進による環境負荷低減策として評価されました。さらに同社は自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)のガイドラインに沿った情報開示も積極的に行っており、自然資本リスクの管理で先進的と見做されています。
開示と利害関係者コミュニケーション
持続可能な森林管理の取り組みは、行うだけでなく積極的に開示・報告することで外部からの評価につながります。CDPフォレストに回答すること自体がその一環ですが、その他にも、
サステナビリティ報告書での開示
調達方針、進捗指標、監査結果、事例などを年次報告します。特に目標達成度合いは重要です(例:「2022年末時点で当社の紙製品のFSC認証率は70%に達し、目標80%に向け順調」)。
利害関係者(ステークホルダー)への説明
NGOや投資家との対話の場を持ち、自社の取組みを説明するとともに意見をフィードバックします。例えば環境NGOが作成する企業の森林対応ランキングに協力し、評価向上を目指すなどです。
問題発生時の透明性
万一サプライチェーンで森林破壊が見つかった場合の対応も計画しておきます。自主的に発表し、是正措置を講じるなど、透明性ある対応が求められます。隠蔽や対応遅れは評判悪化を招くので注意が必要です。
CDPフォレストのスコアで高評価(AまたはA-)を得る企業は、以上のような取組みを体系立てて実施し、公表しています。2023年のCDPフォレストAリストには、日本から花王と資生堂が選ばれました。資生堂はパーム油と紙パルプについて2030年までに100%認証原料化を目指し、2023年時点で既にパーム油は100%RSPO(Book & Claim方式含む)を達成しています。また森林関連のデータ開示も充実させ、初のAリスト入りを果たしました。
https://www.kao.com/jp/newsroom/news/release/2024/20240206-001/
https://corp.shiseido.com/jp/news/detail.html?n=00000000003774
要するに、「方針策定 → トレーサビリティ確保(認証活用) → サプライヤー管理 → 外部連携 → 透明な開示」という一連の流れが持続可能な森林管理の核心です。CDPへの対応を進めることは、この流れを社内に定着させる上でも有用です。評価項目をチェックリスト代わりに活用し、自社の取り組みの抜け漏れを補完していくとよいでしょう。
4. 森林リスクへの対応を競争優位に変える
CDPフォレストプログラムへの対応、および企業の森林リスク対策について見てきました。最後に、その重要性と展望をまとめます。企業にとってサプライチェーン上の森林リスクに対処することは、もはや社会的責任(CSR)の範疇を超え、経営上のリスクマネジメントおよび競争戦略となりつつあります。規制の強化や消費者の意識変化により、持続可能な調達を実践できない企業は市場から淘汰される可能性が高まっているからです。
取引機会の向上
一方で、いち早く森林対応を進めた企業はブランド価値を向上させ、新たな取引機会を獲得しています。例えば、ある繊維メーカーは原料のレーヨン繊維について「古代林木材不使用」「FSC認証調達100%」を実現し、欧米高級アパレルからの受注が増加しました。また、日本の商社も木材調達においてFSC認証材の比率を高めたことで欧州顧客からの信頼を得ています。こうした例は、持続可能性への取り組みが競争優位となりうることを示しています。CDPフォレストスコアで高評価を得ることは、そのまま「当社は森林リスクを適切に管理し、責任ある調達をしている」というお墨付きになります。投資家やビジネスパートナーに対する説得材料となり、ESG投資資金の呼び込みや優良な取引先からの選好につながるでしょう。特に欧州では企業のデューデリジェンス義務化(人権・環境への配慮)が法制化されつつあり、CDPのような第三者評価は取引の前提情報として重要性を増すと考えられます。
自然資本の保全
また、森林対応の強化は気候変動対策や生物多様性保全にも寄与します。カーボンニュートラルを目指す企業にとって、バリューチェーン排出(Scope3)の削減は難題ですが、森林破壊のない原料に切り替えることでScope3の削減に貢献できます。さらに将来的には、自社で保全した森によるカーボンクレジット取得など、新たなビジネスモデルも期待できます。自然資本への投資が価値を生む時代に備え、今から森林との関わりを深めておくことは企業戦略上有益です。無論、持続可能な森林管理は一朝一夕には実現しません。サプライチェーン全体を俯瞰し、多数のステークホルダーと協力しながら進める長期的な取り組みです。しかし、CDPフォレストへの対応を毎年重ね、課題を洗い出して改善策を講じるPDCAを回すことで、確実に前進できます。花王や資生堂、積水ハウスといった先行企業も、長年の取り組みの積み重ねがトリプルAやダブルAという成果につながったのです。
5. まとめ
今後、企業に求められる環境対応は、気候変動からネイチャーポジティブ(自然にプラスの影響を与える)な取り組みへと拡大していくでしょう。森林保全はその中心的課題の一つです。CDPフォレストは、企業が自然と共生する経営への転換を図る上で、有効なガイドラインとなります。これを積極的に活用し、自社のサプライチェーンを持続可能なものへと再構築していくことが、将来の企業価値と競争力を左右すると言っても過言ではありません。企業と森林は、一見離れた存在に思えるかもしれませんが、実は商品を通じて密接につながっています。そのつながりを健全なものに保つことが、企業の責任であり、長期的利益にも適うという認識が必要です。CDPフォレストへの挑戦は、その第一歩として格好の機会です。ぜひ多くの企業がこの取り組みに参加し、森林保全と持続可能な発展の両立に向けた一翼を担っていくことを期待します。
CDP フォレスト レポート 2023: 日本版
https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/009/002/original/CDP_Forests_Japan_2023_0319.pdf