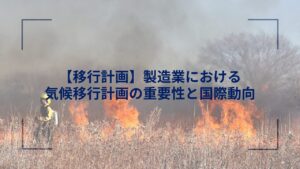2025年3月に公表された「SBTi Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 – Consultation Draft」(以下、本ドラフト)は、気候変動対策に取り組む企業にとって非常に重要なマイルストーンとなる内容を含んでいます。本ドラフトは、従来のVersion 1.2から大幅に改訂され、企業が排出量削減ターゲットを「設定し、実行し、検証し、更新する」までを網羅的に示しています。特に、基準年排出量の第三者保証が義務化される可能性が注目されており、多くの企業が今後の気候戦略を練り直すきっかけとなるでしょう。以下では、各章の要点と今回強調すべきポイントを詳しく解説します。


1. 新ドラフト誕生の背景
近年、地球温暖化の進行が加速しており、パリ協定で掲げられた「産業革命以前比+1.5℃」という目標を達成するための時間的余裕が限られてきました。さらに、欧州を中心に気候関連情報開示が法的に強化されるなど、企業を取り巻くルールもグローバルに厳しくなっています。SBTi(Science Based Targets initiative)はこうした状況を踏まえ、企業の排出削減を継続的・実効的に進めるための新しい枠組みを提示しました。
Version 1.2までのガイダンスは主に「ターゲット設定」に重点が置かれていましたが、Version 2.0では、企業がターゲットを設定した後、いかに達成し、更新し続けるのかをより具体的に示す構成となっています。
2. 新しい「検証モデル」の導入
本ドラフトで示された「検証モデル(Validation Model)」は、企業の脱炭素への取り組みを大きく3つのステージに分けて評価します。これにより、単なる初回の目標設定に終わらず、継続的なモニタリングと改善を組み込んだ仕組みを整備することができます。
エントリーチェック
企業がSBTiにコミットする段階で、経営陣のコミットメントやガバナンス体制、温室効果ガス(GHG)排出量の算定Scopeなど、最低限の要件を満たしているかを確認します。これに合格すると、企業は初回のターゲット設定に進むことが可能となります。
初回バリデーション
エントリーチェック合格後、実際のターゲットをSBTiに提出し、基準年排出量の妥当性や削減目標の科学的妥当性を審査・承認してもらうステップです。Category A(大企業や中堅企業のうち上位所得国で事業を行う企業)は12か月以内、Category B(小規模企業や低・中所得国の中堅企業)は24か月以内にこのプロセスを完了するよう求められます。
更新バリデーション
設定したターゲットの期限(概ね5年間)終了時や大規模な事業変化があった際に、進捗評価を行ったうえで新たなターゲットを設定する段階です。旧ターゲットがどの程度達成されたのかを検証し、その結果を踏まえて次の削減目標を策定・登録します。これにより、企業は継続的に脱炭素の取り組みをPDCAサイクルで回せるようになります。
3. カテゴリー別要件の明確化
本ドラフトでは、企業を「Category A」と「Category B」に区分し、下記のように要件水準を差別化しています。これは企業規模や地域的特性を考慮し、過度な負担を避けつつも、一定の実効性を確保する狙いがあります。
Category A
大企業(大規模上場企業など)
中規模企業のうち上位所得国で営業利益・売上を大きく稼いでいる企業
要件がより厳格(短期的に第三者保証やScope3の包括的計測などを求められる)
Category B
小規模企業(売上・資本規模が小さい事業者)
中規模企業のうち低・中所得国で事業を主としている企業
要件がやや緩やか(短期目標の設定期限や検証プロセスに猶予がある)
4. 第三者保証義務化の可能性
本ドラフトの最大のトピックの一つが、「基準年排出量」への第三者保証の義務化です。特にCategory Aに属する企業は、排出量データの第三者保証を受けることが事実上必須になる可能性が示唆されています。
データの信頼性向上
従来は企業自身の自己申告的な算定が中心でしたが、外部監査法人や公認会計士などの専門家に保証を受けることで、データの整合性・完全性を担保できるようになります。
投資家や規制当局への透明性確保
ESG投資が拡大する中、排出量データの正確性は投資家の意思決定にも大きく影響する要因です。また、欧州を中心に強まる法規制への対応策としても、第三者保証による裏付けは有効です。
内部管理体制の強化
第三者保証を導入するためには、社内で排出量算定のプロセスやデータ管理体制をしっかり構築・文書化し、監査に耐える形に整備する必要があります。企業が脱炭素戦略を本格的に進めるうえでの基盤整備につながります。
保証取得に伴うリスク・課題
ただし、第三者保証には企業にとって以下のような課題も想定されます。
コスト増: 監査法人やコンサルティング会社への支払い費用、内部監査チームの増強など。
データ管理の複雑化: サプライチェーン全体の排出源を正確に把握するには、多種多様な情報を統合・分析する必要がある。
監査Scopeの不確定要素: どの範囲までを保証対象とするのか(Scope1・2だけでなく、Scope3の主要カテゴリを含むか)など、今後さらにガイドラインが具体化される見込み。
5. Scope1,2,3へのアプローチ強化と実務的インパクト
今後は削減についても積極的に考慮される可能性がある。
Scope1・2削減の明確化
Absolute Contraction Approach(ACA)のアップデート
企業の事業拡大・縮小を考慮しつつも、全体として排出量をどれだけ削減できるかを測る手法に、さらなる修正が加えられる見込みです。
再生可能エネルギーの調達要件
従来の場所ベース(location-based)や市場ベース(market-based)の排出係数だけでなく、高品質な電力証書の利用や、時間・空間マッチングを求める動きが検討されています。
Scope3への重点強化
境界設定(Boundary)の再考
Version 1.2では「排出量の67%以上をカバー」などの数値基準が示されていましたが、本ドラフトでは実質的に「最も重要な排出源を優先」して対策を講じるアプローチが注目されています。
トレーサビリティ問題への対応
サプライチェーン全体を直接追跡するのが難しい場合、アクティビティプール(アップストリームの供給地域全体、あるいはエネルギーグリッドなど)を単位として削減を計算する方法が提示されるなど、柔軟性も持たせています。
暫定的に間接的措置を認める方向性
どうしても直接削減が難しい排出源には、ブック&クレーム方式でサステナブル航空燃料(SAF)を調達するなど、特定の方法で間接的に排出を相殺する選択肢を検討する余地が示唆されています。
6. ongoing emissionsへの対処とBeyond Value Chain Mitigation
企業がネットゼロを達成するまでには、排出をゼロにできない「ongoing emissions」が生じます。本ドラフトでは、こうした排出に対して「Beyond Value Chain Mitigation(BVCM)」という枠組みを強化し、企業が自社バリューチェーン外の排出削減プロジェクトへ資金を投じることをより明確に推奨し、認定する仕組みを検討しています。これは、排出削減努力の加速を狙いとした新たなインセンティブであり、長期的には残余排出量(residual emissions)に対するカーボンリムーバルの活用ともリンクしていく可能性が高いとされています。
7. 新たな報告・更新プロセス
今回のドラフトでは、企業が定期的に進捗報告と評価を行うことを「義務」として強調しています。
ターゲット期間終了時(概ね5年)に進捗を評価し、次のターゲットを設定
未達成の場合は、そのギャップを埋める形で新たな削減策や費用配分が求められる
達成した場合も、より高い次元の目標を設定し、排出削減をさらに継続
これにより、企業は「一度認定を受けたら終わり」ではなく、最終的なネットゼロ(2050年またはそれ以前)を視野に入れながら、段階的に目標を引き上げることが求められます。
8. 新ドラフトへの対応:企業が取るべきアクション
新ドラフトでは第三者保証取得、削減対応実行等のリソース配分を決定し、投資計画を見直していく必要があります。
データ管理体制の早期整備
第三者保証を見据えた場合、初期段階から排出量算定のプロセスや証憑資料、システム面をしっかり整備しておく必要があります。特にScope3の大部分を占めるサプライチェーンデータの収集や品質管理がポイントとなるでしょう。
投資計画・リソース配分の見直し
排出削減のための技術導入、再生可能エネルギーへの転換、保証費用などを考慮し、経営計画の中にESG関連コストを組み込むことが重要です。
ステークホルダーとの連携
サプライヤーや顧客など、バリューチェーン全体での温室効果ガス削減を進めるためには、パートナー企業との共同プロジェクトや情報共有を強化する必要があります。特にアクティビティプールを活用した削減策などは、複数社共同の取り組みが前提となるケースも想定されます。
最新情報のフォローとフィードバック
本ドラフトはまだコンサルテーション段階であり、今後さらに内容が見直される可能性があります。企業としては、SBTiの公募意見やパイロットプログラムの動向をウォッチし、可能なら積極的にフィードバックを提供することで、自社実務とのギャップを埋めていくことが期待されます。
9. まとめ
今回の「SBTi Corporate Net-Zero Standard v2.0ドラフト」は、企業がネットゼロ目標を「掲げる」だけでなく、着実に達成し続けるための具体的なステップを示した点に大きな意義があります。特に、第三者保証の義務化やカテゴリー別の要件明確化によって、排出量データの信頼性を向上させるだけでなく、企業ごとの実効的な削減施策を促す構造が強まっています。もちろん、第三者保証のコスト負担や内部体制の整備といったハードルはあるものの、これは企業にとって長期的なリスク管理と企業価値向上の好機とも言えます。世界的にESG投資の潮流が加速するなか、信頼性の高い排出量データと実効的な削減戦略を打ち立てる企業こそが、将来的にも投資家や消費者から選ばれる存在になるでしょう。
最終版は今後のパブリックコメントや実証事例を踏まえて改訂される見込みです。早期から本ドラフトの要件や第三者保証の導入に向けた準備を進めることで、企業は将来の規制強化と競争環境の変化に、より柔軟かつ着実に対応していけるはずです。
引用
SBTi CORPORATE NET-ZERO STANDARD Version 2.0 – Initial Consultation Draft with Narrative March 2025
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-Standard-v2-Consultation-Draft.pdf
※本記事の内容は、「SBTi Corporate Net-Zero Standard Version 2.0 – Consultation Draft」(2025年3月発行)および関連情報をもとに作成しています。最終確定版では内容が変更される可能性がありますので、最新情報はSBTi公式サイトなどでご確認ください。