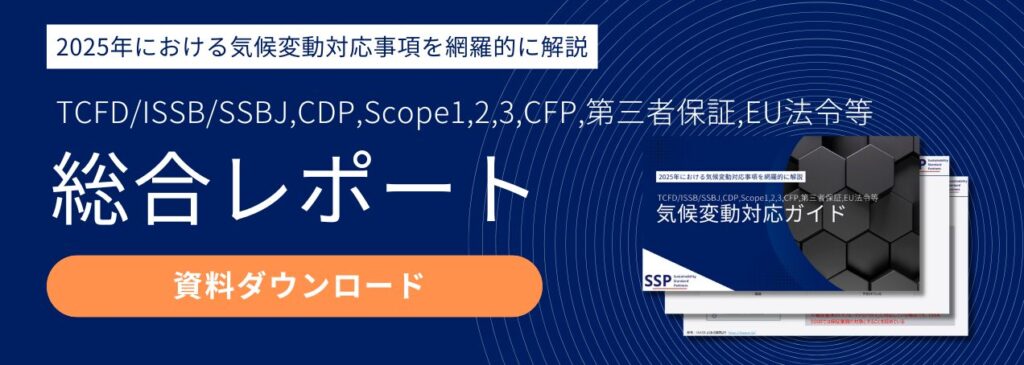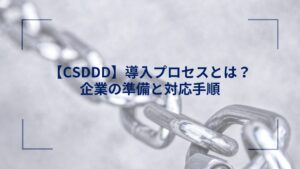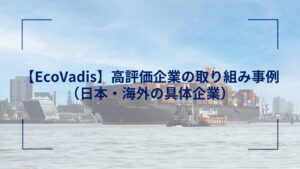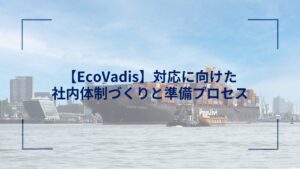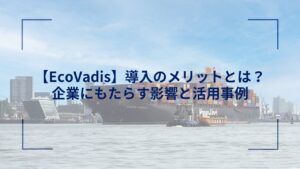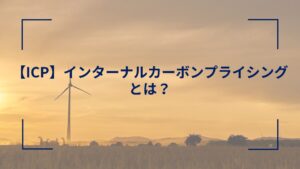EUのCSDDDは、多くの業界に広範な影響を及ぼすとみられています。本記事では、特にどの業界がCSDDDの影響を受けやすいのか、そしてそのサプライチェーンにどのような変化が起こり得るのかを解説します。業界ごとの注意点や企業が取るべき適応戦略についても考察し、CSR担当者が自社の状況に照らして対策を検討できるようサポートします。

1. CSDDDの影響を受ける業界
CSDDDは基本的に企業規模に基づき適用対象を定めていますが、現実問題として一部の業界は他に比べて対応負荷が大きくなると予想されます。主な業界例とその理由を挙げます。
アパレル・繊維業界
ファッション業界はグローバルに長いサプライチェーンを持ち、多くの製造工程が賃金水準の低い発展途上国に外注されています。その過程で児童労働や劣悪な労働環境、過剰残業などの人権問題が発生しやすく、CSDDDの人権デューデリジェンス義務への対応は避けて通れません。また、綿花栽培による環境負荷や廃棄物問題など環境面の課題も抱えており、業界全体で大きなインパクトを受けるでしょう。
電子機器・テクノロジー業界
スマートフォンやPCなど電子機器の製造には、多数の部品とレアメタルなどの原材料が必要です。サプライチェーン上流では鉱山での児童労働・劣悪な労働環境、紛争鉱物の問題があり、組立工程ではサプライヤー工場での長時間労働や安全管理不足が問題化します。これらはすべてCSDDDの射程に入るため、ICT業界も厳しいデューデリジェンスが要求されます。
自動車産業
自動車は数万点に及ぶ部品から構成され、その調達網は世界中に広がります。原材料の採掘(鉄鉱石、レアアース等)から下請け部品工場での労務管理、さらには完成車の排ガスやEV電池のライフサイクル環境影響まで、幅広い視点でのサステナビリティ対応が必要です。特にEV化に伴い重要度を増す電池原料(リチウム、コバルト等)の調達では、人権侵害リスクも指摘されており、対応が急務となっています。
食品・農業
食品業界もまた、原材料の生産現場での労働・環境問題に目を向ける必要があります。コーヒーやカカオ、バナナ等のプランテーション農業では低賃金労働や児童労働、熱帯雨林の開墾による環境破壊が懸念事項です。漁業では違法・無報告・無規制(IUU)漁業や強制労働被害が報告されています。こうした問題はCSDDDの下で「負の影響」として企業に是正が求められる対象です。食品メーカーや商社、小売に至るまで、サプライチェーンの原点に遡った取り組みが必要となるでしょう。
エネルギー・資源産業
石油・ガス、鉱業、化学などの産業は環境負荷が大きく、気候変動への責任も重い業界です。CSDDDではこれら企業に対し、温室効果ガス排出削減の明確な目標設定と移行計画の実行が義務付けられます。また油田開発や鉱山開発では先住民の人権や生態系保護なども問われるため、事業計画段階から徹底したデューデリジェンスが必要です。
以上は一例ですが、共通するのはグローバルな供給網を持ち、人権侵害や環境破壊のリスクを内包する業界であることです。金融業界も直接的には上記に比べ影響が限定的に見えますが、融資・投資先としてこうした産業を支えているため、結果的に自らのポートフォリオ管理の中でデューデリジェンスの考慮を迫られるでしょう。
2. サプライチェーンにおける注意点
影響を受ける業界では、以下のポイントに特に注意が必要です。
複雑なサプライチェーンの可視化
下請けや原料調達先が多岐にわたる業界では、まず自社のサプライチェーンを可能な限り可視化することが先決です。どの国のどんな企業・労働者が関わっているのか把握しなければ、リスク評価も対策も始まりません。近年ではデジタル技術(ブロックチェーンやサプライチェーンマッピングソフト)を活用してトレーサビリティを確保する企業も増えています。
高リスク地域・品目の特定
業界ごとに「この国・地域のこの原料はリスクが高い」というパターンがあります。例えばアパレルなら一部地域の綿花生産や縫製工場、電子機器なら紛争地域産のタンタルやコバルトなどです。業界共通の知見やNGOレポートなどを参考に、自社に該当する高リスク領域を特定し重点対策を講じる必要があります。
業界基準との整合
各業界では既にサステナビリティに関するガイドラインや認証制度が存在します。例として、コーヒーのレインフォレスト・アライアンス認証、水産物のMSC認証、電子業界のRBAコード(責任あるビジネス同盟)などです。これらはCSDDDの要求と方向性が一致しているため、積極的に取り入れることで効率よく対応できます。業界横断のイニシアチブに参加して共同で問題解決を図ることも有益でしょう。
中小企業への配慮
複雑なサプライチェーンの末端には中小企業や零細な事業者が多数存在します。彼らは直接CSDDDの法的義務を負いませんが、大企業からの要求に応える形で対応を迫られます。この際、負担が過度になれば事業継続が困難になる恐れもあります。大企業側は中小企業への技術移転や研修支援、費用面での支援策など配慮をしつつ、現実的な改善計画を進めていく必要があります。
以上のポイントを踏まえ、業界特有の課題に目を配ったデューデリジェンスを設計・実行することが求められます。自社だけではカバーしきれない部分は業界団体や専門機関と連携し、知見とリソースを集約して取り組む姿勢が重要です。
3. 企業の適応戦略
影響の大きい業界の企業は、CSDDD時代に適応するための戦略を早急に描く必要があります。以下は有効と考えられる適応戦略の例です。
サステナビリティ調達戦略
調達先を選定する際に、人権・環境の観点からスクリーニングを行い、基準を満たさない取引先とは契約しない方針を徹底します。一方で既存の重要サプライヤーが基準未達の場合は、即座に切り捨てるのではなく、改善計画を合意して一定期間内の是正を求めるなど段階的な対応を取ります。これにより安定調達と責任ある購買の両立を図ります。
現地とのパートナーシップ
リスクの高い生産地では、現地NGOや有識者と連携したプログラムを実施します。例えば農園における児童労働を無くすため教育NPOと協働したり、工場労働者の健康・安全研修を現地専門家と実施するといった具合です。ローカルパートナーとの連携は文化・言語の壁を越える助けとなり、より実効的な改善が期待できます。
テクノロジーの活用
AIやビッグデータ解析により、サプライチェーン上のリスク兆候を早期に検知する取り組みも進められています。例えばソーシャルメディアや現地ニュースをモニタリングして労働争議の情報をキャッチしたり、衛星画像で環境破壊の兆候を掴むなど、テクノロジーを駆使してリスク情報を収集します。先進企業ではこうしたデジタル監視網を構築し、問題の予防に役立てています。
人材育成
サステナビリティ対応には専門知識を持った人材が不可欠です。企業内で人権・環境の専門チームを育成するとともに、外部からの中途採用やコンサルタントの活用で知見を取り入れます。また幹部社員に対してはデューデリジェンスや国際基準に関する教育を行い、意思決定にサステナビリティ視点を組み込めるようにします。
シナリオプランニング
将来的に考えられる規制強化や環境変化に備え、複数のシナリオを想定して事業計画の柔軟性を確保します。例えば「ある国で深刻な人権問題が発覚して原料の調達が停止したら」「炭素税が導入され製造コストが跳ね上がったら」といった事態を想定し、代替サプライヤーの確保や製品設計変更の準備を検討します。シナリオごとの対応策をあらかじめ用意しておくことで、不測の事態でも競争優位を維持できます。
以上の戦略は業界や企業規模によって適用の仕方が異なりますが、共通するのはリスクを制約ではなく競争力強化の機会と捉える姿勢です。CSDDDへの適応は大変な労力を要しますが、その過程で得た知見や改善されたサプライチェーンは、将来にわたって企業を支える財産となるでしょう。業界全体で知恵を出し合い、この転換期を乗り越えていくことが期待されます。
引用
Proposal for a Directive on Corporate Sustainability Due Diligence (罰則関連条文)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/JA/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0071
EU議会公表の関連レポート・パブリックヒアリング
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/home