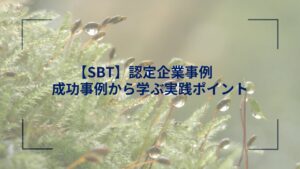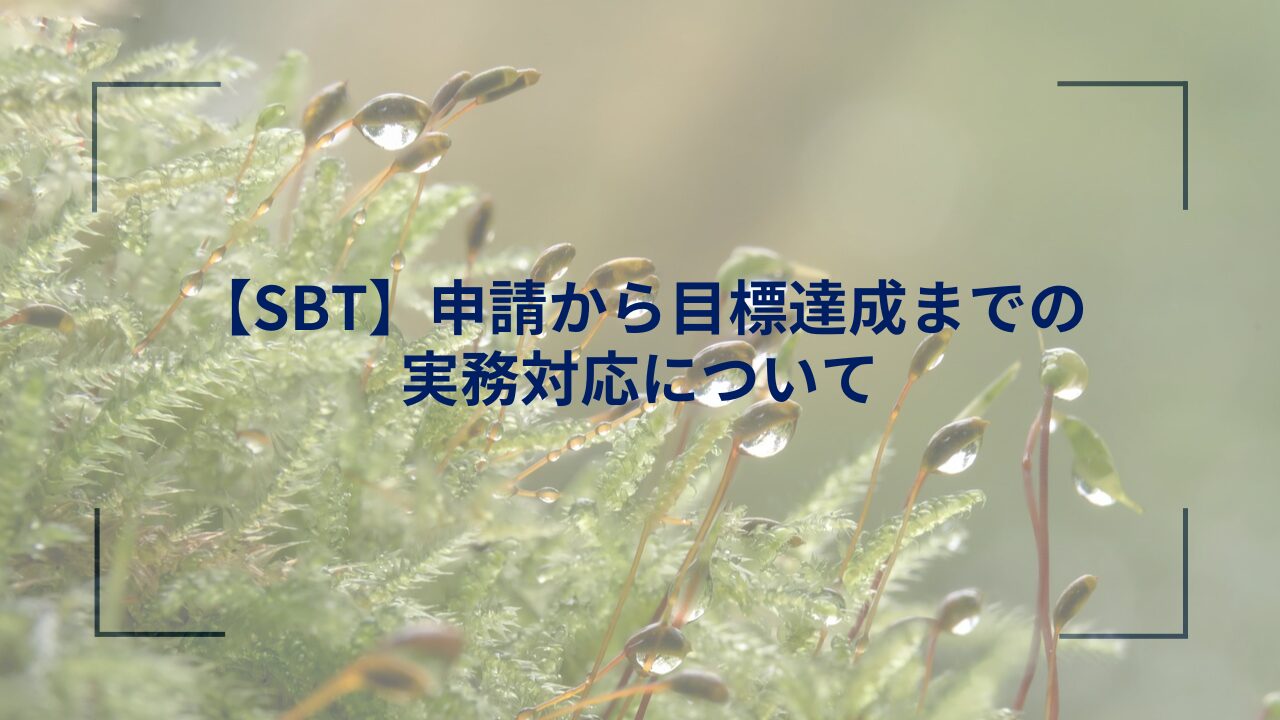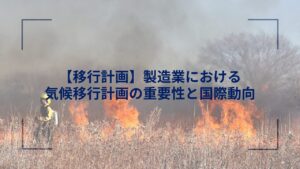SBT導入の全体プロセス(コミットメント、目標策定、SBTi申請、社内展開、進捗管理・報告)を軸に、必要なデータ収集や経営統合のポイントを中心に解説します。


1. SBT導入の全体プロセス
企業がSBTを導入する際のプロセスは、大きく以下のステップに分けることができます。
コミットメント(意思表明)
まず経営トップの承認のもと、SBTを採用することを社内外にコミットします。具体的にはSBTiに対し「科学的目標を設定する意思がある」ことを公式に表明(コミットメントレターの提出)し、通常この時点から2年以内に正式な目標を提出することが求められます。コミットメントは必須ではありませんが、予め宣言することで社内の意識改革や準備を促す企業も多くあります。
現状把握と目標案策定
次に、自社のGHG排出量の現状(インベントリ)を詳細に把握します。Scope1・2・3の排出量を算定し、どの領域に排出が多いか、削減ポテンシャルはどこにあるかを分析します。この段階では関連部門のステークホルダー(生産、設備、調達、物流など)と協議し、どの程度の削減が技術的・経済的に可能か検討します。その上で、SBTiの基準(1.5℃もしくはWell-below 2℃シナリオなど)を満たす中長期の削減目標案を作成します。例えば「2030年までにScope1・2をXX%削減、さらにScope3(カテゴリ1)をYY%削減」のように、基準に沿った目標値と対象範囲を定めます。
社内承認
作成した科学的削減目標案を経営陣に提示し、社内の正式な承認を得ます。SBTのような長期目標は事業戦略にも影響するため、取締役会レベルでの審議・承認が望ましいでしょう。実現までに必要な投資計画や主な施策もこの時点で概略を固め、経営資源の配分方針を決めておきます。また、自社のビジョンや他企業の事例と照らし、目標水準が十分に野心的かつ実行可能かどうかも検討します。
SBTiへの目標申請
社内で決定した目標をSBTiに公式申請します。現在、SBTiでのターゲット検証業務は「SBTi Services」という子会社組織が担当しており、企業はその検証ポータルサイトから申請を行います。申請に際しては所定のターゲット提出フォームに、自社情報やGHGインベントリ概要、設定した削減目標の内容、達成計画の概略、今後の報告方法などを記入します。提出後、まず形式要件の確認や抜け漏れチェック(テクニカルスクリーニング)が行われ、不備があれば差し戻しがなされます。問題なく受理されると、SBTiの検証担当チームによる詳細審査が開始されます。審査期間中、追加情報や質問がSBTiから届くことがあり、企業はそれら問い合わせに対応します。目標検証には通常30~60営業日程度(約1~2か月)を要するとされます。SBTi検証チームは提出された目標が最新の基準(各業界の削減シナリオや必要カバー率など)に適合しているかを精査し、最終的に「承認(Validated)」または「却下(Needs revision)」の判断を下します。承認された場合、企業には正式な承認レターが発行され、次のステップに進みます。
目標の公表(社外発表)
SBTiで承認された目標は、通常1ヶ月以内にSBTiの公式サイト上で「Targets set(目標設定済み)」企業として掲載されます。企業側でもプレスリリースや自社ウェブサイトを通じて目標達成へのコミットメントを公表し、ステークホルダーに向け宣言します。この際、SBTiの名称やロゴ、承認内容を用いた発表ガイドラインが提供されるため、それに沿って対外発表資料を準備します。
削減施策の実行とモニタリング
目標を掲げた後は、その達成に向けた具体的な施策を社内で実行に移します。省エネ投資、再生可能エネルギー導入、製品設計の見直し、サプライヤーとの協働など、事業計画に組み込んだ削減アクションを推進します。同時に、毎年の排出実績をトラッキングし、目標達成に向けた進捗をモニタリングします。進捗状況は社内報告だけでなく、後述するように社外にも毎年開示していく必要があります。
このような一連のプロセスを経て、SBTは単なる宣言から実践フェーズへと移行します。以下では、各段階のポイントや実務対応についてさらに詳しく解説します。
2. SBT目標設定のためのデータ収集(詳細)
SBT設定の出発点は、自社のGHG排出量の正確な把握です。特に基準年(ベースイヤー)となる年の排出量データをきちんと揃えることが重要になります。基準年は過去数年間で排出量が平年並みの年を選ぶのが一般的で、その年についてScope1、2、3の包括的なインベントリを作成します。
インベントリ構築の際には、GHGプロトコルに則り各排出源からのデータを収集しますが、社内のデータだけでなくサプライヤーや輸送業者など外部からの情報提供も必要になる場合があります。データ収集にあたっては、以下のような手順・工夫が実務上有用です。
データ収集計画の策定
どの部門からどのようなデータを集めるか計画を立てます(エネルギー使用量、燃料使用量、購買品目リスト、出張・物流実績など)。各データの担当部署・担当者を明確にし、収集フォーマットや頻度を決めます。
ステークホルダーとの協議
排出源ごとの削減余地を探るためにも、早期に関連部署と話し合いを行います。例えば製造部門には設備の電力使用実績や省エネ計画を確認し、調達部門とは主要サプライヤーの環境対応状況を共有する、といった形で各領域の専門知見を集約します。このプロセスにより、どの分野でどれだけ削減可能か大まかな見通しを立て、目標設定の土台情報とします。
外部データの活用
自社で把握困難なScope3排出などは、環境コンサルティング会社やLCAデータベースから提供される業種平均データや排出係数を活用することも検討します。ただし可能な限り主要サプライヤーには協力を仰ぎ、自社製品に即したデータを入手する方が望ましいでしょう。近年では主要サプライヤーに対しGHG排出情報の提供を求める動きも一般化してきました。
データ検証
集めたデータの整合性チェックや漏れチェックを行います。エネルギー使用量と電力料金の照合作業、購買データと在庫データの突合などにより、大きな抜けや異常値がないか確認します。必要に応じて過去年との比較を行い、想定外の変動があれば原因を調査します。
必要に応じて第三者保証を取得するなど、ステップを踏み、信頼できる排出量ベースラインを確立した上で、SBTの削減目標値を算出します。例えば、基準年総排出量が100万トンCO2であった場合、1.5℃シナリオなら2030年に55万トン以下(45%削減)程度が求められる、といった具合に、SBTiのターゲット計算ツール等を使い削減必要量を割り出します。その上で自社の事情を踏まえ、Scopeごとの削減割合やターゲット年を決定します。
3. SBTiへの申請手順(詳細)
社内で決定した科学的削減目標は、SBTiへの申請(ターゲット検証依頼)を行うことで公式な認定プロセスが始まります。SBTiへの申請手順は標準化されており、通常以下のような流れになります。
検証サービスへの登録と申込
SBTiの検証申請ポータル(SBTi Validation Portal)に企業アカウントを作成し、検証サービスに申し込みます。ここで基本的な企業情報や目標タイプを登録します。コミットメント済企業であればその情報もひも付けられます。
ターゲット提出フォームの記入・提出
次に、SBTi指定のターゲット提出用フォームに必要事項を記入します。このフォームには、会社概要、GHGインベントリ概要(Scope1,2,3の算定範囲と排出量)、設定する削減目標の詳細(基準年、ターゲット年、削減率、カバー範囲)、削減戦略の要約、進捗報告の計画などが含まれます。各設問に沿って詳細かつ正確に記入し、完成したらオンラインで提出します。
スクリーニング(書類審査)
提出後、SBTi Services側でフォーム内容の形式チェックと要件適合チェック(技術スクリーニング)が行われます。ここでは記入漏れがないか、目標値が明らかに基準を満たしているか(例えば削減率が十分か、Scope3要件を満たしているか)などを確認します。不備があればこの段階で差し戻しとなり、企業側で修正して再提出します。
ターゲット検証
書類が受理されると、SBTiのターゲット検証チームによる詳細なレビューが始まります。検証チームは提出フォームと添付資料を精査し、必要に応じて企業に追加質問を送ります。例えば「Scope3の特定カテゴリーについて算定対象から除外した理由」や「特定事業売却に伴うインベントリ影響」など、判断に必要な追加情報を求められる場合があります。企業側は原則2営業日以内に回答を返すことが推奨されています。この質疑応答を経て、検証チームは最終判断を下します。
結果の通知
検証プロセス開始から通常30営業日(約6週間)以内に検証結果が通知されます。結果は「承認(Target Validated)」もしくは「要改善(Conditions/Not Validated)」の形で示され、承認の場合はその内容が正式に確認されます。却下(要改善)の場合、どの基準を満たさなかったかフィードバックが提供され、修正の上再申請することも可能です。
目標承認の公表準備
承認結果を受け取った企業は、1か月以内を目途に目標の公表準備を行います。SBTiのコミュニケーションチームと連携し、公開日や発表内容を調整します。同時に自社でもプレスリリースやウェブ掲載文章を用意し、社内外への説明資料を整備します。
このように、SBTiへの申請手順自体はフォーマット化されていますが、重要なのは事前準備です。申請フォームへの記入項目は多岐にわたり、削減目標の根拠や算定範囲を論理的に説明できる必要があります。前述のデータ収集や社内検討を十分に行い、説得力のある目標ストーリーを構築しておくことで、検証プロセスもスムーズに進みます。逆に準備不足だと、問い合わせ対応や差し戻しで時間と労力を要することになるため、「綿密な下準備」が申請成功のカギと言えるでしょう。
4. SBT認定後の社内展開と実務対応
SBTiから目標認定を受けた後は、いよいよ社内でその目標を実行に移す段階となります。目標達成には長期にわたる全社的な取り組みが必要なため、社内展開の段階では以下のような対応が重要になります。
経営戦略への統合
承認されたSBTを単なる環境目標ではなく、経営目標の一部として位置付け直します。具体的には、中期経営計画や事業戦略にSBT達成を盛り込み、設備投資計画や研究開発の方向性を目標達成に合致するよう調整します。例えば、カーボンニュートラル関連の投資案件を優先順位高く設定したり、新規事業の評価指標に気候インパクトを含めたりすることが考えられます。トップマネジメントが「SBT達成は経営の最重要課題の一つ」と明言し、意思決定に組み込むことが肝要です。実際ソニーでは、CEO自ら「科学的目標の達成はソニーの中核的使命」と位置づけて陣頭指揮を執り、他の経営幹部の支持も取り付けました。このようなトップのコミットメントが他の役員や事業部門に浸透することで、全社的な協力体制が整います。
組織横断の推進体制
SBT達成には複数部署の協力が不可欠なため、社内に横断的な推進体制を構築します。例えばCSO(最高サステナビリティ責任者)直轄の気候戦略委員会を設置し、環境担当役員だけでなく主要事業部門の責任者もメンバーに加えます。定期的な会合で進捗をレビューし、ボトルネックとなっている課題(省エネ投資が進まない、生産プロセス改善が必要 etc.)を特定して解決策を議論します。また必要に応じて分科会を設け、再エネ導入や商品設計見直し、サプライヤーエンゲージメントなどテーマ別のプロジェクトを走らせます。社内推進体制のポイントは、「各部門に自部門の目標を背負わせる」ことです。SBTをブレイクダウンし、部門別・工場別のKPIに落とし込むことで、担当者レベルまで目標が腹落ちします。
具体的施策の実行
目標達成のための具体的な削減施策を実行段階に移します。Scope1・2対策としては、生産設備の省エネ改造、工場やオフィスへの再生可能エネルギー電力導入、自社車両のEV化や燃料転換などが典型です。例えばパナソニックは欧州・中国の全事業所で100%再生可能エネルギー電力化を達成するなど、事業拠点の脱炭素化を加速させています。Scope3対策では、製品使用時の省エネ性能向上(高効率製品の開発)、製品の小型化・軽量化による物流効率化、サプライヤーへのエネルギー転換支援(再エネ電力の共同調達やエネルギー管理ノウハウ提供)などが考えられます。先進企業では主要サプライヤーに対し排出削減目標の設定を働きかける例も増えており、部品調達の入札要件にサステナビリティ評価を加える動きもあります。これら施策は一度に全ては難しいため、短期・中期・長期の行動計画に整理し段階的に実行していきます。例えば「まず2025年までに再エネ率50%、2030年までに100%」といった具合にマイルストンを設定すると社内の進捗管理もしやすくなります。
https://www.panasonic.com/jp/about/sustainability/re100.html
社内浸透と意識改革
長期的な目標を達成するには、最終的には企業文化として定着させることが重要です。従業員の意識改革・能力開発の取り組みも並行して進めます。社内報やイントラネットでSBT関連の進捗や成功事例を共有したり、従業員提案制度で省エネ・脱炭素アイデアを募ったりすることも有効です。経営陣が定期的に「気候リーダーシップ」の重要性を発信し、表彰制度で貢献の大きいチームを称えるなど、ポジティブな動機付けによって社員の巻き込みを図ります。ソニーでは「自社の目標がグローバルな気候目標と整合していることが社内の自信と誇りにつながった」と述べており、SBT認定そのものが従業員の士気を高める効果も期待できます。
以上のように、SBT認定取得後は全社的な実行フェーズへと移行します。言い換えれば、SBTはゴールではなくスタートラインであり、そこから日々の企業活動の中で削減施策を積み重ねていくことが不可欠です。トップから現場まで一丸となった実行力があって初めて、野心的な科学的目標が現実のものとなっていきます。
https://www.sony.com/ja/SonyInfo/News/Press/202209/22-034
5. SBT進捗管理と報告の方法
科学的に整合した目標を掲げても、進捗状況を適切に管理しなければ達成は不可能です。そこで、SBTを設定した企業には定期的な進捗モニタリングと外部への報告が求められます。
進捗管理
まず進捗管理ですが、一般的には毎年度のGHG排出実績をSBT目標と比較する形で行われます。各年の排出量(Scope1・2・3)を算出し、基準年からの削減率やターゲット年までの残り削減必要量を算出します。この際、SBTi承認時の目標値(例えば2030年に△△トンまで削減)と現在地を比較し、削減ペースが足りているか評価します。
例えば「2030年まで年平均-7%の削減ペースが必要だが、直近1年では-5%に留まった」等を把握し、計画の微調整に役立てます。進捗状況は社内の気候戦略委員会などで定期的にレビューし、遅れが生じていれば追加対策の検討や戦略修正を行います。このPDCAサイクルによって、長期目標への軌道修正を機敏に行えるようにします。
報告・開示
SBTiは承認企業に対し毎年の排出量と目標進捗の公開を求めています。具体的には、SBTiの基準と勧告により「企業は毎年、自社のGHG排出インベントリとSBTの達成状況を公開すべき」と定められています。このため多くの企業は、CDPの気候変動質問書への年次報告や、自社のサステナビリティレポートにおける気候KPIの開示を通じて、SBT進捗を公表しています。2022年の調査では、SBT承認企業の76%が何らかの形で目標進捗を対外公表していたとのデータもあります。報告内容としては、基準年比の削減率や各Scopeの排出推移、主要な削減施策の実施状況、未達リスクと対応策などが盛り込まれます。定量データはグラフ等で視覚的に示し、定性的解説も加えてステークホルダーに進捗を説明します。報告の場としては前述のCDP回答やCSR報告書のほか、統合報告書や気候関連財務情報開示(TCFDレポート)でも触れられることがあります。
重要なのは、良い点も悪い点も含めて透明性高く開示することです。そうすることで投資家や社会からの信頼を維持でき、場合によっては建設的なフィードバックや協働の機会を得ることもあります。なお、SBTi自体は現状進捗報告の内容審査までは行っていませんが、今後ネットゼロ基準の運用強化に伴いフォローアップが厳格化する可能性も指摘されています。
いずれにせよ、企業にとっては進捗を定量的に把握し公表することが目標達成への責任ある姿勢といえるでしょう。SBTは長期にわたる旅路であり、その道のりを社内外と共有しながら進むことで、初めて価値が生まれるのです。
引用
WWF ジャパン
https://www.wwf.or.jp/corp/info/923.html
Target services
https://sciencebasedtargets.org/target-services