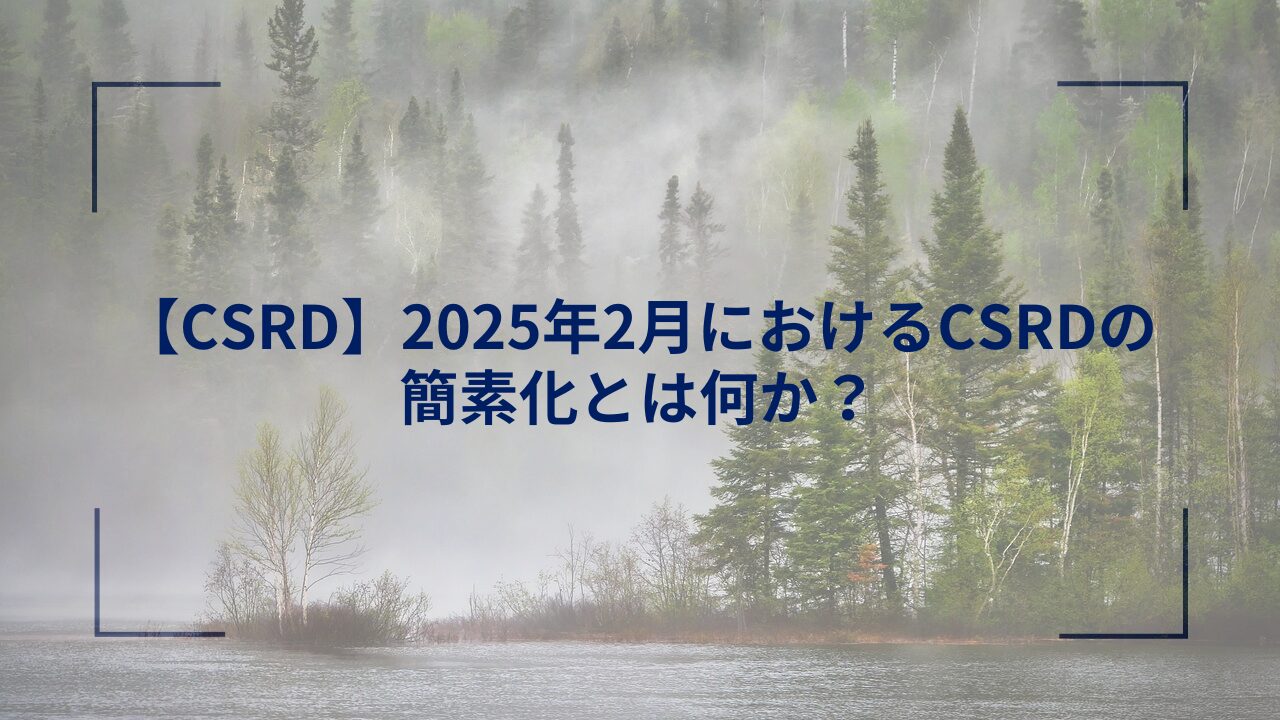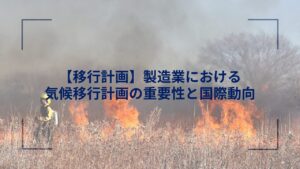CSRDの簡素化は、企業のサステナビリティ報告に関する負担軽減を目的に、欧州委員会が提案した制度見直しです。報告義務の対象を大企業に限定し、中小企業の負担を削減。さらに、報告項目の削減や基準の統一化も進められ、実務の効率化が図られます。一方で、ダブル・マテリアリティ原則は維持され、情報の透明性は確保されます。持続可能性と実効性の両立を目指す規制改革について解説します。


1. CSRD簡素化の背景
CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive、企業持続可能性報告指令)は、EUにおいて企業にサステナビリティ関連情報の開示を義務付ける規則です。2024年度以降、EU域内の多くの企業に環境・社会・ガバナンス(ESG)情報の報告を求め、企業の持続可能性に関する透明性向上を図るものでした。しかし、その対象範囲の広さや開示項目の多さから企業側の負担増大が懸念されていました。
こうした背景を受け、欧州委員会は2025年2月に規則の「簡素化」パッケージを提案し、報告義務を大企業に重点化するとともに中小企業への過度な負担軽減を図る動きを開始しました。この簡素化措置により、CSRDの適用対象企業数がおよそ80%削減されるとも報じられており、企業の報告負担を大幅に緩和する内容となっています。
今回の簡素化は、サステナビリティ情報の報告制度を見直し、必要なデータ開示項目の精選や基準類の整理・統一を進めるものです。以下では、CSRD簡素化に関する変更点の概要を、報告義務の範囲、データ開示の簡素化、基準の統一化の観点から整理します。
2. CSRD オムニバス法案による変更点の概要
まず、大きな変更点として報告義務の対象範囲の縮小が挙げられます。次に報告期間の見直しについて解説していきます。
報告義務の範囲の見直し
現行のCSRDでは「従業員250人以上、売上高5,000万ユーロ超、総資産2,500万ユーロ超」の基準のうち2項目を満たす企業(一般的な大企業)やEU規制市場上場企業など多数が報告義務の対象でした。しかし簡素化案では、この基準が見直され、従業員数が1,000人超かつ売上高5,000万ユーロ超(または総資産2,500万ユーロ超)の企業のみをCSRD報告義務の対象とする方向に変更されています。この改定により、本来CSRD適用予定であった企業数のおよそ80%が対象外となる見込みです。報告義務をより規模の大きい企業に絞ることで、サステナビリティへの社会的影響が大きい企業にリソースを集中し、中小企業への過度な負担を避ける狙いがあります。さらに、報告開始時期にも猶予が与えられる見通しです。
報告期間の見直し
今回の提案では、当初2026年から段階的に適用予定であった中堅企業(Wave 2および3と位置付けられる企業群)の報告義務開始が2年間延期され、最初に適用が始まる大企業(Wave 1)についても開始が1年遅れて2028年になる見込みです。これにより企業は移行準備の時間を追加で確保でき、高品質なサステナビリティ情報を提供する体制整備に余裕が生まれます。なお、今回対象外となる企業(従業員1,000人未満等)に対しては、任意のサステナビリティ報告枠組みが用意される予定です。欧州委員会は、報告義務の無くなる中小規模企業(VSME: 従業員1,000人未満の企業)のために、自主的なESG報告基準を策定し、大企業がサプライチェーン上の取引先に要求できる情報の範囲を限定する方針です。これにより、直接の報告義務を負わない企業であっても、自社のサステナビリティ情報を任意に整理・開示し、大企業との取引関係における情報提供ニーズに応えやすくなると期待されます。
3. データ開示の簡素化とその影響
CSRDの具体的な報告基準である「欧州サステナビリティ報告基準(ESRS)」について、欧州委員会はその内容を見直し、開示データポイント(項目数)を大幅に削減する方針を示しました。これまで詳細に規定されていたESG関連の定量・定性情報のうち、重要度の低い指標や重複する項目が整理される見込みで、企業は報告書作成時に扱うデータ量を減らすことができます。加えて、現行基準で不明確だった規定を明確化し、他の欧州規制との整合性を高める改訂も行われます。これにより、企業は報告要件をより理解しやすくなり、金融当局や投資家に対して一貫性のある情報提供が可能になるでしょう。具体的な簡素化策としては、業種横断的な共通指標に集中した報告への転換が挙げられます。例えば、従来計画されていた業種別の詳細な追加開示基準は策定されない方向となりました。すべての企業が共通の基準に従うことで、業種間で報告内容がばらつかず比較可能性が向上し、企業側も自社の業種特有の追加要件に対応する負担を免れる効果が期待できます。
サステナビリティ情報の保証(監査)水準の引き上げ
当面は限定的保証のままとし合理的保証への移行を見送ることになりました。本来CSRD施行後数年で保証水準を高める計画がありましたが、これを撤回することで、監査対応に伴う追加コストや工数の増大を抑える狙いがあります。さらに、CSRDと併せて企業に求められるEUタクソノミー(グリーン分類)開示も簡素化の対象となっています。タクソノミー規則に基づく売上高や資本的支出のグリーン割合等の報告について、義務付けられる企業範囲が縮小され、売上高がEUR 4.5億以下の大企業はタクソノミー開示が任意扱いになる見通しです。
タクソノミー報告用の様式改定
要求されるデータポイント数が約70%削減されるとともに、売上や資産のうち10%未満を占める非重要な事業活動は開示対象から除外されるなど、大幅な簡略化が提案されています。この変更により、企業は自社の主要なサステナビリティ活動に焦点を当てて報告できるようになり、重要性の低い情報に過度なリソースを割かずに済むようになります。これらデータ開示の簡素化策の影響として、企業の報告実務負担は確実に軽減されるとみられます。報告項目の削減と明確化により、各社は主要なESG指標に注力した効率的な情報収集・開示が可能となります。
「ダブル・マテリアリティ」(二重の重要性)原則は維持
すなわち、企業は自社のサステナビリティ課題が事業に与える影響だけでなく、自社の事業活動が環境・社会に与える影響についても引き続き開示する必要があります。開示項目が簡素化されても、この根本原則が残ることで、ステークホルダーにとって重要な情報は引き続き報告され、高い透明性は担保される仕組みです。企業にとっては重要なポイントを外さずに報告しつつ、細部の煩雑さが緩和されるバランスが図られることになります。
4. 基準の統一化の進展
CSRD簡素化のもう一つの柱が、報告基準の統一化と整合性の向上です。まず、前述のとおり業種別基準の廃止によって、全企業に適用される基準が一本化されます。これにより、企業規模や業種を問わず同じESRS枠組みに沿った報告が行われるため、報告内容の標準化が進みます。ステークホルダー(投資家や取引先など)は企業間のサステナビリティ情報を比較しやすくなり、企業側も統一された指針に従えばよいため報告体制を構築・維持しやすくなるという利点があります。
セクター別ESRS策定権限の削除
また、欧州委員会が当初計画していたセクター別ESRS策定権限の削除も提案に含まれており、これも事実上の基準統一化に寄与します。さらに、CSRD関連の報告基準とその他のEUサステナビリティ規制(例えば気候関連の金融情報開示規則やEUタクソノミー規則)との整合性を高める改訂が行われます。これは、用語や指標の統一・重複排除を通じて、企業が複数の報告制度に対応する際の齟齬を減らす目的があります。例えば、CSRD上の開示項目とタクソノミー開示や金融商品開示規則(SFDR)の要件との間でデータ定義を揃えるなど、基準間の統一性が向上する見込みです。こうした調整により、企業は一貫性のある情報開示戦略を立てやすくなり、報告内容の信頼性も高まるでしょう。
加えて、保証基準の扱いについても統一的な方向が示されました。前述の通り、サステナビリティ報告の第三者保証は引き続き「限定的保証」に留める提案となっており、全ての企業が同一水準の保証要件に応じれば足りる形になります。これにより、将来的に全社一律の保証基準の下で報告書の信頼性確保が図られることになります。保証水準の統一は、監査人にとっても基準策定の簡素化につながり、企業間で保証の有無・程度がばらつかないメリットがあります。
一方で、ダブル・マテリアリティ原則は維持されているため、グローバル基準との相違点は残るものの、EU域内ではこの原則に基づく高い情報開示基準が引き続き統一的に適用されます。これはEUが重視する「企業の持続可能性影響に関する説明責任」を堅持する姿勢の表れであり、基準統一化後も欧州の報告フレームワークの特徴として継続していく見通しです。
5. 企業の対応策
このようなCSRD簡素化の動きを踏まえ、企業のサステナビリティ担当者は以下の対応策を検討すべきです。
自社が改定後のCSRD適用対象に該当するか確認する
新たな基準では「従業員1,000人超かつ売上高5,000万ユーロ超(または総資産2,500万ユーロ超)」の企業のみが報告義務を負う見込みです。まずは自社がこの条件を満たすか精査し、適用対象である場合には報告準備計画の見直しを行います(対象から外れる場合でも、取引関係等で間接的に情報提供が求められる可能性がある点に留意します)。
追加の準備期間を有効活用する
適用対象企業について報告開始時期が最大で2年延期される見込みです。この猶予期間に、自社のサステナビリティ情報収集プロセスを整備し、データ品質の向上や内部統制の強化を図ります。延期によって生まれる時間を活かし、サステナビリティ報告を自社の経営戦略や事業計画に統合する取り組みを進めることで、将来的な報告義務開始に備えます。
対象外となる場合でも自主的な情報開示を検討する
簡素化によりCSRDの直接の対象外となる企業(従業員1,000人未満等)であっても、サプライチェーン上の取引先や金融機関からサステナビリティ情報提供を求められるケースは今後も考えられます。欧州委員会は対象外企業向けに任意準拠できる報告基準を策定し、大企業が求める情報を必要最小限に制限する予定です。自社の信頼性や持続可能性への取り組みを示すため、可能であればこの任意基準に沿った開示を行い、ステークホルダーからの情報要請に応えられる体制を維持すると良いでしょう。
関連法規制の変更動向を継続的にモニタリングする
今回のCSRD改正案は現時点では提案段階であり、欧州議会および理事会での協議・採択プロセスを経て最終決定となります。その過程で細部が変更される可能性もあるため、立法手続の進展を注視しつつ最終的な要件に備えることが重要です。また、CSRD以外にもサステナビリティに関する各種規制(気候関連の財務情報開示やサプライチェーンのデューデリジェンス規則等)にも動きがあります。自社に関連する法規制全般の最新情報を収集し、統合的な対応戦略を検討しておく必要があります。
規制緩和後も主体的なサステナビリティ対応を維持する
CSRDの簡素化は企業負担を軽減しますが、報告義務が軽くなることと企業のサステナビリティ課題が軽くなることは同義ではありません。気候変動への対応やESG経営は規制遵守以上に企業価値や競争力に直結する要素です。欧州委員会も「簡素化によって企業の業務は容易になるが、脱炭素への道筋は確実に維持される」と強調しています。したがって、たとえ法的義務が減少しても、自主的に高い水準の情報開示と持続可能経営の推進に努める姿勢が求められます。
信頼性の高いESGデータの蓄積と開示は、投資家による評価やサステナブルファイナンスの文脈でも重要であり、長期的に見て企業の持続的成長に資するでしょう。
6. CSRD 今後の展望
CSRD簡素化に関する提案は、今後EUの立法プロセスを経て正式決定・施行される予定です。欧州委員会は2025年の作業計画で今回のような重複・過剰な規制の見直しを進め、2029年までに全企業の事務負担を25%削減(中小企業に対しては35%削減)するという目標を掲げています。今回のCSRD簡素化はその一環であり、提案が採択されればサステナビリティ報告分野における規制の実効性とバランスが大きく改善される見通しです。
欧州議会と理事会での協議
今後の展開としては、欧州議会と理事会での協議により詳細が詰められ、2025年末までには必要な法改正が整う可能性があります。特に報告開始時期の延期(ポストポーネメント指令)は迅速に承認される見込みであり、企業は直近の報告対応を急がずに済む公算が高くなっています。一方、報告範囲の縮小や基準変更(アメンドメント指令)については議論が長引く可能性も指摘されており、最終的な落とし所を巡って調整が続くでしょう。企業としては立法の進捗をウォッチしつつ、決定内容に柔軟に対応できる準備を進めておくことが重要です。
グローバルなサステナビリティ報告の調和
欧州の動きに呼応して、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)の基準や他国の開示規制との相互運用性の確保が課題となっており、将来的にはEU基準とグローバル基準の統合的な運用が模索される可能性があります。現時点でも欧州委員会とISSBは基準間の対応関係について協議を行っており、企業が二重の報告負担を負わないよう報告基準の国際的整合性を高める取り組みが進展しています。
こうした国際動向も視野に入れ、特に多国籍企業はEU域外の規制にも対応できる統合報告体制の整備を検討する必要があるでしょう。最後に、サステナビリティ報告の質を高めつつ企業の負担を減らすという「質と量の両立」が今後の鍵となります。欧州委員会のフォン・デア・ライエン委員長は「約束した簡素化を実現した。これにより企業の業務が容易になる一方で、脱炭素目標への道筋は確実に維持される」と述べており、規制簡素化と気候目標の両立を強調しています。企業側もこの方針を踏まえ、効率的かつ効果的なサステナビリティ情報開示を追求することが求められます。
CSRD簡素化の流れは、企業にとってはガバナンス体制を見直し持続可能性情報を戦略的に活用する好機とも言えます。今後も欧州の公式情報を注視しつつ、自社のサステナビリティ報告を進化させていくことが重要です。参考資料: 欧州委員会「競争力コンパス」報告書、CSRD簡素化に関する欧州委プレスリリースおよびQ&Aなど。今回の内容は執筆時点における情報に基づいており、今後変更される可能性があります。最新動向については引き続き欧州当局からの公式発表を確認してください。
引用
Corporate Sustainability Reporting Directive(CSRD
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2464/oj
欧州委員会プレスリリース
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/home/en
欧州委員会サステナビリティ報告
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en