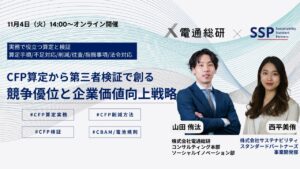

1.化学産業が果たす社会的役割と排出責任
カーボンフットプリント(以下 CFP)とは、製品やサービスがそのライフサイクル全体で排出する温室効果ガス量を二酸化炭素換算で定量化する手法です。なかでも化学産業は、石油・天然ガス・バイオマスなどを原料に幅広い素材や機能性化学品を提供し、グローバルサプライチェーンの川上に位置する基盤産業であるがゆえに、一次排出だけでなくバリューチェーン全体の間接排出に大きな影響を及ぼしています。国際エネルギー機関(IEA)の統計によれば、化学セクターは一次エネルギー起源CO₂排出の約八%を占め、そのうち三分の二以上が原料クラッキングやプロセスガスの燃焼に由来します。さらに、この産業が供給するプラスチック、合成ゴム、肥料、溶剤などは下流で加工・使用・廃棄される際にも追加的な排出を伴うため、ライフサイクルを包括的に計測しなければ真の環境負荷を把握できません。こうした背景から、化学企業はISO 14040/44のライフサイクルアセスメント(LCA)やISO 14067の製品CFP指針を活用して算定精度を高め、投資家や顧客、政策当局へ信頼性の高いデータを提示する責任を負いつつあります。
2.Scope1・2・3にみる化学プロセスの排出特性
ここでは化学プロセス特有の排出形態を見ていきます。
Scope1
スチームクラッカーやアンモニア合成装置などの高温高圧プロセスを運転する化学工場は、炉の燃料燃焼による直接排出(Scope 1)を多量に抱えています。加えて、プロセス反応そのものから副次的に二酸化炭素や一酸化二窒素が発生する場合もあり、これらを正確に区分けして算定することが不可欠です。
Scope2
電力・蒸気・冷熱の購入に伴う間接排出(Scope 2)は、エネルギー集約型の塩素アルカリ電解や多段蒸留工程を持つアロマ化合物工場で顕著に表れます。
Scope3
最終的にCFPを左右する最大項目は、原材料調達から下流製品の使用・廃棄を含むScope 3で、業界平均で総排出量の七割超を占めるとの報告が相次いでいます。具体的には、石油精製、ナフサ分解、バルク化学品の上流工程がカテゴリ 1「購入した製品・サービス」に、合成樹脂製品が燃焼・分解される際の排出がカテゴリ 11「販売製品の使用」に、さらにプラスチックごみ焼却がカテゴリ 12「廃棄」に該当し、それぞれの算定境界をどう設定するかで結果が大幅に変わります。
3.国際規格と業界ガイドラインの整合性
製品単位のCFP算定を進めるうえで最初に参照すべき規格はISO 14067です。同規格は機能単位の設定、システム境界、データ品質評価、配分手法、副産物取り扱いなどの基本要件を示しており、化学製品にも横断的に適用可能です。ただし、化学プロセスは共沸蒸留や共重合体のように複雑な副生成物が多いため、製品カテゴリルール(PCR)など業界固有の補完指針が必要になります。
欧州ではTfS(Together for Sustainability)が2022年に「Product Carbon Footprint Guideline for the Chemical Industry」を公表し、割当方法やデータフォーマットを詳細に規定しています。日本化学工業協会も2023年に独自の算定ハンドブックを公開し、ISO 14067との整合を保ちながら国内企業でも取り組みやすい指針を整備しました。企業はこれらを組み合わせ、独自工程の特殊性をエビデンス付きで説明する必要があります。
4.データ収集の課題とデジタルMRVの台頭
化学CFPを精緻に算定する際の最大の難関は、サプライヤーから得る一次データの不足と秘匿性です。
機密保持と透明性確保
石油化学原料を扱うコンビナートでは、プラント横断的なエネルギー・物質収支をとることで全製品に排出を割り付けますが、同一原料を複数の企業がシェアリングする場合、境界の引き方をめぐりデータの機密保持と透明性確保のジレンマが生じます。そこで脚光を浴びているのが、ブロックチェーン技術やクラウドLCAプラットフォームを用いた「デジタルMRV(計測・報告・検証)」です。リアルタイムで監視されたフレア排気や蒸気消費を原単位データとして暗号化・共有し、サプライチェーン上の関係者だけが参照できる仕組みを導入すれば、データ信憑性を損なわずに算定精度を高められます。欧州の大手化学メーカーは、主要顧客に対し“マテリアル・パスポート”として副産物を含むCFPデータを納品する取り組みを開始し、Scope 3報告の迅速化と受注競争力強化を同時に実現しています。
5.技術革新がもたらす排出削減シナリオ
エネルギー転換では、電力源を再生可能エネルギーに置き換える電化戦略が進んでいます。従来は化石燃料直火加熱が主流だったエチレンクラッカーを、電気クラッカーへ転換するパイロットプロジェクトが欧州で稼働し、理論上はプロセスCO₂排出を九割以上削減可能です。
また、バイオマスナフサやCO₂由来メタノールを原料に混入するマスバランス方式は、サプライチェーン全体の排出残高を着実に減らしつつ、既存インフラを活用できる柔軟性があります。さらに、化学的リサイクルによる廃プラスチックの熱分解油化や、グリーンアンモニア・e-メタノールなどの合成燃料開発が加速し、製品使用・廃棄段階の排出も中長期的に低減する道筋が見えてきました。これらの技術オプションをCFPシミュレーションで比較し、投資優先順位を可視化する手法が経営レベルで重視されています。
6.CFP算定プロセスと報告書作成の実際
算定フローは下記の5段階が一般的です。
①目的・範囲の設定
②インベントリデータ収集
③排出計算と指数化
④結果の解釈・感度分析
⑤報告・第三者検証
まず、機能単位を「ポリエチレン樹脂一キログラム」など明確に定義し、システム境界をCradle to Grave, Cradle to Gateかで定めます。
次に、原料投入量・エネルギー使用量・副生成物生産量・輸送距離などを一次データとし、公共LCAデータベースの二次データで補完します。
その後、GaBiやSphera、openLCAといったソフトウエアにデータを入力し、IPCC 2021年版係数でCO₂e換算を行います。不確実性が大きいパラメータについては感度分析を実施し、結果のばらつきを報告書に示すことで透明性を確保します。
最後に、ISO 14064-3やPAS 2050に基づく第三者検証を受け、監査証跡を整備したうえで顧客や投資家向けに開示します。こうした手順を反復し改善するサイクルが、化学企業のCFP算定リテラシーを高め、サプライチェーン全体の排出削減に寄与します。
7.規制・市場インセンティブと経営インパクト
EUの炭素国境調整メカニズム(CBAM)が2026年以降に化学品全般へ拡張される可能性が議論されるなか、輸出志向の強い日本の化学企業は製品原単位の低炭素化を前倒しで進めざるを得ません。米国では「Buy Clean」政策が連邦調達要件に組み込まれ、低炭素ポリマーやバイオベース化学品の需要が拡大しています。国内金融機関も、サステナビリティ・リンク・ローンのKPIとして製品CFP削減率を設定する事例が増え、排出管理の巧拙が資金調達条件を左右し始めました。CFPを一元管理し、削減ストーリーを明確に描ける企業は、顧客からのサプライヤー評価や投資家エンゲージメントで優位に立ちます。逆に、データ整備の遅れは将来的に市場アクセスを失うリスクとなり、企業価値を大きく損なう恐れがあります。
8.まとめ
化学産業の脱炭素移行は、エネルギー多消費産業から循環型プラットフォーマーへの構造転換を意味します。CFP算定はその羅針盤であり、排出ホットスポットを可視化することで、新原料導入、プロセス電化、リサイクル設計など多様なイノベーションを定量的に評価する基盤となります。ISO準拠の算定体系を整え、デジタルMRVでサプライチェーンを俯瞰し、科学的根拠にもとづく投資判断を下す企業こそが、低炭素社会における真のバリューチェーンリーダーとなるでしょう。
引用
IEA Chemicals
https://www.iea.org/energy-system/industry/chemicals?utm_source=chatgpt.com
Together for Sustainability (TfS)
https://www.tfs-initiative.com/app/uploads/2022/09/TfS_PCF_Guideline_2022_spreads.pdf?utm_source=chatgpt.com
EU規則 2023/956 Carbon Border Adjustment Mechanism
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj/eng?utm_source=chatgpt.com












