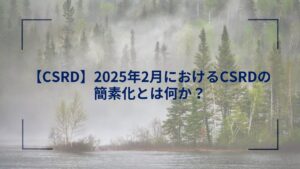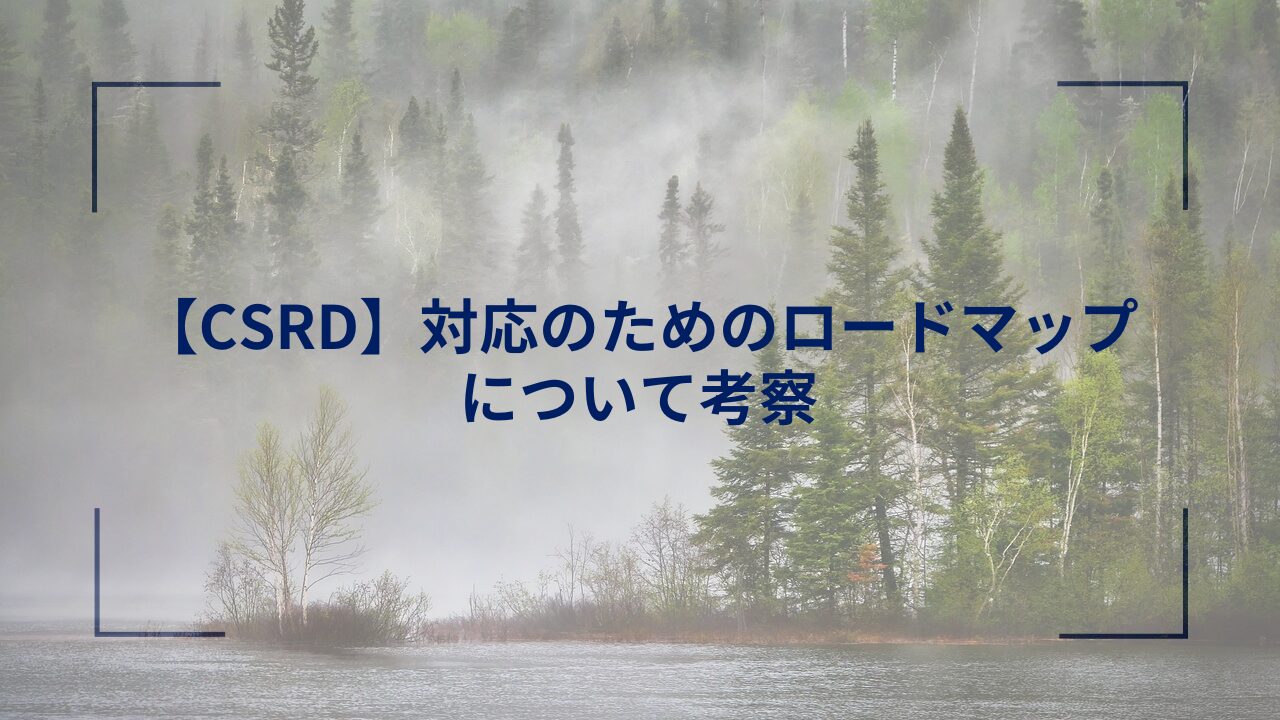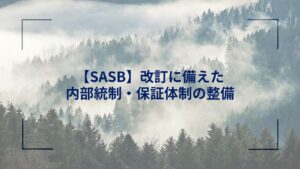CSRDでは、対象企業に対してESRSに基づいたサステナビリティ情報の開示が義務づけられ、内容は取締役会の承認や第三者保証、デジタル形式での提出を含む厳格なプロセスが求められます。開示項目はガバナンス体制やESG戦略、気候変動、人権、サプライチェーンなど幅広く、定量・定性の両面から透明性が重視されます。多くの企業が報告書作成だけでなく体制整備から対応を進めており、先行事例も注目されています。CSRDの報告義務と開示項目について解説します。
※本記事は2025年2月26日に欧州委員会から発表されたオムニバス法案より以前の内容となっています。
オムニバス法案に関しては下記記事を参照してください。
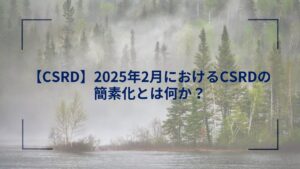


1. CSRD対応の基本ステップ
CSRDへの対応を計画的に進めるには、段階を追ったロードマップを描くことが有効です。一般的に推奨される基本ステップを以下に整理します。
適用要件の確認と社内体制整備
まずCSRDの概要と自社への適用有無・タイミングを把握します(子記事1参照)。その上で社内にプロジェクトチームや責任者を設置し、経営陣の後ろ盾を得ます。初期段階でのトップのコミットメントと全社横断チーム結成が成功の鍵です。
現状評価(ギャップ分析)
次に現在のESG情報開示状況やデータ整備状況を洗い出し、CSRD/ESRSが要求するレベルとの差を明らかにします。このギャップ分析により、追加で収集すべきデータや策定すべきポリシー類、改善すべきプロセスが見えてきます。
重要課題の特定(ダブルマテリアリティ評価)
自社にとって特に重要なサステナビリティ課題を二重の視点(財務的影響と環境・社会的影響)から評価し、優先順位を付けます。これにより報告書で重点的に記載すべきテーマが決まり、以降の作業の指針となります。
データ収集とシステム構築
必要なESGデータを集める仕組みを整えます。社内各部署やサプライヤーから情報を集約するプロセスやITシステムを構築し、定量データの算出方法を確立します。温室効果ガスや人事データなどは専門ツールの導入も検討します。
方針・目標の策定と統合
ギャップ分析と重要課題評価の結果を踏まえ、足りない企業方針や数値目標があれば新たに策定します。例えば人権方針の制定、2030年GHG削減目標の設定などです。これらを企業の既存の経営計画やサステナビリティ戦略に統合し、一貫性を持たせます。
トライアル報告とフィードバック
本番前に一度試行的に報告書ドラフトを作成してみます。実際に書いてみることで不足情報や内部プロセス上の課題が洗い出されます。外部有識者や一部ステークホルダーに意見を求め、改善点を反映します。
正式報告と監査対応
CSRD施行スケジュールに合わせ、正式なサステナビリティ報告書を作成し公開します。並行して監査人による保証業務を受け、必要な修正を経て確定版を提出します。初回提出後は監査所見や社外からのフィードバックを分析し、次サイクルへの改善に活かします。
継続的改善
以降は毎年このプロセスを繰り返しつつ、より効率的かつ高度な報告となるよう継続的に改善します。データ品質向上や社内意識定着、報告内容の戦略活用など、年々レベルアップを図ります。
以上がロードマップの全体像です。それぞれのステップで重要となるポイントを、以下のセクションで詳しく見ていきます。
2. データ収集と開示準備
データ収集はCSRD対応の中核作業です。必要な情報を漏れなく集め、正確な形で報告できるよう準備するには、以下のような取り組みが求められます。
データ項目の洗い出し
ESRSに基づき報告すべき指標をリストアップします。環境、社会、ガバナンス各分野で、自社が報告することになりそうなKPIをすべて書き出します(例:総エネルギー消費量、従業員男女比、取締役会の構成等)。このリストはかなり長くなりますが、重要テーマに絞り優先度付けも行います。
データソースと責任者の特定
各データについて社内のどの部署・システムで管理されているかを明確にします。例えば温室効果ガス排出量なら環境担当部署、従業員データは人事部、人権監査結果はサプライチェーン管理部、といったように、誰がその数字を持っているのかを特定します。その上で、報告用データをとりまとめる中央窓口(サステナビリティ部門など)に各部署が提出する流れを決めます。
データ収集プロセスの構築
実際に毎年データを集める仕組みを作ります。多くの企業ではExcelシートや専用ITツールを用いて各部からデータを集約するでしょう。可能であれば環境・CSR情報管理システムを導入し、自動集計・分析を行えるようにすると効率的です。手作業部分が多いとミスの原因になるため、極力デジタル化・自動化を検討します。
サプライチェーンからの情報取得
Scope3排出量や下請け労働者の労働環境など、自社以外からもらわないとわからない情報については、サプライヤーやパートナー企業への協力依頼が必要です。調査票の配布や契約条件への情報提供義務盛込みなどを通じて、必要データを集めます。特に複数部署・多数の取引先にまたがる場合、経営層から協力要請の通達を出すなどして全社的な協力体制を整えます。
データの品質管理
集めたデータに誤りや抜けがないかチェックします。極端な値や整合性のとれない値はないか、複数年比較で不自然な動きがないかなどを検証します。また、集計方法や計算式が標準化されているか、担当者間で解釈の齟齬がないかも確認します。品質管理には内部監査部門や第三者のレビューを活用しても良いでしょう。
データ格納と文書化
一度集めたデータは将来の参照や監査対応のため適切に保管します。どのように算出したかの算定プロセスを文書化し、後から見ても再現できるようにしておきます。例えば排出量の計算式や係数ソース、労働者集計の範囲定義などは文書化必須です。これらは保証人への説明資料としても役立ちます。
不足データへの対応計画
ギャップ分析の結果、現状では取得できていないデータについては将来取得するための計画を立てます。例えば「現行システムでは地域別のエネルギー使用量を把握できないので、次年度までにシステム改修を行う」といった計画です。これをロードマップに組み込み、担当者と期限を設定して管理します。
データ収集は初回は特に試行錯誤が多くなります。全ての数字が一度に集まらないこともしばしばです。そのため、早めに着手し、締切より十分前に一巡データを集めて問題点を洗い出すことが肝要です。
前述したようにトライアル報告で事前リハーサルを行うのも有効です。また、収集したデータを開示用フォーマットに落とし込む(開示準備)作業も重要です。単に数値を並べるだけでなく、適切なグラフや表にまとめたり、注釈を付与したり、本文記述と関連付けたりする編集作業が必要になります。これも時間がかかるため、データ担当者と報告書作成担当者が連携しながら進めます。
最後に、データは単なる報告のためだけでなく経営改善にも活用しましょう。例えばエネルギー使用量データから省エネ余地を探る、離職率データから人事施策を検討するなど、収集した情報を社内のPDCAに結び付けることで、CSRD対応の労力を有意義なものにできます。データ収集はゴールではなく、そこから得た洞察を経営にフィードバックするところまでが理想です。
3. 企業のサステナビリティ戦略との統合
CSRD対応を成功させるには、企業の既存のサステナビリティ戦略や経営戦略と統合させることが不可欠です。ただ報告書を作るだけではなく、企業活動そのものにESG視点を組み込み、戦略レベルで整合性を取る取り組みが求められます。
戦略との統合が重要な理由
一貫したメッセージ発信: 戦略と報告がずれていると、ステークホルダーに不誠実な印象を与えかねません。例えば経営計画では環境への言及がないのに報告書では環境目標を掲げる、といった齟齬があれば、実態の伴わないお題目と見なされてしまいます。統合により、社内外に一貫したサステナビリティへのコミットメントを示せます。
実効性の向上
報告だけ立派でも実際のビジネスに落とし込まれなければ意味がありません。戦略に組み込むことで、報告対象となる目標の達成に向けた社内の動き(投資判断やオペレーション改善)が進みやすくなります。経営層の関与も深まり、ESG課題への対応が会社の主要議題となります。
競争優位の創出
サステナビリティを戦略の柱に据えることで、新たな事業機会の創出やブランド価値向上につながります。CSRD対応を通じて得た知見を製品開発や市場戦略に反映すれば、単なるコストではなく価値創造の源泉とできます。報告→戦略フィードバックの好循環を作ることが望ましいでしょう。
統合の具体的な進め方
経営トップがビジョンを示すこと
例えば「当社は2030年までに業界で最もサステナブルな企業を目指す」というような高い方針を表明し、それを具体化する戦略を策定します。トップの言葉があると全社の意識づけが進みます。
既存の企業戦略との照合
現在の中期経営計画や事業戦略にESGの視点が欠けていないかチェックし、不足していれば追補します。たとえば市場拡大戦略において規制リスク評価にサステナビリティ関連規制を含める、製品戦略において環境性能向上をKPIに入れるなどです。サステナビリティ戦略そのものを明確化していない場合は、この機会に策定します。マテリアリティ評価を元に自社の重点テーマを定め、それぞれについて目標と行動計画を戦略的にまとめます。これがそのままCSRD報告の骨子にもなります。
戦略策定には主要部門の巻き込みが必要です。CSR部門や経営企画部だけで作るのではなく、事業部門・開発部門・営業部門などが集まり、自社の強みとESGを結び付けるブレインストーミングを行います。部門横断で合意した戦略であれば実行段階でも協力が得られやすくなります。社内制度・文化への浸透も図ります。戦略を作って終わりではなく、従業員への研修や社内報での周知、評価制度への組み込み(管理職KPIにESG目標を入れる等)を通じて、日常業務の意思決定にESGが組み込まれるようにします。この文化醸成が長期的には一番重要かもしれません。
統合の成果を報告に反映
戦略と統合した内容は、当然ながらCSRD報告書にも記載されます。ESRS 2で要求される「事業モデルと戦略への統合」や「ESGリスク・機会への対応状況」のセクションで、統合の成果を示すことになります。例えば「当社は事業ポートフォリオを脱炭素関連分野へ◯%シフトする戦略を採用し、今年度その一環で新製品○○を投入した」等、戦略と実績を絡めて説明できます。これはステークホルダーにも企業の本気度を伝える部分であり、統合がしっかりできていれば自然と充実した内容になるでしょう。
経営戦略と一体化したサステナビリティ対応は、規制があろうとなかろうと企業価値向上に資するものです。CSRDはそのきっかけにすぎません。長期的視点でみれば、統合された企業ほど将来の不確実性に強く、持続的成長を遂げられると考えられます。逆に統合が不十分な企業は、CSRDに限らず今後増えるであろうESG要請に振り回されかねません。ここでしっかり組み込んでおくことが賢明です。
4. 監査対応と外部報告のポイント
CSRD対応では、外部への報告および第三者監査(保証)への対応も重要なステップです。以下にそのポイントをまとめます。
外部監査(保証)への対応
監査スコープの確認
CSRDではサステナビリティ情報に対する監査(独立保証)が義務化されます。初期は限定保証で、主に「明らかな誤りがないか」「報告プロセスが適切か」を確認する範囲ですが、それでも多岐にわたる情報が対象となります。自社のどのデータが監査人のテスト対象になりそうかを想定し(主要KPIや重要開示項目は確実にチェックされます)、その準備を整えます。
監査人の選定
通常は財務監査を担当する監査法人が非財務情報の保証も引き受けるケースが多いでしょう。ただしESG分野に明るい要員がいるか確認し、必要なら専門チームを組んでもらいます。場合によっては別の認証機関(例えばISO審査員など)に依頼する選択肢もあります。どちらにせよ監査人との十分なコミュニケーションが重要です。
予備監査
初年度は特に、事前に監査人にドラフトやデータを見せてフィードバックをもらう「プレ保証」プロセスを入れることが推奨されます。そこで指摘された改善点(データ根拠の不備や説明不足など)に対応し、本番の意見不表明や除外事項を減らします。
エビデンスの整備
監査対応では裏付け資料(エビデンス)の提示が求められます。例えば環境データなら計算シートや外部計測報告書、人事データなら人事システムからの抽出記録などです。こうした証憑を事前に整理・保管し、求められたら迅速に提供できるようにします。
指摘事項への対処
監査の過程でミスや不備を指摘された場合は誠実に対処し、必要なら報告書を修正します。内部統制上の課題指摘などがあれば次回までの改善計画を策定します。限定保証段階では「適合していない部分がないか」程度のチェックですが、将来的に合理的保証になれば監査意見として明確に適否が示されます。そうなって困ることがないよう、早期から真摯に改善を続けます。
外部報告・開示のポイント
読み手を意識した構成: 報告書(開示内容)は法令遵守が第一ですが、同時に投資家や一般読者が理解しやすい構成・表現に配慮します。専門用語には説明を付け、重要なメッセージは図表やハイライトで強調します。あまりに細かい技術情報はAppendixに回すなど工夫し、メイン本文はストーリー性を持たせます。
ウェブと紙面の使い分け
欧州ではオンライン開示が主流になる見込みですが、要約版をPDFで発行したりする企業もあるでしょう。ウェブではデータをインタラクティブに見せたり、グラフを動的更新したりといった表現も可能です。自社のステークホルダーに合わせて効果的な媒体を選択します。
マルチステークホルダー対応
投資家だけでなく、従業員や取引先、地域社会など様々な利害関係者が報告書を目にします。それぞれが関心を持つポイント(例えば従業員なら働きやすさや人材投資の項目、地域社会なら地元雇用や環境影響の項目)に配慮した記述を心がけます。企業としての責任と誇りを持って書くことが大切です。
FAQの準備
公表後によくある質問に答えられるよう、想定問答や追加資料(ウェブサイトのQ&Aページ等)を用意しておきます。例えば「この目標値の根拠は?」「この指標は昨年から定義が変わったのか?」といった質問に備えます。迅速丁寧な対応は企業の信用向上につながります。
メディア発表との連動
サステナビリティ報告書の公表はプレスリリース等で周知することも検討します。特に好事例や革新的取り組みが含まれる場合はニュースとして発信し、積極的に企業イメージアップに繋げます。逆にネガティブ情報(環境事故など)が入っている場合は、その説明と再発防止策を広報で補足するなどフォローします。
初めての外部報告は「守り」を固めつつ「攻め」も意識しましょう。すなわち、不備がないことを徹底確認しつつ、自社のサステナビリティに関する強みや進捗をしっかりアピールするということです。CSRD報告書は単なるコンプライアンス文書ではなく、企業の顔として世に出るものです。監査対応で磨き上げ、読み手に響くよう工夫したレポートは、企業の評価を高め、中長期的な利益にも資する投資となるでしょう。
5. 長期的な対応計画の策定
CSRD対応は一度きりではなく継続する取り組みです。したがって、初年度の報告を乗り切った後も見据えた長期的な計画を策定しておくことが望まれます。以下の観点を盛り込んだ中長期計画を立てておきましょう。
報告プロセスの高度化
初年度で判明した課題(データ欠測、内部統制の弱点、人的リソース不足など)に対する改善策を実行し、翌年以降のプロセスを洗練させます。例えば新システム導入や組織改編、追加人材の投入などを計画に盛り込みます。数年かけて報告プロセスを成熟させ、効率的に高品質なレポートが作れる体制を目指します。
ステークホルダーエンゲージメント計画
報告と並行して、主要なステークホルダーとの対話を深めていきます。投資家とのESGに関する定期面談、地域社会との意見交換会、従業員とのタウンホールミーティングなどを計画的に実施し、そのフィードバックを次回報告や経営改善に取り入れる仕組みを作ります。
目標とKPIのアップデート
企業を取り巻く環境や自社戦略の変化に応じ、サステナビリティ目標やKPIも見直していきます。たとえば達成した目標があれば新たな目標を設定し、また規制強化に備えて基準値を引き上げることもあり得ます。常に最新の状況に合ったチャレンジングかつ実現可能な目標を維持するよう計画します。
将来の規制変化への対応
CSRD/ESRS自体の改訂や追加(セクター別基準、保証レベル強化など)に加え、他国の規制(例えば米SECの気候開示規則)や国際基準の登場にもアンテナを張ります。グローバル企業であれば、地域ごとバラバラな報告を避けるための統合戦略も必要です。将来的な報告基準の統合や二重対応の削減策などを念頭に入れ、社内の情報開示基盤を柔軟にアップデートできる計画を立てます。
人材育成と組織知の蓄積
サステナビリティ報告は専門知識が要求される分野です。社内にそのノウハウを蓄積し、人材を育成する長期計画も重要です。担当者の研修計画やジョブローテーション、ナレッジ共有の仕組みづくり(例えば社内Wikiや事例集の作成)を行い、属人化を防ぎます。外部専門家に頼っていた部分も徐々に内製化していけるよう、人員計画を立てます。
継続的改善の仕組み
PDCAサイクルを回せるよう、毎年の報告後に振り返りの場を設けます。何がうまくいき何が問題だったかを洗い出し、次年度の計画に反映します。これをルーチン化することで、年々報告プロセスと内容が改善されていきます。
予算の確保
CSRD対応には恒常的なコストが伴います。長期計画のポイントは、CSRD対応を企業の恒常業務として定着させることです。最初はプロジェクト的に始まった対応も、ゆくゆくは財務会計と同じように毎年当たり前に行われる業務になります。その段階に至れば、企業内部のリズムとしてサステナビリティ情報開示が組み込まれ、外部環境の変化にも柔軟に対処できるでしょう。
また、長期計画は経営戦略とリンクさせることも重要です。例えば5ヵ年のサステナビリティ目標を中期経営計画に盛り込み、それに沿ってCSRD報告をする、というように、経営と報告の両面で整合性を取ります。これにより社内外の理解も深まり、単独の計画よりも実現可能性が高まります。
長期的視点では「CSRD対応を超えて企業価値をどう高めるか」という発想が大切です。ただ義務をこなすだけでなく、その先にあるレピュテーション向上、顧客信頼獲得、人材採用力強化など様々な恩恵を捉え、それを最大化する戦略を描きます。CSRDはゴールではなく持続可能な企業づくりの一手段です。長期計画をもってその先の未来像を描き、そこに向けて着実に歩みを進めていきましょう。
引用
CSRD 適用対象日系企業のための ESRS 適用実務ガイダンスhttps://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/80fd13a160c18b11/20240005_01.pdf
Questions and Answers on the Adoption of European Sustainability Reporting Standards
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4043
EFRAG と CDP、欧州サステナビリティ報告基準の市場への導入を促進するための協力を発表
https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/008/667/original/CDP_Japan_PR_20231108.pdf