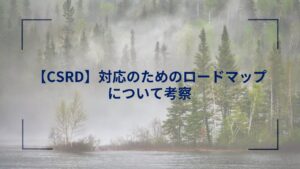CSRDでは、対象企業に対してESRSに基づいたサステナビリティ情報の開示が義務づけられ、内容は取締役会の承認や第三者保証、デジタル形式での提出を含む厳格なプロセスが求められます。開示項目はガバナンス体制やESG戦略、気候変動、人権、サプライチェーンなど幅広く、定量・定性の両面から透明性が重視されます。多くの企業が報告書作成だけでなく体制整備から対応を進めており、先行事例も注目されています。CSRDの報告義務と開示項目について解説します。
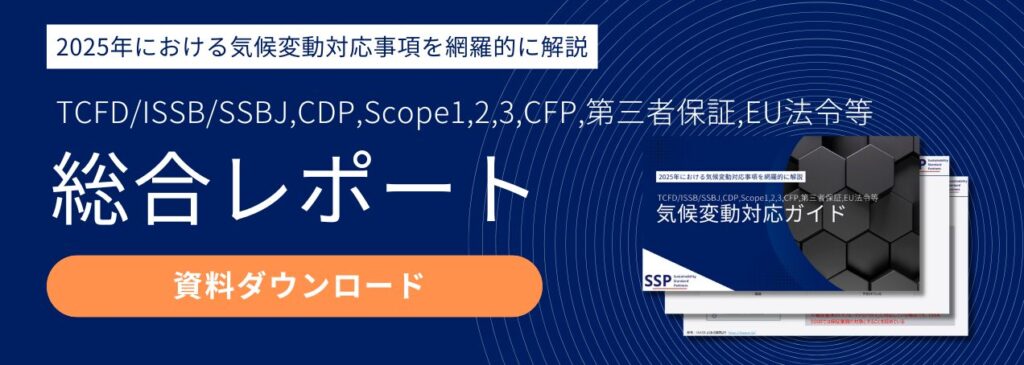
※本記事は2025年2月26日に欧州委員会から発表されたオムニバス法案より以前の内容となっています。
オムニバス法案に関しては下記記事を参照してください。
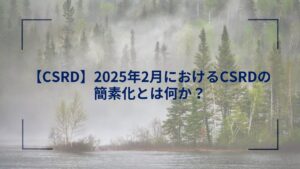
1. CSRDにおける報告義務の概要
CSRDの対象企業に課される報告義務は、単にレポートを提出するだけでなく一連のプロセス全体を包含しています。その概要は以下の通りです。
年間報告の提出
対象企業は毎会計年度ごとにサステナビリティ情報をまとめた報告書を作成し、公表しなければなりません。これは通常、財務諸表と同じタイミングで経営報告書の一部として提出されます。
ESRS準拠
報告内容はすべてEUが定めたESRS基準に沿っていなければなりません。各ESRSの開示要求事項を満たす形で情報を開示し、必要に応じてその基準名や項番も明示することが望ましいとされています。
デジタルフォーマット
報告書は電子的にタグ付けされた形式で提出します。具体的にはインラインXBRLなどの形式で、各開示項目に対応するタグ(デジタルラベル)を付して提出し、欧州単一アクセスポイント(ESAP)に蓄積されます。これにより第三者が機械的にデータを収集・比較できるようにします。
取締役会の承認
サステナビリティ報告は企業の公式開示情報として、財務報告と同様に取締役会等の承認プロセスを経る必要があります。内容については経営陣が責任を負い、虚偽や重大な欠落がないよう統制する義務があります。
第三者保証の取得
提出したサステナビリティ情報には独立した監査人または認証機関による保証を付すことが求められます。初期段階では限定保証(表面的な妥当性チェック)が義務ですが、将来的には合理的保証(かなり踏み込んだ監査)に段階的に移行予定です。保証を受けることで情報の信頼性を裏付け、ステークホルダーにとっての信頼性を確保します。
要約すると、CSRD報告義務とは「毎年、ESRSに則ったサステナビリティ情報をデジタル形式で開示し、経営としてその内容に責任を持ち、かつ監査人のチェックも受ける」という一連の流れを指しています。これは財務情報開示と同等レベルの厳格さでESG情報を扱うことを意味しており、企業にとってはかなり高度な取り組みが要求されます。
なお、CSRDでは「情報開示が困難な場合の説明責任(comply or explain)」も設けられており、例えば一部データがどうしても取得不能な場合などは、その理由を説明すれば直ちに違反とはならない余地もあります。ただしこの適用は限定的で、基本的には要求事項を充足すべく最大限努力することが前提です。
2. 開示すべきESG情報とは?
では具体的に企業は何を報告しなければならないのでしょうか。開示すべきESG情報はESRSに詳細に規定されていますが、大枠を掴むために主要なカテゴリーを整理します。
(1) ガバナンスに関する情報
企業のサステナビリティに関するガバナンス体制を開示します。具体例としては以下のような項目です。
組織内の役割分担
取締役会レベルでサステナビリティを監督する委員会や専門役員(最高サステナビリティ責任者など)がいるか、その職務内容。
内部統制と監督
サステナビリティ目標の進捗管理プロセス、経営陣への報告ライン、報酬制度へのESG目標の組み込み(役員報酬におけるESG評価指標連動など)。
企業行動と倫理
贈収賄防止やコンプライアンス研修の実施状況、ホットライン(内部通報制度)の件数と対応、データプライバシー違反の発生有無等。企業のガバナンス・倫理文化に関する広範な情報を含みます。
(2) 戦略・ビジネスモデルとサステナビリティ
企業戦略にESGがどう組み込まれているか、ESG要因がビジネスにどう影響しているかの情報です。
重要なESGリスク・機会
気候変動や規制動向、社会の価値観変化などが自社の長期戦略に及ぼす影響、およびそれに対する戦略的対応。リスクマネジメントの体制も含め報告します。
事業モデルへの統合
事業ポートフォリオやサプライチェーンにおいて持続可能性を高める取り組み(例:循環経済型のビジネスモデルへの転換、新規のグリーン事業開拓など)の状況。
シナリオ分析
特に気候関連では、将来シナリオ(例:気温上昇1.5℃シナリオ)に基づき財務影響を分析した結果を開示することが推奨・要求されています。これにより企業のレジリエンスを示します。
(3) 方針・目標・行動計画
ESGに関する企業のポリシーや数値目標、実行中のアクションを報告します。
ポリシー
環境方針、人権方針、ダイバーシティ方針など、文書化された社内ポリシーの有無と要点。
目標値
例えば「2030年までにGHG排出50%削減」「2025年までに女性管理職比率30%達成」等の定量目標。その基準年や達成状況も含めます。
実行中の施策
目標達成のための具体策(再生可能エネルギーへの切替、人権デューデリジェンスの実施、社員研修プログラムなど)と進捗。成果や課題も記載します。
パフォーマンス指標
上記施策の結果得られたKPI(例えば前年からのCO2排出削減率、事故件数の推移など)を開示し、効果を検証します。
ESRSでは、上記の方針→目標→行動→成果という流れを各テーマごとに開示することが求められます。これにより単なる数値だけでなく、背景となる考え方や取り組み内容まで含めて伝えることができます。
(4) 環境(Environment)に関する情報
環境分野では気候変動を筆頭に以下の領域で定量データと定性情報を報告します。
気候変動
温室効果ガス排出量(Scope1,2,3すべて)、気候関連リスク・機会、ネットゼロ戦略など。
汚染
大気汚染物質(NOx, SOx, PM等)や水質汚濁物質の排出量、廃棄物の不法投棄有無、環境関連の法令違反や罰金の件数。
水・海洋資源
総水使用量、水ストレス地域での使用割合、排水の水質、海洋への廃棄物排出有無。
生物多様性
自社施設が重要生態系に与える影響(立地が保護地域内か否か等)、生物多様性保全の取り組み(植林や生態系復元プロジェクト等)。
資源利用と循環
原材料使用量、再生素材の比率、廃棄物発生量とリサイクル率、製品の寿命やリユースの促進策など。
環境データは数値計測が必要なものが多く、かつ報告範囲(自社だけでなくサプライチェーン全体まで)も広がるため準備に時間を要します。特に温室効果ガスのScope3排出はサプライヤーや製品使用者から情報を集める必要があり、多くの企業にとって対応のボトルネックとなるでしょう。
(5) 社会(Social)に関する情報
社会分野では主に人に関する情報を扱います。社内・社外のステークホルダーごとに次の観点があります。
自社の従業員
従業員の多様性(ジェンダー、人種、年齢構成等)、採用・離職率、労働条件(平均賃金、男女間賃金差)、労働安全衛生(労災件数、過労対策)、従業員エンゲージメント(満足度調査結果)など。従業員が働きがいを持てる職場か、公平な待遇かを示す指標群です。
バリューチェーン上の労働者
サプライチェーンの工場労働者や下請け労働者に関する人権尊重状況。例えばサプライヤー監査数と結果、重大な労働搾取の発見事例と是正措置、サプライヤー向け行動規範の浸透状況など。
コミュニティ
事業所周辺や進出先の地域社会との関係性。住民への環境・社会影響評価結果(環境影響評価や社会影響評価を実施した場合はその概要)、地域社会への貢献(雇用創出、社会貢献活動、慈善寄付額など)を開示します。
消費者・顧客
製品やサービスが消費者に与える影響。安全性クレームの件数と対応、製品リコール情報、カスタマーサポート指標、消費者プライバシー保護への取り組みなど。BtoC企業では特に重要です。
(6) その他
上記に含まれない特殊な項目もESRSにはあります。例えば税務情報(各国別の納税額やタックスポリシー)や、研究開発投資のサステナビリティ関連比率など、一見ESGに直接関係しないような事項も含まれています。これらはガバナンスの一環として透明性向上を目的に要求されるものです。
総じて、CSRD/ESRSが求める情報は「企業がサステナビリティ上どのような影響を受け・与え・対処しているか」を定性的ストーリーと定量的エビデンスの両面から示すものと言えます。単なるポリシー宣言や目標掲示だけでなく、その実施結果を示す数字や具体例を併せて報告することで、信頼性の高い開示となります。
3. 具体的な開示フォーマットと要求
CSRDの報告はフォーマット(形式)にも一定のルールがあります。重要なポイントを挙げます。
経営報告書内に統合
サステナビリティ報告書は財務諸表とは別冊にする必要はなく、経営報告(マネジメントレポート)の一部として含めます。つまり年次報告書の中に「サステナビリティに関する記述」がセクションとして組み込まれるイメージです。これはESG情報を財務情報と切り離さず一体として扱う趣旨です。
デジタルタグ付け
前述のとおり、報告内容にはXBRLタグを付して提出する必要があります。欧州当局はこれに対応する「サステナビリティ報告タクソノミー(項目体系)」を定めており、各企業はそれに従い項目ごとに正確なタグ付けを行います。これにより提出後に情報がデータベースに整理・格納されます。
項目ごとの構成
ESRSの各Disclosure Requirementごとに情報をまとめる構成が推奨されます。例えばESRS E1-6(スコープ1,2,3排出量の開示)という要求事項に対し、その箇所で必要な数値や注記をまとめて記載します。こうすることで読み手(監査人や投資家)が必要な情報を見つけやすくなります。
比較情報の提示
財務情報と同様、前年(前期)との比較値を可能な限り載せます。例えば排出量や従業員数などは前年との差異も示し、トレンドがわかるようにします。また進捗を示すため、基準年(ベースライン)との比較も重要です。
注記と説明
定量データにはその算定方法や前提条件を注記で補足します。例えばGHG排出なら算定範囲(組織境界)、使用したプロトコル(GHGプロトコル等)、不確実性や見積りの方法を明記します。労働者数なら集計日や定義(フルタイム換算かヘッドカウントか)などを示します。こうした透明性がESRSで求められます。
言語と掲載媒体
CSRD報告は各国語で行われますが、EU域外投資家向けに英語版を併載する企業も多いでしょう。電子的には企業ウェブサイトや年次報告サイトで公開します。欧州単一アクセスポイントにも集約される予定なので、ステークホルダーはそこから横断検索も可能になります。
開示の有無判断
マテリアリティ評価の結果「当社にはこの項目は非該当」と判断した事項も、その判断を下した根拠を簡潔に示す必要があります(完全に黙殺は不可)。例えば「当社は海洋事業を持たないためESRS E3(水・海洋)は重要ではないと評価しました」と記述するといった対応です。
将来目標の開示
数値目標を掲げている場合は、その達成期限や途中経過も開示し続ける必要があります。2025年以降は特に2050年ネットゼロ目標など長期目標への言及が企業に広く求められます。
形式的要求は技術的な内容も多いですが、企業は少なくとも「ESRSごとの要求事項をすべて網羅しているか」と「データに必要な注記説明が付されているか」の2点について、自社のドラフト報告書をチェックすることが重要です。これは財務報告書で脚注や注記をきちんと付ける作業に似ています。将来的に各種テンプレートやITツールが整備され、これらの作業をサポートしてくれることも期待されます。
4. 情報開示のプロセスとチェックポイント
CSRD対応の情報開示は、一度報告書を書いて終わりではなく、その前後に多くのプロセス上の検討と確認が必要です。開示プロセスとチェックすべきポイントを時系列で追ってみましょう。
(a) 準備段階
マテリアリティ評価
まず前提としてダブルマテリアリティ評価を実施し、自社が詳細開示すべきテーマと簡略で済むテーマを仕分けます(子記事1および子記事4参照)。これが曖昧だと、後工程で「何をどこまで書くか」が定まらず迷走します。
データガバナンスの確立
開示に必要な各種データのソースを洗い出し、収集方法と責任者を明確にします。例えばGHG排出量は環境部が算定、人事関連は人事部が提供、といった具合に担当部門を決めます。同時にデータの信頼性を確保するため、計算方法の標準化や内部レビュー体制も設けます。
スケジュール策定
初稿作成から経営層レビュー、監査人チェック、最終版公開までの社内スケジュールを逆算で引きます。特に初年度は時間が読めない部分も多いため、余裕を持った計画とし、途中でのトラブル(データ遅延等)にも対応できるクッション期間を設けます。
(b) 原稿作成段階
チェックリストの活用
ESRSの要求事項を箇条書きにしたチェックリストを作り、各項目に対応する記述や数値が報告書ドラフトに含まれているか逐一確認します。複数名でクロスチェックするなど、漏れ防止に努めます。
データ検証
集めたデータが妥当か再確認します。異常値がないか、前年との差異は説明可能か、外部公開に耐える品質か、といった視点です。必要なら追加調査や計算ミス修正を行います。将来的な保証対応も見据え、エビデンス(元データや計算シート)はきちんと保存しておきます。
記述内容のバランス
定性的記述(戦略や方針の説明など)は、一方的な宣伝や抽象論に偏らず、具体例やデータに裏付けされた内容にします。良いことだけでなく課題や今後の改善点も正直に記載することで、信頼度の高いレポートになります。グリーンウォッシュと捉えられないよう注意が必要です。
社内レビュー
作成したドラフトを関連部署や経営陣でレビューします。財務報告と矛盾していないか、法務観点で問題ないか、などのチェックも行います。特に重大な将来計画等を書く際は開示の適切性について法務部と相談することもあります。
(c) 監査・承認段階
第三者保証の事前準備
監査人(保証提供者)にドラフトを共有し、予備的な見解をもらいます。初年度は不備を指摘される箇所も多いかもしれませんが、早めに把握して修正します。特にデータのトレーサビリティ(追跡可能性)や計算方法の妥当性については質問を想定しておきます。
経営陣の承認
取締役会または経営会議で最終報告案を承認します。ここでは報告内容が企業戦略と矛盾しないか、リスクとなる情報の開示レベルは適切か(秘匿すべき企業機密との境界)など高次の視点でチェックが入ります。必要に応じて微調整し、最終決定します。
(d) 公表後
ステークホルダーからのフィードバック収集: 公開したESG情報に対し、投資家やNGO等から質問や反応がある場合は真摯に対応します。次回報告の改善点として活かすため、どの部分が関心を引いたか、何が不足していたかを分析します。
継続的なモニタリング
開示したKPIは次年度以降もフォローしていく必要があります。例えば「事故ゼロ目標」を掲げたなら、達成に向けた進展を四半期ごとに社内モニタリングするなど、年次報告待たず管理を継続します。これにより、報告が実効性あるマネジメントツールとなります。
最新基準への対応
規制や基準の改訂があれば早期にキャッチアップします。例えば新しいガイダンス文書やQ&AがEFRAGや当局から出た場合、それに沿って自社の報告計画を修正していきます。
以上のプロセスを踏む中でのチェックポイントとして特に重要なのは、「データの完全性(漏れや誤りがないか)」「説明の正確性(誇張や矛盾がないか)」「マテリアリティとの一貫性(重要な事柄に焦点が当たっているか)」の3点です。これらを社内外の目で多角的にチェックすることで、CSRD報告のクオリティを担保することができます。
5. CSRD対応企業の事例
CSRD報告の義務は2025年以降本格化しますが、それに先立ち欧州の先進企業の中には早くもCSRDを見据えた報告を始めている例があります。ここではいくつか事例を紹介します。
事例1
フランスの大手企業 – フランスはもともと企業の非財務情報開示義務(Grenelle II法など)が厳しく、CSRDに通じる報告を先行して行ってきました。そのためフランス籍の多くの大企業は、2022~2023年の年次報告でESRSドラフトに沿った情報開示を試みています。ある調査によれば、フランス企業は他国に先駆けCSRD準拠報告を開始しているとされます。例えばエネルギー企業トタルエナジーズや銀行BNPパリバは、TCFDレポートやGRI報告を充実させつつCSRD対応に備えています。
事例2
デンマークのIT企業 – 欧州の一部企業はCSRD対応をビジネスチャンスと捉え、積極的に情報開示を強化しています。デンマークのIT企業NetcompanyはCSRD要求事項に基づくダブルマテリアリティ評価や戦略統合のプロセスを年次報告書で詳細に説明し、他社のベンチマークとなりました。このように自社の取り組みをあえて詳述することで、ステークホルダーへの説明責任を果たすだけでなく社内意識も高めています。
事例3
多国籍メーカー(日本企業の例) – 日本企業でも欧州に子会社を持つ場合、いち早くCSRD準拠を視野に入れた報告を始めています。例えばトヨタ自動車は2023年の統合報告書で欧州タクソノミー開示を行い、今後のCSRD対応に備える姿勢を示しました。また日立製作所もTCFDやGRI報告を拡充し、ダブルマテリアリティを導入したマテリアリティマトリクスを公開するなど、CSRDを意識した情報開示強化を行っています。こうした取り組みはCSRD直接対象でなくとも、グローバル企業としての透明性向上に寄与しています。
先行企業の共通点として、いずれも「トップマネジメントのコミットメント」が強いことが挙げられます。CEOや取締役会が主導してサステナビリティ戦略を策定・発信し、その一環として報告充実が図られています。また、単にコンプライアンスとしてではなく「ステークホルダーとの対話ツール」と位置づけている点も共通しています。CSRD報告を攻めの経営に活かそうという姿勢がうかがえます。
もっとも、多くの企業にとってCSRD対応は未知の領域であり、試行錯誤が続くでしょう。初年度は「まずは出してみて、次年度以降ブラッシュアップ」というケースも多いはずです。その際、上述の先行事例を参考にしながら、自社らしい報告スタイルを模索していくことが大切です。他社の良い点は積極的に取り入れ、逆に自社ならではの独創的な情報発信も織り交ぜることで、単なる義務に留まらない価値あるサステナビリティ報告を実現していきましょう。
引用
CSRD 適用対象日系企業のための ESRS 適用実務ガイダンスhttps://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/80fd13a160c18b11/20240005_01.pdf
Questions and Answers on the Adoption of European Sustainability Reporting Standards
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4043
EFRAG と CDP、欧州サステナビリティ報告基準の市場への導入を促進するための協力を発表https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/008/667/original/CDP_Japan_PR_20231108.pdf