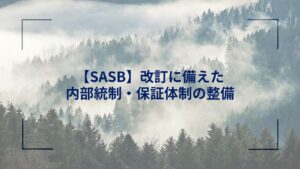ESRS(欧州サステナビリティ報告基準)は、CSRDに基づき企業がESG情報をどのように報告すべきかを詳細に定めた義務的な基準です。全企業共通の横断基準と、環境・社会・ガバナンスのテーマ別10基準から成り、ダブルマテリアリティに基づいた開示を求めます。報告項目は温室効果ガス排出量、従業員の多様性、人権デューデリジェンスなど多岐にわたり、今後はセクター別基準の策定や技術連携も進む見込みです。ESRSの概要とその重要性について解説します。
※本記事は2025年2月26日に欧州委員会から発表されたオムニバス法案より以前の内容となっています。
オムニバス法案に関しては下記記事を参照してください。
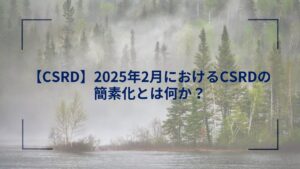


1. ESRSとは?
ESRS(European Sustainability Reporting Standards)は、前述のCSRDに基づき企業が開示すべきサステナビリティ情報の内容と形式を定めた詳細基準です。簡単に言えば「CSRD対応の教科書」のようなもので、企業はこのESRSに従ってサステナビリティ報告書を作成する義務があります。ESRSはEUの独立機関であるEFRAG(欧州財務報告諮問グループ)によって起案され、2023年7月に欧州委員会が初版を採択、同年12月に官報公示され正式に発効しました。ESRS策定の目的は、企業のESG情報開示項目を標準化し、企業間で比較可能かつ網羅的な報告を実現することです。この基準はEUの政策目標(例:パリ協定目標や欧州グリーンディール)に即しており、既存の国際的枠組み(GRI、SASB、TCFD、ISSB基準など)の要素も取り入れながらEU独自の要求事項を盛り込んでいます。結果として、ESRSは現時点で世界で最も包括的かつ詳細なサステナビリティ報告基準の一つとなっています。
ESRSの義務性
ESRSはCSRDの下で法的拘束力を持つ基準です。企業にとってはガイドラインではなく「守らねばならないルール」であり、金融報告におけるIFRS(国際会計基準)や各国会計基準と同様に、遵守しなければ罰則の可能性もあります。これは従来のGRIスタンダードや統合報告フレームワークなど任意基準とは大きく異なる点です。したがってCSRD対象企業は、社内にESRSの知見を十分に取り入れ、自社報告書がESRS要件を満たしていることを確認する必要があります。
2. ESRSの基本構造
ESRSは全体で12本の基準から構成されています。大きく分けると横断的な2基準と、トピック別の10基準です。
横断的基準(クロスカッティング基準)
ESRS 1「一般的原則(General Requirements)」とESRS 2「一般的開示事項(General Disclosures)」の2つです。
ESRS 1は報告全般の原則を定めます。ダブルマテリアリティの考え方や報告境界(どこまでの範囲を報告対象に含めるか)、情報の質特性(正確性・網羅性・タイムリーさ等)についてのガイダンスを提供します。いわば「報告の前提条件」のような内容です。
ESRS 2は全企業共通で開示が求められる事項を定めます。例えばガバナンス体制(サステナビリティ担当役員の設置状況等)、事業モデルとサステナビリティ戦略の概要、主要なリスク・機会の記述、方針・目標・アクションプランの有無など、企業の状況を包括的に報告させる項目です。ESRS 2の多くは全企業必須の開示事項となっています(マテリアリティに関係なく報告が要求される項目が多い)。
トピック別基準(テーマ別基準)
残りの10本がこれに該当し、環境(Environment)5本、社会(Social)4本、ガバナンス(Governance)1本の計10テーマです。
環境(E)
・ESRS E1 – 気候変動
・ESRS E2 – 汚染(大気・土壌・水等の汚染)
・ESRS E3 – 水と海洋資源
・ESRS E4 – 生物多様性と生態系
・ESRS E5 – 資源利用と循環経済
社会(S)
・6. ESRS S1 – 自社の従業員
・7. ESRS S2 – バリューチェーン上の労働者(サプライヤー等)
・8. ESRS S3 – 影響を受けるコミュニティ(地域社会)
・9. ESRS S4 – 消費者とエンドユーザー
ガバナンス(G)
・10. ESRS G1 – ビジネス行動(企業の行動倫理・企業文化)
各トピック基準はそれぞれの領域で企業が開示すべき具体的事項を定めています。例えば、ESRS E1(気候変動)では温室効果ガス排出量(スコープ1,2,3)の開示、気候関連リスクと機会の定量・定性情報、1.5℃目標に向けた移行計画の有無などが含まれます。
ESRS S1(自社の従業員)では多様性・包括性指標(女性管理職比率等)、従業員エンゲージメント、労働安全衛生指標などを報告することになります。ESRS G1(ビジネス行動)では腐敗防止方針の有無、贈収賄事件の件数、サプライチェーンにおける倫理監査状況などが対象です。クロスカッティング2基準は全企業が必須報告しますが、トピック別10基準については自社のマテリアリティ評価結果に応じて、重要と判断したテーマに限り詳細開示する運用となります。
例えば製造業で気候変動や労働安全は重要だが生物多様性は直接の事業インパクトが小さい場合、ESRS E1やS1は詳細開示し、E4は該当なしとして簡略化できる、という具合です(ただし「重要でない」判断の根拠自体も開示が必要)。このようにマテリアリティに応じた適用を行いつつ、最低限の共通項目は全社報告させる構造になっています。
3. ESRSの主要な開示項目
ESRS各基準には多数の具体的開示項目が定義されていますが、その中でも横断的に重要な項目や多くの企業に共通する主要項目をいくつか紹介します。
ガバナンスと組織体制(ESRS 2)
サステナビリティに関する取締役会の監督体制(委員会の設置状況、役割)、経営陣の責任分担、報告ラインや社内統制の仕組みなど。これはすべての企業に共通して求められる情報であり、サステナビリティが経営にどの程度組み込まれているかを示す重要指標です。
戦略とビジネスモデルへの統合(ESRS 2)
サステナビリティ課題が企業の戦略・ビジネスモデルにどう影響し、どう対応しているかの説明。例えば気候変動が事業リスクとなっている場合の戦略対応や、社会課題を新規事業機会としている例などを記述します。企業の長期ビジョンとサステナビリティの関連性が問われます。
ポリシーと目標設定(ESRS 2)
各重要テーマごとに企業が持つ方針(例:人権方針、環境方針)と定量目標(例:2030年までのCO2削減◯%)の有無と内容の開示。目標がある場合は進捗も報告し、ない場合はその理由説明(MDR: 最低開示要求)が必要です。
温室効果ガス(GHG)排出量(ESRS E1)
Scope1(直接排出)、Scope2(エネルギー起源間接排出)、Scope3(バリューチェーン排出)の算定結果を報告。さらにネットゼロ目標やカーボンプライシングも開示対象で、2025年以降はパリ協定整合の移行計画(2050年ネットゼロ戦略)の策定・開示が事実上義務となります。
気候関連リスク・機会(ESRS E1)
TCFDに沿った形で、気候変動が事業にもたらすリスク(物理的リスク、移行リスク)とビジネス機会、およびそれに対する対応を質的・定量的に報告します。シナリオ分析の実施状況やリスク管理プロセスも含まれます。
その他環境指標(ESRS E2-E5)
分野ごとに、例として汚染では大気汚染物質や水質汚染物質の排出量、環境罰金の件数等。水資源では水使用量や水ストレス地域での使用割合。生物多様性では重要生態系への影響や土地利用。資源循環では廃棄物発生量やリサイクル率など。それぞれの業務に関連する定量データと管理策を報告します。
労働(自社従業員)指標(ESRS S1)
従業員数の属性(雇用形態、地域別、男女別等)、多様性指標(ジェンダーバランス、管理職に占める女性割合など)、従業員エンゲージメントスコア、離職率、労災発生率、技能訓練への投資など、人材に関する幅広いKPIを報告します。また公正な待遇に関する方針(例:男女同一賃金方針)や労使関係、労働慣行に関する情報も含まれます。
人権とサプライチェーン(ESRS S2-S4)
自社のバリューチェーン全体での人権デューデリジェンス状況を開示します。サプライヤー監査の実施件数や結果、重大な人権リスク(児童労働・強制労働など)の特定と対策、コミュニティへの影響評価、顧客からの安全性クレーム件数など、ステークホルダー別に情報を提供します。
ビジネス行動・倫理(ESRS G1)
贈収賄や汚職防止のコンプライアンス体制、企業倫理に関する研修実施状況、税務戦略の開示、政治献金の額、データプライバシー侵害件数など、企業行動の公正さ・透明性に関わる指標が報告されます。
以上のようにESRSの開示項目はきわめて広範囲に及びます。合計で1,000を超える個別のデータポイントがあるとも言われ、企業は自社に該当する項目について漏れなく情報を収集・整理する必要があります。ただし前述の通り、すべての企業が全項目を網羅する必要はなく、自社にとって「重要と判断されたテーマ」に関する項目を中心に詳細報告すればよい仕組みです(重要でないテーマについては簡潔な説明で済ませることが可能)。もっとも、気候変動や自社従業員等、多くの企業に共通して重要性が高いテーマについては結局ほとんどの企業がかなりの部分を開示することになるでしょう。
4. CSRDとの関係
ESRSとCSRDの関係は切っても切れません。CSRDは法令として「何を報告すべきか」を定め、ESRSはその詳細ルールを具体化しているという関係にあります。CSRDの条文上でも「欧州サステナビリティ報告基準に従って情報開示しなければならない」と明記されており、ESRSはCSRD指令の実施基準そのものです。したがって、CSRDに対応する=ESRSに準拠した報告書を作成すること、と言い換えられます。このようにESRSはCSRDコンプライアンスのための必須条件ですが、逆に言えばESRSに沿って報告していればCSRD違反にはならないとも言えます。
実務上は、各企業がESRS各基準の要求事項を一つ一つチェックリスト化し、自社の報告書ドラフトがそれらを満たしているか検証する作業が必要になるでしょう。その意味でESRSは企業にとっての遵守すべきチェック項目のリストと位置づけられます。また、ESRSは上述の通り他の主要な報告フレームワークとの対応関係が考慮されています。CSRD対応を進める企業は、これまで任意で行ってきたGRIスタンダードによる報告やTCFD提言に基づく気候情報開示との共通点・相違点を把握しておくことが重要です。例えば気候関連ではTCFDとESRS E1がほぼ整合していますし、人権では国連のビジネスと人権指導原則がベースになっています。
一方でEU独自色が強いのは「ダブルマテリアリティ」の適用範囲や、「欧州グリーンディール政策との紐付け」(EUタクソノミーとの関連開示など)です。このような違いも踏まえつつ、既存の報告プロセスをCSRD/ESRS対応にアップデートすることが求められます。
5. 今後の規制動向
ESRSは一度で完成形というわけではなく、今後も拡張・改訂が予定された“進化する基準”です。企業として押さえておきたい今後の動向をいくつか挙げます。
セクター別ESRSの策定
現在公表されているESRSは全セクター共通の一般基準ですが、CSRD指令では金融業、石油・ガス、鉱業、農業など特定セクター向けの詳細基準を開発することが規定されています。EFRAGは2024年以降、これらセクター別基準のドラフトを順次公開し、意見公募を経て採択される見込みです。当初のCSRDスケジュールでは2024年6月までに第二弾の基準を策定予定でしたが、一部延期が決まっており、実施は2026年頃になる可能性があります。企業は自社業界に該当する基準が出てくるか注視が必要です。
SME向け簡易基準の策定
上場中小企業(SME)はCSRD適用を2年間猶予されますが、その間に簡易版のESRSが用意される予定です。規模の小さい企業でも対応できるよう、開示項目を絞り込んだプロポーショネートな基準になると見られています。ただし現時点では詳細未定であり、SMEも最終的には大企業と同様のテーマについて開示が求められる方向です。
他国・地域での採用
EU域外企業向けに、EU基準に相当する報告を行えばCSRD要件を満たしたと見なす制度も検討されています。例えば、ISSB基準や米国SECルールなど他の枠組みとの「同等性」が認められれば、二重報告を避けることができます。2024年10月には欧州委員会が第三国基準の採用期限を延長する方針を示しており、じっくり他基準との比較検討を行う姿勢です。将来的に「IFRSサステナビリティ基準 + 補足情報」でCSRD要件を代替できる、といった仕組みになる可能性もあります。
定期的な改訂
ESRSは実施状況やフィードバックを踏まえ、数年ごとに改訂されることが見込まれます。初回適用後に企業や投資家から上がった意見を反映し、開示項目の追加・削減や定義の明確化などが行われるでしょう。例えば、現在ガバナンス領域はG1のみですが、将来的に取締役会の構成や報酬に関する基準が増える可能性もあります。
デジタル技術との連携
EUは企業の開示データを収集・活用するための「欧州単一アクセスポイント(ESAP)」構想を進めています。ESRSに従って報告されたデータはインラインXBRL形式でタグ付けされ、デジタルに読み取られるため、AIやビッグデータ解析により横断的な分析が可能となります。将来的にはESGデータプラットフォームを通じてリアルタイムに企業比較やリスク分析が行われることも想定されます。企業はこうした技術動向も視野に入れ、データ品質や即時性の向上に努める必要があります。
以上のように、ESRSを取り巻く環境はこれからも動的に変化します。企業は最新情報をウォッチしつつ、自社の報告手法を随時アップデートしていく体制を整えることが求められます。「ESRSを一度対応すれば終わり」ではなく、継続的にベストプラクティスを学び取り入れていく姿勢が重要です。
引用
EU CSRD
https://commission.europa.eu/publications_en
Corporate sustainability reporting
https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
European Commission – Infringements decisions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_24_4661/INF_24_4661_EN.pdf