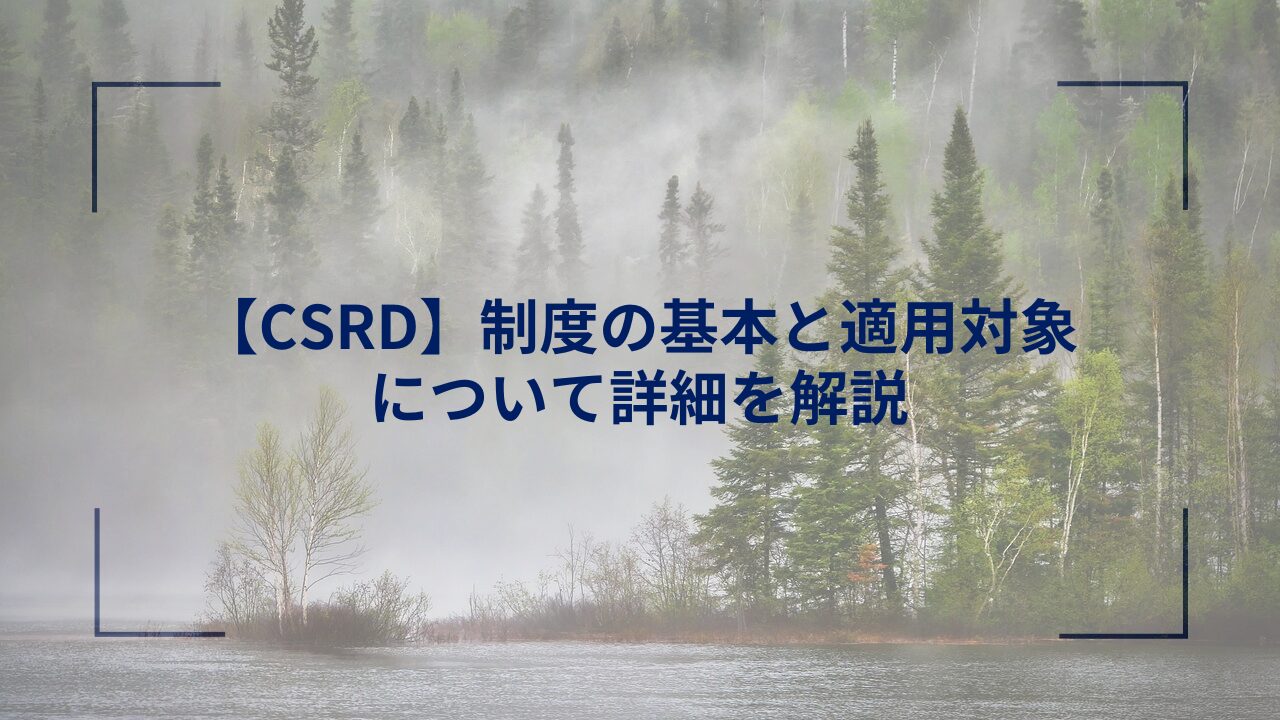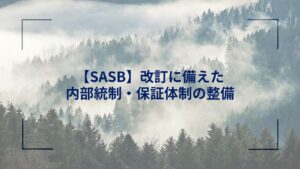CSRD(企業サステナビリティ報告指令)は、EUが策定した企業に対するサステナビリティ情報開示の義務化制度です。従来のNFRDより開示基準を詳細化し、情報の比較可能性と信頼性を高めることを目的としています。対象企業はEU域内外の大企業や上場企業で、財務影響と社会・環境への影響をともに報告する「ダブルマテリアリティ」が特徴です。業種や規模を問わず幅広い企業に影響を及ぼし、サステナブル経営への転換が求められます。CSRDの基本と適用対象について解説します。
※本記事は2025年2月26日に欧州委員会から発表されたオムニバス法案より以前の内容となっています。
オムニバス法案に関しては下記記事を参照してください。
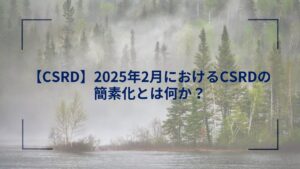


1. CSRDとは?
CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive)は、EUが制定した企業のサステナビリティ情報の開示を義務付ける指令です。2022年に欧州議会・理事会で採択され、2023年1月に発効しました。従来の非財務情報開示指令(NFRD)をアップデートする形で導入され、従来以上に詳細で網羅的なESG情報の報告を企業に求めています。CSRD導入の背景には、近年の気候変動対策や社会課題への対応強化に向けた欧州グリーンディールやサステナブルファイナンス戦略の一環という位置づけがあります。企業による環境・社会へのインパクト情報を透明化し、資本市場や消費者の判断に活用することで、持続可能な経済への移行を促す狙いがあります。
またNFRDでは情報開示企業が限定的で比較可能性にも課題があったため、そのギャップを埋めるべく対象企業の拡大と開示基準の詳細化が図られました。CSRDは法的拘束力のあるEU指令として加盟各国に実施が義務付けられており、対象企業はこの指令に従ったサステナビリティ報告を行わなければなりません。この報告にはダブルマテリアリティの考え方が組み込まれており、企業は「自社の財務に与えるサステナビリティ要因の影響」と「自社の事業が環境・社会に与える影響」の両方を評価して開示する必要があります。この点が、投資家向け情報に重きを置いていた従来の枠組みとの差別化要素となっています。
2. CSRDの目的と背景
CSRDが導入された目的は大きく分けて2つあります。一つは情報の質と比較可能性の向上、もう一つは対象範囲の拡大によるインパクトの増大です。
まず情報面では、従来のNFRDでは開示項目が概括的で企業間比較が難しいという課題がありました。CSRDではこれを受け、詳細な報告基準(ESRS)の下で統一フォーマットによる開示を求めることで、情報の信頼性・一貫性を高めようとしています。具体的には気候変動リスクや温室効果ガス排出量、社員の多様性、人権デューデリジェンスの状況など、ステークホルダーが知りたい具体的指標を網羅的に報告させることで、企業のESGパフォーマンスを適切に評価可能にする狙いがあります。
次に範囲面では、対象企業数の大幅拡大が図られました。NFRDの対象は主にEUの上場大企業(約11,700社)に限られていましたが、CSRDでは非上場の大企業や上場中小企業、さらにEU域内で一定以上事業を行う域外国企業まで含め、対象が約50,000社に増える見込みです。これによりEU経済全体のすそ野でサステナビリティ情報開示が進み、より多くの投資家・消費者に情報が行き渡るようになります。また企業間で「自社だけが開示していると不利」といった不満が出ないよう、競争条件の公平化(レベルプレイングフィールド)にも寄与する面があります。背景として、欧州グリーンディールの目標達成(2050年カーボンニュートラル等)のためには企業の協力が不可欠であり、その進捗を測るものさしとして企業報告の拡充が求められていました。さらに金融市場においてもESG情報開示は重要性を増しており、EUのタクソノミー規則(グリーン投資の判定基準)やSFDR(金融機関のサステナビリティ開示規則)とも連動して、CSRDはサステナブル投資を下支えする役割を担います。
このように政策・市場双方の要請を受けてCSRDは策定され、2020年代半ばにかけて段階的に実施に移されているのです。
3. 適用対象となる企業とは?
CSRDの適用対象(報告義務を負う企業)は、EU域内企業とEU域外企業に分けてそれぞれ定義されています。EU域内の企業: 基本的には大規模企業および上場企業が対象です。EUの会計指令上、「大規模企業」と分類されるには以下の3基準のうち2つ以上を満たす必要があります。
総資産:2500万ユーロ超(約25億円超)
売上高:5000万ユーロ超(約50億円超)
従業員:250名超
これらは従来より厳しい基準となっており(NFRD時は2000万ユーロ・4000万ユーロ・500名超でした)、未上場の大企業も含めて幅広くカバーします。加えて、EUの規制市場に上場している企業(株式や社債を上場している企業)は中小企業であっても原則CSRDの対象です。ただし上場企業のうちマイクロ企業は除外されます。マイクロ企業とは従業員10名以下・売上高70万ユーロ以下・資産35万ユーロ以下という非常に小規模な企業です。EU域外の企業: 本社がEUの外にある企業(たとえば日本企業や米国企業)でも、EU内で相当規模の経済活動を行っている場合にはCSRDの報告義務が課されます。具体的には、「EU域内での年間売上高が1.5億ユーロ(約200億円)超」という条件を満たす企業で、さらに次のいずれかに該当する場合です。
EU内にCSRD基準での大規模企業に該当する子会社を持つ
EU内に売上高4000万ユーロ超の支店(ブランチ)を持つ
EUの証券市場に上場している
例えば、日本に本社があるメーカーでも、EUに大きな子会社がありEU売上が1.5億ユーロを超えていればCSRD報告が必要となる可能性があります。このようにEU域外企業にも間口を広げることで、グローバルに事業展開する大企業は逃れることなく規制網に含める狙いがあります。
以上をまとめると、「大きな会社」はたとえ非上場でも対象、「上場会社」はたとえ小さくても(マイクロ規模除き)対象、さらに「EUで大きく稼ぐ海外企業」も対象、というのがCSRDの適用範囲です。結果として金融・製造・サービス問わず多様な業種の企業が含まれます。特定の業界だけがターゲットではなく、持続可能性はすべての企業に求められるとのEUのメッセージが現れています。
4. 影響を受ける業種と規模要件
CSRDは全業種横断的な規則ですが、特に環境・社会への影響が大きい業種やグローバル企業はその影響が顕著です。いくつか具体例を挙げます。
エネルギー・資源産業
石油・ガス、鉱業、化学などの業種は環境負荷が大きく、開示すべき情報(温室効果ガス排出量や環境影響評価等)が膨大です。またこれらの業種にはセクター別ESRS基準が今後追加策定される予定で、一層詳細な報告が求められる可能性があります。
製造業・自動車
バリューチェーンが広範囲に及ぶ製造業は、自社だけでなくサプライヤーや製品使用段階での環境社会影響も報告対象となります(Scope3排出量等)。自動車産業などでは各部品メーカーまで含めた情報収集が必要になるでしょう。
金融機関
銀行・保険・資産運用会社など金融業は、自らの環境フットプリントだけでなく融資・投資先のサステナビリティまで情報開示が求められます(いわゆる「間接的な影響」)。EUタクソノミーとの関係も深く、報告の複雑さが増しています。
小売・消費財
ブランド力が重要な業種では、CSRD報告によって企業の社会的責任への取り組みが消費者に可視化されます。労働者の人権やサプライチェーン上の労働環境など社会面の開示項目が多く、対応が求められます。
情報通信・IT
直接の環境負荷は製造業等より低く見えるかもしれませんが、データセンターのエネルギー消費や電子廃棄物、プライバシー・AI倫理といったガバナンス課題まで幅広く問われます。大規模IT企業も対象となるため無視できません。
規模要件に関しては前節で述べたとおりですが、自社が基準をわずかに下回っている場合でも油断は禁物です。例えば従業員数や売上高が250人・5,000万ユーロに近い中堅企業は、事業拡大やグループ再編によって将来的にCSRD適用域に入る可能性があります。また、直接義務がなくとも大手の取引先からESGデータ提供を求められるケースも増えるでしょう。
したがって影響を受ける企業は名目上の対象を超えて広がると考え、早めに情報開示の準備を進めることが肝要です。業種によって報告項目の重点は異なりますが、CSRDは基本的に「大きな企業はどの業界でも」適用されます。各企業は自社の業界特有の課題(例えば食品業界ならサプライチェーンの農業生産における環境負荷、アパレルなら児童労働リスク等)にも注意を払いながら、共通枠組みに沿って報告を行うことになります。
5. 企業が考慮すべきポイント
CSRDの適用を受ける可能性がある企業、あるいは既に対象確定の企業は、以下のポイントを考慮して準備・対応を進める必要があります。
適用タイミングの確認
自社(およびグループ会社)がいつからCSRD報告義務を負うのかを明確にします。前述のタイムラインに照らし、初回報告年度を逆算して社内準備計画を立てましょう。上場SMEの場合はオプトアウト期限も検討します。
報告範囲の特定
単体ベースか連結ベースか、グループ全体で報告するか子会社個別に報告させるかを検討します。CSRDでは親会社の包括報告で子会社の個別報告を免除できるケースもあるため、グループ経営の観点で効率的な対応方法を検討します。
既存の報告との整合
すでにGRIスタンダードや統合報告書でESG情報を開示している場合、それらとの重複やギャップを確認します。CSRD対応を機に報告フォーマットをCSRD基準に一本化するか、既存報告と二本立てにするかも方針を決めます。
内部体制の整備
サステナビリティ報告を担当する部署や委員会を設置・強化し、経営層の関与も確保します。財務報告と同様に、環境データや社会データの収集・検証プロセスについて社内ルールやシステムを構築します。特に初期段階では専門知識を持つコンサルタントの助言や社外セミナーの活用も有効です。
重要課題の見直し
自社にとってのESG重要課題(マテリアリティ)を再評価します。最新のステークホルダーの期待や規制動向を踏まえ、従来想定していなかった課題が浮上していないか確認します。例えば人権やサプライチェーン管理など、新たに重視され始めたテーマにも目を向けます。
ステークホルダーへの周知
CSRD対応を進める旨を必要に応じ取引先や投資家にも伝えます。サプライヤーにはデータ提供協力を求める可能性がありますし、投資家に対しては今後の開示強化方針を説明して理解を得ておくと良いでしょう。
長期的視点の維持
CSRD報告はゴールではなくスタートです。初回報告以降も毎年情報更新と改善が求められるため、単発対応でなく中長期的な計画を持って臨みます。継続的なプロセス改善とESG目標の高度化に取り組むことで、単なる義務遂行を超えて企業価値向上につなげることができます。
以上のポイントを踏まえて戦略的に対応することで、CSRDは企業にとって「守りの規制対応」から「攻めのサステナビリティ経営」への転換契機となり得ます。単なる情報開示義務ではなく、自社の持続可能性を高めるチャンスと捉えて前向きに取り組むことが重要です。
EU CSRD
https://commission.europa.eu/publications_en
Corporate sustainability reporting
https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
European Commission – Infringements decisions
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/inf_24_4661/INF_24_4661_EN.pdf