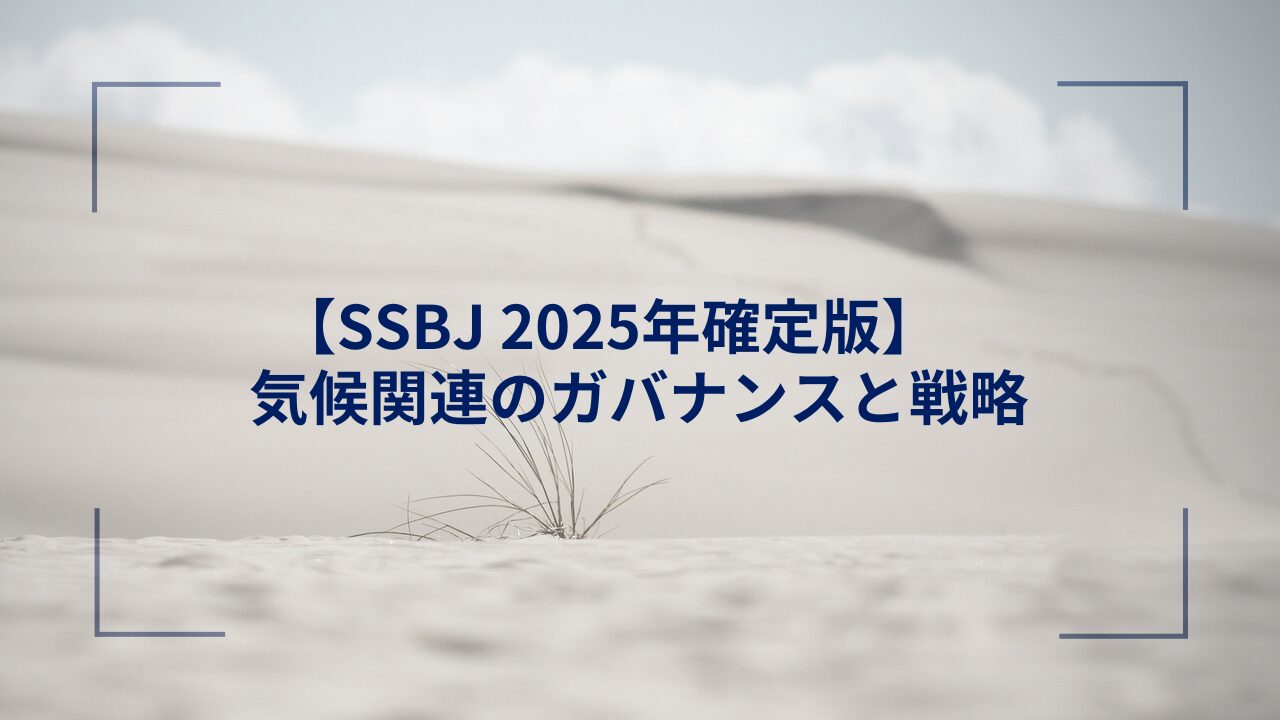企業が気候変動への対応戦略を効果的に実行するためには、適切なガバナンスとリスク管理プロセスが欠かせません。また、脱炭素社会への移行に向けた具体的なロードマップである移行計画を策定し、それを確実に実行していくことが求められます。本記事では、企業の気候関連戦略におけるガバナンスの役割と枠組みについて説明し、気候リスク管理のプロセスおよび戦略的対応の在り方を解説します。さらに、低炭素経済への移行計画の策定と実行プロセスについて触れ、最後に企業が直面する課題と今後の展望を考察します。財務・サステナビリティ担当者にとって、自社の体制整備や戦略立案の参考となる専門的知見を提供します。


1.気候関連ガバナンスの枠組み
ガバナンスとは、企業内での意思決定や監督の仕組みを指し、気候変動のような複雑で長期的な課題についてもしっかり統制を利かせることが重要です。SSBJ一般開示基準および気候関連開示基準において、ガバナンスに関する開示は最初に位置付けられており、それだけ経営者のコミットメントが重視されています。ガバナンスの枠組みで特に問われるのは、「取締役会および経営陣が気候関連リスク・機会をどのように監督・管理しているか」です。
取締役会レベルでの監督
多くの企業では、取締役会にサステナビリティ委員会やリスク委員会を設置し、その中で気候変動課題を扱っています。また、委員会を設けずとも、定期的に取締役会本体で気候関連の報告を受け議論する体制を整えます。SSBJ基準では、取締役会(または監督機関)が誰で、何を(役割・権限)、どう(頻度・手段)行っているかを具体的に開示するよう求めています。
例えば、「当社では指名委員会等設置会社のリスク委員会(年4回開催)が気候変動関連事項を監督し、委員長は独立社外取締役が務めている。リスク委員会はCEOへの勧告権限を持ち、主要な気候KPI進捗と戦略計画を審議する」などといった情報です。
気候変動対策の実行責任
専任の役員(例えば環境担当役員やCSO: Chief Sustainability Officer)を置き、全社横断の気候戦略を統括させる例が増えています。また、各事業部門に気候目標達成責任を割り振り、内部の業績評価項目に組み込むことも有効でしょう。基準では、経営陣が担う気候関連リスク管理プロセスへの関与についても開示項目となっています。経営陣の責任と権限分掌、および組織横断的な実行チームの設置状況などを明示することで、体制の実効性を示すことができます。
取締役会・経営陣の専門性
気候変動は科学的知見や政策動向など専門性が要求される分野のため、経営層が適切な判断を下すには知識・能力の裏付けが不可欠です。基準でも、ガバナンス機関が適切なスキルとコンピテンシーを備えているかをどのように評価しているか開示するよう求めています。企業は、社外から専門人材を招聘したり、研修を実施したり、専門家の助言を受ける仕組み(アドバイザリーボード等)を整えるなどして、知見の強化に努める必要があります。
ガバナンスと他要素(戦略・リスク管理・目標)の連携
優れたガバナンス体制は、単に存在するだけでなく実際に経営判断へ反映されて成果を生み出してこそ意味があります。そのため、取締役会が気候シナリオ分析結果を戦略見直しに活用した事例や、業績評価への気候KPI組み込み(報酬連動)の実施など、ガバナンスが戦略・リスク管理プロセスに及ぼす影響を示すエピソードを共有することも考えられます。
基準では、取締役会が戦略や重要取引の意思決定に気候課題をどのように考慮しているか、経営陣の報酬に気候KPIが含まれているか等も開示対象です。こうした情報から、投資家はガバナンス体制の「実効性」を読み取ります。
気候関連ガバナンスの枠組みでは、取締役会レベルでの監督責任の明確化(委員会設置、頻度、情報入手経路など)、経営陣レベルでの実行責任の明確化(担当役員・部署、横断体制)、経営層の専門性確保策、ガバナンスが実際の経営意思決定に繋がっていることが重要な要素となります。
2.リスク管理プロセスと戦略的対応
気候関連リスク管理は、企業の全社的なリスクマネジメントに組み込まれる形で行われることが理想です。前述の通り、ガバナンス体制が整った上で、実務的にはリスクの特定・評価・対策のプロセスを運用することになります。 リスク管理プロセスではまずリスクの特定が出発点です。企業は自社のバリューチェーン上で起こり得る気候リスク(物理的・移行的双方)を網羅的に洗い出します。その際、社内の複数部門から情報を集約する必要があります。
シナリオ分析
基準では、シナリオ分析をリスク特定に用いているか否か、それをどう使っているかを開示することが求められています。これは、企業が不確実性の高い将来リスクに対してどの程度備えているかを示す指標となります。
リスクの評価と優先順位付け
特定したリスクそれぞれについて、発生確率と影響度を評価し、重要度マトリクスなどで優先度を決定します。この評価は定性的判断だけでなく、可能な範囲で定量的影響分析を行うことが望ましいです。例えば「炭素税導入リスク:2030年までに累計△億円のコスト増見込み」といった分析ができれば、リスクの大きさを把握しやすくなります。評価結果は経営陣・取締役会に報告され、全社的なリスクプロフィールの一部として認識されます。
開示においては、リスク評価に用いた主なインプットやカバー範囲(例えばグローバル全拠点対象か主要拠点のみか)を説明することが求められます。
リスク対応
高優先度の気候リスクに対して、企業は具体的な対策を講じます。物理的リスクへの対策なら、ハード面では工場の防災設備投資や多拠点生産による冗長化、ソフト面ではBCP(事業継続計画)の策定・訓練などがあります。
移行リスクへの対策なら、ポートフォリオ転換やロビイング活動、技術開発投資などが考えられます。重要なのは、これらの対応策が企業戦略と矛盾せず、むしろ一体化していることです。例えば、高炭素事業から低炭素事業への転換戦略そのものが移行リスク対応になりますし、サプライチェーン多元化戦略が物理リスク対応になりえます。このように、リスク管理と戦略的対応は両輪です。
具体的開示項目
・リスク特定・評価・優先付け・モニタリングのプロセス概要(ERMとの統合状況含む)
・リスク特定に用いるインプット・ツール
・リスク管理プロセスが全社的リスク管理に統合されている度合いと方法
開示においては、企業は自社のリスク管理の「仕組み」を説明すると共に、主な気候リスク項目についてどのような対応策をとっているかも言及することが望ましいでしょう。「主要な移行リスクである炭素税リスクに対しては、エネルギーミックス転換計画を加速することで2025年までに炭素コストを売上高比▲%に低減する戦略で臨んでいる」等。これにより、単なる手続き開示に留まらず、戦略とリンクした実効的なリスク管理を伝えることができます。
3.移行計画について
移行計画とは、企業がカーボンニュートラルや低炭素経済への移行に向けて策定する包括的な計画を指します。SSBJ気候関連開示基準でも、企業に移行計画がある場合はその内容を詳細に開示することを求めています。移行計画は、実質的には前述の戦略およびリスク対応策を時間軸に沿ってまとめ、定量目標と具体策を盛り込んだものです。 典型的な移行計画には以下の要素が含まれます。
長期ビジョンと目標
例えば「2050年までに自社の温室効果ガス排出実質ゼロ」「2030年までに特定製品群の売上の50%を低炭素ソリューションに転換」等の目標。
中短期の具体的目標
長期ビジョンを達成するためのマイルストーンとなる2030年や2025年の目標(排出削減率、エネルギー構成、技術導入数など)。
主要な戦略アクション
ビジネスモデル変革、資産ポートフォリオの組替え、新規事業開発、設備投資計画、研究開発計画、人材育成等、移行に必要な具体策。
リソース計画
必要となる投資額、人的資源、提携先など。例えば「今後10年で累計○○億円を低炭素技術に投資」など。
前提条件と想定
計画策定時に置いた主な前提(例えば炭素価格の前提、技術普及シナリオ、規制動向の見通し)。これは計画の信頼性や実現可能性を判断する上で重要です。基準も、移行計画の主要な仮定や計画実現に不可欠な要因・条件を開示すべきとしています。
依存関係
計画の成否が依存する外部要因。例えば「政府の再エネ政策強化」「炭素回収技術の商用化」等がなければ目標達成困難、といった事項です。これも基準で情報開示が求められています。
移行計画の開示により、投資家は企業が移行に向けた道筋を明確にもっているか、その計画にどれだけ信憑性があるかを評価できます。基準の背景解説でも、主要な利害関係者(投資家)は計画の仮定や依存関係を理解する必要があると述べられており、単に目標の表明だけでなく、その裏付けとなる詳細情報が重要視されています。
4.移行計画の実行プロセス
移行計画の実行には、進捗管理と柔軟な見直しが伴います。企業は移行計画にKPIを設定し、定期的に経営陣や取締役会がフォローアップします。計画通りに進んでいない場合、原因分析と対策(リソース再配分、計画変更)を迅速に行います。実行段階での課題としては、技術開発の不確実性、投資負担の大きさ、ステークホルダー(従業員や地域社会)の同意形成などが挙げられます。計画の仮定に狂いが生じた場合、戦略のピボットも必要になるでしょう。
基準は、移行計画を各社の状況に応じた内容にすることを意図しており、千篇一律の開示ではなく、企業特有の戦略とリンクしたものになることを期待しています。
長期ビジョンに対する一貫性と実行可能性
例えば、大手自動車メーカーの移行計画であれば、「●年までに全車種のEV化」「エンジンプラントの再編計画」「必要電池容量の確保計画(提携含む)」「関連従業員のスキル転換研修計画」などを含むでしょう。エネルギー企業であれば、「石炭火力発電設備の段階的廃止スケジュール」「再エネ発電容量の拡大計画」「炭素回収・貯留(CCS)の実証と導入計画」等が盛り込まれるでしょう。
経営計画との一体化
移行計画は社内的には戦略ロードマップそのものであり、経営計画と一体化して管理されます。開示上は紙面の都合で概要のみになるかもしれませんが、投資家説明会などで詳細を補完すると良いでしょう。近年、多くのグローバル企業が「気候変動行動計画」や「トランジションストラテジー」と称して具体的な年次工程や投資計画を公開し始めています。これは市場からの圧力(計画の信頼性を疑われないようにする)も背景にあります。財務担当者にとっては、こうした移行計画が長期財務見通しや資本コストにどう影響するかの分析も必要になるでしょう。
5.企業が直面する課題
最後に、企業が気候関連のガバナンス・戦略強化に取り組む中で直面する典型的な課題について記載します。
組織変革の難しさ
気候変動を本業に統合するには、従来の組織文化や経営フレームを変革する必要があります。短期利益を重視する企業文化だと、長期視点の気候戦略は社内で優先度が下がりがちです。取締役会や経営層から現場まで、この課題に対する意識合わせが不可欠です。
データと分析能力の不足
気候リスク評価やシナリオ分析には高度なデータ分析能力が求められます。特に物理リスクの地域データやScope3排出量の把握など、従来の財務報告にはなかったデータ収集が必要です。こうしたデータ基盤整備と、人材(データサイエンティストや気候専門家)の確保が課題となります。
技術・ソリューションの不確実性
移行計画で前提とした技術革新(例えば水素技術のコスト低減やCCSの商用化)が計画通りに進まない場合、目標達成が危ぶまれます。この技術依存リスクは多くの企業に共通であり、ポートフォリオに柔軟性を持たせたり、複数シナリオを準備したりする必要があります。
規制や市場の変化
カーボンプライシングや気候関連規制は各国で動向が流動的です。また、消費者嗜好や投資家の評価軸も変わり得ます。企業戦略はこうした外部変化にタイムリーに適応する必要がありますが、先読みを誤ると投資のミスマッチが起こるリスクもあります。政策動向の継続的モニタリングとロビイング活動も重要です。
資金調達・コスト面
大規模な脱炭素投資が必要な場合、その資金調達やROI(投下資本利益率)の確保が課題となります。グリーンボンドの発行や、移行計画に信頼性があればESG投資資金を呼び込みやすくなるメリットもありますが、過渡期ではトランジションコストが収益を圧迫するケースも出てきます。このバランスをどうとるかは悩みどころです。
6.今後の展望
ガバナンスと戦略の観点では、企業の気候対応成熟度はますます重要な競争軸になると見込まれます。国際的にはISSB基準(IFRS S1/S2)やEUのCSRD(持続可能性報告指令)など、開示規制が強化されつつあり、気候関連情報の開示は義務化が進むと考えられます。
開示内容と企業価値
日本でもSSBJ基準に基づく開示が本格化し、東京証券取引所の要請等もあり上場企業を中心に迅速な対応が求められます。 そのような環境下で、単に「開示に対応する」だけでなく、開示内容を充実させること自体が企業価値向上に直結するようになります。気候変動への適応力や移行戦略の策定が、投資家の評価(株価や調達金利)に織り込まれる可能性があります。したがって、企業は競合他社との差別化要素としても、先進的なガバナンス・戦略体制を打ち出していくことが考えられます。
レジリエンス経営
気候変動を前提とした複数の未来像に備えるレジリエンス経営が普及するでしょう。取締役会にも科学・技術・サステナビリティの専門家が加わるケースが増え、ボードの構成も変化する可能性があります。気候変動対応はイノベーションを促進する側面(新事業の創出や効率化)もあり、攻めの経営戦略として捉える企業が増えると期待されます。
一方で、企業間比較や報告の質については課題も残ります。例えば各社の移行計画の前提条件が異なると単純比較はできませんし、未だ試行錯誤の領域もあります。しかし標準化が進むにつれ先進事例が共有され、評価手法も洗練されていくでしょう。投資家も企業も共に学習曲線を上っている段階であり、継続的な対話と改善が大切です。
結論として、気候関連のガバナンスと戦略、そして移行計画の策定・実行は、もはやサステナビリティ担当部門だけの課題ではなく経営中枢の課題です。財務・サステナビリティ担当者は経営陣への橋渡し役として、規制動向や基準要件を踏まえつつ、自社の長期価値に資する形でこれらを推進していく使命があります。適切なガバナンスの下、実効的な戦略と計画を持ち、変化に対応できる企業こそが、持続的な成長を遂げられると考えられます。
引用元
サステナビリティ開示ユニバーサル基準「サステナビリティ開示基準の適用」
サステナビリティ開示テーマ別基準第1号「一般開示基準」
サステナビリティ開示テーマ別基準第2号「気候関連開示基準」
https://www.ssb-j.jp/jp/ssbj_standards/2025-0305.html\