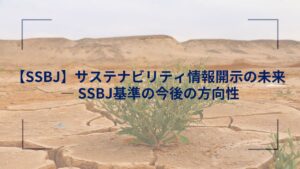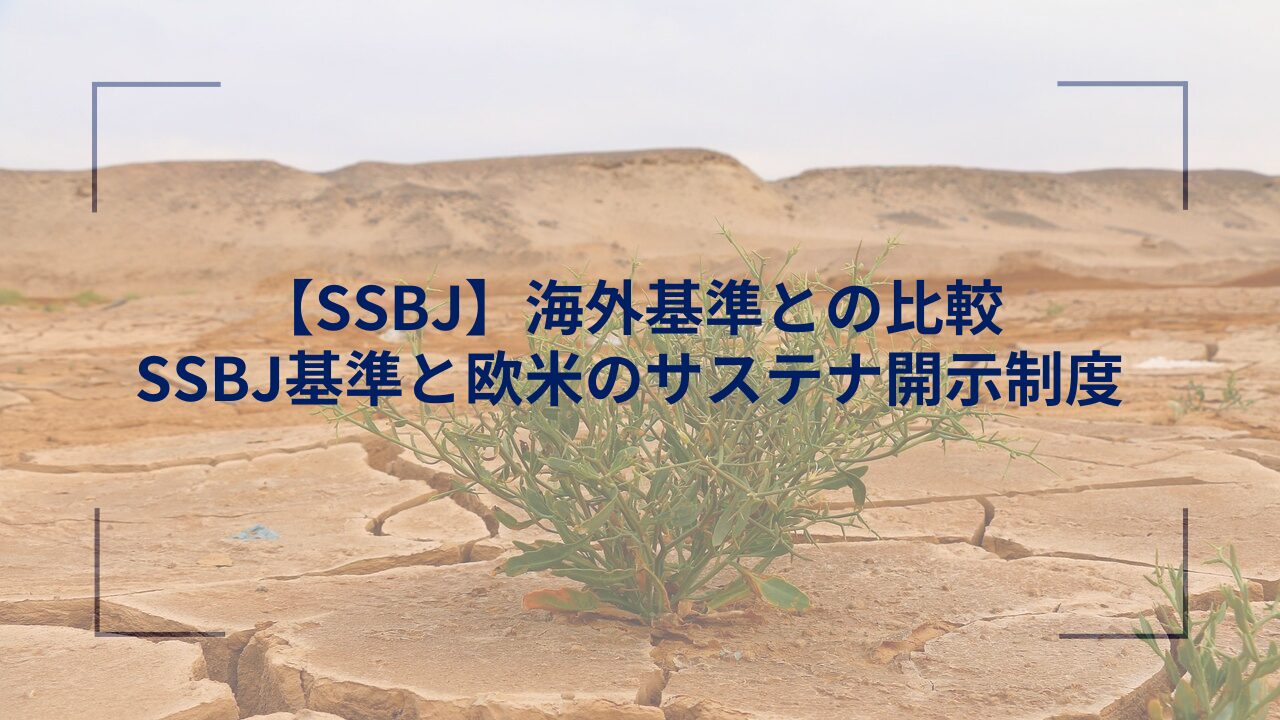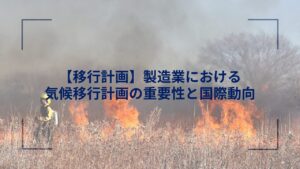SSBJ基準は投資家向けの企業価値関連情報に重点を置く一方、EUのESRSは「ダブル・マテリアリティ」を採用し、環境・社会への影響も開示対象としています。米国SECの規則は気候リスクに特化しており、SSBJ基準より限定的です。各国基準の整合性が進む中、日本企業はグローバル基準との調和を意識した対応が求められます。この違いと企業の対応策について解説します。
※本記事は2025年3月5日にサステナビリティ基準委員会から発表された確定案より以前の内容となっています。
確定案に関しては下記記事を参照してください。



1.EUのESRS基準との違い
欧州連合では、企業のサステナビリティ情報開示に関してCSRD(企業サステナビリティ報告指令)が策定され、これに基づく具体的な開示基準群としてESRS(欧州サステナビリティ報告基準)が2022年に公表されました。EUのアプローチの大きな特徴は「ダブル・マテリアリティ」の概念を採用している点です。すなわち、企業に対して「サステナビリティ課題が企業の財務状況に与える影響」(財務マテリアリティ)だけでなく「企業の活動が環境・社会へ与える影響」(インパクト・マテリアリティ)についても開示を求めています。これに対し、ISSBやSSBJ基準は主として前者の視点(企業価値関連の重要性)に基づいて開示項目を決定するものです。したがって、ESRSは開示範囲・項目がより広範で、気候変動や労働慣行、人権、ダイバーシティ、腐敗防止など、多岐にわたるESGトピックについて詳細な基準が設けられています。
一方、SSBJ基準(ISSB基準)は現在、気候変動に関する詳細基準(IFRS S2)のみがテーマ別基準として存在し、それ以外の人権や環境についてはIFRS S1の枠内で重要な事項を開示するという原則的な要求に留まっています。これが欧州基準とのカバレッジの差と言えます。また適用対象も異なり、CSRDはEU域内の一定規模以上の全ての企業およびEUで上場する企業に適用され、日本企業でもEUに子会社や支店を有する場合にはその子会社等がCSRD報告義務を負うケースがあります。対象企業はEU域内だけで数千社に上るとされ、日本の多国籍企業も相当数がカバーされます。もっともEU当局もISSB基準との相互運用性には配慮しており、ESRSはISSBのIFRS S1・S2と矛盾しないよう設計されていると述べています。実務的にも、IFRS S2の気候開示要件はCSRDの気候開示と整合している部分が多く、共通項目については報告の使い回しも可能と見られます。
要約すると、EUのESRSは網羅的・詳細であり開示負荷が大きい一方、ISSB/SSBJ基準は投資家目線の重要事項にフォーカスし比較的コンパクトという違いがあります。しかし最終的には両者の開示内容に重なる部分も多く、グローバル企業は双方の要求を満たす形で報告対応を行う必要が出てくるでしょう。
2.米国SECの気候関連開示規則との比較
米国における代表的な開示制度として注目されるのが、証券取引委員会(SEC)が提案した気候関連開示規則です。これは連邦レベルで上場企業に対して気候変動リスクやGHG排出量の開示を義務付けようとするもので、Scope1・2のGHG排出量の報告(全企業対象)、Scope3の報告(自社で重要と判断される場合)などが柱となっています。また、一定規模以上の企業にはGHG排出量データについて第三者保証(限定的保証から開始し将来的に合理的保証へ)を義務付ける案も含まれていました。しかしこの規則は提案後、法的な係争や反対意見などにより2023年時点で最終化が遅れており、SEC自体も気候専門部署を解散するなど動きが流動的です(ただしこれは気候対応を放棄したわけではなく通常業務に組み込んだためと説明されています)。
SSBJ基準との比較で言えば、カバー範囲に大きな違いがあります。SEC案は事実上気候変動テーマのみに特化しており、社会・ガバナンス面の開示は対象としていません。一方SSBJ基準(IFRS S1)は気候以外のサステナビリティ要素も含めた全般的な開示フレームワークであり、気候はその一部(IFRS S2に相当)という位置付けです。したがって、仮にSEC規則が原案どおり施行されれば、気候関連についてはSECルールとSSBJ基準でかなり共通する開示が求められることになりますが、SSBJ基準ではさらにそれ以外の重要なサステナ事項(例えば人的資本やサイバーセキュリティなど企業価値に影響を及ぼすESG事項)が開示対象に含まれる点が異なります。また、SECルールは米国市場での法定開示であり、適用範囲は米国上場企業や一定条件の米国債発行体等に限られます。一方、SSBJ基準は日本の上場企業が対象です。ただ、日本企業でも米国に上場している企業はSECのルールにも従う必要があり、またカリフォルニア州など州レベルでの開示義務(全米で事業を行う大企業にGHG開示を義務付ける州法が成立しています)の影響も受け得ます。
つまり大手多国籍企業にとっては、日本基準・米国ルール・EU基準のすべてに対応していく必要が出てくるため、それぞれの共通点・相違点を把握し、効率的に情報開示を行う戦略が求められます。まとめると、米国SECの気候ルールは範囲が限定的である一方、SSBJ基準は包括的であるという違いがありますが、気候に関する具体的開示項目ではTCFDに沿っている点で概ね共通基盤があると言えるでしょう。
3.各国基準との整合性
サステナビリティ開示を巡っては各国・地域で異なる基準やルールが生まれていますが、近年は相互の整合性を高めようとする動きが強まっています。G7首脳も「気候を含むサステナビリティ情報の一貫した比較可能で信頼できる開示」の重要性を強調し、ISSB基準の策定とグローバルに相互運用可能な枠組みの実現を支持する声明を出しました。ISSBのIFRSサステナビリティ開示基準は、各管轄でのグローバルベースラインとして機能することが期待されています。EUも前述の通りESRSとISSB基準の調和を図っており、例えば用語や開示項目の対応表を作成するなど企業報告者が両方に適合した報告を作りやすいよう配慮がなされています。日本のSSBJ基準はISSB基準をフルに取り込むことで、この国際的な調和の流れに乗っています。
一方、各国の法制度には依然差異があり、例えば開示義務化の範囲・時期、保証(監査)の強制力、有価証券報告書など法定書類への位置付け等は国ごとに異なります。日本は金融商品取引法の開示制度にサステナ情報を組み込む形ですが、米国は証券法規則での定義づけ、EUは会計指令の改正による各国法への落とし込みという具合です。それでも根底にある潮流としては、TCFDを起点とした開示フレームワークの共通化があります。TCFDの4つの柱(ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標)はISSB基準やESRS、SECルールでも基本的に踏襲されており、それぞれの詳細要件を横串で見ると共通点が多くなっています。したがって、多国籍企業は各基準間のギャップをマッピングし、一つのマスターレポートから各国提出用に適宜調整する方法で効率化を図れます。幸い、SSBJ基準を適用して開示された情報は、国際的にもISSB基準準拠とみなせる設計になっており、海外投資家からも受け入れられやすいものとなるでしょう。
総括すると、現在は過渡期ゆえ地域差が残るものの、中長期的にはISSB基準を核とした各国基準の収斂が進む可能性が高く、SSBJ基準もその文脈でアップデートされ続けると考えられます。
引用元
EU欧州委員会「Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)」
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
SASB(サステナビリティ会計基準審議会)
https://www.sasb.org/