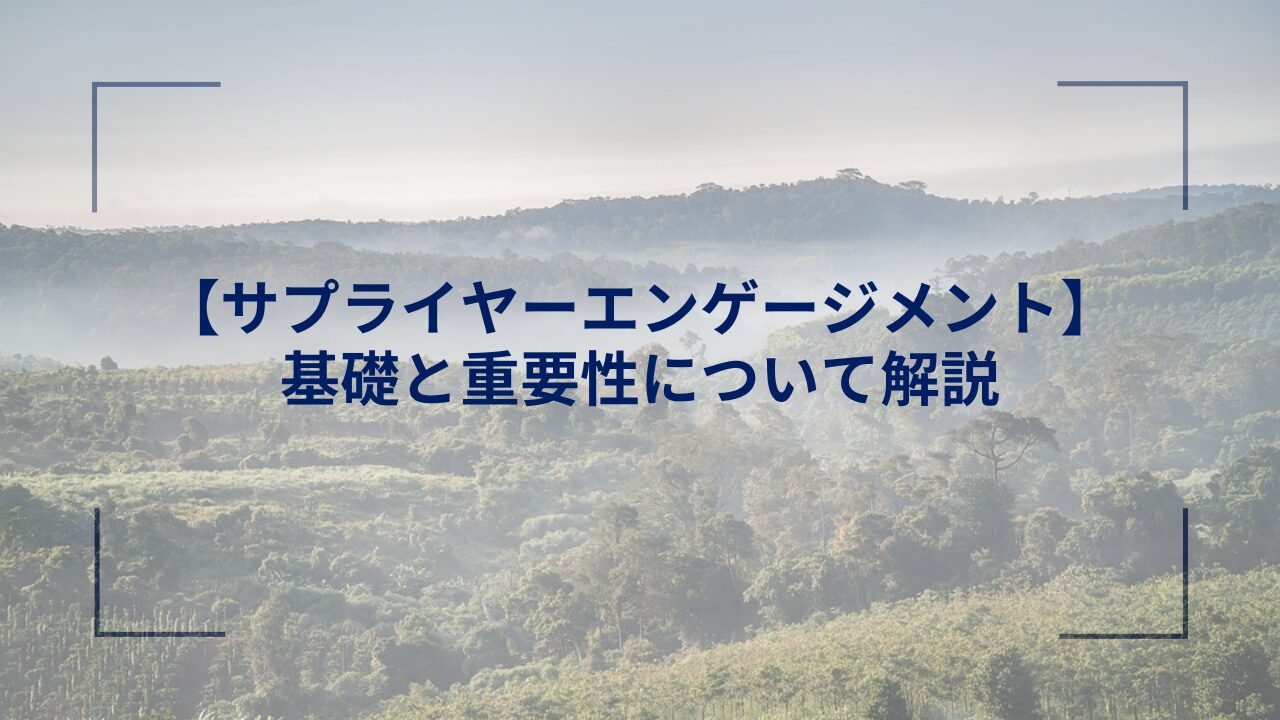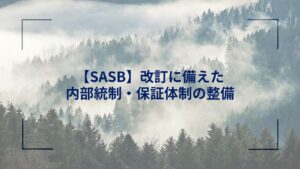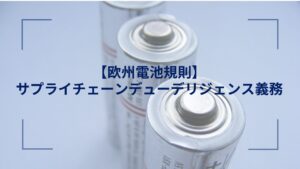サプライヤーエンゲージメントとは、企業とサプライヤーが信頼関係を築き、持続可能性や価値創出に向けて共に取り組む姿勢を指します。従来の交渉型関係を超え、長期的視点での協働や情報共有を重視し、調達戦略やESG対応、規制順守、ブランド価値向上にも貢献します。環境・社会・ガバナンス全般においてサプライヤーと連携することは、企業の競争力や信頼性を高めるうえで不可欠です。サプライヤーエンゲージメントの基礎と重要性について解説します。


1. サプライヤーエンゲージメントの基本概念
ここではサプライヤーエンゲージメントの基本概念、企業とサプライヤーの関係構築や調達戦略について解説します。
企業とサプライヤーの関係構築
サプライヤーエンゲージメントの基礎となるのは、企業とサプライヤーの間に強固な協力関係を構築することです。従来、購買部門とサプライヤーの関係は「交渉相手」としての側面が強く、コスト削減や品質問題への対処に限られがちでした。しかし、持続可能な経営が求められる現代では、サプライヤーをパートナーと捉え、共に課題解決や価値創出に取り組む姿勢が重要です。具体的には、単発の取引ではなく長期的な取り引きを前提に信頼を醸成し、情報や知見を共有し合う関係性を築きます。例えば、定期的な経営層間の対話、エンジニア同士の技術交流、相互の現場視察受け入れなど、「顔の見える関係」を作ることが推奨されます。このような協働により、サプライヤーは顧客企業の戦略や価値観を理解し、自社の改善に活かすことができます。
バイヤーの対応
サプライヤーの課題や提案を真摯に受け止め、必要な支援(トレーニングや資金面の援助など)を提供することで、ウィンウィンの成果を得られます。エンゲージメントの進んだ企業では、自社チームとサプライヤーチームが一丸となって問題解決に当たる文化さえ醸成されています。重要なのは、エンゲージメントが双方向の取り組みである点です。企業側が要求と監視ばかりするのではなく、自社の担当者の能力向上(調達担当者のCSR研修など)や組織体制整備にも努め、サプライヤーにとって協力しやすいパートナーになることが求められます。こうした相互努力により、最終的には企業がサプライヤーから「選ばれる顧客(Customer of Choice)」となり、取引先が積極的に自社へ有利な提案や協力をしてくれる好循環が生まれます。つまり、関係構築に投資することは、長期的には供給安定やコスト競争力、さらにはイノベーション創出につながる戦略的投資なのです。
持続可能な調達戦略
企業とサプライヤーの良好な関係構築を土台に、その関係を持続可能性の向上へと結びつけるのが持続可能な調達戦略です。持続可能な調達戦略とは、一言で言えば「調達にCSR視点を組み込む」ことです。具体的には、購買先の選定基準や契約条件に環境・社会・倫理の項目を設定し、サプライヤーにも企業のサステナビリティ目標に沿った行動を促すことを指します。例えば、調達ポリシーにおいて「ISO 14001認証取得を義務付け」「労働人権ポリシーの有無を評価」「CO₂排出報告を必須化」といった要件を盛り込みます。これにより、サプライヤーはビジネス上、持続可能性への配慮をせざるを得なくなり、ひいてはバリューチェーン全体でのCSR水準底上げが図られます。持続可能な調達戦略は、リスク低減と機会創出の両面で企業にもたらす利点があります。一つはリスク低減です。サプライチェーン上の不適切な行為(違法な排水、強制労働、贈収賄など)は企業本体の信用失墜や法的罰則に直結します。予め厳しい基準でサプライヤーを選別し、定期評価することで問題発生の確率を下げられます。仮に問題が起きても、契約上の対策条項に基づき迅速な是正を要求でき、被害や信用毀損を最小限に留めることができます。
機会創出
サプライヤーとの対話を通じて環境配慮型の新素材開発や、倫理的に付加価値のある商品の共同開発が可能になります。また、調達改革によりコスト削減が可能な場合もあります。例えば、省エネ型機械への更新をサプライヤーに奨励しエネルギーコストを下げれば、将来的に製品価格競争力にも寄与します。このように持続可能な調達戦略は、「環境や社会のためにコストをかける」ものではなく、「将来の競争力と社会的信用を高めるための投資」と位置付けられます。国際規格ISO 20400(サステナブル調達ガイドライン)でも、組織全体の方針としてCSR調達を据え、購買プロセスの各段階(計画・仕様策定・サプライヤー選定・契約・パフォーマンス評価)にサステナビリティ要件を組み込むことが推奨されています。現代の企業経営において、持続可能な調達戦略はもはやオプションではなく必要条件になりつつあると言えるでしょう。
2. 企業がサプライヤーエンゲージメントを強化すべき理由
企業がサプライヤーエンゲージメントに注力すべき大きな理由の一つが、ESG(Environment, Social, Governance)の観点で優れたパフォーマンスを発揮するためです。ESG投資の拡大やSDGsの浸透に伴い、企業は自社のみならずバリューチェーン全体で環境・社会課題に取り組むことが求められています。
E(環境)との関連性
環境(E)の側面では、前述したようにサプライチェーン由来の環境負荷が非常に大きく、気候変動への対応にはサプライヤーの協力が不可欠です。ある調査では、サプライヤーと連携して気候変動対策を行っている企業は、そうでない企業に比べScope3排出削減目標を設定している割合が約7倍も高かったと報告されています。これは、サプライヤーエンゲージメントが気候目標達成のカギであることを示唆しています。具体的には、主要サプライヤーに対し温室効果ガス排出量の報告と削減計画策定を求め、必要なら技術支援を行う企業が増えています。加えて、水資源管理や廃棄物削減など環境面の協働目標をサプライヤーと共有し、定量的なKPIで進捗を管理する例もあります。
S(社会)との関連性
社会(S)の側面でも、サプライチェーン上の人権・労働問題への取り組みは企業評価に直結します。たとえ自社社員の待遇が良好でも、下請け工場で児童労働や過酷労働が横行していれば企業全体として社会的責任を果たしているとは言えません。実際、消費財メーカーやアパレル企業は過去にサプライヤー工場での労働惨事(工場火災や建物崩落事故など)を受けて世界的な批判に晒されたケースがあります。このため、各社は事前にサプライヤーの労働安全衛生状況を監査したり、教育訓練プログラムを提供したりして労働環境改善に努めています。また、近年注目されるダイバーシティ調達(少数者支援企業からの調達拡大)も社会価値創出の一環です。例えば女性経営者やマイノリティ経営者が率いるサプライヤーとの取引を増やすことで、社会的包摂に貢献しつつ新たな供給源を開拓する企業もあります。
G(ガバナンス)との関連性
ガバナンス(G)の側面では、サプライチェーン上の腐敗防止や法令順守が焦点となります。多くの国で調達プロセスにおける贈収賄防止法規が強化されており、サプライヤーへの透明な支払いと公平な選定が求められます。大規模プロジェクトでは下請けによる贈賄リスクも指摘されるため、企業はサプライヤーに対し倫理規範への署名やトレーニング受講を義務付けています。さらに下請けを含めた知的財産や情報セキュリティの管理もガバナンス上重要です。IT企業などでは、サプライヤーのセキュリティ対策状況を評価し協力して強化する取り組みが一般化しています。
以上のように、ESG全ての領域でサプライチェーンにおける取り組みが企業評価や持続可能性目標の達成に関わっており、エンゲージメント強化は不可避となっています。投資家評価においても、CDPや各種サステナビリティ評価でサプライヤー関与度合いがスコアリング対象となっており、先進企業ほどサプライヤーエンゲージメントに力を入れているのが実情です。
3. 規制対応とブランド価値の向上
サプライヤーエンゲージメントを強化すべき第二の理由は、各国で相次ぎ導入されている規制への対応およびブランド価値の維持・向上です。
規制動向
近年、EUを中心に企業のサプライチェーンにおける人権・環境デューデリジェンスを義務付ける法律が制定されつつあります。例えばEUの企業持続可能性デューデリジェンス指令(CSDDD)やコーポレートサステナビリティ報告指令(CSRD)では、一定規模以上の企業に対しサプライチェーン上の人権侵害や環境破壊リスクの特定・開示と、それを防止・軽減する措置を講じることが求められます。ドイツではすでに2023年にサプライチェーンデューデリジェンス法が施行され、企業は自社および主要サプライヤーにおける人権尊重の確保義務を負っています。これらの法規制に違反すれば、多額の罰金や行政処分のみならず企業イメージの失墜につながります。したがって、法の求めを上回る水準で積極的にサプライヤーと協働し、リスク対策を行うことが重要です。
具体的対策
具体的には、人権方針や環境方針をサプライヤーと共有し、是正計画の策定や研修の実施などで支援すること、重大な違反が見つかった場合には速やかに取引停止や公表を行う危機管理体制を整えることです。これらは単に規制対応という消極的理由だけでなく、企業のブランド価値を守る積極的理由にもなります。現代の消費者やビジネスパートナーは、企業の「紛争鉱物を使っていないか」「生産者に正当な賃金を払っているか」といった点まで注目しています。不祥事が発覚すればSNS等で瞬時に拡散し、ボイコット運動に発展することもあります。逆に言えば、サプライチェーン上の高い倫理基準や環境基準を誇ることは他社との差別化につながります。
事例
例えばパタゴニア社は、自社製品の原料供給元や工場名を公開し、フェアトレード認証生地の使用やリサイクル素材活用を進めることで「最も倫理的なアウトドアブランド」としての地位を確立しています。また、ある調査ではサプライチェーンの透明性向上に投資した企業は、消費者からの信頼が強まり売上増加にもつながったと報告されています。これは企業の誠実さや品質保証力への信頼が購買意欲を高めるということです。ブランド価値向上の観点からは、サプライヤーと協働した社会貢献活動も有効です。例えば飲料メーカーが原料農家と協力して農村開発や教育支援を行えば、そのストーリー自体がマーケティング資産となり、消費者にポジティブに受け止められます。事実、大手企業の中にはサプライチェーンのコミュニティ支援をCSRレポートや広告で積極的に発信し、ブランドロイヤルティの向上につなげている例が多く見られます。総じて、厳格化する法規制をクリアしブランド価値を高める上で、サプライヤーエンゲージメントの深化はもはや不可欠と言えるでしょう。
https://www.patagonia.jp/our-footprint/fair-trade.html
引用
ISO 26000: Social Responsibility
https://www.iso.org/iso-26000-social-responsibility.html
UN Global Compact
https://www.unglobalcompact.org
経済産業省:CSR/サステナビリティ関連資料
https://www.meti.go.jp