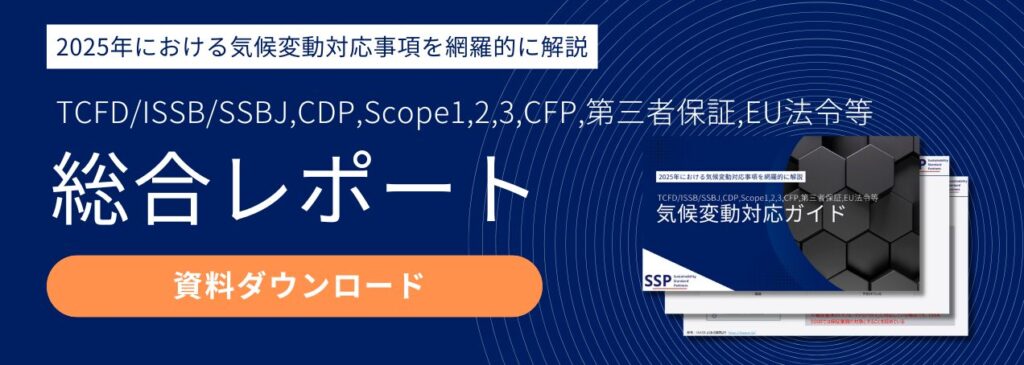CSRD(企業サステナビリティ報告指令)は、EUが定めたESG情報の開示義務に関する新制度で、従来のNFRDを強化し、企業の透明性と説明責任を高めることを目的としています。企業はESRS基準に基づき、ダブルマテリアリティに即した情報開示が求められます。EU域外の企業にも適用される可能性があり、国際的に影響力のある制度です。企業の持続可能性を巡る情報開示の新たな枠組みについて解説します。

※本記事は2025年2月26日に欧州委員会から発表されたオムニバス法案より以前の内容となっています。
オムニバス法案に関しては下記記事を参照してください。
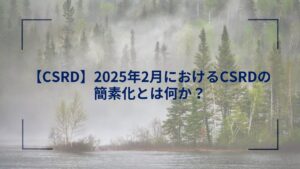
1. CSRDとは? 企業が知るべき基本概念
CSRD(Corporate Sustainability Reporting Directive、企業サステナビリティ報告指令)とは、EUが制定した企業のサステナビリティ情報開示に関する新たな指令です。従来のNFRD(非財務報告指令)を拡充・強化する形で2023年1月に発効し、企業に対して環境・社会・ガバナンス(ESG)に関する詳細な情報開示を義務付けています。この指令の目的は、企業のサステナビリティに関するリスクや影響、およびそれへの対応状況をステークホルダー(投資家や消費者、市民社会など)に分かりやすく伝えることです。その結果、持続可能性に関する企業間の比較可能性や透明性が高まり、持続可能な投資判断や企業経営を促進する狙いがあります。
ダブルマテリアリティはCSRDを理解する上で重要な概念です。これは企業が自社の財務に与える影響だけでなく、企業活動が環境や社会に与える影響も「重要性」として評価・報告するという考え方です。つまり財務的マテリアリティ(サステナビリティ課題が企業の経営や財務に与える影響)と環境・社会的マテリアリティ(企業の活動が環境・社会に与える影響)の両面から重要課題を特定し、開示する必要があります。このダブルマテリアリティの考え方に基づき、CSRDでは企業に対し幅広いESG情報の報告を求めています。
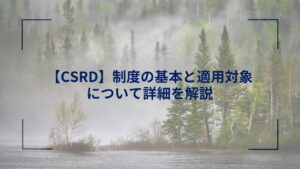
2. CSRDとESRSの関係とは?
CSRDで要求される具体的な開示内容や基準は、ESRS(European Sustainability Reporting Standards、欧州サステナビリティ報告基準)という報告基準によって定められています。CSRDは「何を報告すべきか」を法律で定めたものですが、その報告書を作成する際の詳細な項目や様式を示すのがESRSです。CSRDの適用対象企業は、このESRSに従ってサステナビリティ報告を行うことが義務付けられています。ESRSはEFRAG(European Financial Reporting Advisory Group、欧州財務報告諮問グループ)によって策定された基準であり、2023年12月に最初のセットがEU官報で公表され法律として発効しました。ESRSは横断的基準(ESRS 1:全般的要求事項、ESRS 2:全般的開示事項)と、トピック別基準(環境E、社会S、ガバナンスGに関する個別テーマ)に分かれています。
具体的には環境分野では気候変動・汚染・水資源・生物多様性・資源循環の5領域、社会分野では自社の従業員、バリューチェーン上の労働者、コミュニティ、消費者の4領域、ガバナンス分野では企業の行動倫理(ビジネスコンダクト)の領域について詳細な開示基準が定められています。企業はまずダブルマテリアリティ評価を行い、これらトピックの中から自社にとって重要なものを特定した上で、それぞれのESRS基準に沿った情報開示を行うことになります。
要するに、CSRDという法律上の枠組みの下で、ESRSという具体的な報告基準に従って企業はサステナビリティ情報を開示するという関係になります。CSRDへの対応=ESRSに準拠した報告書の作成、と言い換えることもできるでしょう。またESRSは国際的な標準化動向も踏まえて策定されており、グローバルな基準(例:GRIスタンダードやISSBの基準)との相互運用性にも配慮がなされています。

3. 企業に求められる報告義務と適用範囲
報告義務として、CSRDは対象企業に対し毎年、財務報告と同時期にサステナビリティに関する情報を経営報告書(マネジメントレポート)の中で開示することを求めています。その報告内容は前述のESRSに準拠した詳細なもので、開示されたデータは統一されたデジタル形式(XHTML形式へのタグ付け等)で提出し、EUの単一アクセス可能なデータベースで公開されます。さらに提出情報には外部監査が義務付けられており、当初は限定的保証から始まり、将来的には財務監査並みの合理的保証への移行が予定されています。具体的には2024年度報告(2025年提出分)から限定保証が求められ、2028年までに合理的保証への移行が検討されています。
適用範囲として、CSRDはこれまでのNFRDに比べ大幅に対象企業を拡大しています。以下の企業が報告義務の対象となります。
EU域内の大企業
EUに本拠を置く大規模企業。具体的には、次の3条件のうち少なくとも2つを満たす企業です
・総資産が2500万ユーロ超(従来2000万ユーロから拡大)
・売上高が5000万ユーロ超(従来4000万ユーロから拡大)
・従業員が250名超
(※これらはEU会計指令上の「大企業」基準で、CSRD適用において従来より基準が引き上げられました。)
EUの証券取引所に上場している全企業
上場企業は中小企業(SME)であっても対象。ただし上場マイクロ企業(従業員10名以下かつ売上高・資産が一定以下)は除外されています。上場SMEには報告準備のための経過措置(オプトアウト)があり、2年間報告開始を猶予可能です。
非EU(域外)の企業
本社がEU外に所在する企業でも、EU域内で一定規模以上の事業を行っている場合は対象となります。具体的には「EU内での売上高が1.5億ユーロ(約150百万ユーロ)以上」で、なおかつ次のいずれかに該当する場合です
・EU内に上記「大企業」基準を満たす子会社(子会社自体がCSRD対象)を有する
・EU内に売上高4000万ユーロ超の支店を有する
・EUの規制市場に上場している(証券を発行している)
(※これにより、日本企業であってもEU内に大規模子会社や相当の売上拠点を持つ場合にはCSRDの義務が生じる可能性があります。)
適用開始時期(報告年度)
・2025年提出(2024年度報告)
既にNFRD適用下で報告義務を負っていた企業(従業員500名超の上場企業や金融機関等)は、この年度からCSRD基準での報告開始。
・2026年提出(2025年度報告)
上記以外のすべての大企業が報告開始。
・2027年提出(2026年度報告)
上場SME(小規模上場企業)および一部の中小金融機関等が報告開始(ただしSMEは2028年まで報告免除のオプションあり)。
・2029年提出(2028年度報告)
非EU企業で上記基準に該当する企業が報告開始。
このようにCSRDは段階的に適用範囲を拡大し、最終的にはEU域内外合わせて約5万社近くが対象になると推計されています。これは従来のNFRD下で約1.1万社だった対象から大幅な拡大です。

4. CSRD対応のメリットとリスク
CSRDへの適合(コンプライアンス)は企業にとって負担となる面もありますが、同時に多くのメリットをもたらし得ます。一方で、対応を怠った場合のリスクも看過できません。ここでは主なメリットとリスクを整理します。
メリット
透明性・説明責任の向上
CSRD基準でESG情報を開示することで、企業のサステナビリティへの取り組みをステークホルダーに明確に伝えられます。情報開示が強化されることで企業の説明責任が果たされ、社会からの信頼性向上につながります。
リスク・機会の把握と戦略改善
報告プロセスを通じて、自社のESG上の課題や強みを体系的に洗い出すことができます。例えば、二重マテリアリティ評価により事業戦略上重要なサステナビリティ課題が明確化されれば、その対応策を講じ業務改善や新たな機会の創出につなげることができます。
投資家・取引先からの評価向上
ESG情報開示の充実は、サステナブル投資を重視する機関投資家や金融機関からの評価を高め、資金調達コストの低減や株価の安定化に寄与し得ます。またサプライチェーン上の取引先企業からの信頼も増し、取引機会の拡大につながる可能性があります。
国際基準への適合
CSRDは世界的にも先進的な規制であり、これに対応することは将来的な他地域での規制強化にも備えることになります。報告基準の標準化により中長期的には重複報告の削減や報告業務の効率化効果も期待されます。
リスク(非対応のリスク)
法的罰則・制裁
CSRDの報告義務を怠った場合、各加盟国の定める罰金など法的制裁の対象となります。例えば、公共調達(政府入札)への参加制限や行政罰が科される可能性も指摘されています。違反による金銭的・業務的ペナルティは企業業績にも悪影響を及ぼします。
信用・評判リスク
非開示や情報不足はステークホルダーの信頼を損ね、企業イメージの悪化を招きます。特にサステナビリティへの社会的関心が高まる中、情報開示に消極的な企業は「何か問題を抱えているのでは」と見られかねません。一方、適切な開示に努めることで企業の評判向上につながります。
機会損失
ESG情報開示の不足は投資家から敬遠されるだけでなく、サプライチェーン上で取引を敬遠されたり、優秀な人材確保で不利になる可能性があります。持続可能性を重視する社会の流れに乗り遅れること自体が、中長期的な競争力低下につながりかねません。
短期的なコスト増
CSRD対応には内部体制の整備やデータ収集システム構築、監査費用など即座にコストが発生します。
しかし、これらは将来的な効率化投資でもあり、また規制対応を通じて得られる経営改善効果を考えれば必要な投資と言えるでしょう。
5. CSRDに対応するための基本プロセス
CSRDへの対応を円滑に進めるには、体系立ったプロセスを踏むことが重要です。一般的には次のようなステップで準備を進めることが推奨されます。
制度内容と適用範囲の把握
まずCSRD/ESRSの要求事項や自社の適用対象該当性を確認します。自社やグループ会社がどの報告年度から対象となるか、連結報告の可否(親会社による包括報告で子会社義務を代替できる場合あり)などスケジュールも把握します。経営層への周知・理解促進もこの段階で行います。
現状ギャップ分析(簡易)
現行のサステナビリティ情報開示とESRS要件との比較を行い、不足している項目や体制を洗い出します。特にESRS 2(全般的開示事項)の項目に照らし、現状で報告可能なデータと不足データをざっと確認します(ここでは詳細な数値算定より概要把握が目的)。
ダブルマテリアリティ評価の実施
ESRS 1(全般的要求事項)のガイダンスに沿って、自社にとって重要なサステナビリティトピックを特定します。財務的観点と環境・社会的観点の両面からリスク・機会・インパクトを評価し、報告すべきテーマ(例:気候変動、ダイバーシティ、人権、ガバナンス体制等)を絞り込みます。併せて各テーマごとに適用されるESRS基準の詳細要件を理解します。
詳細ギャップ分析と体制構築
特定された重要テーマごとに、必要なデータや開示体制の整備状況を詳しく分析します。例えば気候変動であれば、GHG排出量(スコープ1~3)の算定方法・データ整備、削減目標の有無などを点検します。不足があれば新たなデータ収集プロセスの導入や社内ポリシー策定など体制強化を図ります。また各テーマに責任を負う部署や担当者を明確化し、社内の役割分担とガバナンス体制を整備します。
ロードマップ策定と実行
上記の分析を踏まえ、CSRD報告に向けた具体的な実行計画(ロードマップ)を作成します。ロードマップには各施策の担当部署、実施スケジュール(短期・中長期)、必要リソース(人員、システム、予算、外部専門家活用)などを盛り込みます。計画に沿ってデータ収集・社内プロセス整備を実行に移し、初回報告書の作成準備を進めます。
以上が基本的な流れですが、実際にはこれらを自社のサステナビリティ戦略と統合しながら進めることが重要です。単なる規制対応に留めず、企業の長期戦略や目標(例えば脱炭素経営や多様性推進計画)とCSRD対応を結び付けることで、報告プロセスを通じた企業価値向上につなげることができます。
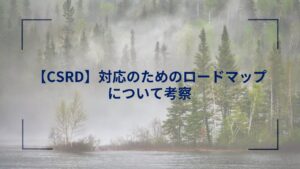
6. CSRDの最新動向と今後の展望
CSRDおよびESRSを取り巻く最新の動向と将来の展望について解説します。まず、最初のESRS基準セットが2023年末に正式採択され、CSRD報告の具体的ルールが出揃いました。今後はセクター別の報告基準(産業ごとの追加開示要求)の策定が進められる予定です。CSRDでは金融業やエネルギーなど特定業種向けの基準を含む第2セットのESRSを順次策定すると定めており、2024~2025年にかけて公表される見通しです。ただし企業負担への配慮から適用期限の延長も検討されており、一部のセクター標準は当初計画より遅れて適用される見込みです。
グローバル基準との調和
EUはISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の策定するIFRSサステナビリティ開示基準(S1一般開示、S2気候関連)との相互運用性を確保すべく取り組んでおり、2024年5月には欧州委員会がグローバル基準とのインターオペラビリティに関するガイダンスを歓迎する声明を出しています。これはEU基準と国際基準の重複を減らし、企業が双方に対応しやすくするためのものです。GRI(グローバル・レポーティング・イニシアチブ)など既存の枠組みとの整合性も図られており、企業は自社の既存のESG報告との連携を取りやすくなっています。
保証の強化
前述の通りCSRDでは2024年度報告から限定保証が導入されますが、欧州委員会は2028年までに保証レベルを合理的保証へ高める方向で制度の評価・見直しを行う計画です。これによりサステナビリティ情報の信頼性が一層高まり、財務情報と同等に扱われる時代が来る可能性があります。他方、企業数拡大に伴う課題も認識されています。対象企業が飛躍的に増えることで各国当局による監督や企業側の対応負荷が懸念されるため、EU当局は加盟国に対し比例原則に基づく運用(中小企業や新規適用企業への配慮)を求めています。実務上、初年度は「学習期間」と位置づけて柔軟な対応がとられる可能性もあります。
今後の展望
CSRDは企業報告の新たな常識を形成すると期待されます。EU域内では約5万社もの企業が順次この詳細なESG報告に移行し、市場に大量のサステナビリティ情報が提供されることになります。投資ファンドや金融機関はこれらデータを活用して企業評価を行い、資本配分を決定していくでしょう。また大企業がバリューチェーン全体の情報を報告する中で、サプライヤーである中小企業にもデータ提供や持続可能性対応を求める動きが強まります。つまりCSRDは直接の法的対象でない企業にも波及効果を及ぼし、サステナビリティ経営の水準を全体的に底上げする可能性があります。
さらに、EUの動きを受けて他地域でも規制強化が進む可能性があります。例えば米国ではSEC(証券取引委員会)が気候関連開示ルールを検討中であり、国際的にも統一的な報告枠組みづくりが議論されています。CSRDはその先駆けとして世界の議論をリードしており、将来的に各国のルールがCSRDやESRSに倣ったものになる、あるいは相互承認されるような流れも予想されます。企業のサステナビリティ情報開示は、もはや一部先進企業だけの取り組みではなくグローバルスタンダードとなりつつあると言えるでしょう。
引用
EU CSRD
https://commission.europa.eu/publications_en
Corporate sustainability reporting
https://finance.ec.europa.eu/capital-markets-union-and-financial-markets/company-reporting-and-auditing/company-reporting/corporate-sustainability-reporting_en
CSRD 適用対象日系企業のための ESRS 適用実務ガイダンス
https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/01/80fd13a160c18b11/20240005_01.pdf
Questions and Answers on the Adoption of European Sustainability Reporting Standards
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_23_4043
EFRAG と CDP、欧州サステナビリティ報告基準の市場への導入を促進するための協力を発表https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/008/667/original/CDP_Japan_PR_20231108.pdf