省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律)と温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)は、日本の気候変動対策における重要な二本柱であり、特に製造業などエネルギー多消費型の企業に深く関わる法律です。本記事では、多排出の製造業企業(中小企業から大企業)を対象に、これら2つの法律の概要と企業に求められる対応策、さらに報告義務のポイントについて解説します。


1. 省エネ法の概要と企業対応
省エネ法は、企業によるエネルギー使用の効率化(省エネ)と非化石エネルギーへの転換を促進するための法律です。年間エネルギー使用量が原油換算で1,500kL以上の企業は「特定事業者等」として指定され、エネルギー使用状況の定期的な報告や省エネ計画の策定が義務付けられます。企業はエネルギー管理責任者を選任し、毎年度のエネルギー消費実績や省エネの取組状況を定期報告書として提出する必要があります。またおおむね5年ごとに中長期計画書を作成し、エネルギー削減目標や具体策を示すことが求められます。省エネ法では各企業に対し、エネルギー消費原単位(生産量あたりのエネルギー消費)を年平均1%以上改善する努力目標が掲げられており、エネルギー削減のPDCAサイクルを回すことが重要です。特に製造業の大規模事業者では、高効率設備への更新、工程の改善、省エネ意識の徹底など効果的な施策が求められます。

改正省エネ法
さらに省エネ法は近年改正により脱炭素化への対応を強化しています。2023年4月の改正では法律名称も「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に改められ、再生可能エネルギーや水素等の非化石エネルギーへの転換が企業の新たな義務に追加されました。具体的には、特定事業者は非化石エネルギー導入の中長期目標を設定し、再エネ電力の使用量などを定期報告で報告することが義務化されています。また、電力需給ひっ迫時や再エネ余剰時に需要を調整するデマンドレスポンス(DR)の実施状況についても報告対象となり、大規模需要家には電気需要の最適化への取組みが求められます。このように省エネ法は、省エネの徹底に加えてエネルギー源の脱炭素化まで含めた包括的なエネルギー対策法へと発展しています。
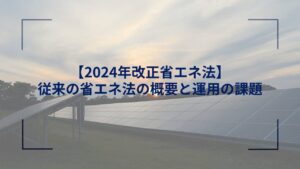
省エネ計画の推進
企業が省エネ法に対応するためには、まず自社のエネルギー使用量を正確に把握し、法の指定基準に該当するか確認することが出発点です。その上で、経営層の関与のもとエネルギー管理体制を構築し、省エネ推進委員会の設置やエネルギー管理統括者のリーダーシップの下で全社的な省エネ計画を策定・実行します。具体的な対応策として、工場設備の高効率化(ボイラーやモーターの更新、インバータ化等)、廃熱の回収利用、スマートメーターやBEMSによるエネルギー監視、照明や空調の制御最適化などが挙げられます。また、生産プロセスの見直しやIoT活用による省エネ運用改善、従業員教育による省エネ意識向上も重要です。こうした取組みを定量的に評価し、毎年の定期報告書で進捗を報告するとともに、中長期計画で将来の設備投資計画や削減目標を明確に示します。省エネ法遵守状況は経済産業省による評価制度にも反映され、取組みが不十分な場合には指導や勧告、さらには合理化計画の作成命令等が行われる可能性があります。悪質な違反(虚偽報告や無報告、管理者未選任など)には罰則規定も設けられており、是正勧告に従わない場合は企業名公表や罰金刑等の対象となり得ます。したがって、法令を遵守しつつ自主的な省エネ努力を積み重ねることが企業には求められます。
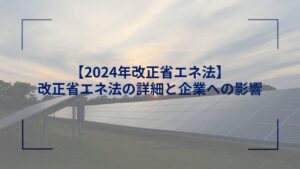
2. 温対法の概要と企業対応
温対法(地球温暖化対策推進法)は、地球温暖化対策を総合的に推進するために制定された法律で、政府・自治体・企業・国民それぞれの責務を定めています。特に企業に関しては、事業活動に伴う温室効果ガス(GHG)排出量の把握と削減努力を促す枠組みとなっています。温対法の大きな特徴の一つが、温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(いわゆる SHK制度)です。これは、一定以上のGHGを排出する事業者に対し、自社の年間排出量を国に報告する義務を課し、国がその情報を集計・一般に公表する仕組みです。具体的には、エネルギー起源CO₂をはじめとする全てのGHG(CO₂、CH₄、N₂O、代替フロン類等)が対象となっており、各企業は毎年度、自社のGHG排出量をガス種別ごとに算定し、環境省へ報告しなければなりません。報告されたデータは環境省により取りまとめられ、公表されることで企業間の排出状況比較や社会全体での見える化が図られます。この制度の狙いは、企業に自らの排出実態を定量的に認識させることで削減計画の策定・実施を促し、政策的にも産業界の排出削減を底上げすることにあります。
温対法の対象
温対法の対象となる特定排出者(報告義務を負う事業者)の基準は明確に定められています。具体的には、年間のGHG排出量(全事業所合計、CO₂換算)が3,000トン以上かつ従業員数21人以上という2要件を満たす企業が該当します。これは中堅以上の製造業やエネルギー多消費産業の多くが該当する水準であり、該当事業者は**「特定事業所排出者」として毎年の排出量報告が義務化されます。また、輸送部門については自社が排出する運輸由来の排出量が一定以上の場合(例:保有トラック台数が200台超など)に「特定輸送排出者」として別途報告義務が課される仕組みです。対象企業は温対法施行令等で定められた排出係数**を用いて自社排出量を計算し(燃料使用量×係数等により算定)、報告書には事業所ごとの排出量データ、削減目標、削減のための具体策などを記載します。例えば「事業者Aの2024年度排出量:CO₂ 5,000t、CH₄ 10t…削減目標:2030年度までに▲40%」といった情報を報告するイメージです。報告書のフォーマットや算定方法は環境省が定めており、必要に応じて第三者検証を受けることも推奨されています。
燃料転換や設備の低炭素化
温対法に基づく企業の取り組みとしては、まずGHG排出量の可視化と計測体制の整備が不可欠です。各工場やオフィスで使用するエネルギーや排出源(燃料燃焼、プロセス排出、廃棄物処理由来など)を洗い出し、データを集約して算定します。その上で、排出削減計画を策定し、例えば燃料転換(石炭からガスへ、ガスからバイオマスや水素へ)、設備の低炭素化(高効率ボイラーや電化設備への更新)、プロセス改善による排出削減、再生可能エネルギー電力の導入など、事業特性に応じた具体策を実施します。また、省エネ法との相乗効果も大きいため、エネルギー効率改善はそのままCO₂削減につながります。報告した排出量データは環境省のデータベースで公開されるため、同業他社と比較して削減の遅れがないかチェックされる可能性があります。社会的な目も意識しつつ、継続的な排出削減努力と内部統制(データ精度や報告内容のチェック体制)の強化が必要です。仮に報告義務を怠った場合や虚偽の報告を行った場合、温対法では20万円以下の過料という罰則規定もあります。この金額自体は大きくありませんが、法令違反による企業イメージ低下や取引先・金融機関からの信用失墜を考えれば、遵守すべき最低ラインといえます。
政府の温暖化対策推進
温対法は企業単独の取組みに留まらず、自治体や国全体での温暖化対策推進とも連動しています。例えば各都道府県や政令市は温対法に基づく地域気候変動対策計画を策定しており、大規模事業所には地方自治体経由で追加的な報告や削減計画提出を求めるケースもあります。また、温対法は1998年制定以降累次改正されており、2021年の改正では2050年カーボンニュートラルの基本理念が盛り込まれ、企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化推進が謳われました。2024年(令和6年)の最新改正では、JCM(二国間クレジット制度)の手続き強化や地域脱炭素化事業の拡充などが盛り込まれており、企業活動においても国内外のクレジット活用や地域と連携した再エネ導入等、新たな展開が期待されています。こうした動きからも、温対法は単なる報告義務の法律にとどまらず、企業の脱炭素経営を後押しする政策ツールへと発展してきていると位置づけられます。

3. 省エネ法・温対法に基づく報告義務と提出方法
省エネ法と温対法における報告義務は、企業が確実に遵守すべき重要な実務事項です。それぞれ報告対象や頻度、提出方法に特徴がありますので、押さえておきましょう。
省エネ法の報告義務(定期報告書・中長期計画書)
省エネ法では、「特定事業者等」に指定された企業は毎年度、前年度のエネルギー使用実績と省エネ取組状況を記した定期報告書を提出する義務があります。報告書には、全社および事業所ごとのエネルギー使用量(電力、燃料等を原油換算した値)、エネルギー消費原単位の前年からの改善率、実施した省エネ施策の内容、削減効果などを詳述します。また概ね5年ごとには中長期計画書を提出し、今後数年間の省エネ目標値(例えば「今後5年でエネルギー消費原単位▲5%」等)や達成のための投資計画・技術導入計画を示す必要があります。
スケジュールや提出情報
報告先は所轄の経済産業局(資源エネルギー庁)で、提出期限は毎年度概ね翌年度の7月末頃とされています(具体的な締切日は年度により通知)。例えば2024年度(2023年度実績分)の定期報告書は、2024年7月末までに提出するスケジュールです。対象企業には提出の数ヶ月前に経産局から通知・様式案内がありますが、企業側でも年間スケジュールに組み込み、余裕をもってデータ収集と報告書作成に着手することが実務上のポイントです。データ集計には各工場・事業所から燃料使用量や購入電力量の情報を集め、所定のフォーマット(エクセル様式等)に入力します。特に複数拠点を持つ企業では、本社主導で統一的なデータ収集プロセスを確立し、支社・工場からの報告を締切前に取りまとめる体制が必要です。
EEGS
省エネ法の報告手続きは近年オンライン化が進み、2022年から環境省・経産省が共同運営する「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」が利用可能となっています。経済産業省は原則としてEEGS上での電子提出を推奨・要求しており、定期報告書・中長期計画書・エネルギー管理者の選解任届出など各種手続きがウェブ上で完結できます。EEGSを利用するためには事前に利用登録(アクセスキーの取得)が必要ですが、一度登録すれば省エネ法と温対法の両方の報告を同じプラットフォーム上で行えるため、企業の事務負担軽減につながります。実際の入力画面では燃料種別ごとの使用量や原単位改善率などを入力すると自動計算機能で原油換算量や改善状況が算出されるなど、利便性が高められています。電子報告システムを活用することで記入ミスの防止やデータ蓄積も容易になるため、大規模事業者は早めに電子化に移行するとよいでしょう。
罰則
省エネ法の報告内容については、提出後に資源エネルギー庁による書面審査や必要に応じた立入検査が行われます。提出物に不備がある場合やエネルギー管理体制に問題があると判断された場合は、経産局からの問い合わせや是正勧告が発出されるケースもあります。報告を怠ったり虚偽の記載をした場合は罰則(省エネ法では100万円以下の罰金等の規定や社名公表措置など)が科される可能性もありますので、正確かつ期限遵守が鉄則です。エネルギー使用量の管理から報告書提出までを社内の年間行事としてスケジュール化し、確実な法令遵守に努めましょう。
温対法の報告義務(排出量算定・報告・公表制度)
温対法における報告義務は、前述のGHG排出量算定・報告・公表制度として具体化されています。対象となる「特定排出者」に指定された企業は、毎年度の温室効果ガス排出量を環境省に報告しなければなりません。報告対象期間は基本的に毎会計年度(4月~翌3月)で、報告期限は毎年7月末(対象が事業所排出者の場合)と規定されています。ただし、自社が大量の燃料を使用する輸送事業者の場合(特定輸送排出者)は6月末までとされるなど、業種区分により若干異なります。報告は温対法電子報告システム(前述のEEGS)上で行うことができ、省エネ法の定期報告と同様にオンライン提出が推奨されています。
温対法の報告内容
温対法の報告内容は、事業者単位での総排出量と内訳を中心に据えています。具体的には、CO₂(化石燃料由来)、CO₂(非エネルギー起源:例・石灰石分解等)、CH₄、N₂O、フロン類(HFC/PFC/SF₆/NF₃等)ごとに、全事業所合計の排出量(トンCO₂換算)を算定して報告します。算定にあたっては環境省が毎年公表する排出係数(電力会社ごとのCO₂排出係数や燃料種別ごとの標準係数)が用いられます。例えば電力使用量については各電力会社の係数(調整後排出係数)を掛け合わせてCO₂排出量を計算し、燃料(ガソリン、重油等)は使用量×固定係数でCO₂量を計算するといった形です。これら個々のガスの排出量を合算した事業者全体の総排出量が公表対象となります。
削減目標
報告書には排出量データのほか、排出削減のための目標や取り組み内容も記入する欄が設けられています。具体的には「〇〇事業者は2030年度までにGHG排出量を40%削減することを目標とし、そのために再生可能エネルギー導入や省エネ投資を進める」等の記述を盛り込みます。これは努力目標的な要素ですが、企業の姿勢を示すものとして環境省がフォーマットに組み入れているものです。また、フランチャイズチェーン事業など複数法人にまたがる事業の場合、フランチャイズ本部が加盟店を含めた排出量を一括報告する特例(特定連鎖排出者に関する規定)も存在します。自社が該当する報告カテゴリーを正確に把握し、それぞれの提出書類名(特定事業所排出者報告書、特定輸送排出者報告書等)に従って報告する必要があります。
温対法における報告内容は、提出後に環境省のシステム上でチェックされ、不備がなければ毎年秋頃から環境省ウェブサイトで全報告事業者の排出量データが公表されます。公表情報は事業者名や業種、総排出量などであり、これにより社会的な透明性が確保されます。他社と比較して突出して排出量が多い、削減努力が見られないといった場合には、ステークホルダーから指摘を受ける可能性もあるため、単なる報告の義務履行にとどまらず積極的な排出削減行動が求められます。
提出方法
提出方法については、前述のEEGSを利用することで省エネ法報告と一体的に処理できるほか、特定排出者コードという企業固有の識別番号が環境省から付与されており、これを用いてログイン・データ入力します。初回登録時には経産省(省エネ法用)と環境省(温対法用)の両方への届出が必要ですが、一元化されたプラットフォーム上で情報管理が可能です。紙面提出も制度上は可能ですが、将来的には完全電子化が見込まれるため早めの対応が望ましいでしょう。
罰則
温対法の報告義務違反についても、報告遅延・未報告や虚偽報告に対する罰則が定められています。具体的には、報告を行わない場合等には20万円以下の過料処分となり得ます。これは金銭的制裁としては軽微ですが、法令違反として社名公表が行われる可能性も指摘されており、企業信用に悪影響を及ぼすリスクがあります。また、環境省からの報告催促や立入検査の対象となるケースも考えられます。いずれにせよ、省エネ法と同様に温対法の報告も確実かつ正確に期限内提出することが、企業のコンプライアンス上不可欠です。
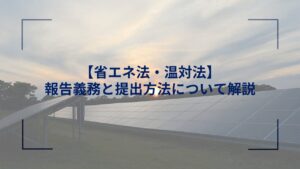
4. 法令遵守と脱炭素経営への実務的連携(サステナビリティ戦略への統合)
省エネ法・温対法への適合は、単なる法令遵守の問題に留まらず、企業が長期的な脱炭素経営戦略を描く上で核となる要素です。気候変動への対応が企業にとって経営課題となる現代において、これら環境関連法規への対応を自社のサステナビリティ戦略に統合し、実務レベルで連携させることが重要です。
脱炭素経営の加速
第一に、法令遵守そのものが脱炭素経営の土台となります。各国で環境規制やGHG削減目標の強化が進む中、企業が省エネ法・温対法を確実に遵守し、自社のエネルギー使用削減やGHG排出抑制を進めることは、将来の規制強化に備え法的リスクを回避する上で不可欠です。日本でも政府の「2050年カーボンニュートラル宣言」を受け、政策の継続性・予見性を高めるためこれを法律に明記し、企業の脱炭素投資やイノベーションを加速させる方針が示されています。例えば省エネ法では前述の通り再エネ利用拡大やDR実施が新たに求められるようになり、温対法でも企業排出情報のオープンデータ化が進められています。さらに政府のGX(グリーン変革)戦略においては、2028年度までにカーボンプライシング(炭素に対する賦課金)導入が検討されており、将来的にはエネルギー多消費や排出量の多い企業ほど直接的なコスト負担が生じる可能性があります。このように今後10年で規制や経済的インセンティブが大きく変わる局面に向け、現時点から省エネ・排出削減を着実に進めておくことが、企業の競争力維持の面でも賢明な戦略と言えます。
経営戦略への積極的な活用
次に、法令対応で得られるデータや経験を経営戦略に活用する視点が重要です。省エネ法・温対法への報告を通じて、企業は自らのエネルギーコスト構造や排出プロファイルを詳細に把握することになります。この蓄積データは、単なる報告用途にとどめず社内のKPI管理や投資判断にフィードバックすべき資産です。例えば、エネルギー原単位やGHG排出原単位の推移を毎年トラッキングすれば、自社の環境効率改善のトレンドを把握できますし、設備ごとのエネルギー消費を分析すればムダの大きいプロセスが浮き彫りになります。こうした知見をもとに、中長期の脱炭素ロードマップを策定し、どのタイミングでどの技術に投資すべきか(高効率設備更新や燃料転換、カーボンオフセット活用等)、バックキャスティングの発想で経営計画に組み込むことが可能となります。
開示のベースライン
実際に、多くの先進企業では省エネ法報告の数値を社内目標として管理し、役員報酬の評価指標に組み入れたり、温対法の排出量データを開示してSBT(Science Based Targets)やTCFD報告に活用する動きが広がっています。ESG経営の文脈では「環境(E)」への対応が重視されており、これら法令対応はESG情報開示のベースラインともなります。2024年以降、金融当局が上場企業に温室効果ガス排出量の開示を義務づける方針を示すなど、サステナビリティ情報の透明性確保が一層求められています。自社の環境データを正確に把握・報告できる体制を整えることは、そのまま社外への信頼性の高い情報発信につながり、資本市場での評価向上や調達コスト低減(環境格付けやサステナビリティ・リンク・ローンの優遇など)というメリットも享受できます。
内部統制
さらに、脱炭素経営を推進する上で社内外のステークホルダーとの連携も実務的に重要です。社内では、省エネ法対応を所管するエネルギー管理部門や工場の設備部門、温対法対応を所管する環境・サステナビリティ部門や経営企画部門が連携し、データや課題を共有する仕組みを構築しましょう。例えば、エネルギー使用削減の現場ノウハウと、GHG算定の専門知識を結集させることで、より効果的な削減策(省エネが同時にCO₂何トン削減かを可視化する等)を生み出すことができます。またトップマネジメントのコミットメントも欠かせません。経営陣が率先して2050年カーボンニュートラルや中期的な脱炭素目標を掲げ、省エネ法・温対法の遵守を「当社の最低限の義務であり、かつ競争戦略の一部」と位置づけることで、社内意識が高まり投資判断も後押しされます。
バリューチェーンでの連携
社外に目を転じると、脱炭素への取り組みはバリューチェーン全体での協調が求められます。大企業の多くはサプライチェーン全体でのGHG削減目標を掲げており、自社の取引先にも排出削減や情報開示を求め始めています。このため、中小企業であっても省エネ法・温対法を遵守し、可能な範囲で自主的な削減努力をしていることが取引条件になるケースも増えています。実際、調査によれば大企業の約2割が既にサプライヤーに脱炭素化の要請を行っているとの報告もあります。自社の法令対応状況や環境目標を取引先や金融機関に共有し、協力して改善策を模索することは、企業間の信頼関係を深めビジネスチャンスを広げることにもつながります。例えば、工業炉の排熱発電をサプライヤーと共同で導入したり、物流網全体でモーダルシフトを進める、といった共同プロジェクトはその典型です。
公的支援
最後に、脱炭素経営への実務的連携を進める上で公的支援策の活用も賢明です。国や自治体は、省エネ設備導入補助金、再エネ設備補助金、ESG金融支援策など様々なメニューを用意しています。特に経済産業省や環境省の補助制度では、省エネ法や温対法の対象事業者を優先する枠もあり、自社の脱炭素プロジェクトに対して資金面・技術面の後押しを得られる可能性があります。例えば、中小企業が工場のヒートポンプ導入を行う際の補助金や、CO₂削減診断の無料派遣制度などがありますので、自社の計画に合致する支援策を調査・活用するとよいでしょう。
以上のように、省エネ法・温対法の遵守を出発点として、それを超える自主的な脱炭素経営への統合を図ることで、法令遵守+αの企業価値向上が期待できます。実務的には、法対応で培ったデータ管理・改善施策を経営戦略に反映し、社内体制やバリューチェーン全体で協働することで、コスト削減・リスク低減・新たなビジネス機会創出という好循環を生み出すことが可能です。これら環境への取り組みは、カーボンニュートラル社会の実現に貢献すると同時に、自社の持続的発展にも資する競争力の源泉となるでしょう。
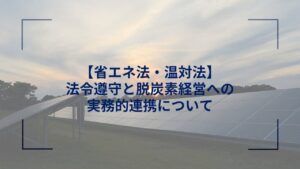
参考リンク
資源エネルギー庁「省エネ法の概要」
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/
資源エネルギー庁「2023年4月施行の改正省エネ法」
https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/shoene_houkaisei2023.html
環境省「地球温暖化対策推進法の概要(改正内容)」
https://ondankataisaku.env.go.jp/carbon_neutral/topics/20250425-topic-71.html












