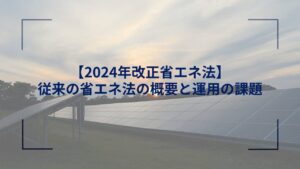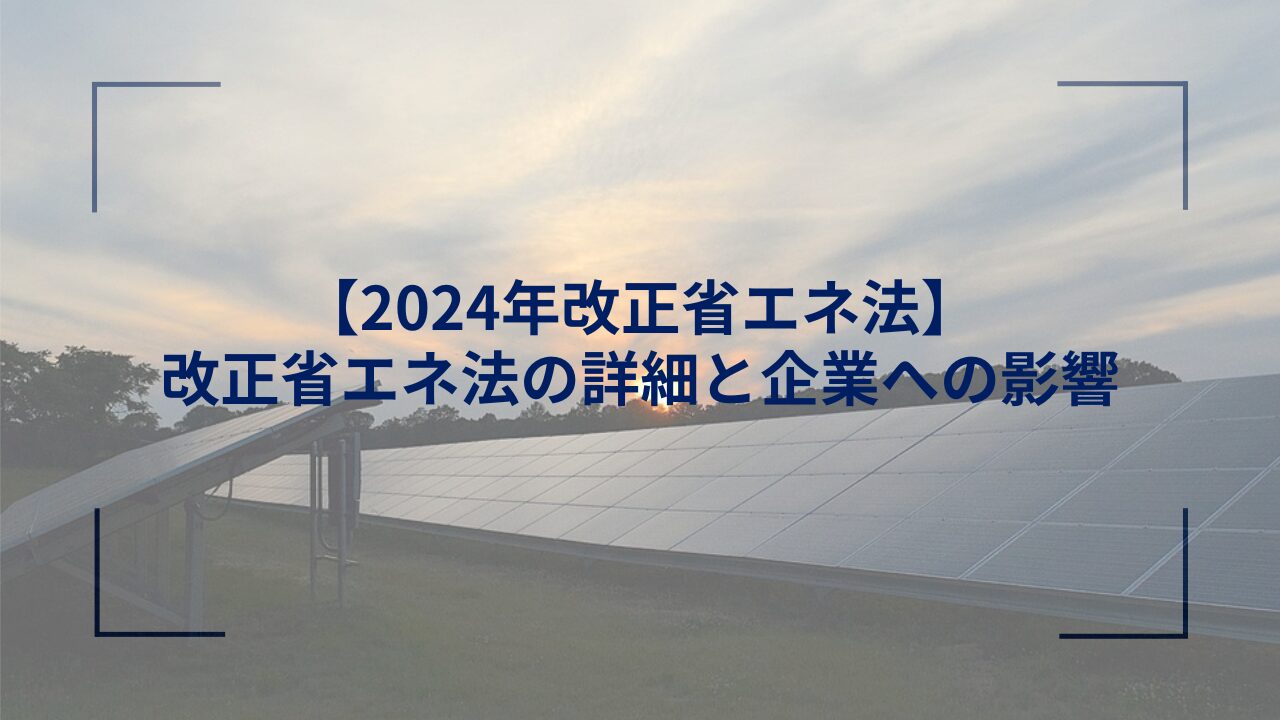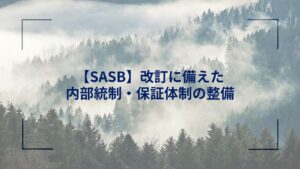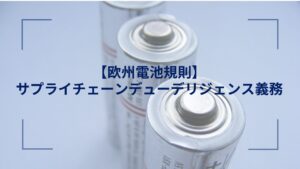2024年改正省エネ法では、従来の省エネに加え、非化石エネルギーへの転換や電力需要の最適化が新たに義務化され、法の正式名称も変更されました。企業は再エネ利用やディマンドレスポンス実績の報告が必要となり、エネルギー管理体制の強化が求められます。これにより、企業には脱炭素対応と競争力強化の両立が期待されています。本記事では、改正省エネ法の詳細と企業への影響について解説します。


1. 改正の目的と背景
前編で述べた課題を踏まえ、日本政府は省エネ法の抜本的見直しに着手し、「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度温室効果ガス46%削減」の目標達成に資するよう法制度を強化しました。具体的には、省エネ法の適用範囲と要求事項を拡大し、エネルギー消費の削減だけでなくエネルギー供給源の転換や需要パターンの最適化まで含めた包括的な仕組みに改めています。この改正により、省エネ法の正式名称も「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」に変更され、法律の目的に非化石エネルギー転換が明確に位置付けられました。
改正省エネ法は2023年4月に施行され、2024年7月末に改正後初回の定期報告提出期限を迎えます。企業は2023年度のエネルギー使用実績から新制度に沿った対応が求められることとなり、以下では今回の改正の主要なポイントを整理した上で、企業への具体的な影響と求められる対応について考察します。
2. 改正省エネ法の主な変更点
エネルギー使用合理化の対象範囲拡大
改従来は省エネ法上「エネルギー」と言えば石油や石炭等の化石エネルギーを指していましたが、改正法では再生可能エネルギーなどの非化石エネルギーも含むすべてのエネルギーが効率化の対象となりました。これに伴い、企業が毎年提出する定期報告書でも、化石燃料由来エネルギーだけでなく、太陽光・風力など非化石エネルギーの利用量を含めて報告することが義務化されています。
非化石エネルギーへの転換義務の新設
改正省エネ法では、大規模事業者(特定事業者等)に対し、自社のエネルギー源を化石燃料から非化石エネルギーへ転換していくための中長期計画の策定が新たに義務付けられました。この計画書には将来に向けた再生可能エネルギーや水素等の利用拡大目標(例えば「2030年までにエネルギーの○%を非化石化」等)を盛り込み、毎年度の定期報告でその進捗状況(非化石エネルギーの使用実績)を報告する必要があります。特に、政府が2030年度に向けた目安を示している業種(セメント、自動車、鉄鋼、石油化学・ソーダ、製紙業の5業種)では、提示された指標を踏まえた積極的な転換努力が求められます。これにより、企業は単にエネルギー消費量を減らすだけでなく、自ら使うエネルギーのクリーン化についても責任を持って取り組むことが制度上明確化されました。
電力需要の最適化(ディマンドレスポンス)の促進
エネルギーミックスの転換に加え、改正法では電力の需要側調整の取組も重視されています。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、天候などによって電力供給が過剰になったり逼迫したりする場面が増えるため、需要側で柔軟に対応する「ディマンドレスポンス」の体制整備が不可欠です。改正省エネ法では、特定事業者等の大口需要家に対して、自社の電力需要を供給状況に応じて調整した実績を報告することが義務づけられました。具体的には、電力が余っている時間帯には消費を増やす「上げDR」、電力不足の際には消費を抑える「下げDR」の取り組み状況を定期報告で届け出る必要があります。これにより、企業の需要側調整の取り組み状況が定量的に可視化され、エネルギー効率だけでなく需要の柔軟性も含めた評価・管理が行われるようになります。
報告制度・罰則の強化
今回の改正により、上記のような新たな義務(非化石エネルギー転換計画の提出、DR実績の報告等)が追加されたため、省エネ法の報告様式や項目も大きく見直されています。企業は2023年度分より、中長期計画書と定期報告書を新様式で作成し、非化石エネルギーに関する項目や電力需要最適化の実績値を盛り込んだ内容で提出する必要があります。これら新報告事項の未履行や虚偽報告に対しても、従来同様の罰則規定が適用されます。例えば、新たに義務化された計画書・報告書を提出しない場合には50万円以下の罰金対象となり得ますし、省エネや非化石転換の取組状況が著しく不十分な事業者には是正勧告や企業名公表・命令といった措置、命令違反時には100万円以下の罰金が科される点は改正後も変わりません。
このように、法改正によって報告・遵守すべき事項が増えた分、適切に対応しない企業は行政から指導・勧告を受けるリスクが高まったと言えます。
3.改正による企業への影響と求められる対応
改正省エネ法は、エネルギー管理に関する企業の取り組みに質的な転換を迫るものであり、多方面に影響が及びます。まず、企業は自社のエネルギー利用実態を改めて精査し、エネルギー使用量の算定範囲を拡大する必要があります。これまで報告対象外であった再生エネルギー由来の電力や熱も含め、統合的にエネルギー使用量をモニタリング・集計する体制を整備しなければなりません。また、非化石エネルギー転換計画の策定にあたっては、自社の事業計画や設備更新計画と整合させつつ、実現可能でありながら意欲的な脱炭素目標を設定することが重要です。場合によっては太陽光発電設備の導入拡大や再生可能エネルギー電力の調達契約締結など、エネルギー供給源の転換に向けた投資が必要になるでしょう。
電力需要最適化への対応も不可欠です。工場やビル等の需要家は、自社の電力使用パターンを分析し、ピークシフトやDRに参加できる余地を見極める必要があります。例えば、蓄電池の活用や操業時間帯の調整などにより、DR要請に応じられる体制を整えることが考えられます。さらに、省エネ・脱炭素の取組が優秀な企業は経産省の評価制度でSクラスに位置付けられ、補助金申請時の加点など優遇措置を受けることができます。したがって、企業にとって改正省エネ法への対応は法的義務の履行というだけでなく、自社の競争力強化やステークホルダーからの信頼獲得の機会と捉え、前向きに捉えるべきです。
4.改正の意義と実効性の検討
2024年改正省エネ法は、日本の産業界におけるエネルギー利用の在り方を大きく転換しうる重要な政策転換です。従来は省エネ(効率化)中心だった企業の目標に、脱炭素化(エネルギー源の転換)と需給調整力の向上という新たな要素が加わったことで、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた実効的な一歩となることが期待されています。もっとも、改正の効果を最大限に引き出すためには、実効性の確保が極めて重要です。単に計画書提出を義務化しただけでは、前述のような「計画倒れ」に終わるリスクもあるため、計画内容のフォローアップと実行支援策が不可欠でしょう。例えば、定期報告に盛り込まれた中長期計画の達成状況を毎年チェックし、優良企業には表彰や補助金での支援を、遅れている企業には専門家の派遣支援や資金助成策を講じるなど、きめ細かな対応が求められます。
政府もグリーントランスフォーメーション(GX)実現に向けた補助金や税制優遇措置を拡充しており、改正省エネ法で求められる施策を実行に移しやすい環境整備が進みつつあります。企業側も罰則を恐れる消極的な姿勢ではなく、改正の趣旨を踏まえて的確に対応を進めることで、自社の価値向上と脱炭素社会の実現を両立させていくことができるでしょう。
引用
改正省エネ法(経済産業省ウェブサイト)
https://www.meti.go.jp/index.html
e-Gov法令検索(改正後の省エネ法条文)
https://elaws.e-gov.go.jp
資源エネルギー庁「脱炭素社会に向けたエネルギー政策」
https://www.enecho.meti.go.jp/index.html