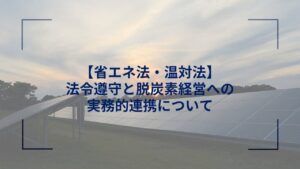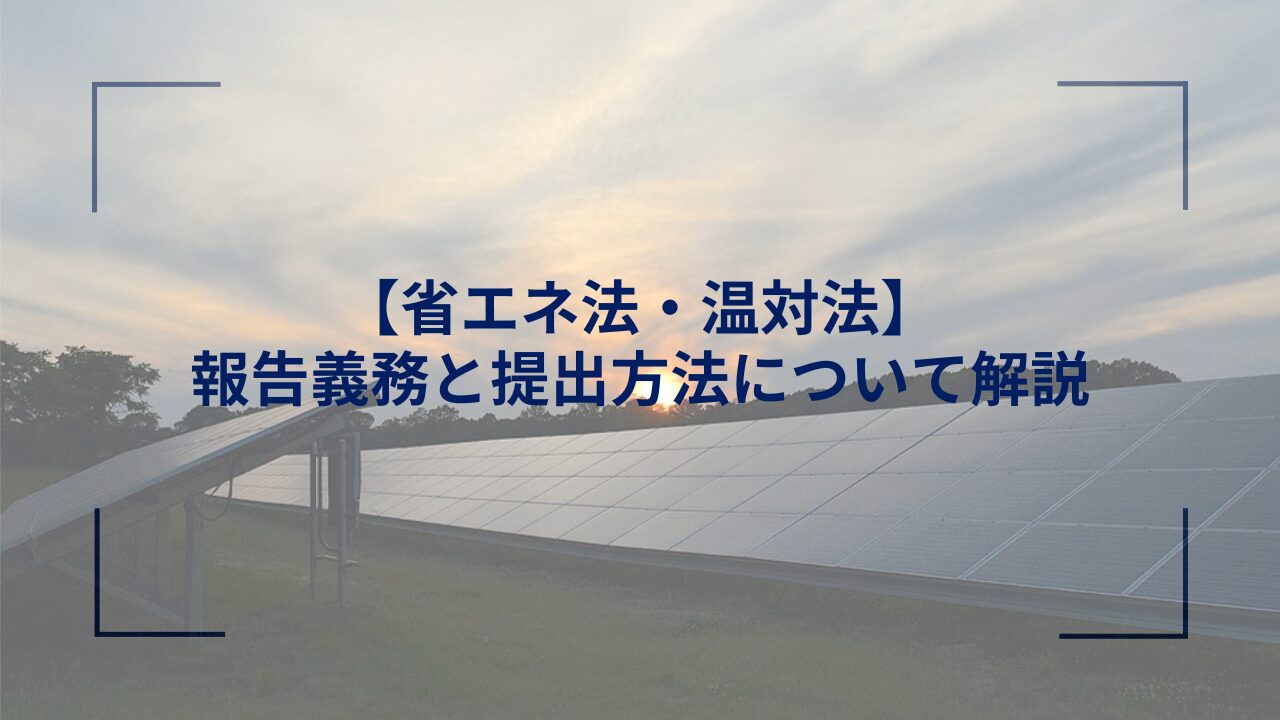省エネ法および温対法に対応する上で、企業にとって極めて実務的かつ重要なのが各種報告義務への適切な対応です。本記事では、両法に基づく報告制度の概要と具体的な提出方法について詳しく説明します。報告内容を漏れなく把握し、円滑に提出することは法令遵守の基本であり、持続的な脱炭素経営のための第一歩でもあります。


1. 省エネ法の報告制度
省エネ法では、「特定事業者」(年間エネルギー使用量1,500kL以上の事業者)に対し、毎年度の定期報告書と、おおむね5年ごとの中長期計画書の提出が義務付けられています。これは企業単位での報告となり、企業全体のエネルギー使用状況を包括的に報告するものです。
定期報告書
前年度(直近の事業年度)のエネルギー使用実績と省エネの取組状況を報告する文書です。具体的には、全社および事業所別のエネルギー使用量(燃料・熱・電気の種類ごと、原油換算値)、エネルギー消費原単位の前年比改善率、省エネ対策実施内容およびその効果(例: ボイラー高効率化による燃料○○L削減)などを記載します。また、第一種/第二種エネルギー管理指定工場ごとの詳細データや、省エネベンチマーク指標該当業種の場合はその達成状況も含めて記述します。定期報告書は毎年度必須で、原則として翌年度の7月末までに提出することが求められます。
中長期計画書
今後のエネルギー削減目標および実施計画をまとめた文書で、3~5年ごと(経年により提出年度が指定)に提出します。ここでは、例えば「今後5年間でエネルギー消費原単位を平均年▲1%以上改善する」「老朽ボイラーを高効率型に更新し年間○kL削減見込み」等、中長期的視点の目標と具体策を示します。中長期計画書は次回提出時に進捗評価も併せて行うため、達成状況がフォローアップされます。提出対象は、「特定事業者」および「特定連鎖化事業者」(フランチャイズ本部など、加盟店含め1,500kL以上)です。また、エネルギー管理指定工場を有する事業者の場合、各工場ごとの詳細情報(エネルギー管理者氏名や工場ごとの使用量等)も報告書内で必要となります。
提出方法とスケジュール
提出先は、事業者の主たる事務所所在地を管轄する経済産業局(資源エネルギー庁の地方支分部局)です。近年、提出方法は大きく電子化が進展しており、オンライン提出が基本となっています。具体的には、環境省・経産省が共同運営する「省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム(EEGS)」を利用してウェブ上で報告書を作成・送信する方法が推奨されています。経済産業局からも「原則EEGSで提出するように」との通知が出されており、紙媒体での提出は例外的な扱いです。
利用者登録
事前にEEGS利用のための届出(様式43「電子情報処理組織使用届出書」)を経済産業省に提出し、アクセスキー(ID)を取得します。これは一度登録すれば省エネ法・温対法共通で使えるIDとなります。
ログインと入力
EEGSポータルサイトにログインし、省エネ法の定期報告書様式に沿って数値や事項を入力します。各種エネルギーの使用量や設備の効率等、画面の指示に従って入力すると、自動で原油換算や原単位計算が行われ、チェック機能も働きます。添付資料のアップロード: 必要に応じ、計算根拠のエクセル表や補足説明資料をアップロードできます。特定事業者指定を受けるための初回届出(エネルギー使用状況届出書)や、エネルギー管理者の選解任届もここから提出可能です。
送信
入力内容を確認し、期日までに電子送信します。送信後、経済産業局側で受領されると受付番号や確認通知が画面上で確認できます。EEGS利用により、同時報告・ワンスオンリーが実現します。すなわち、省エネ法と温対法に重複するデータは一度の入力で両方に反映され、各省庁にもそれぞれ送信されます。このため、特定事業者かつ特定排出者である企業はEEGS上で省エネ法定期報告書と温対法排出量報告をワンストップで提出可能です。なお、EEGS未使用の場合は、経済産業局所定のエクセル様式等に記入し、印刷・押印のうえ郵送または持参で提出する方法もあります。しかし2021年度以降、電子提出が本格稼働し、紙提出は急速に減少しています。電子提出では即座にデータベースに登録され後続処理が効率化されるため、企業にとってもフィードバックが早まるメリットがあります。
提出期限については、経済産業局から毎年通知がありますが、一般的に定期報告書は毎年7月1日~7月末日の間に提出(4~6月に事前案内)となります。中長期計画書は提出年度が限定されますが、概ね定期報告と同じ時期に提出します。期限を過ぎると経済産業局から督促が来るほか、悪質な遅延は法令違反となるので注意が必要です。
報告情報の活用と経産省のフィードバック
提出された定期報告書の内容は、資源エネルギー庁において集計・分析されます。たとえば業種ごとのエネルギー効率動向、ベンチマーク指標の達成度分布などです。さらに事業者クラス分け評価制度として、特定事業者ごとの省エネ取組状況を相対評価しランク付けする制度も導入されています。これは各社の定期報告データを基に、S/A/B/Cといった評価を行い、公表・フィードバックする仕組みです。優良な取組みを促し、遅れている事業者にはエネルギー管理診断の受診勧奨など支援策とセットで改善を促すことが目的です。
また、提出内容に不備があった場合は経済産業局から修正依頼やヒアリングがあります。例えば「前年と比べて使用量が激増/激減しているが理由は何か」「ベンチマーク指標が未記入なので提出し直してほしい」といった問い合わせです。これらには速やかに対応し、必要に応じて訂正報告を行います。特に虚偽記載や重大なミスは罰則(50万円以下の罰金等)の対象となり得ますので、誠実に対応しましょう。
2. 温対法の報告制度
温対法の報告制度、すなわち温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(通称: 温対法報告制度)は、前述したとおり対象事業者(特定排出者)にGHG排出量の年次報告を義務付けるものです。省エネ法報告との違いや留意点を中心に見ていきます。
報告対象ガスと期間
報告すべきGHGはCO₂(エネルギー起源・非エネルギー起源に区分)、メタン、亜酸化窒素、代替フロン類(HFC/PFC/SF₆)、三フッ化窒素(NF₃)です。これらのうちCO₂, CH₄, N₂Oは通常の事業年度(例:4月~翌3月)ごとに算定し、フロン類4ガスは暦年(1月~12月)ごとに算定する決まりです。したがって報告書では年度ベースと暦年ベースの両方の数値を含む場合があります。
報告内容
事業者全体のガス種別排出量が中心ですが、その内訳として事業所別排出量や、輸送部門の排出量も区分して記載します。特定輸送排出者(自社輸送)である場合は自動車燃料による排出量も別立てで報告します。また排出量削減に関する目標・取り組みも任意記載項目として設けられており、自主的な削減計画や実施中の施策をアピールできます。
報告様式
かつては紙様式(環境省令様式第二号等)がありましたが、現在はEEGSによる電子報告が主流です。EEGS上では省エネ法と統合されており、例えば燃料ごとの使用量を入力すればCO₂排出量が自動算定され省エネ法側にも流用される、といった設計です。なおフロン類(オゾン層破壊物質)に関しては、別途フロン排出抑制法の報告システムとも連携しています。
報告期限
毎年度7月末が基本です(対象区分ごとに若干異なるが統一運用されている)。輸送部門のみの事業者は6月末となっていますが、エネルギー消費と輸送の両方を行う事業者の場合は遅い方の7月末に合わせて一括報告可能です。
報告先
環境省(オンラインで送信され環境省サーバーにデータ蓄積)。経産省経由EEGSで送れば自動的に環境省にも届く形です。
提出手順と電子システム
提出手順は省エネ法同様、EEGSでの電子提出が標準です。前述のアクセスキー取得が済んでいれば、省エネ法報告メニューから続けて温対法報告メニューに移行できます。温対法報告ではまず事業者情報・事業所一覧を登録し、そのうえで各ガスの排出量を入力します。電気使用量や燃料使用量は省エネ法側から自動入力されるため(二重入力不要)、それ以外のプロセス由来排出や廃棄物由来排出などあれば追加で数値を入れます。CO₂以外のガス(CH₄等)は各排出源ごとの排出量を直接入力しますが、多くの事業者ではCO₂が大半を占めるため、電気・燃料データからの自動計算部分が主作業となります。
EEGSポータルでは、温対法の参考資料として各種の排出係数リストや算定ガイドラインへのリンクも提供されています。また不明点があれば環境省のヘルプデスクに問い合わせ可能です。初めて報告する際は前年以前の基礎データが無いので多少時間を要しますが、一度テンプレートができれば翌年以降は更新部分のみの修正で済むため、毎年の負荷は軽減します。
報告データの公表
環境省は提出された各事業者の排出量データを集計し、毎年公表しています。公表方法は環境省ウェブサイト上でのPDFまたはデータベース公開で、事業者名・業種・排出量が一覧で掲載されます。例えば「2021年度温室効果ガス排出量(確報値)」として、全対象約1万社の排出量データが見られるようになっています。これにより、自社が業界内でどの位置にいるか、過去からの増減はどうか、といったことが一目で分かります。
公表データは社外からの評価にも用いられます。投資家やNGOなどはこの情報を基に企業の気候変動対策状況を評価し、気候変動対策に消極的な企業を名指しする報告書を出すこともあります。また取引先企業がサプライチェーンの排出量管理のために閲覧するケースもあります。従って、単に提出して終わりではなく、提出後に公表される自社データをどのように解釈されうるかも意識しておく必要があります。例えば、生産量増加で排出量が増えていても原単位は改善している場合、温対法報告ではそこまで読み取れないため、必要に応じ自社のサステナビリティ報告書等で補足説明する、といった対応も考えられます。
報告データの利活用
温対法報告データは、政府の統計・政策立案にも活かされています。日本全体の排出量算定や、業種別削減ポテンシャルの分析などです。直近では企業排出データをオープンデータ化し、研究者や他企業が活用しやすいよう環境省がシステム整備を進めています。
違反時の措置
温対法報告については、省エネ法ほど厳しい勧告・命令のプロセスはありませんが、報告遅延・未報告や虚偽報告は違法行為です。環境省は提出状況をチェックし、未提出企業には督促を行います。それでも提出がない場合、過料(20万円以下)の徴収手続きが裁判所を通じて行われます。実際に過料が科された事例は限定的ですが、法的にはその規定があります。また、環境省が悪質と判断すれば企業名公表など社会的制裁も考えられます。
したがって、温対法報告も軽視せず確実に遂行することが肝要です。特に初年度などは報告漏れが発生しがちですので、社内で複数人チェックし、提出漏れのないよう管理しましょう。省エネ法対応企業は大体温対法の対象にも該当しますので、両者をセットで進捗管理するのがおすすめです。
3. 複数法令への一元対応と実務上のポイント
省エネ法・温対法の報告義務は上述のように多くの共通点があります。さらに業種によってはフロン排出抑制法(冷凍空調機器の管理状況報告)や化管法(PRTR届出)など環境関連報告が複数ある場合もあります。これらをバラバラに対応すると非効率になりがちです。
社内で環境法令報告の総括責任者を置く
例えば環境担当マネージャーが省エネ法・温対法・フロン法などを一括管理し、各担当部署と連携してスケジュールと整合性を図る。
共通データ基盤の整備
エネルギー使用量や排出量の基本データを一元管理するデータベースを社内に構築し、各種報告書はそこから自動生成・流用する。可能であれば専用ソフトやクラウドサービスの活用も検討。
年間スケジュール作成
1~12月までにどの報告をいつ準備・提出するか一覧化し、繁忙時期を把握して人員配置や負荷分散を行う。一般に温対法(7月)と省エネ法(7月)が重なりピークになるので、データ収集は年度切替直後から着手するなど前倒しを意識する。
定期的な見直し
報告手続きを実施した後、関係者間で改善点を共有し次年度に反映する。例えば「今年はデータ取りまとめに手間取ったので、来年はエクセル様式を統一し自動計算マクロを導入する」といった改善を行う。
これら工夫により、報告義務を単なる事務負担ではなく社内の環境情報管理力向上のチャンスと捉えることができます。法令遵守と業務効率化を両立させ、さらに得られたデータを経営に役立てるという視点が重要です。
最後に強調すべきは、期限遵守と正確性です。どんなに立派な環境経営を掲げていても、法定報告を怠れば企業コンプライアンスに疑問符が付きます。提出期限は絶対厳守、データは根拠を持って正確に――この基本を押さえた上で、報告内容を自社PRや改善活動に活かしていく前向きな姿勢が望まれます。
引用
資源エネルギー庁「省エネ法定期報告情報の開示制度
enecho.meti.go.jpenecho.meti.go.jp
東北経済産業局「EEGS(電子報告システム)について」
tohoku.meti.go.jptohoku.meti.go.jp
環境省「温室効果ガス排出量報告制度ガイド」(環境省サイト)
business.enechange.jpbusiness.enechange.jp