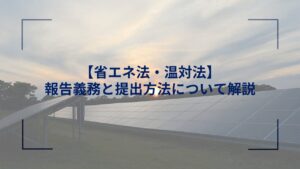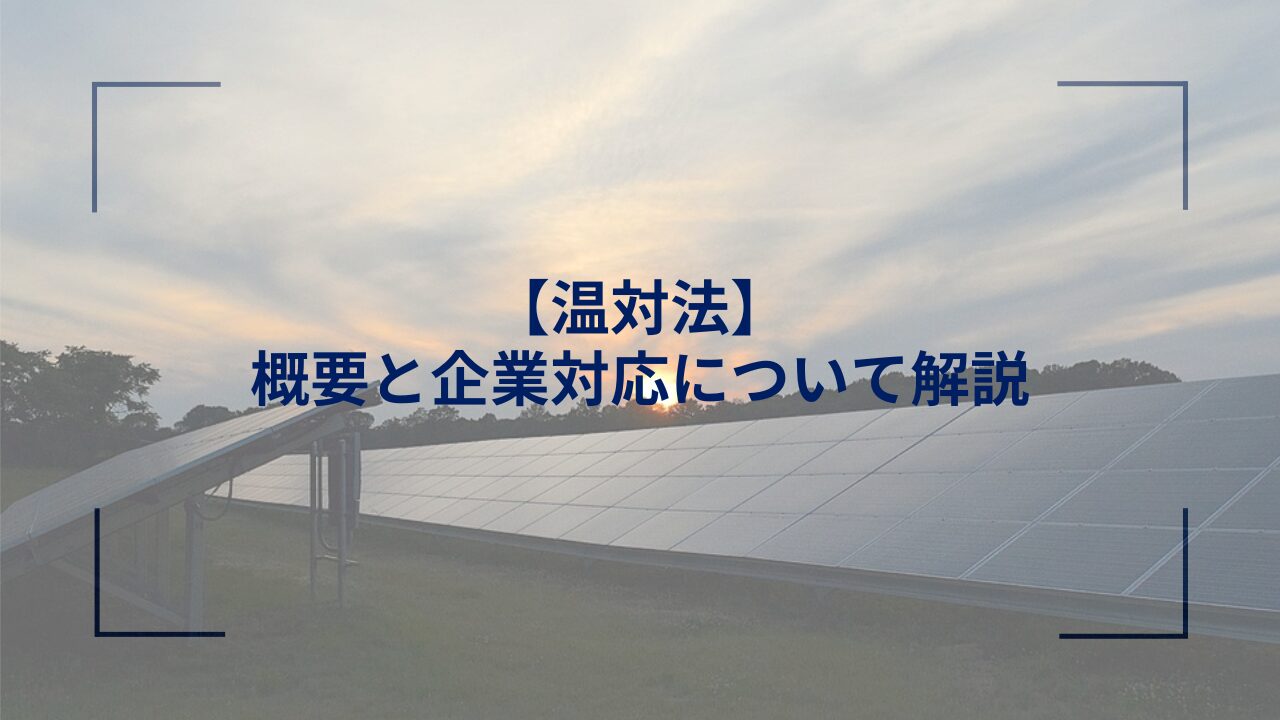温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)は、日本における地球温暖化対策の基本法であり、政府・自治体から企業・国民に至るまで幅広い主体の役割と施策の枠組みを定めています。本記事では、その中でも企業に関連する制度や義務に焦点を当て、温対法の概要と企業が取り組むべき対応策について解説します。特に製造業など温室効果ガス排出量の多い事業者に有用な情報を整理します。


1.温対法の目的と全体像
温対法は、1998年に京都議定書を受けて成立した法律で、その目的は「気候系に対して危険な人為的干渉を防止するため、大気中の温室効果ガス濃度を安定化させる」ことにあります。つまり地球温暖化を防止するため、社会経済活動による温室効果ガス(GHG)排出の削減と吸収源の保全・強化を図ることが法律のミッションです。温対法は単独の法律で完結するというより、これに基づいて地球温暖化対策計画(政府の基本計画)が策定され、各自治体でも実行計画が作られ、企業や国民の具体的行動につなげるという推進法的性格を持ちます。
責務
法律上は、国・地方公共団体・事業者・国民それぞれの責務が明記されています。国は基本方針の策定や進捗管理、国際協調などを担い、自治体は自ら率先して排出削減に努め地域計画を作成、企業(事業者)は事業活動に伴う排出抑制に努め、国民もライフスタイル面で協力する、といった役割分担です。これらを総動員し、政府全体で掲げた中期・長期の温室効果ガス削減目標(例えば2030年度▲46%、2050年カーボンニュートラル等)を達成しようというのが温対法の基本思想です。
改正
温対法の成立以降、京都議定書目標の達成やパリ協定への対応など節目ごとに改正が重ねられてきました。特に企業に関連する重要な改正ポイントとしては、2005年改正で導入された「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」(後述)や、2021年改正で盛り込まれた「2050年カーボンニュートラルの基本理念」と「企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化推進」が挙げられます。直近の2024年改正では、JCM(二国間クレジット)の実施体制強化や地域脱炭素化促進事業の拡充など、国際貢献と地域振興の両面が強化されています。これら改正動向からも、温対法は国内排出削減の仕組み作りと国際的取組みへの対応という二つの軸で進化していることがわかります。
2.企業に関わる主要制度
温対法には様々な施策が含まれますが、企業に直接関係が深い主要制度は以下の通りです。
温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)
この制度は、温対法の中核と言える企業の排出量報告制度です。先述のように2005年改正で導入され、2006年度から本格施行されました。一定以上の温室効果ガスを排出する事業者は、自ら毎年度のGHG排出量を算定し、国(環境省)へ報告する義務があります。環境省は報告されたデータを集計し、全体傾向や事業者別排出量を取りまとめて公表します。この制度によって、日本全体の産業部門・エネルギー転換部門などの排出状況が網羅的に把握でき、政策立案や企業間の自主的な努力比較にも資する情報基盤が形成されています。
報告義務の対象
報告義務の対象となる「特定排出者」の基準は法律施行令で定められており、一般的には「年間排出量がCO₂換算3,000トン以上かつ従業員21人以上」という2要件です。具体的には、事業者(法人)全体で見て、化石燃料の燃焼などエネルギー起源CO₂やその他GHGを合算して3,000t-CO₂以上排出する企業が対象となります。対象ガスはCO₂、メタン(CH₄)、亜酸化窒素(N₂O)、代替フロン類(HFC/PFC/SF₆/NF₃)など京都議定書の6ガス全てです。算定方法は環境省のガイドラインに従い、各活動(燃料使用量や生産量等)に統一の排出係数を乗じて排出量を計算します。例えば、ある工場で年間電力1,000,000kWh使用し、契約電力会社のCO₂係数が0.0005[t-CO₂/kWh]であれば、その工場のCO₂排出量は500tとなります。同様に燃料使用やプロセス排出も計算し、企業全体を集計します。
締切
各事業者は毎年、この算定結果を7月末までに所定の様式(電子報告システムEEGS)で提出します。提出情報には、事業者名・所在地、GHG排出量(ガス種別ごと)、削減目標、削減の取組内容などが含まれます。環境省はその情報を翌年公表し、誰でも閲覧できるようになっています。公表データからは業種別の排出量ランキングや、各社の排出増減傾向などが読み取れるため、企業イメージやステークホルダー評価にも影響を与えます。なお報告を怠った場合等には20万円以下の過料が科される罰則規定があります。
事業者排出削減指針
温対法には、事業者による排出抑制等の指針(環境省策定)と、それを受けて事業者が排出削減に努める努力義務規定があります。いわばガイドライン的なもので、例えば「エネルギーの効率的利用」「再生可能エネルギーの導入促進」「製品・サービスライフサイクルでの排出削減」等の事項が掲げられています。法的強制力はありませんが、産業界団体を通じて自主行動計画の策定が促されたり、各企業が自社の脱炭素経営計画を策定する際の参考とされています。最近ではSBT(科学的目標)認定取得やESG投資への対応の一環として、中長期のGHG削減目標を公表する企業も増えており、温対法の枠組みを超えて自主的に高い目標設定を行う例も多く見られます。
実行計画の策定
また地方公共団体も温対法に基づき、自らの事務事業や地域全体の排出削減に関する実行計画を策定することになっています。これに関連して、都道府県や政令市では管内の大口事業所に対し温対法以上に詳細な報告や計画提出を課す条例を制定している場合があります(例:東京都の環境確保条例による総量削減義務と排出量取引制度など)。従って、大都市圏で事業を行う企業は温対法だけでなく自治体条例にも注意が必要です。
その他の関連制度
温対法には他にも、温暖化対策推進センター(全国および都道府県に設置され普及啓発を担う機関)、地球温暖化対策推進本部(内閣に設置され総合調整を行う)、フロン類排出抑制法との連携、森林吸収源対策の推進、国民運動(COOL CHOICEなど)の位置付け等、多岐にわたる規定があります。しかし企業対応という観点ではやはりGHG排出量の把握・報告と、その削減努力が中心となるでしょう。
3.温対法に基づく企業の具体的対応策
温対法の枠組みの中で企業が求められる対応策の1つ目はGHG排出量の的確な管理・報告です。まず、自社の温室効果ガス排出量を正確に算定・把握する体制を整えることが出発点です。これは温対法報告制度への対応であると同時に、脱炭素経営の現状を知る上で不可欠なステップです。具体的には、以下のような取り組みが必要です。
排出量算定の仕組み作り
社内でエネルギー使用量や生産量など必要データを収集・集約するフローを構築します。エネルギー(電気・燃料)使用量は省エネ法報告とも共通する部分が多いので、エネルギー管理担当部署が中心となり、温対法用にCO₂換算する作業を追加する形が効率的です。必要に応じて会計システムや生産管理システムからデータを自動抽出するなど、ITも活用します。
社内ルール・責任者の明確化
排出量データの算定責任者を定め(例えば環境管理責任者など)、各部門・工場からのデータ報告締切を決めます。温対法の年次報告期限(7月末)から逆算して、社内のデータ集約は5~6月には完了するようスケジュールを組み、余裕を持って確認・修正できるようにします。
第三者検証の活用
報告制度上は必須ではありませんが、排出量算定の信頼性を高めるために外部の第三者検証(ISO14064-3等の基準で行う温室ガス検証)を受けることも検討価値があります。金融市場での開示には第三者保証が求められる流れもあり、先進企業では温対法報告のデータを兼用して有償で保証を取得するケースもあります。
電子報告システムの利用
前述のEEGSなど環境省の電子システムを活用し、人為ミスを減らします。EEGSでは、報告対象事業者か否かを検索できる「特定排出者コード検索」機能や、過去報告値との比較チェック機能もあるため、有効に使いましょう。
これらを通じ、温対法への報告を単なる義務作業とせず排出量マネジメントの一環と位置づけることが重要です。算定された排出量を毎年トップマネジメントに報告し、中期目標と比較して進捗を評価するなど、社内で活用すると社内意識も高まります。
3.温対法に基づく企業の具体的対応策
温対法の枠組みの中で企業が求められる対応策の2つ目はGHG排出削減の実行の二点に集約されます。排出量を把握したら、次は実際のGHG排出削減に取り組みます。削減策の方向性は業種や事業形態によりますが、一般的には以下のような柱があります。
省エネルギーの徹底
省エネ法で述べた内容と重複しますが、エネルギー消費削減はそのままCO₂削減につながります。エネルギー起源CO₂が大半を占める企業では、まず省エネ対策を強化するのが近道です。高効率設備への更新、工場やビルの省エネ診断実施と対策実行、IoTによるエネルギー管理高度化などを進め、結果をCO₂量で評価します。
燃料転換・再エネ導入
ボイラー燃料を重油からLNGへ転換する、フォークリフトをディーゼルから電動に置き換える、工場敷地に太陽光パネルを設置して自家消費する、電力調達を再エネ電力メニューに切り替える(非化石証書の購入含む)等、エネルギー源自体を低炭素化・脱炭素化する施策です。近年は企業のRE100参加や自社PPAによる太陽光導入なども増えており、温対法上も報告項目に「再エネ電力使用量」が追加されるなど重視されています。再エネ導入は直接排出削減のみならず、サプライチェーン全体の脱炭素アピールにも有効です。
プロセス・製品の革新
工業プロセスからの非エネルギー起源CO₂(例:セメント製造時の石灰石由来CO₂等)を排出する業種では、プロセスそのものの革新が必要です。代替素材の利用やCCUS(CO₂回収・有効利用・貯留)の導入検討などが考えられます。また、自社製品の使用段階や廃棄段階での排出削減(省エネ製品開発やリサイクル)も広義には企業の排出削減貢献となり、温対法の理念に沿うものです。
クレジット・オフセットの活用
国内外のクレジット(JCMクレジットやJ-クレジット等)を購入して、自社排出の一部をオフセットすることも可能です。温対法の直接義務ではありませんが、自主目標達成やカーボンニュートラル宣言の手段として活用されます。ただし本質的には自社努力が優先であり、クレジットは補助的手段と位置づけるのが望ましいでしょう。
サプライチェーン対応
Scope3(サプライチェーン排出)まで見据え、調達先への協働要請や物流のモーダルシフト推進など、間接排出削減にも着手します。これにより取引先大企業からの信頼確保や将来的リスク低減につながります。温対法自体はScope1+2(自社直接+エネルギー由来)対象ですが、先進企業はScope3情報開示も始めており、対応が求められる場面も増えています。
4.投資計画と投資戦略との統合
温対法の文脈で重要なのは、これら排出削減策を自社の経営計画や投資戦略と統合することです。ただ闇雲に削減するのではなく、コスト削減効果や競争優位性向上も睨みながら優先順位を付けます。例えば「エネルギーコスト削減額>設備投資償却費」となる省エネ投資は真っ先に実行し、次にブランド価値向上に資する再エネ導入を検討、最後に困難だが将来重要になる革新的技術へは実証的に着手する、といった段階的アプローチです。こうした戦略的取り組みは企業価値向上や市場評価の向上にも直結します。実際、脱炭素経営に積極的な企業はESG投資家から高評価を受け、融資条件が有利になる(サステナビリティ・リンク・ローン等)事例も出ています。逆に言えば、温対法対応を怠ったり削減消極的な企業は、投資家・金融機関から将来リスクが高いと見做される可能性があります。
5.コミュニケーションの重要性
最後に、社員や社会へのコミュニケーションも忘れてはいけません。社内には自社のGHG排出量や目標を共有し、全員参加の削減活動に発展させます。社外には、温対法報告のデータやそれ以上の野心的目標を開示することで、企業の姿勢を示します。これら情報開示は単に義務だから行うのではなく、透明性と説明責任を果たす企業としての信頼向上に資すると捉えるべきです。温対法に対応する企業活動は、そのままSDGs(持続可能な開発目標)の達成や社会貢献にも繋がるものであり、従業員の誇りや企業ブランドの向上要因ともなり得ます。
6.省エネ法との違いと企業が留意すべき点
最後に、しばしば混同される温対法と省エネ法の違いについて簡単に整理します。
目的の違い
温対法は気候変動(温暖化)対策が目的で、GHG排出削減そのものに焦点。当初は枠組み的要素が強い。一方、省エネ法はエネルギー資源の有効利用(省エネルギー)が目的で、結果的にCO₂削減ももたらすが直接のターゲットはエネルギー消費効率。
対象範囲
温対法はGHG排出事業者が対象(=排出サイド)。省エネ法はエネルギー使用事業者すべてが対象(消費サイド)。事業者ベースで見るとかなり重なるが、省エネ法は輸送や機器製造業者など間接的な部分も含む。
義務内容
温対法は排出量の算定・報告・公表が中心で、個別企業に削減義務や罰則(報告違反以外)は無い。省エネ法はエネ管理者の設置、年1%効率改善目標、報告と計画義務など具体的行動義務が課され、改善不十分なら勧告等がある。また省エネ法にはエネ性能向上(トップランナー制度等)も規定。
所管官庁
温対法は環境省(基本方針は内閣)所管。省エネ法は経済産業省(資源エネルギー庁)所管。報告先も温対法は環境省、省エネ法は経産省。
罰則
温対法は報告義務違反に過料(行政罰)20万円以下のみ。省エネ法は命令違反に刑事罰(50万円以下罰金等)あり、より強制力が高い。
7総評
企業としては、両方に対応が必要な場合がほとんどであり、実際の業務ではデータの共通部分も多いため、可能な限り統合的なアプローチが望ましいです。例えばエネルギー使用量データを元に省エネ法報告(エネルギー量)と温対法報告(CO₂量)を同時に作成する、社内のサステナビリティ委員会で両法の進捗をまとめて確認する、といった形です。「省エネ=CO₂削減」であり二重投資にならないため、省エネ法対応が温対法対応を内包し、温対法対応が省エネ法対応を後押しする関係と捉え、相乗効果を高めるとよいでしょう。
また、省エネ法では罰則リスクがより高い点からコンプライアンス優先度は高めですが、温対法も取引や評価への影響力が増しています。例えば、金融庁が全上場企業にGHG排出量の開示を義務化する方針を示すなど、事実上温対法報告レベルの情報開示が求められる流れです。したがって両法とも「最低限守れば良い」ではなく、攻めの経営課題として前向きに取り組むことが、中長期で自社の成長と信用力強化につながります。
引用
環境省「地球温暖化対策推進法 成立・改正の経緯」
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keii.html
全国地球温暖化防止活動推進センター「算定・報告・公表制度の概要」
https://policies.env.go.jp/earth/ghg-santeikohyo/index.html