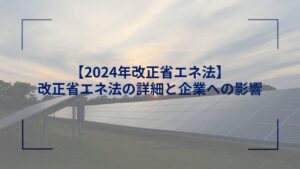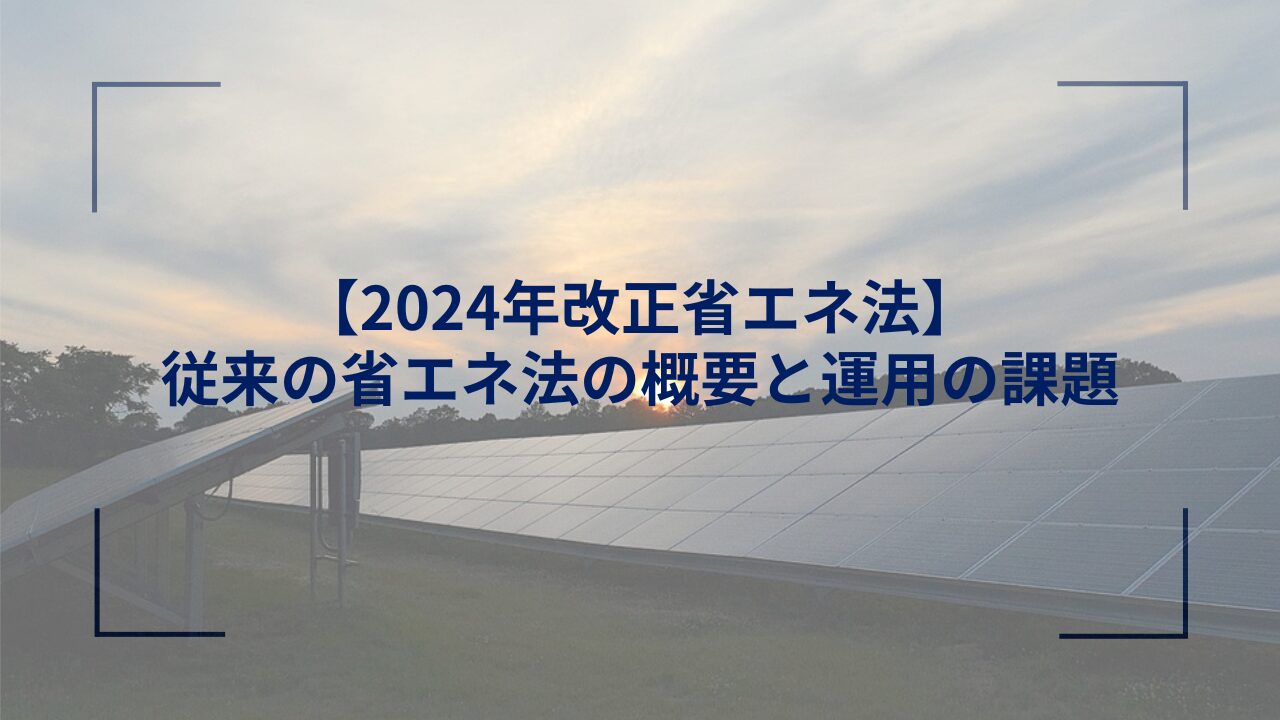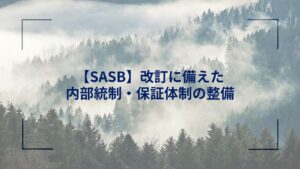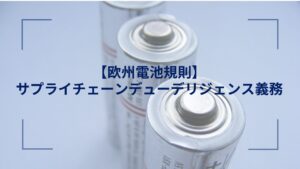省エネ法は、エネルギーの効率的利用を目的に1979年に制定され、特定事業者に対し報告義務や管理体制の整備を求めています。しかし、企業側の負担や、省エネ余地の限界、再エネ導入後の電力需給変動など、運用上の課題が指摘されてきました。2050年カーボンニュートラル達成に向け、より柔軟で包括的な制度改革が求められています。本記事では、従来の省エネ法の概要と運用上の課題について解説します。


1.省エネ法の目的と制度概要
省エネルギー施策の根幹である「省エネ法」(正式名称:「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」)は、1970年代のオイルショックを契機に制定され、エネルギーを効率的に利用することを目的として発足しました。化石燃料資源に乏しい日本において、エネルギー消費の無駄を省き、経済成長とエネルギー安定供給、さらには地球温暖化対策との両立を図る趣旨を持っています。省エネ法は一定以上のエネルギーを使用する事業者(いわゆる「特定事業者」)を主な対象とする直接規制の枠組みを持っています。具体的には、年間エネルギー使用量が原油換算1,500kL以上の企業に対し、毎年エネルギー使用状況等の定期報告を義務付け、省エネの取組状況を把握します。
行政指導
また、同法は工場・事業場や輸送(物流)分野といったエネルギー多消費部門の事業者に対し、省エネのための「判断基準」を示し、各社がそれに沿った効率化努力を行うことを期待しています。エネルギー使用量が基準を超える事業者にはエネルギー使用状況の届出(定期報告)が求められ、提出された報告内容に基づき、省エネの取組が不十分な場合には行政当局から指導・助言や合理化計画(省エネ計画)の作成指示が行われます。このように、省エネ法は企業の省エネ活動を促すための報告義務と行政指導の枠組みを備えています。
2.対象企業に課される主な義務
上記のように特定事業者とされた企業には、大きく二つの義務が課せられます。
エネルギー使用状況の定期報告
毎年度のエネルギー消費量や省エネの取組内容をまとめた報告書を主管官庁に提出することです。報告には、工場や事業所単位での燃料・熱・電気の使用量、エネルギー消費原単位(生産量あたりエネルギー使用量)の推移、省エネ対策の実施状況などが含まれ、企業全体のエネルギー効率を定量的に把握する役割を果たします。
エネルギー管理体制の整備
特定事業者は事業所ごとにエネルギー管理責任者(エネルギー管理統括者やエネルギー管理者などの有資格者)を選任し、エネルギー使用の把握と効率化推進を社内で管理する体制を整える義務があります。これはエネルギーの専門知識を持つ人材を配置することで、現場レベルで継続的な省エネ改善を図るねらいがあります。
実際、エネルギー管理担当者の選任・解任については所管当局への届出が必要であり、選任を怠った場合には罰金が科される規定も設けられています。また、特定事業者は中長期計画書(5年程度のエネルギー消費削減計画)を策定し提出することが求められており、エネルギー効率目標(例えば年平均1%以上のエネルギー原単位低減目標)を掲げて計画的な改善に取り組むことが期待されています。以上の義務違反に対しては、一定の罰則や行政処分が定められています。
罰金
例えば、定期報告書や中長期計画書を提出しない、あるいは虚偽の報告を行った場合には50万円以下の罰金が科されます。また、省エネ取組が著しく不十分な事業者には是正を勧告し、それでも改善されない場合には企業名の公表や命令を発し、最終的に命令違反に対して100万円以下の罰金が科される仕組みとなっています。
このような措置により、企業に対して省エネ法の遵守を促し、実効性を担保することが図られています。
3.従来制度の運用上の課題
従来の省エネ法の枠組みは、大企業を中心としたエネルギー多消費事業者に省エネのPDCAを求めるものでしたが、それに伴う実務上の負担も指摘されてきました。
企業側の遵守負担
毎年の定期報告作業では、事業所ごとの詳細なエネルギーデータ収集・集計や書類作成が必要となり、エネルギー管理担当者にとって相当の労力となります。特に全国に多数の拠点を持つ企業では、各拠点からエネルギー使用実績を集約し、本社で統合的な報告書をまとめる必要があるため、内部統制やデータ管理のコストが無視できません。また、省エネ法に対応するための専門知識を持つ人材(エネルギー管理士など)の育成・配置も不可欠であり、人員確保が難しい中堅・中小規模の企業では対応のハードルが高い状況でした。省エネ設備への投資は初期費用や投資回収期間の問題があり、企業によっては経営判断上消極的にならざるを得ないケースもあります。こうした遵守コストの問題は、企業側から省エネ法運用に関する負担感として認識されていたと言えます。
省エネ取組の実効性に関する課題
一方で、制度の実効性という観点からも幾つかの課題が指摘されています。まず、エネルギー使用の定期報告や中長期計画の提出が形式的な手続きに留まり、実際の省エネ改善行動につながっていない恐れがある点です。例えば、多くの企業が提出する中長期計画は、計画策定そのものが義務化されていることもあり、単に書類上目標を掲げただけの「形式的」なものになってしまっている可能性があります。この場合、計画を策定してもそれが現場で十分に活用されず、実質的な省エネ投資や運用改善が進まないという問題につながります。
削減負荷
また、定期報告で提出されるデータは各事業者の自己申告に基づくものであり、行政による精査や横比較が十分でない場合には、せっかく集めた情報が政策全体のPDCAに活かされない恐れもあります。さらに、従来の省エネ法では各企業にエネルギー消費原単位の年平均1%以上改善という努力目標が課されていましたが、既に省エネを進めてきた産業分野では追加的な原単位改善が徐々に難しくなっている現状もあります。省エネ余地が小さくなった企業にとっては、さらなる効率化投資のハードルが高く、現行制度の一律目標では実情に合わないケースが出てきました。
需要側のエネルギー対策という点では、2013年の法改正で「電気の需要の平準化」の努力目標が盛り込まれましたが、近年の再生可能エネルギー導入拡大に伴う電力需給の変動に対しては十分な対応とは言えませんでした。従来の平準化策は主に夏季のピーク電力削減等を念頭に置いたものでしたが、太陽光発電の出力変動など新たな課題に対しては、より柔軟な需要応答の取組が必要とされてきたのです。
法制度の改善が求められた背景
上述のような運用上の課題に加え、政府が掲げた「2050年カーボンニュートラル実現」や「2030年度温室効果ガス46%削減(2013年度比)」という高い目標を達成するには、従来のエネルギー利用のあり方を抜本的に見直し、需要サイドでのさらなる省エネ強化とともに、非化石エネルギーへの転換や電力需要の最適化を進めていく必要があるとの認識が高まりました。さらに、昨今の世界的なエネルギー価格の高騰や不安定化(ロシアによるウクライナ侵攻等に起因)を受け、日本でもエネルギー安全保障の観点から省エネ・脱炭素の重要性が一層増しています。
こうした背景の下で、省エネ法の制度を単なる化石燃料の効率利用促進策から、あらゆるエネルギーの効率利用とクリーンエネルギーへの転換促進、需要側の柔軟な需給調整促進までを包含する包括的な仕組みへと再構築することが求められるようになりました。
引用
e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000049
経済産業省「省エネポータルサイト」
https://www.enecho.meti.go.jp/index.html
省エネ措置、企業の事例紹介
https://www.meti.go.jp/index.html